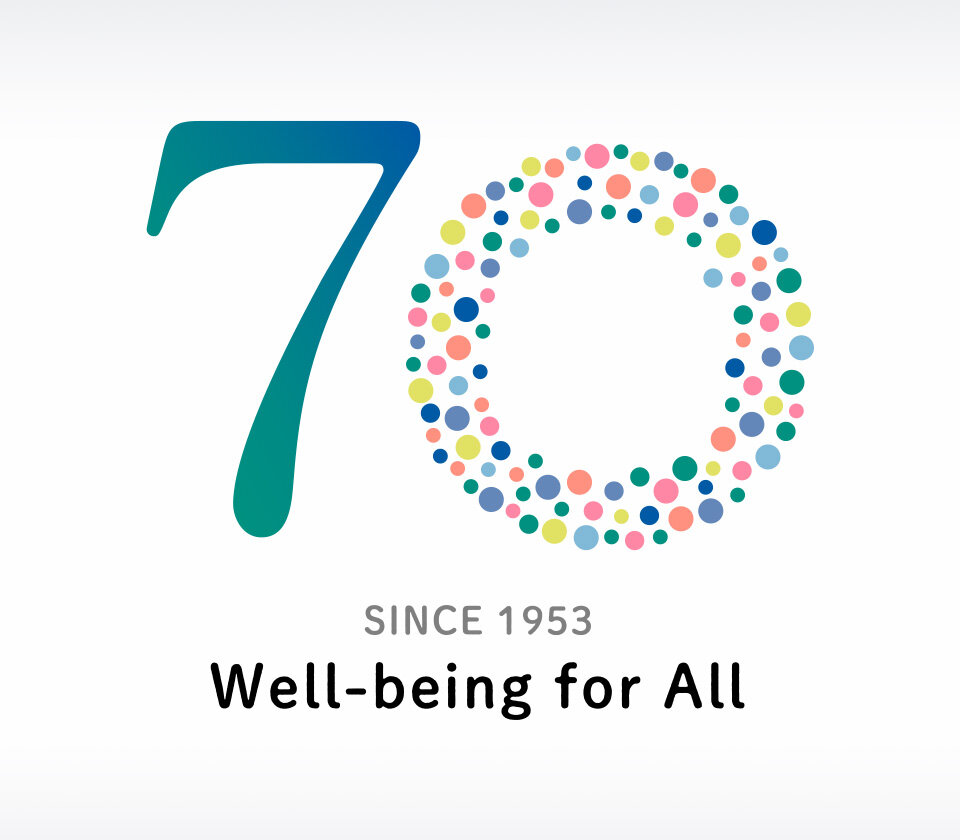国際フィールドワークⅠ
世界に飛び出して現場を見つめ、自分や日本社会を見つめ直す

開催実績
2023年度研修レポートより
フィリピン研修

プログラムは、キャンパスでの講義、都市部でのフィールドワーク、農村でのフィールドワーク、ホームステイで構成されました。
キャンパスでの講義で、大学教員や地域団体の方からコミュニティ構築のための住民の組織化、障害者の理解と生活環境の改善などについて、フィリピンの現状を聴きました。
講義で社会的背景と現状を把握した後、キャンパス外でのフィールドワークを通じて五感で体験して自らその状況を確認し、体験したことを全員で振り返り、学びを深めていきました。
カンボジア研修

カンボジアの貧困解消と環境改善をビジョンに掲げるCRDTの取組や、メコン川の自然保護活動について話を聴きました。
都市部を離れた全校生徒128人の村の小学校訪問では、クメール語の授業を見学したり、校舎へのトイレ建設を手伝ったりしました。
電気・水道のないトゥナウト島の村でのホームステイも経験しました。村人へのヒアリングを通して村の日常生活について理解を深めたり、仏教行事に参加したりしました。
五感をフルに使って様々な経験をする中で、人とのつながりの大切さや生活様式を学びました。
日本研修

前半はひめゆり平和祈念資料館や旧海軍司令部壕を見学して戦争について学び、地元ガイドの方から米軍基地との関係について話を聞きました。
後半は読谷村で民泊を行い、日本人家庭で沖縄の生活様式を体験しました。民泊先の家族と文化交流をし、日本語で積極的にコミュニケーションを図りました。
From a student

研修国:フィリピン
佐々木 心優 さん
フィリピンと聞いて一番初めに思い浮かんだのは「人柄の良さ」でした。なぜそのようにプラスの考え方の人が多いのか知りたくなり、現地で多くの方の人柄に触れて考察しました。
スラム街を訪れると、道行く人々は笑顔を向けてくれるだけでなく、手を振ってくれる人もいました。決して快適な環境とは言えない中で、なぜ笑顔でいられるのかと質問すると、「笑顔でいないといけないから。どんなに辛いことがあっても明日が来ることを信じる。時間は過ぎていく。」という回答でした。笑顔でいることの大切さを知るとともに、笑顔の裏の思いを知り衝撃を受けました。
農村でのフィールドワークでは、先住民族のアエタ族を訪問しました。ここでもとても親切に接してくれました。「私達アエタ族は、肌の色や文化が違っても人に優しくできるということを知ってもらうため」と、見知らぬ私たちを温かく迎えてくれました。誰の子どもであっても関係なく、みんなで力を合わせて育児をする姿、民族のために遠く離れた大学に通っている姿など、お手本にしなければいけない姿がたくさんありました。
これらの体験を通して、フィリピンの人のやさしさの根っこは「つらさを知っているから人にやさしくできる」だと考えました。
人に与える余裕なんてないという考えだった私に、フィリピンの人達が心の優しさを教えてくれました。自分を優先するのではなく、「周りの人とともに」ということを心に留めて行動したいと思うようになりました。この感謝の気持ちを、これから関わる多くの人に還元していきたいです。
事前・事後学習について
本研修で用意されている事前学習では 1.研修機関・研修内容の紹介、 2.渡航国の特徴(社会、文化など)、 3.日本と渡航国との比較、 4.安全管理・危機管理等について学びます。そして帰国後にフィールドワークの総括としてレポート提出と報告集作成の作業があります。事前学習と事後学習ではSNS(ソーシャルネットワークキングサービス)の活用、ホームページ等も利用して学び、この学習活動を通して効果的なICT利用技能も習得します。
※本科目の関連科目:「国際ファシリテーション演習」、「English Presentation」、「異文化理解」
渡航前の安全対策準備について
本学で実施する研修は本学学生のみを対象に、協定校・協力校の協力を得て開発し、安全面に細心の注意を払いながら企画されたものです。また、実施にあたって、引率者が全期間同行し、いつでも緊急時の対応ができるように危機管理対策本部を設置したりするなど、安全面の対策を講じています。皆さんも参加する上では自身で責任を持ち、安全情報や健康維持管理のための情報収集等を十分に行ってください。
研修国の安全情報など以下を参考にしてください。
外務省領事局海外邦人安全課 海外安全相談センター
TEL(直通):03-5501-8162
外務省海外安全ホームページ
外務省在外公館リスト