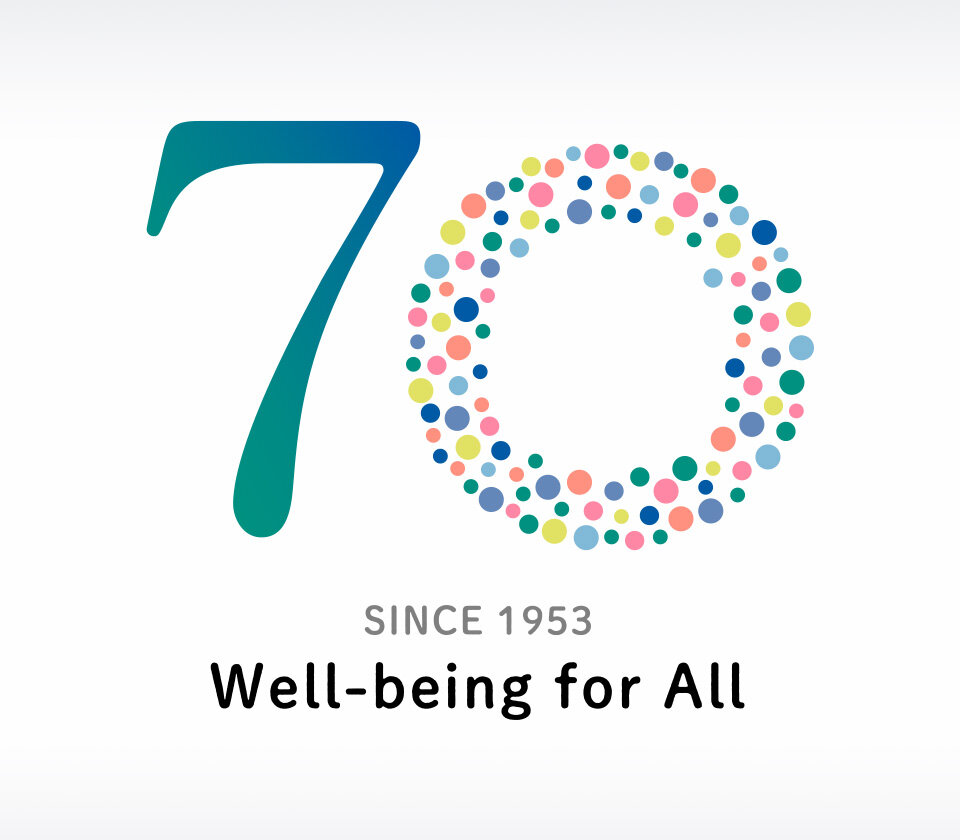カリキュラム(理学療法学専攻)
4年間の学習の流れ
これからの理学療法士に求められる力を
系統立てて培う4年間
1年次
医学の基礎知識を教員・先輩の指導の下早期から修得する

医学の基礎と身体の仕組みを、教員や上級生のサポートの下、時間をかけて徹底的に学習します。同時に、医療人として必要なコミュニケーション能力を、講義や基礎演習を通じて養います。
2年次
専門性を少しずつ高め実習に挑戦!疑問や気づきを得る

国家試験を少しずつ意識しながら、医学的知識をさらに修得。評価実習では、これまでの授業の学びを活かして実際に患者と関わります。現場で得た疑問や気づきを新たな学びにつなげます。
3年次
理学療法における多角的な視点と高度な実践力を養う

理学療法の最新トピックに触れながら、多角的な視点や発展的なスキルを培います。実習では就職後をイメージしながら実践力を磨き上げるとともに、現場で見出した課題を卒業研究に活かします。
4年次
国家試験対策と4年間の集大成となる卒業研究に注力する

実習経験を振り返り、自分に不足している知識や能力を整理・改善します。就職活動と国家試験対策に力を注ぐと同時に、卒業研究では関心のあるテーマを追究し、高度な研究能力を手に入れます。

主な実習先
名古屋大学医学部附属病院/名古屋市立大学病院/愛知医科大学病院/浜松医科大学医学部附属病院/半田市立半田病院/知多厚生病院/名古屋第二赤十字病院/常滑市民病院/刈谷豊田総合病院/一宮市立市民病院/蒲郡市民病院/小牧市民病院/掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター/公立丹南病院/高岡市民病院/あいち小児保健医療総合センター/市立伊勢総合病院/主体会病院/名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院/四日市羽津医療センター/静岡県立こども病院 など
学生の卒業研究テーマ
- 経皮的末梢神経電気刺激療法の鎮痛効果と作用機序についての検討
- パーカッシブ・マッサージにおける実施時間の違いが柔軟性および筋力に及ぼす影響
- 足底部チップが下肢機能および姿勢制御に与える影響について
- 温熱刺激はステロイド受容体の核移行を阻害することでステロイド誘発性の骨格筋萎縮を抑制する
- 福山型先天性筋ジストロフィーをもつ児に対する電動移動機器の使用が発達に及ぼす影響
- 膝関節屈曲角度の変化がDynamic Valgus Angleに及ぼす影響-ジャンプ着地動作に着目して-
科目PICK UP
理学療法の最新テーマをトップランナーから学ぶ
疼痛医学
「痛み」は老若男女・疾患を問わず共通した訴えであり、医科学の広い領域に関連します。授業では、痛みが発生するメカニズムを理解した上で、痛みに伴う身体的・精神的・社会的障害を多面的に捉え、障害からの回復をサポートできる医療従事者を育てます。
救急医学
救急搬送者の医学的管理や超急性期のリスク管理、外傷の対処法、災害医学について学ぶとともに、実際に救急医療に携わる講師を招いて心肺脳蘇生法を実習します。救急医療における理学療法士・作業療法士に求められる役割の違いについても理解します。
前庭リハビリテーション
人間の姿勢制御に関わる「前庭系(平衡感覚を司る器官)」に着目したリハビリテーションを学びます。前庭系の解剖・生理・病態についてや、小脳・大脳、眼球運動との関係を理解し、加齢によるふらつきやスポーツ障害、頸部障害などに対する理学療法を実践します。
スポーツ理学療法学
プロアスリートをはじめ、スポーツをする人と理学療法士が関わる機会が増えています。近年は競技復帰を目標としたリハビリテーションだけでなく、外傷予防策としても理学療法が活用されています。授業では、広い範囲のスポーツ理学療法の手法を学びます
がん理学療法学
がんの病態に応じた医学的治療を理解し、理学療法評価・プログラム立案の手法を身につけます。また、がんとともに生きていく患者のQOL向上を支えられるように、緩和ケアの目的や意義を知ることに加え、チーム医療における理学療法士の役割を考えます。
理学療法特論
ロボットリハビリテーションをはじめ、理学療法に関する最新トピックスを複数教員から学び、就職後を見据えて知識と技術の幅を広げます。また、治療に際して安全管理のポイントや総合的なプログラムの構築方法を学び、多職種連携のスキルを磨きます。
学びの紹介
リハビリテーションの大切さを、一人でも多くの人に。
水泳部に所属していた中学時代。足首の骨折をしたときに、リハビリを受けないまま競技に復帰した結果、靱帯が伸びてしまい、競技を続けることが難しくなりました。この経験から、多くの人にリハビリの大切さを知ってほしいと考え理学療法士を志すように。大学入学後は水泳教室のアルバイトで子どもたちに泳ぎ方を指導することを通じて、子どもの運動機能の発達や身体構造への関心が深まり、小児領域を学べる研究室を選択しました。
卒業研究テーマ
脳性麻痺者のN-of-1trialによる水中歩行-ABABデザインを用いた検討-
私を変えた科目
-
人間関係とコミュニケーション(1年次)
医療現場で必要となる、患者さんやその家族、さまざまな職種とのコミュニケーションについて、社会学・心理学・老年学などの視点から学びました。言語・非言語など、人と関わる方法の多様さに気づくことができました。
-
運動療法学(1・2年次)
理学療法を安全に実施するための知識や、限られた時間で効率よく身体機能の改善を図れるようにプログラムを組み立てる手法を学びました。解剖学・運動学・生理学との関連に気づき、基礎科目の重要性も実感できました。
患者さんの全身を診られるように、妥協せずに技術を磨く。
臨床実習では、患者さんやそのご家族が、病気が良くなることを願って真剣にリハビリテーションに向き合う姿を目の当たりにし、私も中途半端な技術や知識で満足してはいけないと、強い責任感をもって取り組みました。患者さんの抱える主な疾患以外にも、併存疾患や合併症など心身の状態すべてを把握することの重要性を学んだことから、将来は高度急性期病院に就職し、全身を診ることのできる理学療法士になるという目標ができました。
卒業研究テーマ
VDT作業後の頸部筋疲労に対するストレッチが歩行時動的姿勢制御に与える影響
私を変えた科目
-
総合実習(3年次)
評価実習や講義で学んだ知識やスキルを統合して治療を実践し、理学療法士としての総合力を養いました。医師や看護師など多職種と意見を交わす中でより詳細な病態を知ることができ、チーム医療の重要性を理解しました。
-
ヘルスプロモーション(4年次)
中高年の代表的な疾患に加えて、産業保健分野の課題(職場環境の改善や労働者の健康増進など)についても学び、社会で誰もが健康で快適な生活が送れるように理学療法プログラムを組み立てる手法を身につけました。