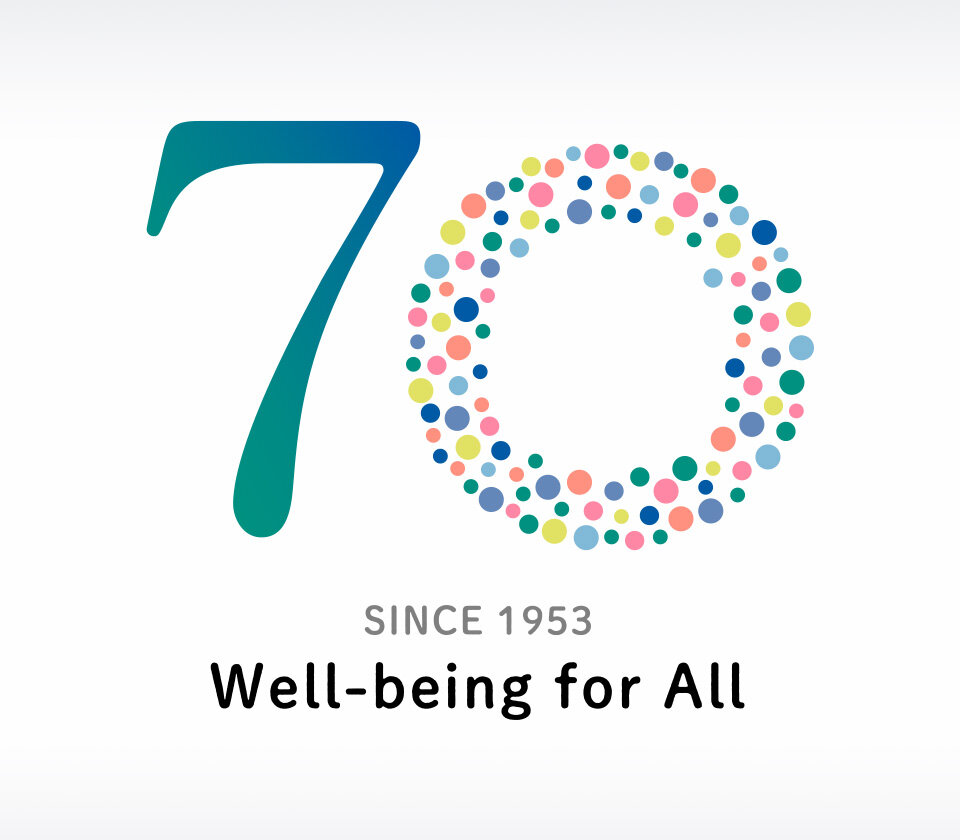ゼミ紹介(こども学科)
ゼミ紹介

MATSUYAMA SEMINAR
松山ゼミナール
- #多文化保育
- #保育社会学
"当たり前"に捕らわれず、
多文化保育を考える。
海外にルーツのある子どもが通う保育・幼児教育施設は全国で6割に上り、多様な文化を尊重する保育の重要性は今後さらに高まっていきます。ゼミの学生たちは、日本の季節行事を一緒に楽しむ多文化プレスクールや読み聞かせイベント、ハワイの保育施設での実習などを通して、さまざまな国の子どもと関わります。そこで学ぶのは、世界には幅広い保育の形があり、自分の知る保育が決して"当たり前"のものではないということです。言語や文化の違いに戸惑う子どもや保護者の存在に気づき、適切な保育を柔軟に考えて実践する人をめざしましょう。

WATANABE SEMINAR
渡辺ゼミナール
- #子ども家庭支援
- #障害児支援
- #予防型支援
子どもだけでなく、
家庭全体を支える保育者に。
子どもの健やかな成長においては、安定した「家庭」の存在が大切であり、経済的困窮や虐待などの家庭の問題を未然に防ぐ「予防型支援」の重要性が高まっています。当ゼミでは、夏休み合宿で先進的な取り組みのある施設を視察したり、定期的に地域の親子行事に関わったりと、支援を必要とする人々の視点に立って「当事者性」を養う一方、学校教育学科の学生を交えた議論や研究活動を通じて、科学的根拠に基づき支援を検討する「専門性」も培います。子どもだけでなく親や家庭にも目を向けて寄り添える保育者になってほしいと願っています。

EMURA SEMINAR
江村ゼミナール
- #幼児造形
- #陶芸
ものづくりの楽しさを、
子どもと一緒に味わおう。
「うまくできないから・・・」と、絵や工作に苦手意識を持つ学生は少なくありません。一方で子どもたちに目を向けると、上手に作ることよりも、できあがる過程に面白さを見出し、目を輝かせていることに気づくはずです。子どもの気持ちを知る一番の近道は、子どもと一緒に楽しむこと! ゼミでは地域の保育現場を訪れ、巨大バルーン遊び、粉から作る粘土遊びなど多様な活動を行います。大人の常識を超えた子どもの発想力に触れ、夢中で遊びに向き合う中で、子どもが「こうありたい」と憧れる大人の姿へと近づいてほしいと思います。