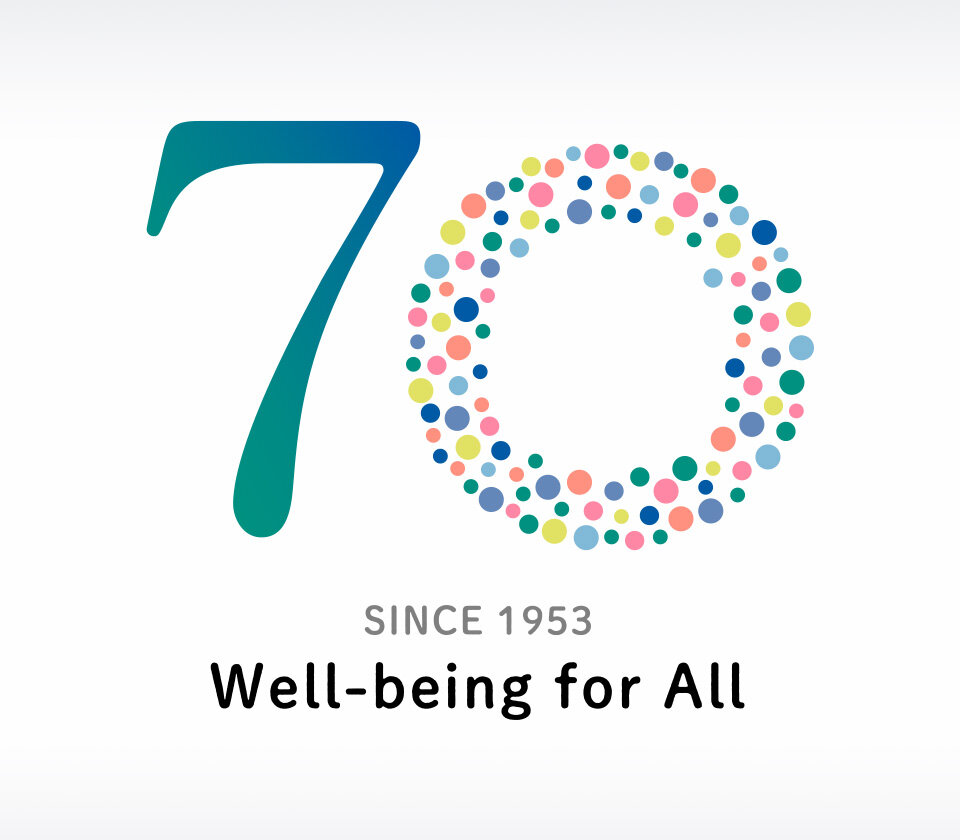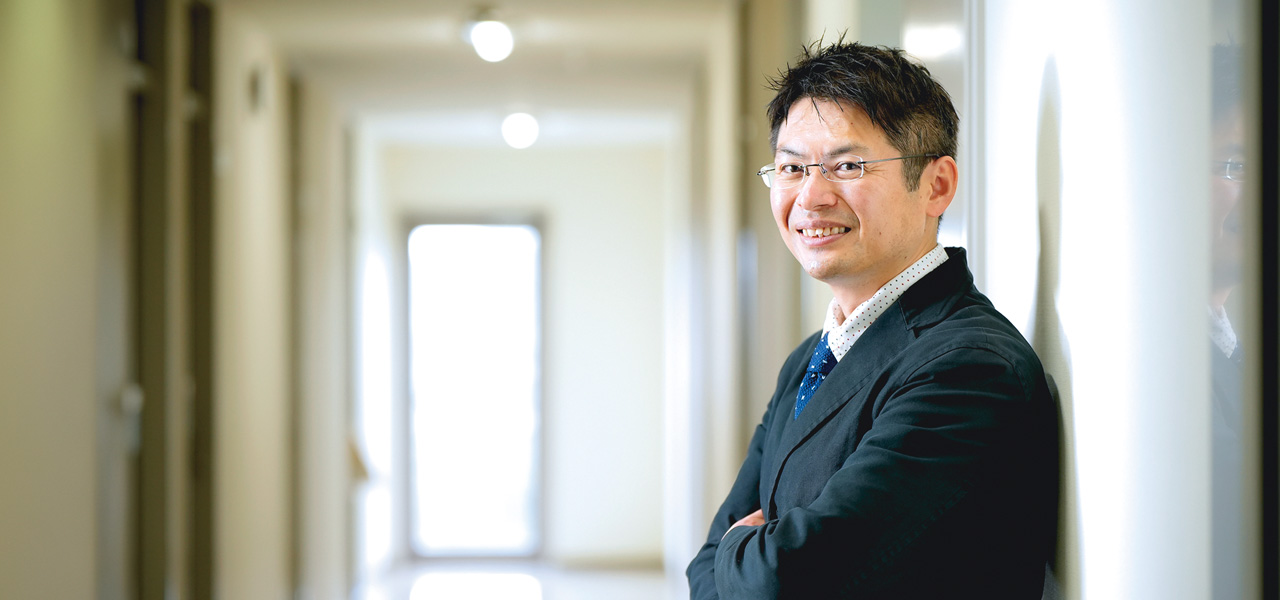履修プログラム
キャリアの可能性を広げる
履修プログラム
大きな広がりを持つ専門科目群を、履修プログラムにグループ化し、多彩な教員陣を配置しました。興味のあるプログラムを選んで学ぶことで体系的な知識が身につきます。また、複数プログラムから選ぶことで多面的な考え方が養われ、キャリアの可能性が広がります。プログラム選択に迷った時は、いつでも教員からアドバイスが受けられるので心配ありません。ここでは各プログラムの魅力を教員が紹介します。
プログラム選択の参考に
総合政策入門・現代社会入門
各専修の学びの全体像をつかみ、2年次後期からの履修プログラム選択のヒントを得る入門科目。複数教員によるリレー講義のほか、関連分野の職業人を招いて話を聞くことで、卒業後のキャリアを描くことができます。
就職活動にも活用できる
履修プログラム修了証を発行
各プログラムの中から一定以上の科目を選択履修した学生に修了証を発行します。体系的知識を身につけた証となり、就職活動でもアピールすることができます。
総合政策領域プログラム
公共政策

ふくしマインドを持った公共政策の担い手に。
「誰一人取り残さない社会」の実現に向け、貧困をなくす、ジェンダー平等、働きがいと経済成長の両立など、国や地方自治体がやるべきことは数多くあります。ここでは社会政策や経済政策といった具体的な政策手段のみならず、公共政策の基礎理論や社会正義の考え方、政策形成過程についても実践的に学び、ふくしのマインドと広い知識を持った公共政策の担い手を育てます。
主要科目
公共政策学、社会正義、行政学Ⅰ・Ⅱ、行政法、社会政策論
地域・まちづくり

現場で"気づき"、持続可能な社会を"築く"。
「書を携えて、地域に出よう!」。本プログラムが行うのは、大学内に閉じた学びでも、教員と学生という固定的なメンバーでの研究でもありません。まずは問題が起きている地域に出向き、五感を通じたフィールドワークによる"気づき"を得ます。その上で客観的・論理的な原因分析を行い、多様な地域主体との協働実践を展開。持続可能な地域社会の実現("築き")を展望します。
主要科目
政策形成実践特講Ⅰ・Ⅱ、福祉行政とまちづくり、SDGsとまちづくり
福祉行政
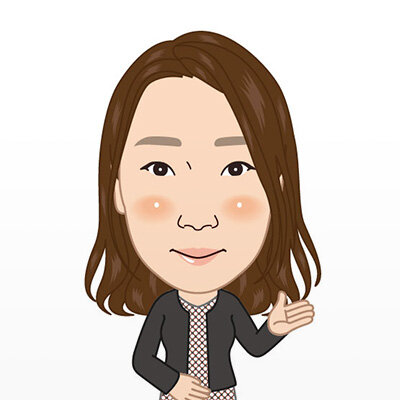
困難から人々を守る公務員福祉職を養成。
地方公共団体は、虐待・貧困など困難な状況にある子どもと大人の権利を最前線で守る役割があります。ソーシャルワーカーである公務員福祉職のニーズは高く、多くの卒業生が児童相談所や福祉事務所で活躍しています。ここでは社会福祉士資格を基盤に、面接技術や心理的支援も学び、自治体や社会福祉協議会の職員として人々の安全と安心に貢献する人をめざします。
主要科目
トラウマインフォームド実践論、心理療法、社会保障論
司法福祉

福祉の視点で司法領域の課題を解決。
犯罪や非行からの立ち直りに向けて社会はどうあるべきか、財産トラブルが片づいた後の生活支援はどうすべきかなど、法的な問題の背景にある社会的課題を福祉の視点で考えます。講義やゼミのほか、裁判傍聴や少年院の見学なども実施。法務教官・家庭裁判所調査官・保護観察官・法律事務所で働くソーシャルワーカーなど、福祉の視点を活かして司法領域で働く人材を育てます。
主要科目
司法福祉論、権利擁護を支える法制度、福祉法学(刑事政策)
ふくし社会創造領域プログラム
ダイバーシティ・インクルージョン
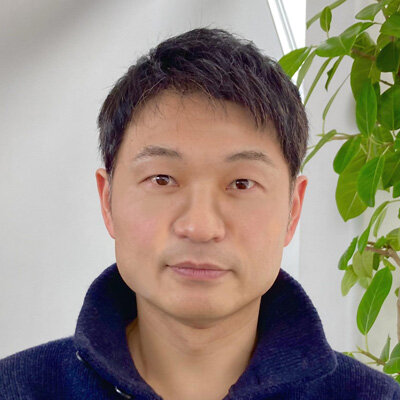
違いを尊重し合える社会をつくり出す。
多様性(ダイバーシティ)はさまざまな分野で用いられる用語ですが、社会福祉では人間の多様性(ヒューマン・ダイバーシティ)に着目します。本プログラムでは、他者との違いを理由に起こる攻撃や排除、差別や偏見に対し、問題解決のための理念や方法を学習。異なる視点や経験を尊重・共感する能力を獲得し、社会にインクルーシブな環境をつくり出す人材をめざします。
主要科目
ダイバーシティとソーシャルワーク、ディスアビリティ・スタディーズ、ジェンダー論
ソーシャルデザイン

社会を変えるための多様な手法を獲得。
ソーシャルデザインとは、まさに「社会を変える」ことをめざすプログラムです。そのためには、まず何が社会の課題となっているのかを見定めることが必要です。地域の中で支援を求められない「声なき声」を丁寧に聞き取るアプローチもあれば、データサイエンスを駆使して社会の現状を読み解くアプローチもあります。社会課題を解決する多様な手法をみんなで学びましょう。
主要科目
比較福祉国家論、福祉NPO論、社会企業論、地域福祉論Ⅱ
こども・教育領域プログラム
ユース・スクールソーシャルワーク
こどもと若者のみらいを支える実践力を。
社会福祉学部が、子ども・若者の権利を守り保障する人材を育てる革新的なプログラムをスタート! スクールソーシャルワーカーとユースワーカーをめざす学生に、専門性と実践力を習得するチャンスが広がります。多様な背景を持つ子ども・若者に対し、教育・福祉・地域が一丸となって支援をし、一人ひとりの可能性を引き出すことをめざします。子ども・若者の未来とイマを支えるプロフェッショナルを、日本福祉大学から。
主要科目
スクールソーシャルワーク論、ユースワーク
若者と社会をつなぐ「ユースワーカー」

ユースワーカーとは、若者と向き合い、信頼関係を築きながら可能性を引き出す人材です。多分野と連携し、若者が自分の生活や人生に関するあらゆることを意思決定(参画)できるように支援し、権利を保障します。最も大事なことは、あらゆる活動や機会で、若者と共に(by youth, with youth, for youth)あることです。
福祉教員

高校生にふくしの魅力を伝える教員に。
主に福祉系の学科・コース等のある高校で、ふくしを教える教員を養成するプログラムです。高校生にふくしの知識・技術、価値を魅力を持って伝えられるように、「ふくしを自分の言葉で語る方法」や「多様な人と関わる態度」、「生徒とともに学ぶ姿勢」を身につけます。本プログラムで学んだことを、教員をはじめ、ふくしを伝える多様な仕事に活かしてほしいと思っています。
主要科目
ふくしと教育・学習、福祉教育論、生涯学習論、福祉科教育法
こども家庭ソーシャルワーク

子どもの権利を大切にする支援者を育成。
子どもの権利を尊重しようという動きが活発になる一方で、子育て不安、児童虐待、貧困、不登校、ヤングケアラーなど、子どもと家族を取り巻く福祉課題がなくなることはありません。このプログラムでは、児童相談所、市の子育て相談課、施設、NPO法人などさまざまなところで求められている、子ど家庭福祉の理念・知識・技術を持ったソーシャルワーカーを育成します。
主要科目
子ども家庭ソーシャルワーク論、社会的養護、子どもの保健、子どもの貧困と居場所
こころとからだ領域プログラム
心理カウンセリング

心理と福祉の両方に強い支援者をめざそう。
カウンセラーかソーシャルワーカーか迷ったら、福祉心理士の資格が取得できるこのプログラムです。「なぜ人はそんなことをするの?」「つらい気持ちに寄り添う方法は?」そんな想いに応えます。性格や行動の特徴、生涯にわたる発達、人間関係におけるつらさ、虐待等によるトラウマといった問題を詳しく学び、こころのケアができるソーシャルワーカーになりましょう!
主要科目
臨床心理学、老年心理学、障害者心理学、カウンセリング(心理相談)、心理療法
医療ソーシャルワーク

患者さんや家族が抱える困難の解決を支援。
本学は長年にわたり医療ソーシャルワーカー(MSW)を育成・輩出してきた伝統校です。医療機関における社会福祉の専門職であり、患者さんや家族が抱える不安や困難の解決のために知識や技術を身につけるとともに、多様な人の人生に接することで自分自身も成長できる仕事です。ここではMSWの仕事内容や多職種・他機関との連携方法を学び、専門職としての自己を確立します。
主要科目
医療福祉論Ⅰ・Ⅱ、保健社会学
精神保健福祉
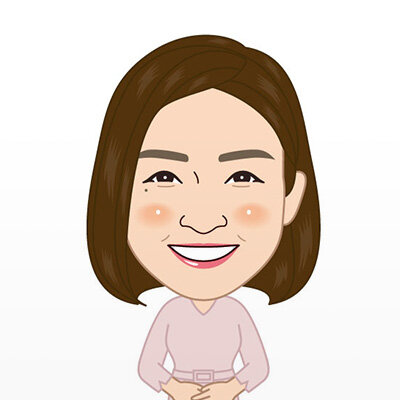
こころの悩みを抱える人の課題解決を支える。
精神保健福祉士は、こころの悩みを抱える人々に寄り添い、支援するやりがいのある仕事です。このプログラムでは、社会福祉や心理学を深く学び、相談支援の技術を身につけ、精神科病院や福祉施設、行政機関などでの活躍をめざします。人のこころに触れ、社会に貢献したい方にぴったりの学びができます。一緒に、こころがゆたかになる社会をつくっていきましょう!
主要科目
精神保健福祉論、精神保健学、精神保健領域のソーシャルワーク
ヒューマンケア
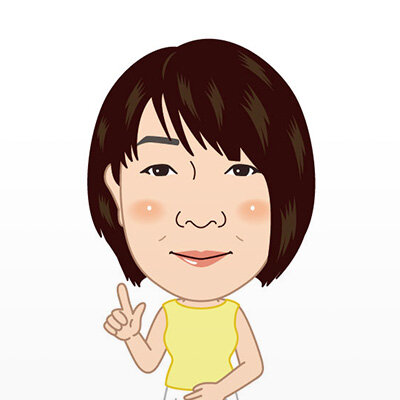
個人と地域を大きな視点でケアする専門職に。
生きづらさを抱える人や家族をケアする「個別支援力」と、地域に働きかける「地域支援力」。社会福祉の専門職に求められる2つの力を得るために、介護だけではない大きな概念として「ケア」を捉え、生活支援・相談支援、多職種連携・地域連携の実践力を養います。包括支援センター等の相談機関や、高齢者・障害者福祉事業所等における中核的人材の養成をめざします。
主要科目
ヒューマンケア論、介護福祉論、チームマネジメント論