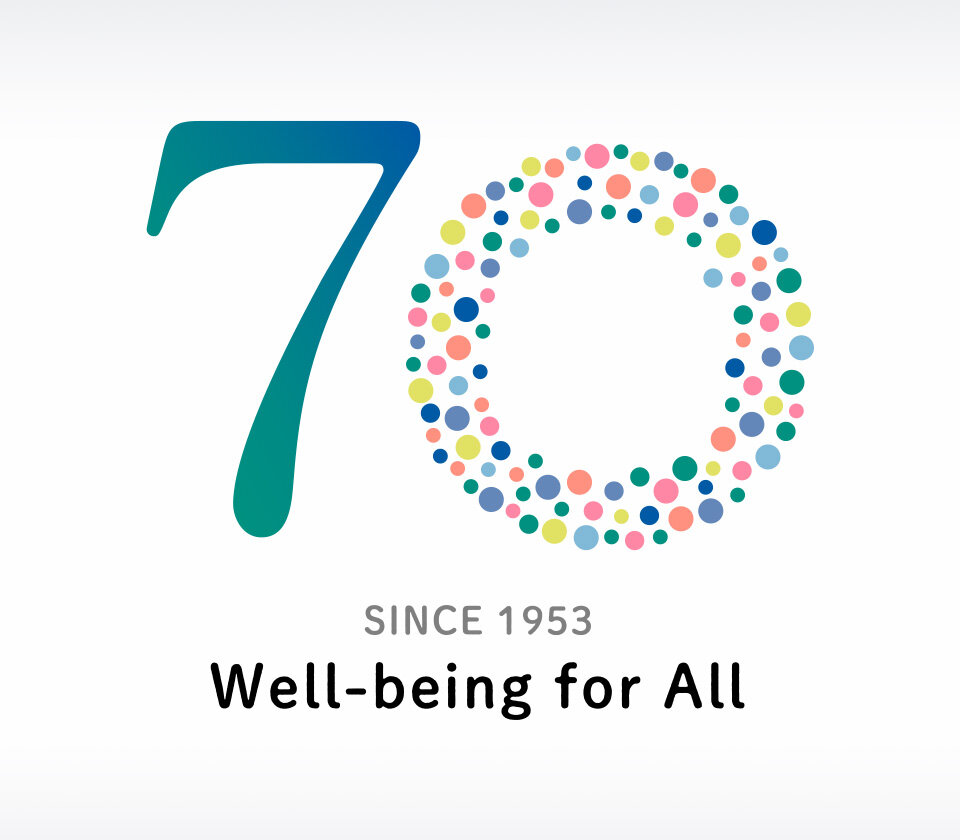学園・大学案内 お知らせ
トップページ 学園・大学案内 学園・大学案内 お知らせ 電動カート導入でポジティブ感情が増加し要介護リスクが低下 ~健康社会研究センターが1年間の縦断調査で確認~
電動カート導入でポジティブ感情が増加し要介護リスクが低下 ~健康社会研究センターが1年間の縦断調査で確認~
日本福祉大学健康社会研究センターの斉藤雅茂教授、渡邉良太客員研究所員、福定正城主任研究員らの研究グループは、千葉大学予防医学センターの小林周平特任研究員、井手一茂特任助教、近藤克則特任教授らと共同で、大阪府河内長野市および奈良県王寺町に在住する65歳以上の住民726人を対象に調査を行いました。その結果、電動カートをきっかけに「楽しみ」「明るい気持ち」「生きがい」といったポジティブ感情が増加した高齢者は、1年後に要介護リスクが低下することが明らかになりました。
研究の背景
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、移動手段の確保が欠かせません。公共交通機関の利用が難しい地域では外出機会が減少し、身体機能の低下や孤立感が要介護リスクを高める要因となります。近年、国土交通省が推進する「グリーンスローモビリティ(電動カート)」は、移動支援に加え、外出や社会参加の促進、ポジティブな感情の向上といった心理社会的効果も期待されています。本研究は、電動カート導入後1年間の変化を追い、その効果を検証したものです。
研究の方法
調査は2022年7~8月に電動カートの運行を開始した両自治体で実施。65歳以上の住民に対し、電動カート導入前と1年後の2回、自記式郵送調査を行いました。要介護リスクの評価には「要支援・要介護リスク評価尺度(48点満点)」を用い、併せて「楽しみが増えた」「気持ちが明るくなった」「生きがいを感じた」といった主観的指標の変化を調査しました。
研究の成果
運行が継続していた王寺町の高齢者のうち、ポジティブ感情が増加した人々は、そうでない人に比べて1年後の要介護リスク点数が低い傾向を示しました。さらに、このリスク点数の差を介護給付費に換算すると、6年間で最大約140万円の費用削減につながる可能性があることも示されました。
今後の展望
本研究により、電動カートが単なる移動支援手段にとどまらず、介護予防に寄与する可能性が確認されました。日本福祉大学は今後も、地域における移動支援と介護予防のあり方について研究を進め、持続可能な地域福祉の実現に貢献してまいります。