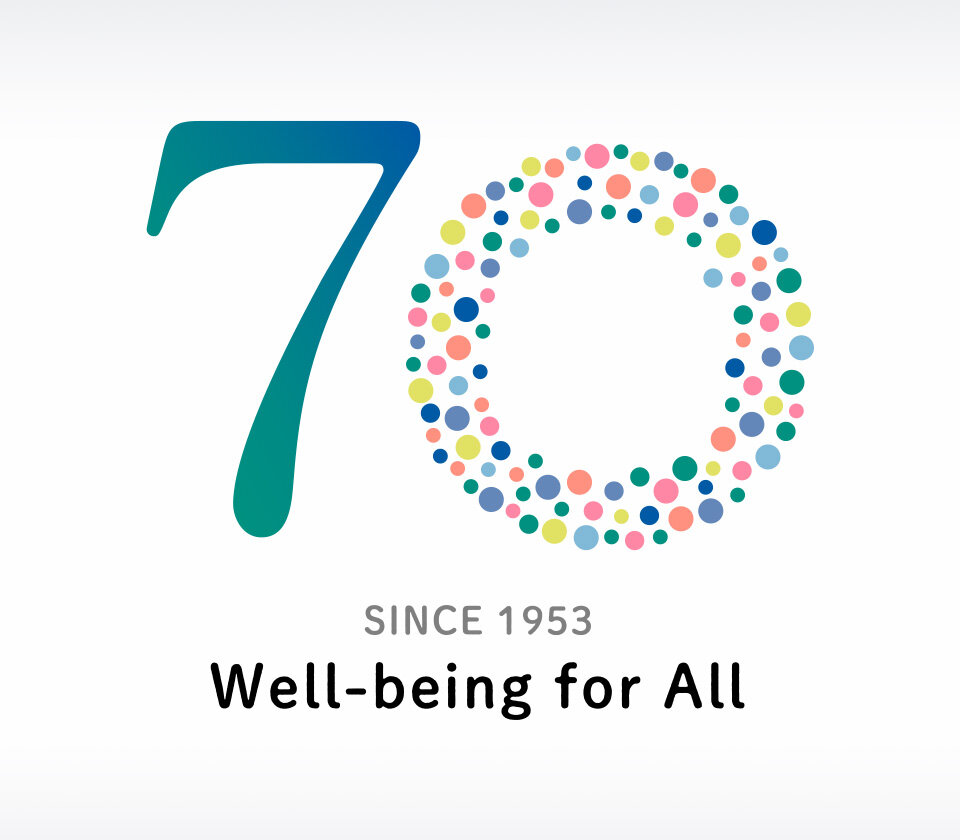各学部の留学・海外渡航プログラム(国際学部/国際福祉開発学部)
トップページ グローバル 各学部の留学・海外渡航プログラム 各学部の留学・海外渡航プログラム(国際学部/国際福祉開発学部)
国際学部/国際福祉開発学部では1年次に「国際フィールドワークⅠ」でフィールドワークの基礎を学んだ後、2年次以降は学生自身の関心に応じて、国内外で様々な活動を行っています。
特に2年次の11月頃~3年次の5月末頃までの約半年間は、ゼミや教職課程科目以外の配当学年科目を配置しない「アクティブラーニング期間」とし、学生の国内外での長期活動(フィールドワーク、インターンシップ、ボランティア)を促進しています。
これは自分を成長させるための期間であり、学生は以下に紹介する「国際フィールドワークⅡ~Ⅵ」や「グローバルフィールドインターンシップⅠ・Ⅱ」などの単位認定制度を活用して自らの学びを深め、卒業論文の執筆やキャリア形成につなげています。
国際フィールドワークⅠ

現地学生のサポートのもとで多様な現場を訪問して調査・研究を行い、個人旅行では難しいフィールドワークならではの体験をしています。人々の生活やものの見方・考え方の違いに気づき、学生自身や日本社会の課題・問題を見つめ直す機会にもなります。

2023年度
フィリピン人のマインドセット

佐々木心優 さん
農村でのフィールドワークでは、先住民族のアエタ族を訪問しました。ここでもとても親切に接してくれました。「私達アエタ族は、肌の色や文化が違っても人に優しくできるということを知ってもらうため」と、見知らぬ私たちを温かく迎えてくれました。誰の子どもであっても関係なく、みんなで力を合わせて育児をする姿、民族のために遠く離れた大学に通っている姿など、お手本にしなければいけない姿がたくさんありました。
これらの体験を通して、フィリピンの人のやさしさの根っこは「つらさを知っているから人にやさしくできる」だと考えました。
人に与える余裕なんてないという考えだった私に、フィリピンの人達が心の優しさを教えてくれました。自分を優先するのではなく、「周りの人とともに」ということを心に留めて行動したいと思うようになりました。この感謝の気持ちを、これから関わる多くの人に還元していきたいです。
国際フィールドワークⅡ~Ⅵ
「国際フィールドワークⅡ~Ⅵ」は、1年次の「国際フィールドワークⅠ」の経験を踏まえ、2年次以降により具体的なテーマを持ちフィールドワーク(一週間以上)に臨むものです。フィールドワークの実践を通して、グローバルな現場や多文化共生社会で協働するための知見・スキルを獲得します。
海外に限らず、国内でのフィールドも対象です。
参加者が自ら研修・調査計画を立て、現地にて計画に基づいたフィールドワークを行い、終了後には研修成果として報告書を作成します(成果を審査の上、単位認定されます)。
これまで、ベトナムの日本語学校での日本語教育実践を通じた日本語教育の現状・課題調査、北欧での環境問題の解決に向けた取組状況調査、福島県での伝統農業と地域復興の在り方調査など、様々な国・地域でフィールドワークを実施しています。
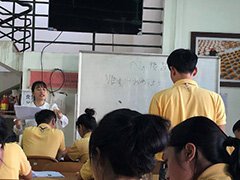

グローバル就業実践Ⅰ・Ⅱ
国内外の企業や福祉開発現場における就業体験(10日間以上)を通じて、国際社会における日本の文化や経済を再認識します。自己開拓したインターンシップ先での活動を行い、その成果を報告書にまとめます(成果を審査の上、単位認定されます)。
海外進出企業、外国人旅行者を対象とする旅行代理店やホテル、国際ボランティアや在日外国人向けの活動を行っている団体などがインターンシップ先として想定され、これまで、障害者支援センターでの支援体験、フィリピンの児童養護施設での施設運営補助などを行っています。