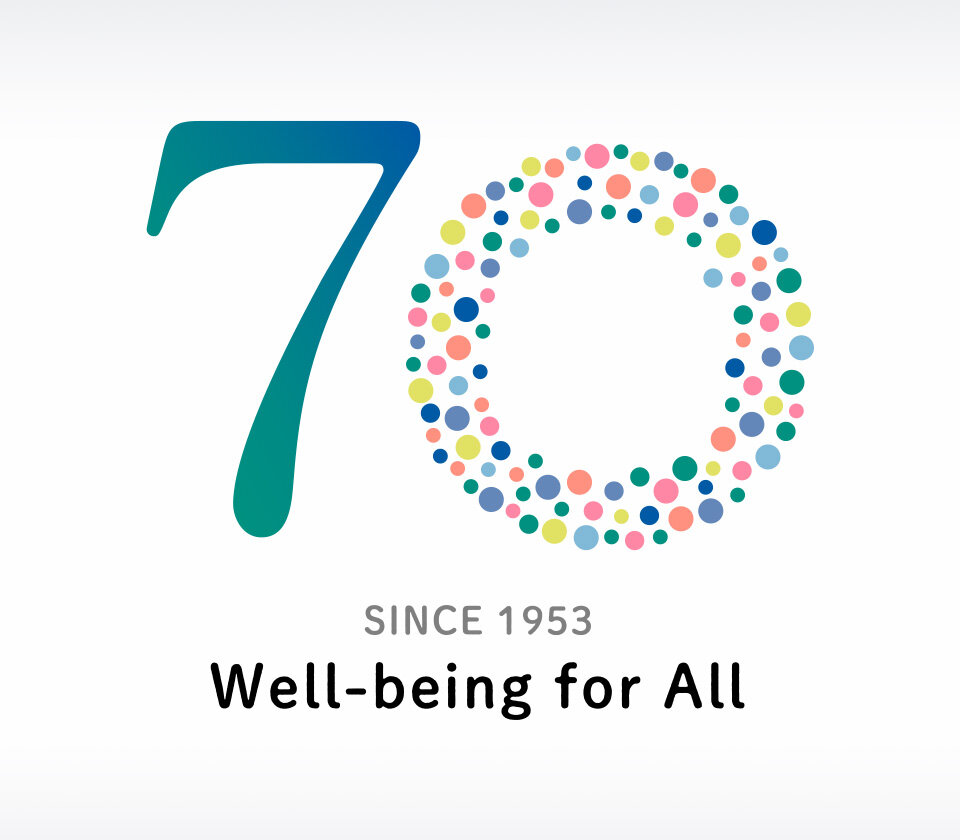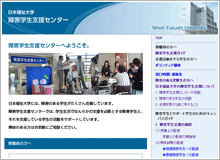健康管理・学生相談
すべての学生が安心して学べる環境づくり
日本福祉大学では、バリアフリー施設・設備の拡充はもちろん、障害のある学生をサポートする学生支援センター、心のケアを行う学生相談室の設置など、すべての人が学びやすいキャンパスづくりに取り組んでいます。
学生相談室
あなたの学生生活を、健康で充実したものにできるようにと願いを込めて、学生相談の窓口はとびらを開いています。
たとえば、こんなことで悩んでいる時、
相談室のとびらをノックしてみませんか
心身の健康に関する悩み
- 夜、眠れない。朝、起きるのがつらい
- 一人で下宿に居るのが怖い
- 気持ちが落ち込んでいつも晴れない、いつもイライラする
学業に関する悩み
- 大学で学ぶ意味がわからなくなってきた
- 勉強はきらいじゃないのにやる気がでない
- 人前では緊張してしまってグループワークや実習が不安
- 授業になかなか参加できない
進路に関する悩み
- 就職できるのかどうか心配
- やりたいことが見つからない
- 将来について考えたい
学生生活全般に関する悩み
- 初めてのひとり暮らしで落ち着かない
- ちゃんと食事をとれない
- ついついゲームやネットを見てしまって昼夜逆転生活
- 友達や周りの人とのトラブル、対人関係に関すること
- 自分のことや友人、家族のことに関する悩み
- 経済的なことを相談したい
- アルバイト先、サークル、ボランティア先でのトラブル
- 性に関する悩みや考え方を聴いてほしい
- ストーカーやDV、消費者問題やしつこい勧誘について相談したい
家族のことや友達のことで心配な事がある
- 友人や家族、パートナーの事で相談したい
- 心配な学生の事で相談したい
学生相談室はこんなところ
- いわゆる大学生活に関わることの「よろず相談」窓口です。学生支援相談員(臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・特別支援教諭等の資格を持つスタッフ)が相談に応じます。
- 悩みをお聴きすることによって、一緒に解決方法を考えます。担当の相談員と、相談の目標について話し合ってください。
- 相談内容によっては、必要な支援を行うために、学内外の関係機関を紹介することもあります。
- 医療との連携について
ご相談される内容に関連して病院を受診されている、または受診されていたことがある場合は、主治医の承諾と指示が必要になります(例:眠れない、気持ちが滅入るなど、精神保健上のご相談にかかりつけの医師がいる場合)。主治医の承諾が得られない場合は学生相談室でのご相談をお受けできない場合があります。
学生相談室の開室時間と予約方法
学生相談室では、学内での相談と「日本福祉大学こころのホットライン(学外相談)」による相談が可能です。
学内での相談
- 開室時間は月曜日~金曜日10:00~17:00です。土日祝日、キャンパス閉鎖期間中は閉室します。
- 電話相談やメールによる継続的な相談は行っていません。相談予約のみの取り扱いとなります。
- 面接時間は50分です。
- 相談は予約制です。ご自身が所属しているキャンパスの窓口までご予約、ご相談ください(方法は下記参照)。
- 継続相談を希望する場合は、初回相談の担当者にお申し出ください。予約状況によってはお待ちいただくこともあります。
- 継続相談の方で4回以上、ご連絡なくキャンセルが続いた場合は、担当の相談員からご連絡をさせていただきます。
ご連絡が取れない場合は、やむを得ず予約枠を取り消す場合があります。 - 相談を中止、終了したい場合は、担当の相談員までご連絡をください。
日本福祉大学 こころのホットライン(学外相談)
学外の業者が提供しているカウンセリングサービスを無料で利用できます。
相談内容は、ご本人の許可なく大学に知らされることはありません。
匿名での相談も可能です。
保護者の方も利用できます。
- 電話相談は、9:00~22:00年中無休・予約不要です。1回あたり20分を目安として利用できます。
- スポットカウンセリング(Web)は、24時間・年中無休・予約不要です。
- 継続カウンセリング(対面・電話・オンライン)は年5回まで利用可能です。
詳しい利用方法は、下記リンクからチラシをご覧ください。
利用可能期間:2024年4月1日から2025年3月31日まで
各キャンパスの学生相談室と予約方法
美浜キャンパス
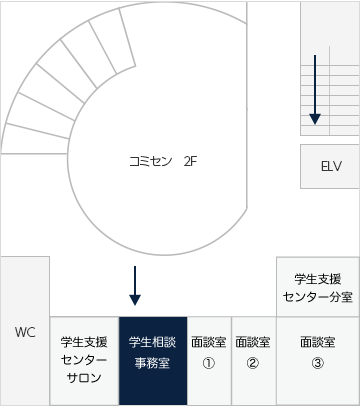
美浜キャンパス 学生相談室
電話番号:0569-87-2394(相談室)
〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田11号館(コミュニティセンター)2階
予約・連絡方法
予約メールアドレス
(※大学のメールアドレスを使って、①学籍番号、②氏名、③連絡先、④希望日と希望時間帯、⑤ご相談の簡単な内容、を明記してください。)
gakuseisoudan-mihama@ml.n-fukushi.ac.jp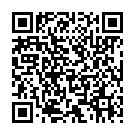
美浜キャンパスグループ活動(場所:11号館2階学生支援センターサロン)
- こころの休憩所
- ひだまりランチ会
※どの活動も祝日はお休みです。
半田キャンパス
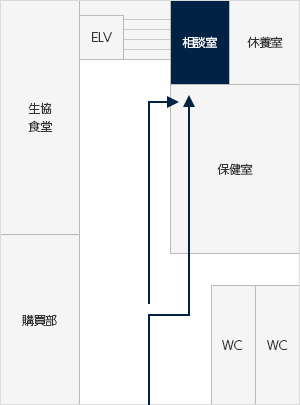
半田キャンパス PS室
電話番号:0569-20-0116
〒475-0012 愛知県半田市東生見町26-2 コミュニティーセンター棟1階
保健室内(別室)
予約・連絡方法
予約メールアドレス
(※大学のメールアドレスを使って、①学籍番号、②氏名、③連絡先、④希望日と希望時間帯、⑤ご相談の簡単な内容、を明記してください。)
gakuseisoudan-handa@ml.n-fukushi.ac.jp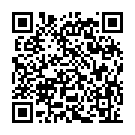
東海キャンパス
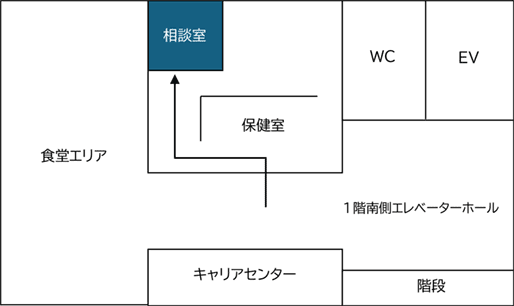
東海キャンパス 学生相談室
電話番号:0562-39-3811(代表)※予約はメールでお願いします。
〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田1071番地 中央部5階 C510
予約・連絡方法
予約メールアドレス
(※大学のメールアドレスを使って、①学籍番号、②氏名、③連絡先、④希望日と希望時間帯、⑤ご相談の簡単な内容、を明記してください。)
gakuseisoudan-toukai@ml.n-fukushi.ac.jp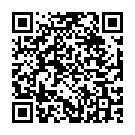
保健室
皆さんの健康を守り、病気の予防・健康の保持促進のため様々な援助相談活動を行っています。
大学生になったことを機会に「自分のからだの健康を自分の手で守っていく」自覚や能力を身につけましょう。
保健室開室時間
美浜キャンパス(コミュニティセンター1F)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 講義期間平日 | 9:30~11:30 | 月・火・水 12:30~18:30 木 12:30~17:00 金 12:30~18:30 |
| 講義期間土曜 | 9:30~16:00 | |
※講義期間外は別途掲示いたします。
電話番号:0569-87-2358
半田キャンパス(コミュニティセンター棟1F)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 講義期間平日 | 10:00~11:40 | 12:40~17:00 |
| 講義期間土曜 | 10:00~13:00 | |
電話番号:0569-20-0132
東海キャンパス(南ウイング1F)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 講義期間平日 | 10:00~11:40 | 12:40~17:00 |
| 講義期間土曜 | 10:00~17:00 ※講義日、補講日、行事のみ |
|
電話番号:0562-39-3815
保健室の活動
| 定期健康診断 | 学校保健安全法に基づき、毎年3月~4月に実施。実習、就職等の健康診断書を発行するためには健康診断を受診する必要があります。 健康診断の結果はnfu.jpのサブメニュー「健康管理」から確認できます。詳細は「健康管理ポータルサイト利用案内」をご覧ください。 |
|---|---|
| 予防接種関連 |
感染症抗体検査の結果はnfu.jpのサブメニュー「健康管理」から確認できます。詳細は「健康管理ポータルサイト利用案内」をご覧ください。 感染症抗体検査の結果で「陰性」となっている場合は以下の手順で早めに予防接種を受けて下さい。
*治療中やアレルギー等で予防接種を受けるのが心配な方は、各自担当医にご相談ください。予防接種ができないと判断された場合は、保健室までお知らせください。 【予防接種済証明書】 美浜キャンパス 半田キャンパス 東海キャンパス |
| 健康相談 | ・健康上の相談、医療機関の紹介等 |
| ・学校医による相談(美浜キャンパスのみ) ※日程等詳細は美浜保健室にお尋ね下さい。 |
|
| 傷病の応急手当 | ケガや病気の応急手当、医療機関の紹介 |
| 検査 | 尿、血圧検査、視力測定など |
学内外における大学が認めた課外活動中に発生した事故 、および大学施設内の事故に対して援助をしています 。
※但し、学生教育研究災害傷害保険の支払い対象となる場合は援助がありません。
- 援助の内容
医療機関を受診した際の初診治療費本人負担額を援助します。(補助金額上限あり) - 手続き方法
申請用紙は保健室にあります。
申請用紙に領収書の原本を添えて申請してください。 - 申請窓口
保健室
申請は、受診から速やかに行ってください。(前年度分の申請はできません)
学生教育研究災害傷害保険(Aタイプ、通学特約あり)
入学手続き時に全員が加入している保険です。
正課時間中・学内外での課外活動中、通学途中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害をおった場合に保険金が支払われる制度です。
- 援助の内容
詳細は『学生教育研究災害傷害保険のしおり』(入学時オリエンテーション 配布資料)のとおりです。 - 手続方法
事故の日から30日以内に"事故の通知"をし、その後保険金の請求手続きをします。 - 申請窓口
保健室
※この保険の有効期限は、通常の在学年限(4年間)です。
留年などの事情により在学年限を超す場合、新たに超過した年数分の保険料を納付する必要があります。
学生支援センター
美浜キャンパスの総合コミュニティセンター1階にある学生支援センターは、障害学生のサポートをコーディネートする総合窓口です。必要な支援・援助を障害学生と一緒に考えて、ボランティアの募集・養成・支援コーディネートを担っています。ボランティアに興味のある学生は、ぜひ学生支援センターにおこしください。
学生支援センターの主な取り組み内容
- 障害のある学生の学生生活上の具体的な困難への支援・援助
- 障害のある学生支援に携わるサポート学生の募集・養成および派遣のコーディネート
- キャンパスバリアフリーに向けた施設・設備の点検と整備改善
- ボランティア講座(要約筆記・生活介助・手話等)の開講
- 地域や関係団体との連携、他大学、諸機関との情報交換・経験交流の推進 など