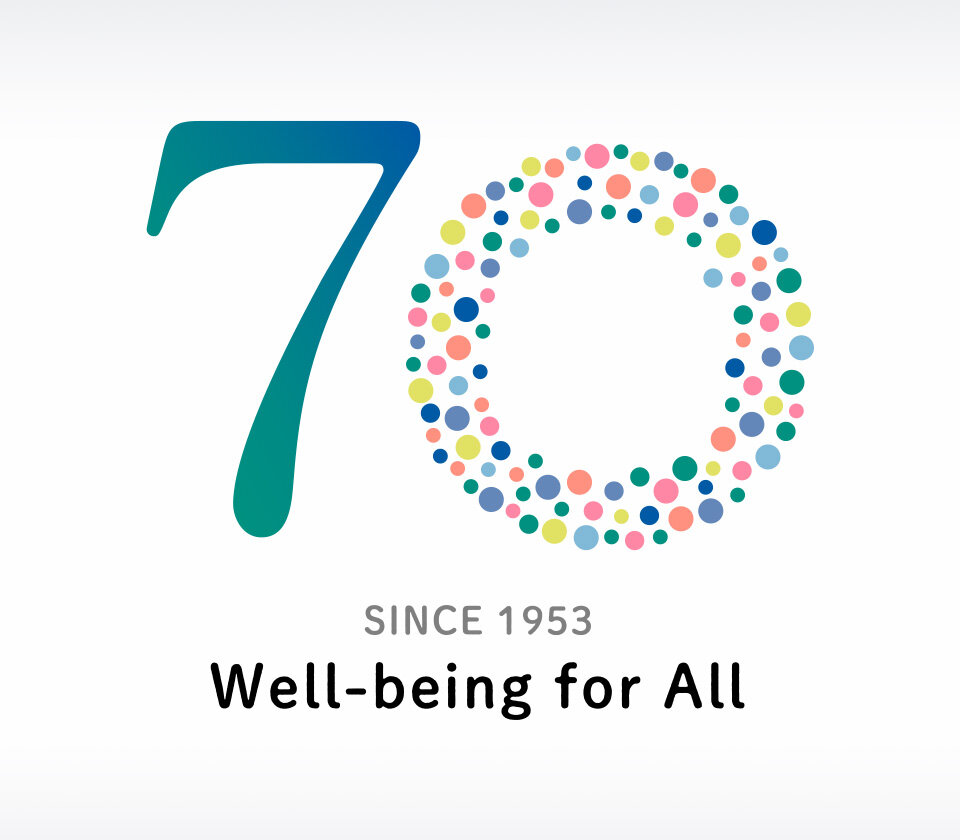学園・大学案内 お知らせ
トップページ 学園・大学案内 学園・大学案内 お知らせ 【理学療法×建築 クリニック設計プロジェクトのご報告】設計プロセス最終回
【理学療法×建築 クリニック設計プロジェクトのご報告】設計プロセス最終回
知多郡阿久比町に新たに開設される整形外科の設計に向けて、健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻の浅井教授研究室の学生と、福祉工学科建築バリアフリー専修(2025年4月より工学部工学科建築学専修)の村井准教授研究室の学生が連携し、空間づくりに取り組む横断型のプロジェクトが進行しています。
8月6日、半田キャンパスにて第4回ワークショップが実施され、今回はプロジェクトの設計を担当しているTSCアーキテクツの田中建築士が登壇。学生たちに向けて、現在の設計図面やCGによる動画を用いながら、最新の設計内容について丁寧に説明が行われました。
田中氏は、「30歳になるまでに、現場を知る経験をたくさん積んでおくことが大切。構造や素材の仕組みなど、理論だけでなく現実を知ることで提案に説得力が生まれる」と、建築士としての実感を込めて学生たちに語りました。


実際に学生たちは、内装・サイン・外構のプランを検討してきましたが、「自分の考えた案が採用されていて嬉しい」「設計の意図や想いを伝えることの重要性に気づけた」などの感想が寄せられ、机上の学びとは異なるリアルなプロジェクト体験を通じて、多くの気づきを得た様子がうかがえました。


田中氏はまた、「図面上の一本の線が、実際に人の暮らしに関わる建物になっていく。その責任の重さと、完成したときのやりがいは建築の魅力そのもの」と語り、建築業界を志す学生たちにエールを送りました。
さらに、整形外科で診療を行う予定の服部医師からは、理学療法学専攻の学生たちに対し、「これから在宅療養が増える中で、患者のみなさんがどのような環境で生活しているのかを知ることが重要になる」とコメント。在宅支援を担う専門職として、住環境や建築との接点を持つことの意義が改めて確認されました。


教員からのコメント
健康科学部 リハビリテーション学科理学療法学専攻 浅井教授
これからの理学療法士を目ざす学生たちにとって、本プロジェクトは、治療技術だけでなく、施設管理の視点から患者様が治療を受けやすい導線設計やリスク管理への気づきを学ぶ機会となりました。
さらに、退院後の住宅改修等においても建築構造の知識は他職種との連携に役立つものであり、企画段階から関わることで視野を広げ、職業人としての創造力も養われていくと考えています。
健康科学部福祉工学科 建築バリアフリー専修 村井准教授
今回のプロジェクトは、学生にとって「なぜこのデザインなのか」という提案理由の大切さを実感する機会となりました。また、提案までに多くの検討や調整が必要であることも学べたと思います。
医療施設においては、使いやすさや心地よさに加え、医療を受けることへの信頼や安心感までも建築が担うべき重要な要素です。
建築は“使われて初めて成立する”ものです。理学療法士を目ざす学生との協働を通じて、建築士を目ざす学生たちは、建物が完成したその先を見据える意識や責任感を育む貴重な経験になったのではないかと思います。
今回のワークショップをもって、設計工程としての学生の提案活動は一区切りを迎えましたが、プロジェクトを通じて学生たちは、建築と医療、それぞれの専門分野の立場から実際の空間づくりに関わる貴重な機会を経験しました。学部の枠を越えて協働し、社会にある“現場”の声に触れることで、専門職としての視野を広げる実践型教育の一端が形となった取り組みです。
今後は、実際の建築現場の視察なども予定されており、学生たちの学びはさらに現場へとつながっていきます。