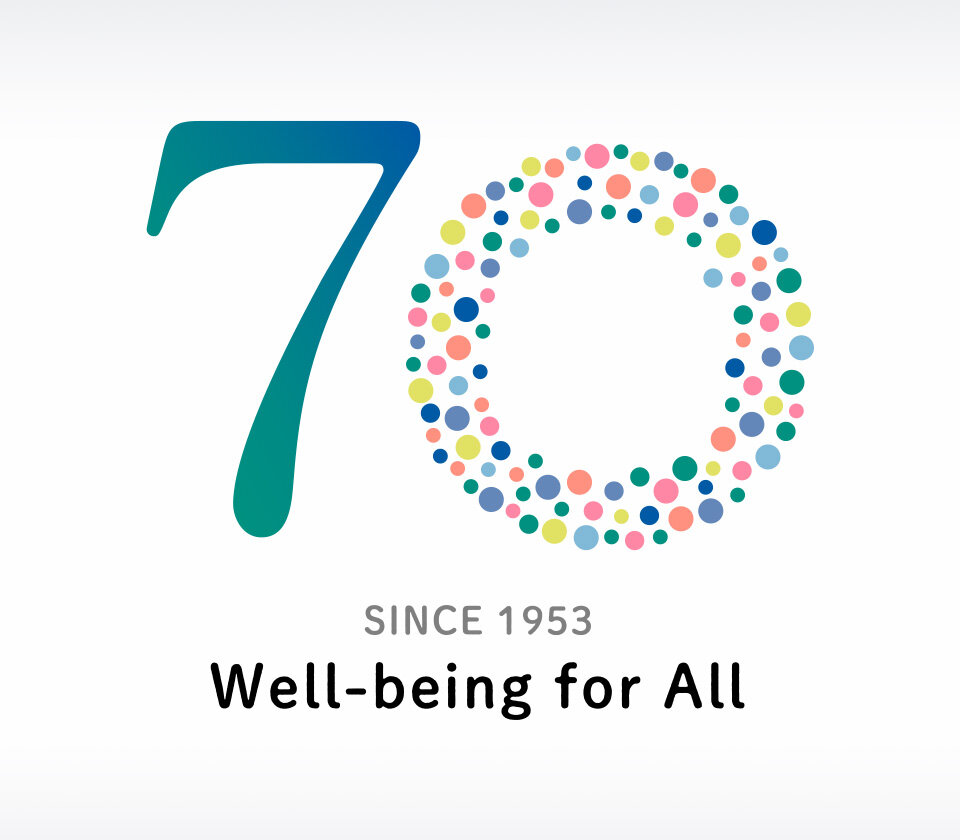学園・大学案内 お知らせ
トップページ 学園・大学案内 学園・大学案内 お知らせ 第18回 提携社会福祉法人サミットを開催しました
第18回 提携社会福祉法人サミットを開催しました
本学と全国各地の14の社会福祉法人は、それぞれが教育・研究と実践の事業交流を図ることで地域社会の発展や社会福祉の更なる充実に取り組んでいます。本年度からは、提携社会福祉法人運営協議会が発足し、政策の動向や、法人の経営、福祉人材の育成といった諸課題について相互に学び合う「提携社会福祉法人サミット」を開催しています。
2月22日(土)に開催した18回目となる今回は、「地域共生社会の実現に向けて 身寄りのない高齢者等が抱える課題への対応」と題して、政策動向勉強会を行い、14法人の関係者と本学関係者合わせて61名(対面45名・オンライン26名)が参加しました。
開会挨拶

開会に先立ち、原田正樹本学学長が挨拶を行いました。
「本学は通信教育部の開設に伴い、全国型の提携社会福祉法人のネットワークを構築し、2007年度にはじめてのサミットを開催しました。その後、2011年の東日本大震災で被災された仙台市社会福祉協議会の呼びかけによって被災地支援に関わらせていただいたことを契機として、法人間の連携の大切さを再認識することになりました。あわせて、社会福祉法人制度改革の議論から、法人と大学が如何に社会課題に向き合っていくかという課題を共有し、これからの社会福祉のあり方を共に学び、創出する機会としたい」と述べました。
基調講演
講師:日原知己厚生労働省社会・援護局長「地域共生社会の実現に向けて」

冒頭、厚生労働省が定めている「地域共生社会」の概念を改めて説明した上で、地域共生社会の在り方検討会議の趣旨や主な検討事項を説明。以下の3点について、検討会議の進捗や課題が報告されました。
①「地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応」
今後、急速に単身世帯が増加する予想が出ており、2050年には44.3%に達する見込みとなっている。頼れる「身寄り」がいることはもはや当たり前ではなく、「身寄り」がない事自体が第2のスタンダードであると考えて制度設計する必要がある。ごみ捨てや入院等、生前に困る日常から住居の権利やペットの行き先等、死後に至るまでの具体的な内容について、利用者が安心してサポートが受けられる体制(自治体・関係機関・事業者)の仕組みの確立が必要だとし、モデル事業の進捗状況の紹介がされました。
②「成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実」
認知症高齢者の増加に伴い、今後更に権利擁護支援ニーズが増加・多様化することを見据え、市町村が生活支援・意思決定支援に関与し、制度や事業にするための効果検証やモデル事業を進めている。具体的には、市町村や委託機関が中核機関として支援機能を持ち、家庭裁判所が制度運用・監督機能を果たし、NPO団体や社会福祉協議会等の各種機関が有機的につながるよう、地域で暮らす全ての人の生活を支えるというもの。国内外の動向も踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討を進めていくことが報告されました。
③「社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の地域共生社会の担い手としての役割」
社会福祉法人の地域における公益的な取り組みは、制度外サービスの創出や相談窓口の設置等、各地域において広がりを見せている。社会からの期待も高く、好事例集の作成を行い、一層促進していくことができるよう、働きかけている。
社会福祉連携推進法人制度は、2つ以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することを目的としている。ニーズ調査から現場での支援、他機関との連携まで行うことができるため、地域福祉が充実すると考えている事が述べられました。
最後に、「『地域共生社会』とは、制度の縦割りや支え手と受け手の関係、世代や分野を超えて住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会である。世帯の複合課題や制度の狭間、自ら相談に行く力がない方への支援体制の確立等、問題は多岐にわたるが、より良い社会を創るために協働していきたい」と講演を締めくくられました。
シンポジウム「身寄りのない高齢者等が抱える課題への対応」
シンポジウムに先立ち、本学の藤森教授による導入と課題提起が行われました。
コーディネーター:藤森克彦(本学福祉経営学部長)「国立社会保障・人口問題研究所の将来推計が示す未来」

日原知己厚生労働省社会・援護局長と重複する部分もあるが、1980年~2020年までの全世帯数に占める世帯類型別割合の実績値から2030年~2050年までを推計すると、単独世帯数は2倍以上に、夫婦のみの世帯は1.5倍となっており、身寄りのない世帯が急速に増加していることがわかる。「身寄り」の大きな問題は、これまで日本でよく見られた家族による「日常生活支援」、「身元保証」、「死後対応」の確保と、孤立する人の生きる意欲や自己肯定感が乏しいという点。この問題について、シンポジウム内で議論を重ねていきたいと述べました。
林祐介(本学社会福祉学部准教授)「病院・施設における保証人問題の現状と課題」

保証人問題とは、退・転院の際に、保証人や親族がおらず、手続きが困難になることを定義している。医療機関内でも成年後見制度の申し立てや身元保証等高齢者サポート事業につなげられないため、支障が生じている状況である。現時点では、問題解決はできていないが、医療ソーシャルワーカーの認識深化を含め、着実に改善に向けた取り組みが進んでいると感じている。しかしながら、既存の制度や社会資源だけでの問題解決は難しい。地域の中での支援ネットワーク構築や診療報酬の加算等、問題解決に向けた研究を進めていきたいと報告しました。
奥山智弘氏(青山里会 四日市市南地域包括支援センター長)「高齢者終活支援事業の活用」

身寄りがない人(家族の支援が得られない人を含む)は、入院や入所、死後事務の課題が発生し、支援が複雑化する。法人内で「施設が保証人に求める役割」を調査したところ、①緊急連絡先、②入退院手続き、③遺体遺品の引き取り、④利用料金の支払い保証、の4つが特に挙げられる結果となった。四日市市では、「高齢者終活支援事業」を行っており、終活全般の相談対応や啓発、必要時に必要情報を関係機関に提供する取り組みを進めている。「まだ運用にさまざまな課題はあるが、この取り組みを進めていきたい」と報告しました。
今井友乃氏(知多地域権利擁護支援センター理事長)「成年後見制度に限らないおひとりさま支援~互助会連動型くらしあんしんサポート事業~」

当法人は、NPO法人と社会福祉協議会の役割を兼ね備えており、①中核機関として、権利擁護支援に関する相談、啓発、②法人後見(処遇困難者を対象とした受任)を行っている。特におひとりさま当事者が抱えている不安や必要としていることを話し合う場「互助会」を重視しており、今活動の普及啓発を進めている。「『本人が中心』という基準を大切に、利用者の生活が窮屈にならないような支援を行っていきたい」と述べられました。
3名からの報告後、藤森克彦本学福祉経営学部長をコーディネーターとしてシンポジウムを開催しました。
今井氏は、「互助会を作った意味は、成年後見人という法律を介した関係性ではなく、普段から対等にやっていける「お互いさま」の関係づくりが重要と考えるからで、その仕組みには自助力の涵養が必要になる」と話されました。
奥山氏は、高齢者終活支援事業を始めるに至った経緯について「ご遺体の引き取り手の問題や遺物の整理など、いざとなった時、どこへ連絡し、どう支援をするかということがきっかけとなった。また生前、家族に納得のいく形で本人の意思を伝える手段としてもその役割がある。他方で、入院・入所時の対応に関して、行政や包括支援組織がどこまで役割を担えるかが大きな課題となっている。個々の事情に即した支援が求められることから、ケアマネーシャーは常に迷いの中で活動している」との現場からの意見を報告しました。これに関連し、林氏からは、「退院後の支援は、個々の医療ソーシャルワーカーの力量に依るところがある。踏み込んだ個別支援については、職場の理解も得られにくく、地域のネットワークの中核となる組織がある事が望ましい。」と応答がありました。また、身元保証団体の課題については、「現状で所管する省庁や行政が関与する仕組がなく、自治体の責任を明確化することや、入院や入所時に身元保証を求めないための具体的な手続きが必要である」と述べられました。
コメンテーターの日原氏からは「本日は地域共生社会の実現に向けた最新の研究や現場の事例をご報告いただいた。林氏の報告からは、身元保証には様々な要因が複合的に重なっており、医療機関や社会福祉施設が求めていることを一つひとつ明確にすることの重要性を再認識した。また、奥山氏の報告から親族がいることが前提の高齢者支援に関する制度設計は現状とのズレが大きくなってきている。利用者が判断能力を有している間に、行政が終活情報を登録したり、代理や代行が意志を汲み取り、死後にさまざまな手続きを行うことが重要であると学ぶことができました。
今井氏の報告では、成年後見制度を使用しても利用者の生活が窮屈にならない『ライフエンディング(おひとりさま)支援事業』の一環として行う『互助会』の取り組みをご報告いただいた。当事者同士で不安や必要としていることを話し合う場を設けることで、支援者にとっても求められる支援を確認できるようになる。安心して人生の最後を迎えることができる地域づくりの方策について共有できた」と述べ、シンポジウムをまとめられました。
閉会挨拶

提携社会福祉法人運営協議会幹事法人である、社会福祉法人甲山福祉センターの服部英司理事長より、政策動向勉強会閉会の挨拶がありました。
「本日は、地域共生社会の実現というテーマで講演と議論が行われました。このテーマは以前のサミットでも取り上げられましたが、その後、コロナ禍で社会が分断され、改めて地域共生社会のあり方を考える、時機を得たテーマでありました。厚生労働省の日原氏からは、現在の国の議論から、成年後見制度や身寄りのない高齢者の課題に焦点を当ててお話をいただき、その課題が良く分かりました。また、実践報告として、林氏から病院・施設における身元保証人の問題、奥山氏から高齢者の終活支援の実践例、今井氏から権利擁護センターという活動を越えて互助会を使った“おひとりさま支援”の実例が紹介され、これらの取り組みはまさに、地域共生社会を支えるものだと感じました。社会福祉法人が、今までのように制度に基づいた事業をしているだけではなく、地域福祉やその狭間にあるものに如何に取り組むか、社会福祉のセクターとしてその存在意義が問われており、地域共生社会の中でどう役割が果たせるかを深く考えてみたい」と述べられました。