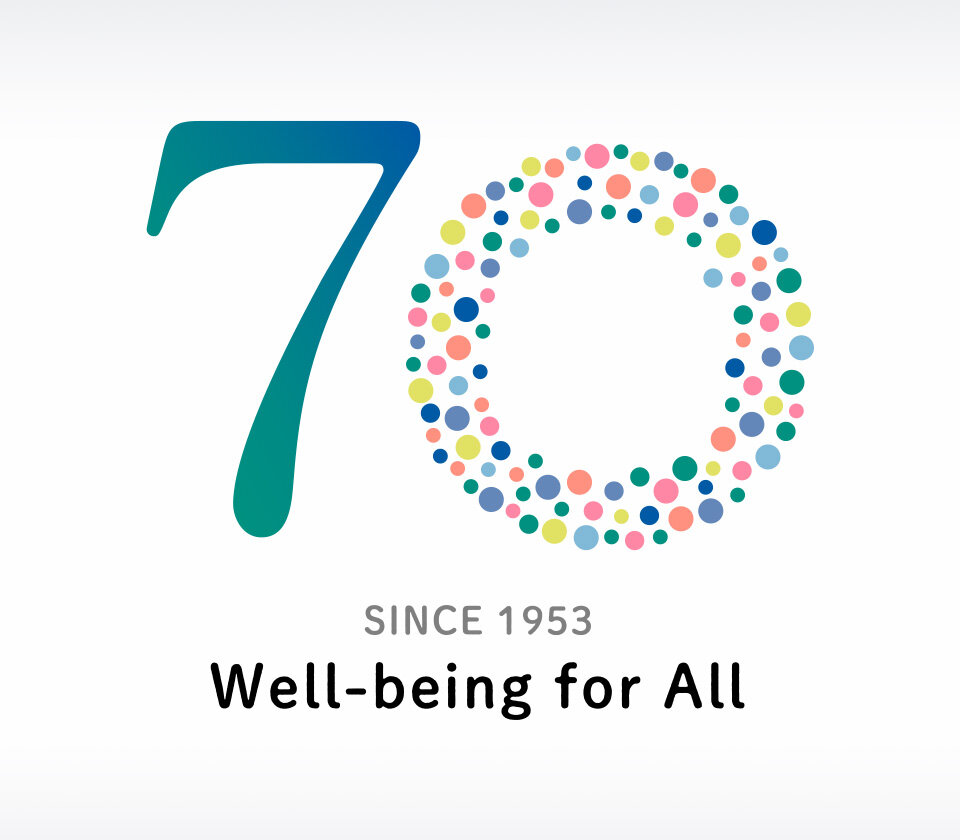学園・大学案内 お知らせ
トップページ 学園・大学案内 学園・大学案内 お知らせ 美浜町・美浜町社会福祉協議会共催事業「みんなの減災カレッジ2024」を実施しました
美浜町・美浜町社会福祉協議会共催事業「みんなの減災カレッジ2024」を実施しました
毎年、美浜町・美浜町社会福祉協議会では、町内の居住・就労・通学者を対象に、南海トラフ地震などの大規模地震に備え、地域の防災力向上と長期避難生活に伴う地域コミュニティの重要性を再認識することを目的に、「みんなの減災カレッジ」を実施しています。今回は「美浜キャンパス安全の日企画」として協力し、11月30日に講座を実施しました。
はじめに、美浜町社会福祉協議会の中西澄江主任専門員からオリエンテーションがあり、次に、家田知尚美浜町厚生部福祉課主査より、「要配慮者の防災支援~福祉課視点での災害対応に関する現状や課題~」と題し、ご講演いただきました。講演では、要配慮者の定義は、①高齢者、②障害者、③乳幼児、④その他の特に配慮を要するもの、と説明。その後、防災と福祉が連携する必要性が生じた事例として、西日本豪雨では死者51名のうち80%が要配慮者、東日本大震災では死者15,900名のうち65%以上が高齢者であったと紹介しました。「①自ら災害に対する備えとしての「自助」、②地域と助け合う「共助」、③公的機関が行う「公助」があるが、普段から実践できる「自助」と「共助」の姿勢を大切にしてほしい」と講演を締めくくられました。

続いて、野尻紀恵学長補佐、減災連携・支援機構長が、「減災に向けて~ふくし視点の避難生活~」と題して講演しました。冒頭、阪神淡路大震災に被災した際に感じた実体験をもとに、困ったことや家族との会話、当時勤めていた学校の先生や生徒の様子を話し、発災直後の「共助」の大切さを伝えました。その後、避難場所の種別や家族防災会議(安否の確認方法や避難場所の確認等)の重要性を説明。そして、「誰しもが支援者という立場から被災者になることもある。地域との関係づくりは大切だが、自分が困っていることを言語化し、周囲に助けを求めることも必要。災害は他人事ではないという姿勢を忘れないでほしい」と話しました。

昼食は、町や社会福祉協議会から提供されたアルファ米を水・お湯で作り、社会福祉協議会から提供された非常食の試食や、避難所を想定した炊き出しの配給が行われました。能登半島の復興を願い、美浜町で子ども食堂「ふぁみりー基地」を行う野尻ゼミ生の皆さんが石川名物「めった汁」を炊き出しし、参加者一同舌鼓を打ちました。
また、カセットガスボンベを使用できる炊飯器で炊いたご飯や、美浜町のつくだ煮が振舞われました。




昼食後、髙村秀史災害ボランティアセンター長による「避難生活リアル体験」を実施しました。はじめに、参加者は普段触ることができないダンボールベッドやテントに触ることで、避難生活へのイメージを深めました。


その後の講演では、被災時には、①自助、②近助(近くにいる他人との助け合い)、③共助、④公助、と大きく分けて4つの助け合い・支援が発生する。どれも大切なことだが、特に重要なのは「自助」で、これははただ生命活動をすることを指すのではなく、『よく生きる』(QOLの維持・向上)ことを意味する。被災によって身体的および肉体的な負担が増え、災害関連死につながるケースは非常に多いと話しました。
そして、「元気な大人が良かれと思って、子どもや高齢者に役割を与えないことで、本人たちが長期にわたって無力さを感じて気に病むケースがある。トイレの誘導や紙皿作成、ゴミ拾いなど、できる仕事はあるはず。共に生きる仲間として一緒に頑張ろうとする姿勢を大切にしてほしい」と話しました。

最後に、グループワークを行い、今回の学びや帰ってからすぐに実践すると誓った防災への意識を発表。参加者全員で意識共有を行いました。櫻井悟美浜町社会福祉協議会事務局長は、「3名の講師による防災意識を向上させるための講演を通して、被災時に支援者として関わるための引き出しを増やすことができた。自分だけでなく、家族や友人にもぜひ伝えていただき、『よく生きること』を大切にしていただきたい」と講評しました。



中西澄恵美浜町社会福祉協議会主任専門員は、「今回、会場である5階の大会議室に初めて入り、見晴らしのよさを感じた一方で、海が近いことで津波の危険性を感じた。先ほどのグループワークで発表した内容を実践することが、防災意識向上への第一歩になるので、ぜひ今後も災害は他人事だと思わず、防災備蓄や地域のつながりづくりに取り組んでほしい」と話し、本日の企画を締めくくられました。

参加した学生は、「冬の体育館の底冷えや防災用品の利便性を体感することができた。髙村秀史災害ボランティアセンター長の「よく生きる」という言葉の意味を再認識することもでき、満足感の高い企画だった。このような経験は非常時に活きてくると思うので、ぜひ次回も参加したい」と感想を述べました。