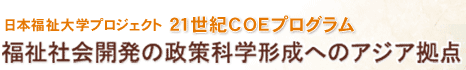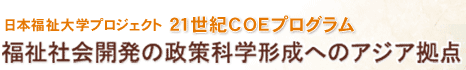|



 |
 |
リンク集 |


|
 |

  |
 |
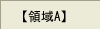 |
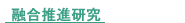 リーダー 平野隆之 リーダー 平野隆之 |
|
 |

| 本プロジェクトの追う美の要の役割を果たす。「福祉社会開発学の構築 |
| に向けての諸研究」を横断的に行うとともに、従来、複数地域を対象に |
| して行ってきた「日本の中山間地域の再生・福祉社旗開発研究」の統合、 |
| 国内およびアジア地域での「人材養成研究」の融合(手法・方法・研究 |
| 成果の共有化)をめざす、これにより福祉社会開発学の理論の精緻化を |
| 進めたい。 |
| |
|
| ● |
平野グループ |
| |
|
福祉社会開発学構築に向けての諸研究 |
| ● |
近藤・穂坂・原田グループ |
| |
|
愛知県・武豊町介護予防介入プロジェクト |
| ● |
野口・小松・原田グループ |
| |
|
山形県・最上町地域福祉研究 |
| ● |
牧野グループ |
| |
|
長野県における「健康地域づくり」研究 |
| ● |
穂坂グループ |
| |
|
東南・東アジアの人材養成研究 |
 |

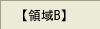 |
 リーダー 近藤克則 リーダー 近藤克則 |
|
 |

| 領域Bの「先進国の福祉政策評価研究」は、「政策評価」「健康の不平 |
| 等」「社会的排除」に関する研究の先進国であるイギリスと日本との比 |
| 較検証を通して、先進国における「福祉社会開発学」の要素・概念を明 |
| らかにすることを目的として推進されている。 |
| |
| ● |
木戸グループ |
| |
|
社会的排除研究 |
 |

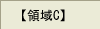 |
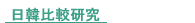 リーダー 二木立 リーダー 二木立 |
|
 |

| 研究の上半期に複数の研究分野にまたがっていた個別の日韓比較研究を |
| 再統合するとともに大幅に強化する。 |
| 4グループが連携しつつ、延世大学を中心とした韓国の諸大学、東京大 |
| 学を中心とした国内の諸大学の研究者と共同して、日韓の社会保障・社 |
| 会福祉の総合的比較研究を行っている。 |
| |
| ● |
野口・後藤グループ |
| |
|
日韓における福祉国家の形成・再編と福祉社会開発研究 |
| ● |
勅使グループ |
| |
|
保育・幼児教育と子育て支援の比較研究 |
| ● |
近藤グループ |
| |
|
高齢者ケアの日韓比較・敬老堂研究 |
| ● |
二木・野村グループ |
| |
|
保健医療福祉の統合システム |
 |

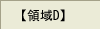 |
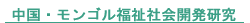 リーダー 野口定久 リーダー 野口定久 |
|
 |

| 本研究の基本的方向は、次の2点である。①本領域の研究推進の方法論 |
| は、地域福祉・居住福祉に収斂させる。②中国・モンゴル研究の成果を、 |
| 人材養成(都市計画・地域福祉計画、居住福祉のまちづくりの公共部門 |
| 及び民間部門のソーシャルプランナー、ソーシャルワーカー)のプログ |
| ラム開発及び教材開発に向けられている。 |
| |
| ● |
野口・児玉グループ |
| |
|
中国の福祉社会開発研究 |
| ● |
陳グループ |
| |
|
中国の高齢者福祉ならびに研究者養成研究 |
 |

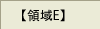 |
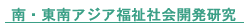 リーダー 穂坂光彦 リーダー 穂坂光彦 |
|
 |

| これまでE領域では、①福祉社会開発の基礎的分析枠組に関する理論研 |
| 究、②都市農村貧困層の生存戦略と支援政策に関する事例研究、③参加 |
| 型社会システムと評価に関する研究、④南・東南アジアとの比較におけ |
| る日本のNPO型福祉開発の研究、を行ってきた。 研究の経緯とこれから |
| の方向については、領域Eのページを参照されたい。 |
| |
| ● |
余語グループ |
| |
|
福祉社会開発の基礎的分析枠組に関する理論研究 |
| ● |
穂坂グループ |
| |
|
都市農村貧困層の生存戦略と支援政策に関する事例研究 |
| ● |
雨森グループ |
| |
|
フィリピンにおけるセーフティネット生成の研究ならびに日本のN
PO研究 |
 |

|

|