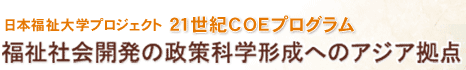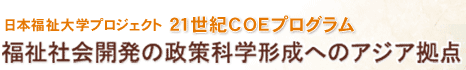|



 |
 |
リンク集 |


|
 |

 |
|
領域E 南・東南アジア福祉社会開発研究 |
| |
領域リーダー 穂坂光彦 |
|
|
 |
 |

 |
 |
| |
この領域の主眼は、住民主体の福祉メカニズムの形成と「地域」でそれを支える政策環境のありようについて、南・東南アジア(および対比的に日本、韓国)を中心とする個別研究を踏まえて理論化し、それらの比較の枠組みを提供することである。
2006年度の理論研究部門では、余語教授により地域社会の分析枠として「基層社会と統治機構」による類型が理論化され、これを基にしたグローバルな国際比較事例研究が進展した。またミジレイ客員教授とともに「生産的福祉」の概念分析を行い、この観点から韓国の「参与型福祉」政策を検討した。事例として韓国の「社会連帯銀行」の調査を実施し、同銀行との共同セミナーをソウルで開催した。
事例研究にあっては、以下の分野で、教員、COE主任研究員、同客員研究員、博士課程院生、研究協力者による各論的実証研究を進めた。
・自立運営型福祉と政策環境形成(マイクロ保険の生成、日本のNPOバンク、ホームレス起業)
・「開発と障害」の基礎研究(CBR、自助グループの比較、障害の「家族モデル」再検討)
・貧困と社会的排除(日韓の居住貧困、条件不利地域と「スラム」、コミュニティ組織化論)
・エンパワメントと社会開発(女性と農村開発、人身売買、複合差別、カーストと居住空間)
・参加型計画システム(人間安全保障と難民再定住、地方分権と参加、エイズ予防)
マイクロ保険の生成に関するスリランカ、タイ、フィリピンの事例調査を基に研究ワークショップを開催した。この成果はGrassroots Social Security: Mutual Associations, Micro Insurance and Social Welfare(仮題) として出版予定である。全COE主任研究員は客員研究員としてフィリピン大学に招聘され、東南アジアでのコミュニティ組織化方法論について韓国との比較研究を行った。久野COE客員研究員の論文CBR and Participation of Disabled Peopleに対してイーストアングリア大学から、また南COE研究協力者の「日本における住宅政策変化の特性に関する研究」に対してソウル大学校から、いずれも博士号が授与された。
アクションリサーチに着手し、近藤教授チームによる武豊町介護予防研究に本領域からも参加し、高齢者サロン形成の同時進行型プロセス評価に携わった。これは、これまで東南アジア人材養成領域においてフィリピン大学に対して支援してきた「参加型ビデオ手法」を適用したものである。また全COE主任研究員を中心に名古屋での新たなホームレス支援プログラムに関わり、自立経営型福祉の観点から考察を深めた。
最終年度には諸分野の中での「選択と集中」を行い、成果の出版に結びつける。また「福祉社会開発人材」養成の方法論確立や教材作成の面で力を注ぎたい。
|
|
 |
 |

|