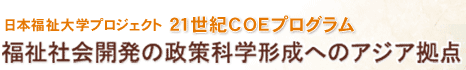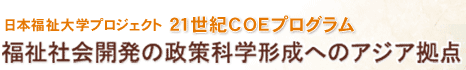|



 |
 |
リンク集 |


|
 |
本学の研究教育プロジェクト「福祉社会開発の政策科学形成へのアジア拠点」が、わが国の大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的とした文部科学省の2003年度「21世紀COEプログラム(社会科学分野)」に採択されてから、早や1年が経過しました。それの初年度の取り組み、2年度の研究計画を簡単に報告します。
本プロジェクトの目的と全体像
その前に、本プロジェクトの目的と全体像を簡単に説明します。本プロジェクトの目的を一言で述べますと、本学の大学院社会福祉学研究科が蓄積してきた先進国の高齢者ケアを中心とする福祉分野の政策科学・評価研究と、本学の大学院国際社会開発研究科が蓄積してきた発展途上国の貧困地域の参加型社会開発研究とを融合・統合して、「福祉社会開発学」とでも呼ぶべき新しい学問領域を創出し、本学を中心にその「アジア拠点」を形成することです。
この目的を達成するために、次の5分野の研究を推進しています。①高齢者ケアの政策科学形成、②日本の中山間地における地域ケア、福祉社会開発モデル研究、③東南・南アジアにおける福祉社会開発の方法論的研究、④東アジア福祉社会開発研究、⑤保健医療福祉の統合システムの研究。これらの研究の多くは、本学と学術交流協定を結んでいる中国・南京大学、韓国・延世大学校をはじめ、フィリピン国立大学、モンゴル国立大学、イギリス・マンチェスター大学等と共同で行っています。合わせて、「福祉社会開発学」に係わる国内外の専門職・準専門職の養成、研修教育のためのプログラムを設けています。
本プロジェクトは、本学の教員だけで約42人(うち「事業推進担当者」10人)、他大学の教員、本学の大学院生・研究員を加えると総勢70人以上が参加する、本学史上最大規模の研究教育プロジェクトです。なお、社会福祉学領域で21世紀COEプログラムに採択されたのは本学だけであり、この意味では本プロジェクトは、社会福祉学領域で史上最大の研究教育プロジェクトとも言えます。
初年度の取り組み
21世紀COEプログラム採択の初年度は、上記5分野の個別研究を精力的にすすめました。
あわせて本プロジェクトでは、各分野の研究を統合した「社会福祉開発学」を確立するために、毎月開催しているCOE推進委員会で、それぞれの分野の責任者の「問題提起(話題提供)」に基づく自由討論を継続しました。従来は、本学のような中規模大学でも、研究領域・所属学部の枠を超えた共同研究を継続することは困難でしたが、COEプログラム採択を機会に、一気に大規模な学際的研究が進んでいます。それにより、従来ほとんど接点のなかった、福祉分野の政策科学・評価研究と参加型社会開発研究との間に、研究視点・方法論上予想外の共通点があることが確認され、両者を統合・融合した「福祉社会開発学」確立の見通しが立ちました。
さらに本研究プロジェクトでは研究成果の社会還元を重視しており、初年度は以下の2回のシンポジウムを開催しました。1つは昨年11月28日に開催した「COE採択記念国際シンポジウム-福祉社会開発:コミュニティー支援への政策科学の形成」、もう1つは本年2月28日に開催した「21世紀COEプログラム日本福祉大学2003年度シンポジウム-福祉社会開発の政策科学形成に向けて」です。
第2年度の課題
第2年度は、初年度に引き続き、5つの分野の個別研究を旺盛に進めるとともに、「福祉社会開発学」の形成の視点から、それらの統合と集中を進めます。
第2年度は、特に研究成果の出版を重視し、以下の12冊の研究書を出版する予定です(順不同、書名は一部仮題)。①『福祉社会開発学の構築』、②『「医療費抑制の時代」の時代を超えて-イギリスの医療福祉改革』(近藤克則著。第1分野)、③『フィードバック型介護保険プロジェクト』(第1分野)、④『在宅終末期ケア-全国訪問看護ステーション調査』(第1分野)、⑤『中山間地域における福祉社会開発モデル研究』(第2分野)、⑥『居住福祉学の構築-地域再生の論理』(第2分野)、⑦~⑨『社会開発事例の国際比較(理論編・事例分析編)』(第3分野。英文。全6冊で2004年度中に3冊出版)、⑩『日本と韓国の福祉国家の再編と福祉社会の開発』(第4分野)、⑪『日中韓の居住福祉』(第4分野)、⑫『医療福祉経営の課題』(第5分野)。
さらに第2年度には、以下の2つの国際シンポジウムの開催が決定しています。①「高齢者ケアの政策評価の日英比較シンポジウム」(9月)、②「日本・中国・韓国における子育ての社会的支援と子どもの権利保障の現状と課題」(10月)。 今後とも、本プロジェクトへのご支援・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 |

|