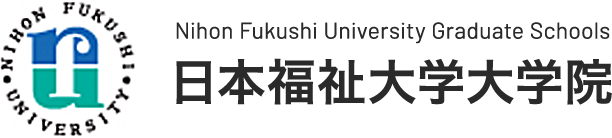- 吉野 真紀(よしの まき)教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ
心理学研究法特論
臨床面接特論Ⅱ - キーワード
- 体験的心理療法、臨床心理アセスメント、ロールシャッハ・テスト、精神科病院臨床、性別違和
- 自己紹介
- クライエントが未完の出来事を完結し、自分自身の物語を生成し自己を生きていく過程に関心を抱き、人間性心理学的な立場から体験的心理療法の臨床実践に取り組むとともに研究テーマとしています。医療・教育・産業分野において、心理療法および心理アセスメントに携わり事例研究を続けながら、現在は性別違和のある方々の心理的特徴についてロールシャッハ・テスト等を用いた研究を行っています。
- 早川 すみ江(はやかわ すみえ)教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ
臨床心理査定演習Ⅱ
心理学研究法特論
投影法特論 - キーワード
- 精神分析的心理療法、転移・逆転移、ロールシャッハ・テスト、精神力動
- 自己紹介
- ロールシャッハ・テストと精神分析的心理療法について関心があります。精神分析的心理療法の実践を行いながら、心理療法過程の中での精神力動との関係や、心理療法過程の中で起きる転移・逆転移やクライアント-セラピスト間の交流のあり方などについて、事例研究を行っています。またロールシャッハ・テスト上にあらわれる力動的特徴が心理療法の中でどのようにあらわれるかということにも関心があります。
- 瀬地山 葉矢(せちやま はや)准教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ
発達臨床心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) - キーワード
- 関係性の発達、親子の相互作用観察、アタッチメント、セラピストークライエント関係、臨床心理学的介入
- 自己紹介
- 親と乳幼児の相互観察を通じて、個人内体験と対人関係体験との間にどのような相互循環過程が展開していくのか、またその相互過程の中身が個の人格発達、自己理解にどのように結びついていくのかをみていきたいと思っています。こうした対人関係を基盤にして起こる自己理解の過程は、心理療法におけるセラピストークライアント関係の理解や両者の交流を基盤とした自己物語生成にも通じる問題だと考えています。
- 福元 理英(ふくもと りえ)准教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ
心理学研究法特論 - キーワード
- 発達障害、学習障害、アセスメント
- 自己紹介
- 発達障害児とその保護者への支援に関心があり、具体的な支援内容・方法に関する研究に取り組んでいます。最近は、子どもの学習・生活における困難についてアセスメントし、学校の先生方や保護者と連携して、その子に合った支援を行い、環境を整えていく方法について検討しています。こういった取り組みを通して、人と人との関わりのなかで、互いに育ち合っていく過程について学んでいきたいと思っています。
- 堀 美和子(ほり みわこ)准教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ
心理学研究法特論
発達臨床心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) - キーワード
- 自閉症スペクトラム障害、発達支援、プレイセラピー
- 自己紹介
- 主に小児の心理的発達やその適応に関心を持って研究および臨床に取り組んでいます。最近は発達障害を持つ方々やご家族、学校や園の先生との臨床上のお付き合いが多くなっていますが、そうしたかかわりの中から、私たちが日ごろ「あたりまえ」だと感じていることが実はとても貴重で得がたいものだと実感させられています。また、お子さんが心理的な問題として示していることは、実際にはご家族全体や親御さんのSOSを代わりに表現していることがあります。ですから小児の臨床とはお子さんを持つおとなの方の臨床でもあり、小児期の未解決な問題をもった青年期のかたがたの臨床でもあります。その奥深さに日々、身が引き締まる思いでいます。現在、大学の相談室だけでなく小児科や小学校・園、NPOなど様々な場所で臨床を行っていますが、それぞれの場でこれからも多くの方々と出会って行きたいと思っています。
- 髙橋 蔵人(たかはし くらと)教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
臨床心理基礎実習
臨床心理実習Ⅱ
臨床心理学特論
心理療法特論 - キーワード
- 心理療法、カウンセリング、精神科医療臨床、児童養護施設臨床
- 自己紹介
- 精神科医療現場を中心に児童養護施設、企業内相談室でも臨床実践を積み重ねてきました。学派や臨床領域によって変わることのない心理臨床の基本、とくにフロイトの「真実性Wahrhaftigkeit」、ロジャーズの「無条件の肯定的配慮unconditioned positive regards」と言った概念に関心があり、それらの心理臨床実践におけるあり方について考えています。また、それらの基本をしっかりと身につけた心理臨床家を養成したいと思っています。
- 小松原 智子(こまつばら ともこ)准教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
臨床心理基礎実習
臨床心理実習Ⅱ
臨床心理学特論
臨床心理面接特論Ⅰ
心理療法特論
心の健康教育特論 - キーワード
- 体験過程、フォーカシング、芸術療法、産業臨床・メンタルヘルス、スクールカウンセリング
- 自己紹介
- 関係の中で生きている人の「経験」が、その人のあり方や発達にどのように影響を与えているのか、どのように変容していくのかというプロセスに関心を持っています。その人のあり方が表出されている語りや描画等の理解を、体験過程を大切にするフォーカシングを活かしながら考えています。臨床活動領域は医療・産業・教育・司法で、ここでの臨床事例を研究に活かしています。現在は児童養護施設に関わる人の支援にも関わりを持っています。
- 辻野 達也(つじの たつや)准教授
- 担当科目
- 臨床心理実習Ⅰ-①②③④⑤(心理実践実習)
臨床心理基礎実習
臨床心理実習Ⅱ
臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践)
教育臨床心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開)
心理療法特論 - キーワード
- 深層心理学、風土臨床、臨床人間学、学校臨床
- 自己紹介
- これまで主に教育と医療の領域で分析心理学(ユング心理学)をオリエンテーションに心理臨床の実践を行ってきました。医療領域では甲状腺疾患の治療や口腔癌の緩和ケア、教育領域ではスクールカウンセラーや学校危機への支援や被災地支援の実践および研究に取り組んできました。また、風土臨床という概念を提唱し、沖縄での祭事や聖地のフィールドワークを行い、風土とひとのこころの関連について研究しています。
※修士論文の指導は、担当科目欄に「心理臨床研究演習Ⅰ・Ⅱ」が記載されている教員が担当します。