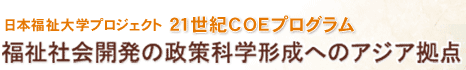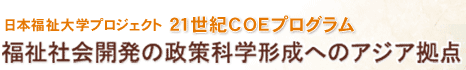|



 |
 |
リンク集 |


|
 |
| 第5分野の事業推進者は二木立教授であるが、拠点リーダーでもあるため、現状としては、共同研究者野村秀和教授を研究グループリーダーとして活動を進めている。野村グループは、協同組合福祉に研究の焦点を絞り、各協同組合組織との連携や支援を得て、地域福祉を組合員(住民)サイドから構築していくという「福祉コミュニティ」のモデル構想を研究している。メンバーは、本学教員4名、社会人院生2名、他大学等3名の9名でこの他他グループの3名の研究協力者で構成している。 |
 |
| 本研究は、協同組合等による地域ケア統合システムの現状調査とそれが現在抱えている課題を明らかにすることにより、地域医療・福祉の担い手としての協同組合等の今後果たすべき役割を研究することにある。協同組合は、組合員によって組織されており、地域との結びつきが強い。それぞれの協同組合は、設立趣旨に基づいた事業を行っており、その事業の特性がそれぞれの協同組合の性格を特徴付ける。既に、一定の発展を遂げ、社会的信認も厚く、高齢化社会の到来の中で、本体事業の他に福祉助け合い活動から福祉事業に乗り出す単協も登場してきた。JAには厚生連という病院経営を担う組織がある。生協には医療部会があり、病院・診療所などによる医療活動に従事している。このように、主要協同組合組織には、医療分野が存在する。 |
 |
| JA、日本生協連、医療生協、労働者協同組合などの全国連合会や県連、有力単協への訪問調査を行い、資料収集(経営情報を含む)を行う。研究ティームメンバーは、会計専攻の研究者を主力としている特徴を活かし、経営データによるマネジメントの解析や経営管理に関する分析を実施する。 |
 |
| 日常的な住民の医療・福祉ニーズに応えていくには、地域特性を踏まえる必要がある。協同組合は、組合員組織を媒介にして地域との結びつきが強い。しかも、共同の助け合い活動の経験を持ち、地域の貧困層の組織化にも役割を果たしている。行政や医療機関が、サプライサイドからの医療・福祉を志向するのに対し、協同組合組織は、医療・福祉の受け手として、クライアントそしてその家族さらに地域住民の自主的な参加組織である。コミュニティからの視点で、福祉社会形成を検討する場合、きわめて重要な役割を担うことになる。さらに、医療保険や介護保険の制度改訂により、負担が強まり、受診抑制が進んでいる。そのため、事業者収入は低下し、厳しい経営状態にある。経営データによるマネジメント視点からの調査は、事業の展望を探る上で貴重である。また、2003年3月には、第1回の協同組合福祉フォーラムを名古屋で開催した。現在第2回のフォーラムを千葉で開催する準備を進めている。この取組みは、COE以前からのものであるが、協同組合福祉の研究にとって不可欠の取り組みである。JAから労働者協同組合までを、全国規模で横断的に組織している。 |
 |
| 協同組合では、医療生協が、アジアでの国際交流の事務局を担っている。アジア太平洋地域保健協同組合協議会(APHCO)の理事会やセミナーが開かれている。この面で、アジア拠点形成に側面から寄与できるかもしれない。 |
|
 |


大学院
情報・経営開発研究科
教授
野村秀和 |


社会福祉学部長
教授
二木 立 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| (執筆:野村秀和) |

|