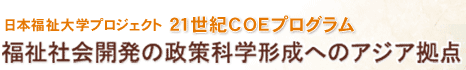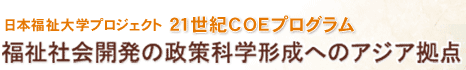|



 |
 |
リンク集 |


|
 |
この分野では、主として東南アジア・南アジアの発展途上国における参加型地域社会開発の視点から、地域の福祉向上へのアプローチを考究する。
途上国の社会開発が直面している最大の課題は、人々を民族紛争や環境破壊へと追いやる貧困を解決し、誰もが明日を信じて安心して暮らすことのできる「人間の安全保障」を、政策的に、確保することである。国レベルの経済成長が市場を通じて自動的に国民全体に福祉をもたらす、とする開発戦略は、すでに過去のものとなった。
そこで私たちが対象とするのは「福祉社会開発」の可能性である。それは、人々の力を剥奪している制度的社会的バリアを取り除くことを通じて、貧しく排除されていた人々も含め諸個人が共同的な生活能力を開花させ、市場や行政を利用し変容させながら自らの福祉を向上させる、そうしたことを可能とする地域社会の意識的・政策的な形成、を意味する。そこでは、多様な組織・関係・制度を自ら創り出すような地域社会の展開を、政策としてどのように支えるべきか、施策や制度のあり方、それらの変化のあり方、に注目することになる。
こうした「福祉社会開発の政策科学」樹立を目的に、この分野では以下の三種類の活動を推進する。 |
 |
「地域自治としての福祉」の理論的基礎を「資源の移転機能」に求め、世界各地の農村開発事例を一般化して、資源の動員水準から見た地域社会の類型化を行う。「資源・組織・規範」や「組織化の利益と費用」といった主要な概念装置は、すでに援助機関に広く採用されるところとなっているが、この理論の創始者でありCOE事業推進者の余語トシヒロ教授と世界5ヶ国の国際社会開発研究科在外教授らを中心に、本格的な国際比較研究を通じ、社会開発の分析枠を提供する基礎理論を国際的に確立する。
それとともに、ジェームズ・ミジレイ客員教授(COE事業推進者)による「社会福祉と開発研究の統合としての社会開発」理論を深化させ、ニーズへの事後的一方的対応でなく、人々のケイパビリティ拡大(Sen)の条件を整える投資としての福祉政策の枠組みを、世界各地の事例を蓄積しつつ掘り下げる。
これに関連して、アジアの都市農村の貧困をマクロに規定する現代のグローバル化の動向と、その背景にある国際援助機関の開発戦略の変化を、詳細に把握する。 |
 |
「障害と開発」が大きな知的実践的領域として台頭しているが、その焦点となる「地域に根ざすリハビリテーション(CBR)」は、アプローチの多様化、諸概念の変容、地域の経済レベルの分化、多様な障害への注目など、さまざまな要素があいまって、とくに東南アジアでは岐路に立っている。これらを理論的に整理し、各地の現場の実態に則して課題を汲み上げ、CBRの新しい政策展望を導くとともに、実践的な教育研修の拠点を形成する。
またグローバル化による生活の脆弱化に対応する「住民の生存戦略」としてアジアの都市貧困地域に展開しつつある住民主導型セイフティネットを対象に、その共同資源の形成や運用のメカニズムを比較調査する。とりわけ対応する行政施策のスタイルないし外部機関の役割に注目し、多様な主体の形成と相互作用を通じて政策と政策環境が最適化の方向へ変容していく、そのプロセスを主たる対象とする「非ブループリント」型政策科学の樹立を目指す。 |
 |
手法レベルでのPLA(参加型調査法)、住民ワークショップ、参加型都市計画フレームワーク、住民工事契約制度等について、それらの意義をあらためて参加型開発理論のなかで位置づけ、理論と実践のギャップを特定し、参加型手法の洗練強化を推進する。これらを通じて、本学を、参加型計画の理論化に携わる高度専門家養成と開発現場の準専門家養成のための拠点とする。
またCOE連携拠点校であるフィリピン大学社会福祉コミュニティ開発学部におけるソーシャルワーカー・開発ワーカー専門教育の体系化に協力し、とくに準専門家向け研修プログラムを支援して、近隣諸国に対する拠点性を高める。 |
|
 |


大学院
国際社会開発研究科
教授
穂坂光彦 |


大学院
国際社会開発研究科
研究科長・教授
余語トシヒロ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| (執筆:穂坂光彦) |

|