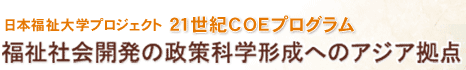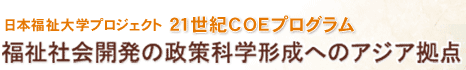|



 |
 |
リンク集 |


|
 |
| 本プログラムのなかでの第2分野の課題を端的に言い表すと、日本における中山間地域の再生戦略のシナリオを描くことにある。長年来、とくにバブル経済の崩壊後、わが国の中山間地域は、少子高齢化・過疎化・地域経済の衰退化等の問題状況に苦悩している。また、今では、市町村合併や「三位一体改革」等の課題にも直面している。第2分野では、主として「中山間地域における福祉社会開発モデル研究」、「中山間地域における地域ケア事業のモデル研究」、「保健・医療・福祉を統合した中山間地域における健康地域づくり研究」の3本の柱を構成した。 |
 |
| 第2分野の目的は、第1に少子高齢化と過疎化、そして地域産業の衰退化が進行している中山間地域において、そのコミュニティ資源(人、財、空間、文化)を活用し、コミュニティを再生することのできる保健・医療・福祉職の人材および地域再生の総合的なリーダー養成のプログラムを開発すること。第2に、同分野の研究チームを結合して、具体的に長野県、岩手県、高知県に研究拠点を形成すること。第3に、地域ケアと福祉社会開発モデル研究を基盤に、中山間地の地域再生にむけた地域福祉論や居住福祉学の理論化を行い、最終的には中山間地再生のシナリオを提示することに向けられる。 |
 |
| 21世紀が始まり、人間の生命と環境の課題を、グローバルな視点とローカルな視点から解明しようとする大きな流れが感じられる。これらの課題解明には、自然科学、社会科学、人文科学の総合的かつ協働的な取り組みが重要となってきている。その融合領域として地域福祉と居住福祉による福祉社会開発モデル研究の実践的理論的な位置づけが求められている。ここでは、現代日本の中山間地の家族や地域社会で生じている福祉問題へのアプローチと問題解決への理論枠組みを示しておく。 |
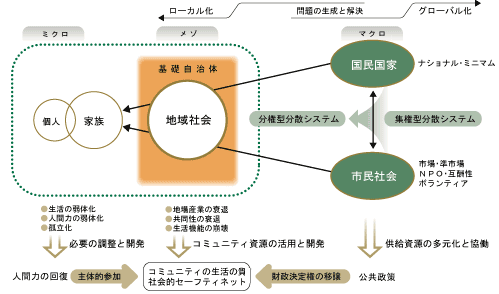
| ▲ 地域再生に向けた福祉社会開発モデル研究の概念図…空間と政策と実践(野口定久) |
| これからの中山間地再生のための福祉社会開発モデル研究の前提は、主として現代福祉問題の生成の場としてのグローバル化と、主としてその福祉問題の解決の場としてのローカル化の視点を、これからの地域再生論の理論的背景として構造化することである。また、この分野で主として用いる地域福祉論や居住福祉学は、実際に現場で生じている事実や人々の声に耳を傾ける学問である。このような方法は、人材養成及び拠点形成、現実からの理論化には不可欠の方法である。 |
 |
地域福祉が目標とする福祉コミュニティ社会の実現というのは、何人をも排除せず、人権尊重とノーマライゼーションの理念に基づき、一人ひとりの生涯にわたる生活を総合的に支える仕組みを、地域を基盤に住民の主体的な参加を基盤とした公共私の協働実践を通じてこしらえていく営み、そのものであるといえる。
もうひとつの方法論は、「伝統文化の再創造」である。「地域の小伝統の中に、現在、人類が直面している困難な問題を解くかぎを発見し、旧いものを新しい環境に照らしあわせてつくりかえ、そうすることによって、多様な発展の経路を切り拓く」(鶴見和子)という内発的発展の事例研究法である。
そして、具体的なプログラムの推進方法としては、「人材養成講座」を講義(記念講演、シンポジューム)、ワークショップ(演習、ゼミナール)、実地研究の3本柱で組み立て、研究拠点化と理論化をめざしていきたい。 |
|
 |


大学院
社会福祉学研究科
教授
野口定久 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| (執筆:野口定久) |

|