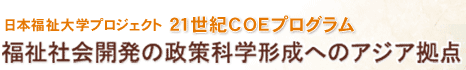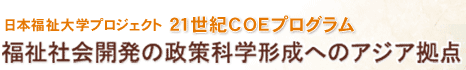|



 |
 |
リンク集 |


|
 |
| 第一分野「高齢者ケアの政策科学」分野は、今後の福祉社会形成において、ますます重要となる高齢者ケアの質向上をめざしている。質の高いケアを実現するためには、臨床・事例レベルの取り組みだけでなく施設・事業所、自治体、国レベルでの取り組みも重要である。(図1)持続的な質向上を追求するには、あらゆるレベルにおいて、PDCA(Plan-Do-Check-Action)マネジメント・サイクルを回すこと、臨床・事例レベルで言えば介護予防から終末期ケアにいたる全過程でのQOLの向上が求められる。(図2) |
| ▼(図1)
高齢者ケアの政策科学形成研究プロジェクト |
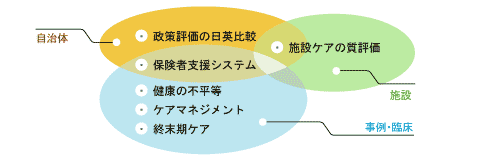 |
| ▼(図2)
事例・臨床レベルの研究課題 |
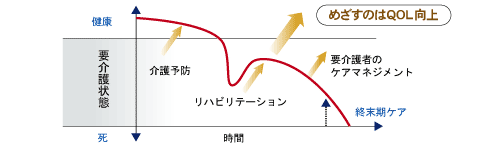 |
 |
| イギリスは、政策評価先進国の一つである。福祉分野でもベンチマーク指標が開発され、政策効果だけでなく効率も公正も評価基準として採用されている。マンチェスター大学PSSRU(対人社会サービス研究所)と共同し、高齢者ケアの政策評価のあり方を比較研究している。 |
 |
介護保険の推進には、保険者である市町村における主体的な取り組みが不可欠であり、そのためにはサービス利用状況や政策効果の評価、そこから引き出される課題などを、各保険者レベルで把握することが不可欠である。この目的で開発した介護保険給付実績分析ソフトは、全国の6割の自治体で利用されている。
新たに146自治体のデータを用いて、介護保険による効果などを多自治体間で比較する方法の開発に取り組んでいる。その特徴は、二時点間の変化を分析していること、保険者の要介護認定データなど既存データと独自追加調査によるデータの両者を用いること、臨床・事例データも用いること、7次元(<1>地域特性、<2>対象、<3>投入、<4>サービス利用状況、<5>効果、<6>効率、<7>公正)の指標群で多面的に評価すること、などである。分析結果だけでなく政策や計画の経験交流を図るなど、自治体へのフィードバックを重視した自治体支援システム構築をめざしている。 |
 |
| 施設・事業所レベルにおける第三者評価手法の開発を、三重県との共同研究として進めている。第1段階は、特別養護老人ホームにおける評価であった。現在、第2段階に入り、対象を老人保健施設に拡大している。 |
 |
| 南北間だけでなく、先進国内でも社会経済格差は拡大し、健康の不平等もむしろ拡大している。不健康をもたらす社会・経済・心理的危険因子とその影響プロセスを明らかにすることで、福祉社会開発の基礎的知見を得ることを目的としている。特徴は、3万人を対象にした大規模な縦断追跡(コホート)研究であること、健康寿命の喪失(要介護+死亡)の危険因子を分析していること、個人レベルだけでなく地域社会のあり方も健康に影響するという仮説の検証をしようとしていることなどである。 |
 |
| 要介護高齢者と介護者のQOL(生活の質)を高めるケアマネジメントのあり方を明らかにすることを目的に、7000人を超える要介護者と介護者を対象に調査を進めている。虐待や放置が疑われる要介護者が約2割も見られること、介護者にはうつが多いことなどが判明してきている。今後、要介護認定データなど保険者の持っているデータと結合して、要介護度の悪化を防止するケアプランのあり方などについて、分析を進めていく予定である。 |
 |
在宅・ホスピス・特別養護老人ホーム、グループホームなど、多様な場における終末期ケアの質向上を図るため、関連する要因の分析やケアマネジメント手法の開発に取り組んでいる。三次にわたる全国訪問看護ステーション調査の結果をとりまとめたほか、緩和ケア用のアセスメントツール(MDS-PC)の信頼性調査を行った。また、事例検討方式による公開研究会を継続し、終末期ケアマネジメントの方法論を検討し蓄積している。
以上、高齢者ケアの質を高めるため、政策からケアマネジメントまでを対象に、マネジメント・サイクルを回すための評価研究を軸にした政策科学形成に、多面的に取り組んでいる。 |
|
 |


大学院
社会福祉学研究科
教授
平野隆之 |


大学院
社会福祉学研究科
教授
近藤克則 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| (執筆:近藤克則) |

|