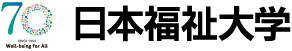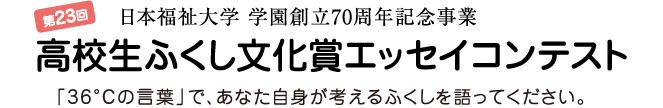
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
わたしが考えるこれからの社会
わたしが考えるこれからの社会 入賞作品
支えることのその先に
杉田 遥香(光ヶ丘女子高等学校 2年)
「母さんもうダメかもしれん。救急車呼んだぞ。」
「嘘でしょ。すぐ行くから落ち着いて。」
祖母は九十一歳。病気もせず元気な人だったが、近年は足腰や認知機能が弱り、助けが必要になった。両親は昼夜を問わず祖母の世話に奔走し、私は学校帰りに様子を見に通った。外出も旅行もままならない日々。私達の生活はいつも『祖母ありき』だったのだ。
二度目の救急搬送を機に、医師の勧めで施設の入居が決まった。気乗りがしない祖母に、申し訳なさそうな両親。私はどちらの気持ちもよく知っていたので、何も言うことができなかった。
だが入居の日、施設の職員さんが、
「よく、ご家族だけで頑張ってこられましたね。これからは私達も一緒です。みんなでお祖母様の幸せを考えていきましょう。」
と声をかけてくれた。その瞬間、張りつめていた糸がぷつりと切れたように父と母が泣き出した。ああ、私達はもう限界だったんだ。
今、祖母に家族のように接してくれる施設のみなさんは、私達にとっても家族のような存在だ。毎朝笑顔で声をかけてくれる人。服薬の度にそっと手を添えてくれる人。そんな一人ひとりのおかげで、祖母だけでなく、父や母の表情も少しずつやわらいでいった。
誰かを支える中で、気づかぬうちに自分達も支えられていた。そんな経験を通じて、私はこれからの社会に必要なのは『頼ることを恐れないこと』だと感じている。支える側も、支えられる側も、同じように尊重される関係であってこそ、人は安心して生きられる。
私には看護師になるという夢がある。いつか、かつての私達のように悩み、行き詰まっている人達の傍で支えられる存在になりたい。『支えることのその先』にあるのは孤独じゃない。つながりとぬくもりだと信じている。だから手を差し伸べよう。笑顔が絶えない社会の実現のために。
審査員のひとこと
祖母の施設入所をめぐる経験をもとに、家族の揺れ動く心理と専門職の役割を高校生ならではの視点で鮮やかに描いています。苦しい時にはSOSを発し、人に頼ることの重要性にも気づかせてくれました。
単に支える優しさを見つめるだけにとどまらず、支えられる側になる経験をしたことから、支える側・支えられる側の関係性を深く考察している点も評価できます。施設職員の方への深い感謝が表現されていて、介護現場に携わる方々にも、ぜひ読んでいただきたいと思いました。
皆で災害に立ち向かう
大野 真奈 (愛知県立時習館高等学校 2年)
静岡への家族旅行の帰り道、駿河湾で地震が発生した。津波警報で高速道路は閉鎖され、大渋滞が起こり、車が全く進まなくなった。私が一歳の時の事なので当時の記憶はないが、いつ帰れるかもわからない不安の中、道路沿いの家の人々が、困った私たちにお手洗いを貸してくれて本当に助かり、その温かさに心が救われたのだと、何度も親が聞かせてくれた。
そして、中学三年の六月、私の家の周りでは線状降水帯が発生して、記録的な大雨が降った。道路が川のようになり、動かなくなった車が何台も立ち往生していた。何時間も車に取り残されている人は食べ物もない中、不安に違いない。
今度は私が助ける番だ。雨が止んだ後、母とおにぎりを何個も作り、川のようになった道を歩いて車に乗っていた人たちに配った。後日、わざわざ家を訪ねて「本当に助かりました。ありがとう。」と感謝を伝えに来てくれた方がいて、無事でよかったと心からほっとした。
災害が起きてしまったら、国や自治体の助けの来ないような小さなトラブルはたくさん起こる。もし来てくれたとしても、何時間も経ってからになってしまうだろう。いざという時に必要なのは自分たちで助け合う意識なのだと強く実感した。
しかし、共助はとても勇気がいることで、その場ですぐに動けるものではない。私自身、もらった恩を誰かに繋げたいという思いで行動することができた。災害がいつ起こるかわからない日本で、今大切なのは、自助の備えはもちろんのこと、共に支え合う意識を、皆で共有することではないだろうか。
困っている人に迷わず手を差し伸ばし、自分が困ったときにはためらわず助けを求められるような絆が日本中、世界中で育まれることを願う。世の中が排他や分断に傾きがちな今だからこそ、自分のことだけを考えるのではなく、相手を思いやり、共に助け合う気持ちを忘れない。その気持ちによって救われる人、生活が必ずある。
審査員のひとこと
災害の多い日本で、いざというときに頼りになる「共助の心」に焦点を当てています。自身の体験をもとに、災害時のリアルな出来事や行動について具体的に語っていて、大切な学びがありました。
災害時の共助を出発点に、世の中の排他や分断にも目を向けており、福祉を単なる優しさではなく、社会の公平や正義として捉える視座は、他にはあまり見られないものでした。第3分野のテーマでもある「これからの社会」のあり方を明確に示している点も評価に繋がりました。
心配ご無用!
石井 奏羽(中央大学高等学校 2年)
「あれかっこいい!僕も乗りたい!」街角で響いた、幼い男の子の声。その視線の先には、姉が乗る車いすがあった。私の双子の姉は脳性麻痺で、普段の移動は車いす。「そうだよね。車いす、かっこいいよね」と微笑ましくなった、その瞬間だった。「こら!そんなこと言っちゃダメでしょ!」鋭い怒号が空気を裂いた。男の子の首元をぐっと掴んで無理矢理頭を下げさせ、「早く謝りなさい!」と叱責する母親。目を丸くし、石像のように固まる男の子。戸惑いながら「ごめんね」と呟いた。まるで、大きな過ちを犯したかのように。こんな光景を、私は何度も見てきた。無邪気な好奇心が「失礼」にすり替えられ、純粋な言葉が「間違い」として扱われる。そして、何も教えられず無知のまま大人になる。これじゃ、何も変わらない。
障がいがあるから「気を遣わなきゃ」と思うことは、決して間違いではない。事実、私も家族として、その優しさにたくさん救われてきた。しかし、私が望んでいるのは、姉が「当たり前の存在」として生きていくこと。なにも、特別な配慮が欲しいわけではない。
ちょうど一時間前、学校からの帰りの電車でスマホを眺めていたら、ある動画が流れてきた。海外のお笑いショーの動画だった。その芸人さんは、いわゆるイジリ系芸人。障がいのあるお客さんに対して一切遠慮せず容赦ないイジリを連発する姿に、「流石にこれはちょっと……」と正直ハラハラしたが、本人含め会場全員が笑いに包まれていた。「ああ、これが彼なりの優しさなんだ」「共に生きるって、こういうことなんだ」そう思った。
偏見が渦巻くこの社会を変えるために私たちができることは、一体何だろうか。それは、誰かを理解しようと心構えすることではなく、互いの存在を「当たり前」として受け入れることではないか。無知は罪ではない。興味を持つこと、教え合うこと。これこそが、社会から偏見をなくす鍵になると、私は思う。
審査員のひとこと
脳性麻痺の姉を持つ作者が周囲の反応に対して抱く感情を、ユーモアを交えながら率直に表現しています。障害当事者の本音が見えにくい中で、「当たり前の存在として生きたい」という、その家族の発信は貴重です。障害のある人を特別扱いするのではなく、「当たり前」の存在として受け入れることの大切さを訴えている点に、審査員から強い共感が寄せられました。
自分の体験と海外動画の巧みな対比をはじめ、文章のリズムや言葉選びに作者の豊かな感性が光っています。タイトルも素敵です。
わたしが考えるこれからの社会
~全ての人が幸せであるために~
松井 椎香(九里学園高等学校 3年)
私は「きょうだい」である。
私には、障がいのある弟がいる。私は幼いころからずっと、弟に障がいがあることを周囲に積極的には伝えてこなかった。伝えることが怖かった。「周りの人に知られたらどう思われるのだろう」と考え始めると不安で仕方なかった。「可哀想だと思われたくない」「憐れんだ目で見られたくない」という、ネガティブな印象しか持てない自分も嫌だった。同時に、家族を大切に思っているのも事実で、家族のことを人に伝えたくないと思ってしまう自分自身のことも嫌だった。こんな気持ちは誰にも言わなかったし、話す場もなかった。
しかし、「きょうだい」という言葉を知ったとき、自分と同じような立場の人たちが、当たり前に他にもいるということを意識した。私は自分と同じ「きょうだい」である高校生たちにそれぞれ話を聞いてまわった。すると、障がいや家庭の状況はそれぞれ違っていても、考えていることや悩みは互いに共感できる点が多くあり胸がいっぱいになった。
知り合った「きょうだい」たちと座談会をひらいたり先行研究を調べたりしていくと、障がいがある子の親の会は多く存在するが、兄弟・姉妹が悩みを共有できる場は少ないようだった。私は地元の養護学校の先生のご協力もあり、自分の「言えなかった」気持ちと向き合っていくうちにいつしか自分で「きょうだい」である十代の人たちが気軽に話せる場を創りたいという目標ができた。みんながそれぞれの悩みを共有できる環境が大事だと感じたからだ。
「きょうだいとしての私」と「ひとりの人間としての私」、自分の中でひとつになっていくような気がした。悩んでもその分たくさん自分と向き合える機会を持てる「場」を近い将来この手で創りたい。この「場」を通して、互いを、自分を受け入れられるように手助けできる社会創りを目指していきたいと思えた。「きょうだい」である私だからこそ、持つことができた夢だ。
審査員のひとこと
障害のある人の「きょうだい児」が感じる寂しさや悩みといった、近年ようやく光が当たり始めた問題を、当事者が論じた貴重な作品です。冒頭の一文、平仮名で表記した「きょうだい」に込められた意味や想いを、改めて認識させられました。
作者は自分の感情や体験を見つめるだけでなく、「きょうだい」の声を聴き取るために自ら行動を起こし、悩みを共有する場づくりを目標とするまで視野を広げています。今後の社会に一石を投じていて、ぜひ多くの方に読んでいただきたい力作です。
速さに寄り添う福祉
中村 琴葉(静岡県立富士東高等学校 1年)
二〇二五年。私たちが生きるこの時代は、流行、情報、人との関わり、全てが「速い」。私も、無意識にその環境の中で日々を過ごしていた。しかし、そのように日々生きられていたのは、私が、高齢者でも、障がい者でも、静かな歩みを大切にする人でもなかったからだと、とあることから学んだ。
私の祖父は、ここ数年で、聴力と膝の力が少し衰えた。なかなか言ったことが伝わらなかったり、歩くのがゆっくりだったりする。その姿を見ていると、私自身がいかに「速さ」を前提に生きていたのかに気づかされた。祖父に伝わるように話すには、目を見て、はっきりゆっくりと話す。外出するときは、祖父の歩調に合わせて一歩一歩ゆっくり確実に歩く。その時間は、私にとっては「遅さ」であったが、祖父にとっては「適度な速さ」だったのだ。このことから、私の中での「遅さ」が、次第に、「丁寧さ」や「思いやり」という大切なものへと変わっていった。
耳が遠くても会話を楽しみたい、膝が弱っても外に出たいという気持ちは、祖父の中でも大きいと思う。ただ、その願いを実現するには、家族の支えや周囲の理解、環境の良さなどが欠かせない。福祉とは、単なるサービスや制度ではなく、人と人が互いに違いを認め合い、その人が毎日を楽しく、充実して生きていると感じられるように、周りがサポートしていく営みのことを表すのではないかと私は思う。
私たちが生きるこの社会は、速く、正確にできる人が称えられることが多い。しかし、そんな風潮によって、弱さや遅さを抱えた人々を置き去りにしてはいないだろうか。祖父と過ごす時間は、「速さ」に偏りすぎた私にゆっくりであることの意味を教えてくれた。これからの社会に必要なのは、多様な歩みを受け入れられる余裕だ。私は、祖父と共に、そんな、余裕を大切にできる社会を歩んでいきたい。
審査員のひとこと
「速さ」を切り口に福祉を考えており、テーマと内容が秀逸です。「タイパ」重視の現代社会は、全てが加速する傾向にあります。それに対して、社会には耳が遠い、膝が弱いなど多様な事情を持つ人々が存在し、置き去りになってはいないかと、作者は自身の反省も踏まえて鋭い問題提起をしています。
祖父が「速さに偏りすぎていた私にゆっくりであることの意味を教えてくれた」という、結びに近い一文がいいですね。タイトルは「『遅さ』に寄り添う福祉」の方が分かりやすいかもしれません。
生きててよかったと思える社会へ
原田 聖衣(Thornton Academy Grade 12)
冬休みを祖父母の家で過ごしていた。日の当たるテーブルで本を読んでいた時、祖母がオレンジジュースを何度も何度も運んできた。認知症の症状による行動だとわかっていても、私はだんだん苛立ってしまい、「もう持ってこなくていい!」とつい声を荒げてしまった。祖母は困惑した表情で、「あら、もう持ってきてたの? 生きててごめんね。」と悲しそうに囁いた。その瞬間、後悔の念が私の胸を貫いた。その言葉は、私の心に留まり続けた。
記憶障害や幻覚が進み、祖母との会話は壊れた。厳しい言葉を浴びせられる事も増えた。大好きだった祖母と一緒にいるのが辛くなってきた自分がいた。かつて祖母は、私が友人を助けて喜ばれた話を嬉しそうに聞いてくれた。だが今の私は、その祖母を助けられない。
アルバムをめくっていくと、最初のページに、私を抱く祖母の優しい笑顔があった。祖母の人生を想像しながら、かつて愛をもって私を育み、多くを犠牲にして家族を支えてきたことを感じた。人生の最終章を、尊厳と喜びをもって過ごしてほしい。それは後に続く私の希望でもある。今度は私が助ける番だ。
私は、可能な限り寄り添うことにした。休暇の度に祖父母の家に滞在し、部屋を掃除し、生活の手助けをした。祖母が夜に幻覚で不安になるときは「大丈夫だよ」と声をかけた。双方向通話カメラを設置して、離れていても繋がれるようにした。祖母の大好きなマイウェイを何度も一緒に歌いながら、私は「支える喜び」に気付き始めた。祖母はその存在によって、私に大切な事を教えてくれていた。
身体が弱ってきて、祖母は入院した。祖母の手を握り、「ばあば、ありがとう。」と囁いた時、祖母は微かにほほ笑み、「生きててよかった。」と確かに言った。あの時祖母に謝らせてしまった後悔から、私は救われた気がした。高齢者が申し訳なさそうに生きるのではなく、生きててよかったと思いながら暮らせる社会づくりに貢献すると、その時決意した。
審査員のひとこと
認知症の高齢者に対する本質的な理解を感じさせ、高齢者が生きていてよかったと思える社会への願いが込められた作品です。具体的なエピソードを通して、祖母と過ごした歳月の重み、作者の心の動きが伝わってきます。
冒頭の「生きててごめんね」という悲痛なセリフが、「生きててよかった」という希望に回収されていて、鮮やかな対比が印象に残りました。認知症の家族に接する人が増えていく時代に響く、ストレートなメッセージが胸を打ちます。
地域で育てる、誰かの明日
石山 遙夏(昭和女子大学附属昭和高等学校 3年)
「ごちそうさまでした!」とみんなが嬉しそうな、どこか安心した表情で立ち去っていく。それは、商店街の一角にある子ども食堂での光景だった。私は高校生になって、学校の近くにある子ども食堂にボランティアとして参加し始めた。子ども食堂を利用したことはなかったが、名前の通り子どものためだけに作られた場所なのだろうと考えていた。しかし、実際に足を運んでみると、そこには子どもだけでなく、親子で来ている家庭や老夫婦の姿があり、年齢や立場を問わず、さまざまな人々が集まる場所であることを知った。
ある日、子ども食堂の代表の方がこう語ってくれた。「普段、子育てや仕事で忙しい親が肩の力を抜けるような場所にしたいんです」と。実際、食堂に来ていたある母親がスタッフと親しげに会話を交わしながら食事を楽しむ様子を見て、子ども食堂は単なる食事の場ではなく、安心して気持ちを共有できる場になっていると感じた。そこには確かな信頼関係と地域のつながりがあった。
昔の日本では、親以外にも多くの大人が子どもに関わり、地域とのつながりが密接であった。つまり、地域全体で子どもを見守り、育てていたのだ。しかし、現代社会では地域内のつながりは希薄化している。私自身、近所の人とすれ違った際に挨拶するべきか悩むことがあり、そのことを身に染みて感じている。
子育てする親にとって、助けてくれる人や子育てについて相談できる相手が近くにいないという状況はどんなに心細いだろうか。今の社会には子ども食堂のような「誰でも来ていい」場所が必要なのではないだろうか。私は子ども食堂での経験を通して、地域の人々が年齢や立場を超えて支え合う空間の重要性を学んだ。「お互い様」という精神を持って地域が支え合う仕組みや意識をもう一度育てていくことがすべての人が安心して暮らせる社会への第一歩なのだと思う。
見えない涙を、見ようとする勇気
鈴木 逢紗(日本福祉大学付属高等学校 3年)
「このチョコレートの裏には、誰の涙があるんだろう?」
フェアトレードを学んだとき、先生がつぶやいたその言葉が、私の中に静かに沈んだ。包装紙の向こうに、人の涙があるかもしれない。そんな想像をしたことがなかった。
ある日、豊橋の戦争跡地を訪れた。ひび割れた壁、焦げたレンガ、静かな空気の中に消された日常の気配が残っていた。ここに確かに人がいて、笑って、暮らして、そして突然、全てを奪われた。戦争は「昔話」ではない。あの場所で、私は「平和はあたりまえではない」と初めて感じた。
環境問題を調べた時も、ショックを受けた。海に流れ着いたプラスチックが、ウミガメの命を奪っていた。誰かが捨てたゴミ。……もしかしたら、それは私だったかもしれない。自分の出したものが、見えない場所で命を奪っている現実に、胸が苦しくなった。
「知らなかった」では、もう済まされない。無関心は、静かな加害だ。だから私は、知ったことを伝えたい。考えることをやめたくない。選び、声を上げ、行動し続けたい。
たった一人の選択では、世界は変わらないかもしれない。けれど、何も変えないままの選択は、誰かを苦しめるかもしれない。未来は、遠い場所にあるのではない。私たちの毎日の中に、今この瞬間にも積み重ねられている。
私はまだ高校生だけれど、それでも信じている。小さな行動が、誰かの明日を守ることを。私は微力かもしれないけれど、それでも無力じゃない。だから今日も声を上げる。誰もが涙を流さずにすむ社会を、自分の手でつくりたい。そのために、「見えない涙を、見ようとする勇気」を、ずっと持ち続けます。それが私にできる、確かな「強さ」だと思うから。
公正について
岩渕 帆花(昭和女子大学附属昭和高等学校 3年)
近頃、ニュースやSNS、映画などで「多様性」や「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」という言葉をよく見かけるようになったと思います。多様性を認め、誰もが生きやすい社会をつくろうという考えはとても大切だと思ったのですが、最近の社会の動きを見ていると、「多様性を認めること」と「多様性を特別扱いすること」が混ざってしまっているように感じることがあります。例えば、ディズニーの実写映画で、原作では白い肌のキャラクターを黒人の俳優が演じ、話題になったと聞いたことがあります。もちろん、どんな肌の色の人がどんな役を演じてもよいと思うし、演技力や表現力を重視するのは当然のことだと思います。しかし、「多様性のためにあえて黒人を起用した」というような説明を聞き、それは本当に平等なのだろうかという疑問が湧きました。私は平等とは誰かを「優遇する」ことではなく、「全員を同じ目線で見る」ことではないかと思いました。
ポリコレは、差別をなくしマイノリティの人々が安心して生きられる社会を目指す考え方ですが、その目的のために少数派を「守らなければならない存在」として特別に扱うことは、かえって逆差別に繋がってしまう恐れがあると思います。例えば、学校で「女子だから配慮する」「外国人だから優しくする」という行動も、相手にとっては逆に生きづらくなる原因の一つになるかもしれません。
私は本当の多様性とは、違いを理解しながらも特別扱いせず誰に対しても同じように接することだと考えています。「肌の色」や「性別」「国籍」などに関係なく、全ての人に同じチャンスがあり、同じ基準で評価される社会こそが理想の平等ではないでしょうか。
今後の社会では、多様性と平等の「バランス感覚」がより一層求められていくと思います。一人一人がその意味を考えて行動することが、誰もが幸せに生きられる社会への第一歩になると私は考えます。
幸せのつかみ方
山下 梨花(昭和女子大学附属昭和高等学校 3年)
SNSが発達した時代、知りたいことはなんでも片手一つの動作で情報が手に入る。料理のレシピ、可愛いあの子、世界のニュース、知らない誰かの生活。便利になりすぎている時代だ。けれど、私は時々思い出すことがある。「小さい頃はどうやって過ごしていたのだろうか」と。学校から帰ってきて宿題をして、遊んで夕飯を食べて寝る。それだけで毎日心が満たされていた気がする。時間にも心にも余裕があり、穏やかな気持ちで過ごせていた。他人の生活を覗くことがなかったから比べることもしなかった。でも今は、知らなくていいことまで勝手に情報が目から、耳から入ってくる。誰かの自慢や楽しそうに何処かに出かけている投稿に「自分はダメ人間だ」と自分を下げてしまうこともある。情報が溢れすぎると心が疲れてしまうこともあるのだ。
私はそんな時「自分の機嫌は自分で取る」を大切にしている。ネガティブな感情になって落ち込んでも少しでもできたことを考えて自分の中の小さな幸せを見つけるようにしている。例えば、好きな甘いものを食べる、外の夕日を見てリラックスする。忙しい私たち高校生だからこそ一歩身を引いて止まって物事を俯瞰して見る大切さに気付くことができる時間をこれからも作っていきたい。
私が考えるこれからの社会とは、誰かと幸せを比べて測るのではなく、自分なりの幸せを尊重し、認め合える時代になることだと思う。便利になった世の中、膨大な情報を精査し、良くも悪くもどう解釈するかは自分次第であって「誰かの正解」に縛られず、「自分の幸せ」に自信を持てる社会を目指せば、多くの人たちが安心して暮らせる世の中になると私は信じている。そのためにまず、自分自身の心に正直に生きることが、より良い社会の第一歩なのではないか。一人一人が他者を思いやる気持ちを持ち、多様な価値観を認め合うことが大切だ。私は、そんな社会の一員として行動していきたい。
「できた!」その喜びを共に
狩谷 美穏(水戸平成学園高等学校 2年)
「できた!」
その一言は私に多くの喜びを与えた。
私には軽度知的障害がある三歳下の弟がいる。日常生活では気づかれにくく、小学校時代は、学習面、コミュニケーション面などで苦労していた。クラスに上手く馴染めなかったり、周りの子たちと同じように振る舞えず先生から何度も注意を受けたりすることもあった。私が小学六年生の時、授業についていけず、休み時間にクラスメイトから、
「なんでできないの?」
と囃し立てられ、何も言い返せずに俯く弟の姿を目の当たりにした時、学校は学びの場であるのにどうしてこんなにも辛い場所になってしまうのだろうと疑問を抱いた。
小学校での苦悩を経て弟は特別支援学校への進学を決めた。現場の先生方は、弟のペースや特性に合わせた指導をしてくださり、弟が新しい漢字を覚えてきて、
「できた!」
と家族に満面の笑みで報告してくれた時、私は喜びに満たされた。集団で埋もれがちだった弟の個性が特別支援学校では発揮されているように感じた。それと同時に一人ひとりに合わせた支援の重要性に気づいた。また、このような弟の変化を見て、両親に安堵の笑顔が戻ったのも印象的だった。
世の中には、見た目だけではわからない「困りごと」を抱えている人が数多くいる。だからこそ、私たちは人の見た目や表面的な情報だけで判断せず、その背景にあるかもしれない「困りごと」=「見えない壁」に思いを馳せる必要があると思う。誰もが自分に必要な支援を受け、その壁を乗り越えられる社会を実現するために、将来は大学で特別支援教育について深く学び、教育現場から誰もが幸せを感じながら生きていく手助けをしたいと考えている。