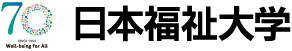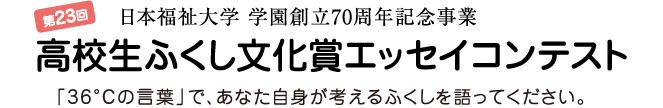
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
わたしがふくしを感じたとき
わたしがふくしを感じたとき 入賞作品
同じ世界を生きる
百武 愛心(日本福祉大学付属高等学校 1年)
このあいだ久しぶりにおばあちゃんと一緒にご飯を食べに行った。いつものように最近あったことをお互いに話していたら、おばあちゃんが最近嬉しかったことを私に聞かせてくれた。
「この前お昼過ぎの暑い時間に外を歩いていて、赤信号で止まっていたとき、小学校から帰る途中の女の子が『一緒に日傘の中入りますか?』って聞いてくれたの!暑いので赤信号の間だけでもって。」その話を聞いて私は単純にいい子だなと思って「いい子だね。日本は優しい国だね。」と言った。するとおばあちゃんが「その子は日本人じゃなくて外国人の子だったよ!日本語もとっても上手だったんだ。」と言った。私はとても驚いた。私はなんとなく日本は優しい国で外国はそうじゃないと勝手に思っていた。しかし、それは間違いであることに気付いた。
世界中の誰もが人に優しくしようという心を持っていて、その心は周りの人にふつうのくらしのしあわせを与えることができるのだと強く感じた。そして、それは同じ国の人同士だけでなく、他国の人との間でも作り上げることのできる感情だと知った。世界中が幸せになるための第一歩は他人を思いやる「ふくし」から始まるのかも知れない。
審査員のひとこと
祖母に傘を差し出してくれた少女が外国人だった―。それを知った作者が、自身の思い込みに気づき、思いやりに国境はないことを考察した過程を素直に綴っています。今まさに発信されるべき大切なメッセージが込められていると、審査員一同、高く評価しました。文章には1年生とは思えない読ませる力があります。限られた字数の中に驚きや発見が盛り込まれ、精緻に組み立てられた展開も優れています。
久しぶりのおめかし
千葉 心晴(鈴鹿工業高等専門学校 2年)
「すみません、近鉄四日市までの行き方はわかりますか?」
駅の改札前で、一人のおばあさんに声をかけられた。ちょうど私も同じ方面へ向かうところだったので、「一緒に行きましょう。」と伝えると、おばあさんは安心したように微笑み、ぽつりぽつりと話し始めた。
ご主人が体調を崩して車の運転ができなくなったこと。いつもは車で送ってもらっていたので、ひとりで電車に乗るのが少し不安だったこと。そして、四日市では五年ぶりに昔からの友人とカフェで会う予定があること。「久しぶりにおめかししたのよ。」とはにかんだように笑う姿がとても印象的だった。
私はただ道を教えただけだったけれど、気づけば心がぽかぽかと温まっていた。福祉とは特別な制度や資格の話だけでなく、こうした日常の中にある、ささやかな助け合いにも宿っているのだと思った。
自分のちょっとした行動が、誰かの安心や笑顔につながる。そんな体験を通して、人と人とのつながりの大切さを改めて感じた。たった一度の出会いが、こんなに胸を熱くするとは思わなかった。あのおばあさんの「久しぶりのおめかし」が心に残る宝物になった。
審査員のひとこと
駅で出会ったおばあさんとのつかの間の交流。その温かな情景が、自然と目に浮かびました。福祉が特別なものではなく、身近な日常に息づいていることが分かります。主張は控えめながらも、短い時間の中で人生の機微に触れる会話を交わした様子がうまく描写できており、構成が優れている点も評価されました。実に微笑ましい作品で、さわやかな読後感と優しい余韻を残してくれました。
祖母からのメール
赤井 亜月葉(大阪府立工芸高等学校 1年)
「元気ですか?高校は楽しい?」祖母からのメールだ。私は昔から祖母が大好きである。私は幼い頃は母子家庭で小学校に上がると同時に母が再婚した。幼い頃から育った祖母のいる母方の家を離れ、現在の家に住んでいる。
再婚したあとは二人の兄弟ができた。二人は野球をしており休日はいつも野球に行っていた。父と母は二人に付き添い、家を空けていることが多かった。小学生の私はそれが寂しかった。少しでも自分を見てほしかったのだろう。
そんなある日、私は祖母のもとに泊まりに行くことになった。いつも一人家で遊ぶだけだった休日が祖母との楽しい休日になった。寂しさはいつの間にか消え私は毎週のように泊まりに行った。現実逃避だ。
しかしある日、祖母にずっと寂しかったと言うと母にしっかり伝えるべきだと言われた。私はその通りだと思った。けれど怖い。だけどずっとこうして逃げているのはもっとダメだと思い、家に帰った時私は泣きながら母に「ずっと寂しかった!もっと沢山話がしたい」そう伝えた。中学・高校に上がり泊まる頻度は少なくなったが祖母はメールをくれる。その私を想った優しい言葉に私はまた返信をする。「元気だよ!学校も家もめっちゃ楽しい!」
審査員のひとこと
再婚した母に本心を言えなかった作者に対し、祖母が促したのは行動でした。感情を素直に伝えることは難しいものですが、それでも作者は正面から向き合い、勇気を振り絞ります。結果は、高校生らしい最後の一文に凝縮され、その後の展開まで想像させてくれました。感情の揺れや寂しさを抱える日常が繊細に表現された文章は、随所に祖母への信頼と感謝がにじんでおり、読み手の心に沁
「いただきます」を彩る時間
―母からのメッセージ―
梶原 陽奈(日本女子大学附属高等学校 3年)
昼休み、それは私が一日の中で一番好きな時間だ。友達と机を並べ、美味しいお弁当を食べる。長い間コロナと共に過ごしていたため、皆でご飯を食べられることが何よりも嬉しかった。
そんな私にはもう一つ、お昼が楽しみな理由がある。お弁当のふたを開けると、小さなカードが一枚。学校のお昼だけでなく、幼い頃の保育園の遠足や塾での夕飯など、母が作るお弁当には必ず入っていた。カードには「午後も頑張れ」「ちょっと冷凍食品多めかな」など、母の手書きの文字が並んでいるのだ。読むと自然と笑みがこぼれ、なぜか安心する。でもその言葉が当たり前になっていて、特別なものだと思わずに捨てていた。
ある日、友達がふと「このカード、取っておいたら?」と言った。その何気ない一言で私は気づいた。毎朝忙しい中でお弁当を作りメッセージを書くことは凄く大変な作業だ。 高校三年生になり、毎日のお弁当生活に終わりが近づいている。今年から私は、母の思いが込もったカードを全て取っておくようにした。ふとした時にカードの束を見返すと、心が温かくなる。
もうすぐ昼休み。ふたを開けたら、今日はどんなカードが入っているのかな。
審査員のひとこと
毎日のお弁当に添えられた母の手書きのメッセージカード。友人の一言で、その手間をかける母の思いに気づいた作者の気持ちが、飾らない言葉で綴
母娘の豊かな日常の一コマが表現され、読み手が温かな気持ちになる素敵なエッセイです。
祖母と向き合う
倉元 美温(静岡県立掛川東高等学校 2年)
「どちら様ですか。」 この言葉は認知症の祖母が私に向かって放ったものだった。あまりに突然で、私はショックのあまり涙が止まらなかった。 祖母が認知症と診断されたのは、もう四年も前のことだ。以前の祖母は何事もテキパキとこなす頼もしい人で、私の憧れだった。なくし物をしたときは一緒に探してくれたり、風邪をひいたときには、すったりんごを持ってきてくれたりもした。
それが今では、泣き叫んだり、乾燥剤を食べてしまったりと、まるで別人のようになってしまった。私は戸惑いと悲しさから、そんな祖母に冷たく接してしまうことが増えた。最低だとわかっていても、現実をどうしても受け止めきれなかったのだ。
そんなある日父と祖母のケアマネジャーが話しているのが聞こえた。
「忘れる本人が一番苦しいんですよね。」
その言葉に私はハッとさせられた。
私はこれまで、自分の気持ちしか見えていなかった。忘れたくて忘れているわけではない祖母に私は苛立ち、傷つけてしまっていた。だから私は、これから祖母の心に寄り添い向き合う。恩返しをするために。
審査員のひとこと
認知症になった祖母の姿に、真っすぐ向き合い、リアルに描いています。つらい状況を直視する作者の姿勢が、文章に力強さを与えているように感じました。
特に「忘れる本人が一番苦しいんですよね」という一文には、胸を打たれました。この気づきは普遍的であり、社会に対する大切なメッセージになっています。審査員からは自身の今後への示唆にもなった、と評価する声が上がりました。
7時27分のバス
四倉 若奈(山梨県立甲府東高等学校 3年)
七時二十七分。いつも通りバスに乗っていると盲導犬を連れた目の不自由なおじさんが乗ってくる。この時間のバスはいつも満員だ。そんな中、盲導犬は前の方にある優先席の周りをぐるぐると回り、席が空いていないか確認している。最初の頃は優先席に座っている小学生達は見て見ぬふりをして誰も席を譲ろうとしなかった。
しかしある日、一人の小学生が優先席に座っている子に「おじさんに席譲ろうよ。」と声をかけていた。その行動からバスの乗客みんなの意識が少しずつ変わっていった。「座りますか?」と勇気を出し声をかける子やおじさんの手伝いをする子も出てきた。私はその変化を見て心がじんわり温かくなった。
福祉とは難しい制度のように思っていたが、そうでなく、“気づく”ということから始まるものだと子ども達の姿に教えられた気がする。法律や点字ブロックなども大事だが、目の前の人へ敬意を向ける心がなければ意味がない。声をかける、一歩譲る。そんな些細な行動が社会をやさしく書き換えるインクとなる。明日も私は小さな優しさが生まれる瞬間を見つめながら自分にできることを考え、少しの勇気を行動に変えていきたい。
審査員のひとこと
毎朝、同じバスに乗り合わせる盲導犬ユーザーの男性と、周囲の小学生たちの行動の変化を生き生きと描いています。バスの中での出来事を機に、目の前の人へ優しさと配慮を向けることの意味が、作者に実感を持って根づいたことがうかがえました。
福祉を難しく考えるのではなく、気づきが大切と軽やかに宣言している点も評価に繋がりました。キャッチーなタイトルも秀逸で、作品の魅力を高めています。
素敵な文通
斉藤 桜彩(日本女子大学附属高等学校 3年)
「お祖母様はお元気?」家の前の通りで声をかけてくれた女性に私は見覚えがなかった。その女性は私が幼い頃に斜向かいに住んでいらしたそうで、当時私に会いに来ていた祖母と何度か話したことがあるのだという。そして私が「元気です」と答えると祖母と同じ年齢なのだと言って嬉しそうに笑った。その話を祖母に電話で伝えた数日後、その女性に渡してほしいという手紙が祖母から届き、それがきっかけで二人は文通を始めた。祖母は綺麗な便箋を探しに出かけるのが楽しいと言い、時折、見かける女性も祖母からの贈り物だと言って扇子を見せてくれたりする。今年、八十歳を迎える祖母達は元気でとても楽しそうで、見ている私まで明るい気持ちになる。
しかし先日、祖母が入院した。転んで腰を痛めただけというが心配でお見舞いに行くと祖母は文通のことを気にかけていた。「入院の事は秘密ね。お互いに友達の元気が自分の元気の秘訣!」と言うのだ。私は祖母達の文通が元気の送り合いだったのだと気付いた。
祖母は今、早く元気になろうと頑張っている。私は胸の中でこの優しい秘密に封をして祖母の回復と、二人の素敵な文通がいつまでも続くように祈っている。
「ふつう」になれたら
多田 和奏(日本福祉大学付属高等学校 1年)
「ふくし」とは、ふつうのくらしのしあわせのことだ。と教えてもらった。その時私は「ふつう」とは何だろう。と疑問に思った。なぜなら「ふつう」の感じ方は人それぞれで、曖昧なものだからだ。そこで私は「ふつう」の意味を調べた。
ふつう(普通)とは、特に変わっていないこと。ごくありふれたものであること。それがあたり前であること。とあった。やはり曖昧なものだった。しかし、この曖昧さから分かることは、「ふつう」には正解がない。間違いもない。つまり、自分で自分の「ふつう」を作ることができるということだ。
私は今、「ふつう」は特別なものだと思っている。日々のあたり前が壊れることを知らず、毎日をなんとなく過ごしている私たちは、間違いなく幸せだ。だから「ふくし」なんだろう。だから私たちは「ふくし」を国中に、世界中に広げていかなければならないのだろう。もちろん簡単なことではないが、難しすぎるわけでもない。それなら少しずつ「ふくし」の輪を広げて、地球丸ごとつつんじゃえ。
八分から伝わる愛情
野口 陽茉理(日本女子大学附属高等学校 3年)
「二十二時三十分に着きます。」
塾の最寄り駅に着くと、必ず送るメールがある。宛先は迎えに来てくれる父だ。
受験生に休みという概念は無い。睡眠不足に体調不良。心の余裕も無く、両親とぶつかることも、八つ当たりをしてしまうことも少なくなかった。しかし、父はそれでも「塾まで送っていこうか」と片道一時間の道のりを何てことないという顔をして送ってくれる。正直、申し訳なかった。思わず「どうしていつも送ってくれるの」と聞いてみた。すると、父は自分の息抜きのため、治安が悪いからと誤魔化すように色々なことを理由にした。その時、私は少し意地悪な質問をしたことに気付いた。父が私を大切に思っていることは分かっていたのだから。
幼い頃、私は母ばかりだったが、風邪の時にうどんを作ってくれたのも、進路の悩みや弱音を打ち明けたのも父だった。行動で示す父だからこそ、迎えに行く、送ってあげるという行動に父なりの愛情が込められていた。最近は塾まで送ってもらうことは無いが、駅から家までのたった八分。私はその八分がお気に入りだ。今日も電車に乗る。「今日はどんな話をしようかな」と考えながら。
春がくれたもの
野島 みらい(大阪府立鳳高等学校 3年)
春休みも終盤にさしかかったある日の早朝、バスケットボール部に所属する私は、試合会場へ向かう為、電車に揺られていた。隣の人と肩が触れ合う程沢山の人であふれ返る車内で私が「ふらつくものか」と両足でふん張りつり革をきつく握りしめていたのは、私の隣がヒールの高い靴をはいて窓をじっとにらみつけている金髪のお姉さんだったからかもしれない。
私の降りる駅まであと二駅。つり革を握る手に力が入る。その時だった。お姉さんの隣のベビーカーから大きな泣き声が聞こえた。その子の母親であろう女性はあたふたしながら必死にベビーカーを揺らしている。平日の早朝。周りの大人は眉にしわを寄せ、車内の空気は窓から差す春の暖かい日差しと違って、ひんやりと冷たかった。その空気が変わったのはお姉さんが鞄の中から小さなうさぎの人形を取り出した瞬間だった。お姉さんは泣いている子供に人形を差し出し、にっこりと笑った。いつのまにか泣き声は止んでいた。
電車を降りてから、彼女に少しでも偏見の目を向けた自分をひどく恥じた。春。私に新たな学びと憧れをくれた季節になった。
宝物の日々
大野 美結(岡山県立岡山大安寺中等教育学校 4年)
「今日も、じいじ、ばあばのお世話に行くんだ!」とお友達に言うと、大抵「えっ、大変だね。」と返される。でも私のするお世話は、大変とは少し違うのかもしれない。
曽祖母が左手の骨折で通院していた時、病院の待合室で「あんた、どっか悪いん?」と私を心配してくれる。ギプスに黒マジックで『骨折しているので取らないでね』と書いてあげたら、「あれ?私、骨折したんかな?」と笑っている。曽祖父も陽気な人で、大腸検査の下剤を、大好きなお酒のようにごくごくと飲んだ。検査準備室はまるで小さな宴会場みたい。しかもその日はクリスマス。紙コップ片手に、得意げに看護師さんに笑顔をふりまく姿には、付き添う私も笑いがとまらない。
二人が晩年を迎えた頃、私は中学生になっていた。お見舞いは決まって「初めまして」の挨拶から。何度となく話してくれた昔の苦労話、復員の話は胸にしみるものがあった。
高校生になり、「今まで、助けてくれてありがとう。」と母に言われ、あの頃の私の存在が、母と曽祖父母をつなぐ救いになっていたことを知った。あの日々は、誰かの力になれる喜びを教えてくれた宝物だ。これからも、そっと誰かを支えられる人であり続けたい。