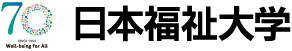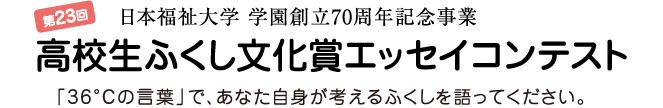
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
スポーツ・文化活動を通して
スポーツ・文化活動を通して 入賞作品
かんちゃんのお弁当
松尾 栞奈(東洋女子高等学校 1年)
「かんちゃんのお弁当を食べると元気が出るよ」
その一言が、今でも私の背中を押してくれている。コロナ禍で社会が不安に包まれていた小学五年生のとき「私に何かできることはないか」と考えたことが活動のきっかけだった。私は、ひとり暮らしの高齢者や路上生活者の方に、手作りのお弁当を届ける活動を始めた。お店のように豪華ではないけれど、心を込めて一つひとつ丁寧に作っている。
活動は五年目を迎え、私が作るお弁当はいつの間にか「かんちゃんのお弁当」と呼ばれるようになった。受け取ってくれる方は、人とのつながりがなく、孤立している方が多かった。最初はお弁当を受け取ってもらうことも、言葉を交わすことも難しかった。たとえ 会話にならなくても手紙を添え、わずかなやりとりから体調確認へつながるよう工夫した。
活動を通して、人は人とのつながりがなくなることで、いつの間にか目指していた夢や目標を見失い、自分自身のことさえ諦めてしまうことに気づいた。孤独は一番の敵だ。
「もう一度頑張ってみるよ」
今では路上から社会へ戻る方も増えていった。人は何度でも変われる。この活動で一番大切にしていることは、人との「つながり」だ。出会った方に、誰かと比べることなく「その人らしく生きること」に自信を持ち、生まれてきて良かったと思ってほしいからだ。
「無関心」は何よりも悲しいことだ。住む場所があってもなくても、同じ命に変わりない。誰もが生きる権利も、幸せになる権利もあるのだ。困ったときに「助けて」と言える社会、誰もが孤立しない仕組みこそが「ふくし」であり、私がこの活動に込めた願いでもある。
今後も思いやりのある社会を目指し、人との「つながり」を大切に活動の輪を広げていきたい。私の作るお弁当が、これからも誰かの笑顔のきっかけになるように。
審査員のひとこと
小学生の頃から、一人暮らしの高齢者や路上生活者に手作りのお弁当を届け続けている作者。その行動力と継続力には、審査員一同、大きな驚きと感動を覚えました。一人でいくつぐらいのお弁当を作っているのか、それがわかるともっとよかったという意見も出て、「ぜひ、会って話を聞いてみたい」と声が上がるほど、活動内容や作者の人柄への興味をかき立てる文章です。
活動を通して福祉への理解を深めるプロセスに迫力を感じさせ、「ふつうのくらしのしあわせ」をつくる「ふくし」の意味を的確に表現しています。エッセイとしても優れており、多くの審査員から支持を集めました。
限られた時間に思いやりを込めて
中川 桂大朗(愛知県立高浜高等学校 3年)
学校代表に選ばれた瞬間、胸に広がったのはうれしさと覚悟だった。介護コンテストでは利用者の情報を分析し、7分間で介助と声かけを実践しないといけない限られた時間の中でどれだけの思いやりを届けられるのか。その問いに向き合う日々が始まった。
練習が始まると、先生の指導は厳しくなった。「本気になっていないよね?なんで笑っていられるの?」その言葉に、私は揺れた。どんな時も笑顔でいることはコミュニケーションの基本だと思っていた。しかし、ただ表情だけで満足していたかもしれない。笑顔に込めたつもりの思いやりが本当に伝わっているのか、自問するようになった。それ以来、声のトーン、手の動き、視線の先にまで心を込めることを意識するようになった。
代表には選ばれなかった仲間が、毎日遅くまで私達の練習に付き合ってくれた。先生や家族、友人からアドバイスをもらった。「サポート役は脇役じゃない。場合によっては指導者になる。」その言葉は、私の役割に対する視点を大きく変えた。メインで介護をする子の動きを理解しようと努め、互いに分かり合おうとする中で、私達の介護は深まっていった。
本番では迷う場面があった。利用者さんが荷物を自分で取りに行くか、私が渡すか。私は自立支援になると考えて、一緒に行くことを選んだ。結果、時間切れになってしまった。落ち込む私に、家族が言った。「本当の介護には時間制限なんてないんでしょう。寄り添う介護ができてよかったじゃん。」その言葉に救われた。「いや、ブザーはならないけど時間って限りがあると思う。」気が付くとそう返していた。複数の利用者さんを支える現場では、時間もまた命だと考えるようになった。
だから私は、技術を磨き続けたい。将来は時間に追われる現場でも、心に届くケアができるようになりたい。“その瞬間”に、すべての思いやりを込められるようになる。それが、私の目指す介護のかたちだ。
審査員のひとこと
「全国高校生介護技術コンテスト」出場に向けた作者の奮闘ぶりが、生き生きと浮かび上がってきました。その学びの姿勢やコンテストに臨む態度は、真面目で誠実。今という時代に、こうした若者が介護分野を志すことがうれしく、将来に希望を抱かせます。
飾らない等身大の文章は高校生らしく、好感を持ちました。場面がイメージでき、スポーツの団体戦に通じる緊張感やチームの一体感なども伝わってきて、最後までワクワクしながら読み進めることができました。
理想的なスポーツのカタチ
平林 宙(香川県立坂出高等学校 2年)
スポーツとは何だろう。汗を流し、声を張り上げ、勝敗を競い合う。多くの人はそう思うに違いない。かつての私もそうだった。だが、その考えはある日の光景によって大きく揺さぶられた。
曽祖母が入居していた施設を訪れた時のことだった。小さなホールに流れていたのは、懐かしい童謡。ピアノの音に合わせて、高齢者の方々が両手を軽やかに動かしていた。指を折ったり、手を叩いたり、誰にでもできる簡単な手遊びだった。しかし、その空間には驚くほどの笑顔と活気が満ちていた。
私はその輪の中に曽祖母を見つけた。普段は穏やかで控えめな彼女が、まるで子どものように目を輝かせ、隣の人と顔を見合わせて声を出して笑っていたのだ。「スポーツ」に対するイメージが一新した。
スポーツとは、必ずしも全速力や力強い競技だけを指すのではない。ほんの小さな体の動きが、人の心をほぐし、笑顔を生み、つながりを深めることがある。そこには勝敗も記録も存在せず、ただ「楽しさ」と「温かさ」だけが存在している。その光景は、私にスポーツのもうひとつの姿を教えてくれた。
そして私は気づいた。スポーツの持つこの優しさこそ、「ふくし」とつながっているのだと。誰もが無理なく参加でき、共に楽しみ笑い合う時間は、人を支え、人を幸せにする営みそのものだ。
私は曽祖母の笑顔から、スポーツの奥深さと、ふくしの本当の意味を学んだ。スポーツは、競うものでもあり、分かち合うものでもある。そのふたつが共に存在するからこそ、人は心から豊かなになれるのだろう。
これからも私は人と人とをつなぐ温かなスポーツの力を信じ続けたい。なぜなら私が目の当たりにした曽祖母のあの笑顔こそが、私たちの目指すふくしの最も理想的なカタチであると信じているから。
審査員のひとこと
第2分野のテーマに最も合致した内容として、高い評価を集めました。スポーツというと、ついオリンピックのようなハイレベルな競技や勝敗に目が行きがちです。しかし、作者は曽祖母の様子から、スポーツの「人の心をほぐし、笑顔を生み、つながりを深めるもの」という側面を発見します。
単に速さや強さを争う競技とは全く異なる視点から、福祉につながるスポーツのあり方、すなわち「分かち合う」ことの価値を深く考察し、見事にまとめ上げている点を称えたいと思います。
完璧な共感は不必要
飯尾 むつは(日本女子大学附属高等学校 3年)
「病気の子供達とそのご家族の為に、ご協力をお願い致します!」これは、私が募金をお願いする際によく言うフレーズだ。私は約二年前から、難病と闘う子供たちとご家族の為の宿泊施設で、毎月ボランティア活動をしている。普段はその施設内で活動をしているが、スポーツの試合会場や街頭で募金活動をすることもある。そして、募金活動をすると毎回考えることがある。
それは、「社会は完璧な共感は必要ない」ということだ。見知らぬ誰かにお金を渡す行動には共感が必要で、それが欠ければ難しいだろう。しかし心のどこかで、「もっと立ち止まって欲しいな、理解して欲しいな」と思う。一方で私自身、街中で募金活動を見て見ぬふりをしてしまう時もある。すると何だか、募金をしてほしいと思うのは、自分本意なのではないかと考え始めた。そのような気持ちと共に募金箱をかかえていると、ボランティア先の職員の方が、「まずは存在を知って頂くこと。温かくお声を掛け続けたらきっと、むつはちゃんの想いは伝わるよ。」と話して下さった。
完璧な共感を得られなくても、少しでも私の声が耳に届くならば本望である、と一瞬見失った大切なことに気付かされた。誰もが全てを理解できる訳ではない。けれども、声が届いたその瞬間に、小さな繋がりが生まれる。断片的な繋がりの一つ一つが意味のあるものであり、それらを紡いでいくことで、社会は支えられているのだろう。
もし、完璧な共感のみで社会が満たされていたら、現在ある一つ一つの共感の重みが軽くなってしまうかもしれない。だからこそ、重要なのは共感を強制することではなく、どんな形でも心を寄せ合い、手を取り合うことだ。その集合体が豊かな社会を創り上げる。ボランティア活動を通じて学んだこと。それは、小さな共感が他者を温かいものにし、ひいては社会の中の優しさを育むということだ。ボランティア活動は間違いなく、私のアイデンティティの一つだ。
審査員のひとこと
「共感が大事だ」という認識を持って募金活動を行ってきた作者。しかし、活動に真剣に取り組む中で「共感」を巡って、自ら抱え込んだ矛盾や葛藤を誠実に言葉にしています。完璧な共感を求めてしまうことに疑問を持ち、問いを深く掘り下げて、懸命に答えを出そうとした姿勢がすばらしいと感じました。
終盤では、「小さな共感をつむぐことが、豊かな社会を創る」という真理に自らの力で到達し、力強いメッセージを発しています。
やさしさをくれた花の声
藤原 柚葉(昭和女子大学附属昭和高等学校 3年)
一輪の花に、こんなにも心を救われる日が来るとは思わなかった。
放課後、なにもかもうまくいかなくて、重たい気持ちのまま部活に向かった。手元はぎこちなく、思うように花がいけられない。気持ちが沈んでいる私に、先輩がそっと言った。「花はね、焦らなくていいって、教えてくれるよ。」
その言葉に背中を押され、私はもう一度花と向き合った。小さな葉、曲がった茎、そっと開いた花びら。無理に整えず、自然のままを受け入れたとき、作品に静かな調和が生まれた。不思議と、私の心もふっと軽くなった。
華道を始めた頃は、ただ形を整え、手本をまねることに夢中だった。しかし、花には一つとして同じものがなく、それぞれに違った美しさがあることを知ってから、私は「どう見せたいか」ではなく、「この花はどう生きたいのか」を考えるようになった。
ある日、完成した作品を祖母に見せると、目を細めて「部屋が明るくなったようね」と笑ってくれた。たった一つの花が、誰かの心を温める。そんな小さな奇跡を、私は何度も目にしてきた。
思うようにいかないときもある。そんなときは、作品を見た先生が「あなたの花は、優しいのね」と声をかけてくれた。その言葉に、私は心が温かくなった。花と真剣に向き合った時間が、誰かの心にも届いていたのだろうと思うと、胸がいっぱいになった。
華道を通して私が大切にしているのは、「ありのままを受け入れ、心を込めて向き合うこと」。
花はいつも無言で私に問いかけ、癒し、気づきを与えてくれる。これからどんな道を進んでも、人や物ごとに誠実に向き合い、小さなやさしさを届けられる人でありたい。
一輪の花のように、静かでも、誰かの心をそっと照らせる存在になれたら――それが、私の願いだ。
審査員のひとこと
華道を通して、自分と向き合う時間をリズム良く描いています。「花と向き合う」ことは「自分と向き合う」こと。作者は花を生けることで自分の気持ちを見つめ直し、丁寧に言葉を紡いでいます。
SNSなどに時間を吸い取られがちな現代にあって、しっかり自分と対話する時間が持てている作者は、素敵ですね。花との対話というテーマにふさわしい、流麗な言葉で綴られた文章はとても魅力的。美しいエッセイとして審査員の心をつかみました。
奉仕の心
井髙 友里菜(四日市メリノール学院高等学校 2年)
聖歌隊に入ってもうすぐ4年になる。聖歌隊は「奉仕の心で歌う」をモットーに、学校行事や施設訪問等様々な場所で歌を届ける部活だ。3年前の冬、聖歌隊で出会ったお客様から私は大切なことを教えてもらった。
2022年12月25日。その日は部員全員が待ちに待ったクリスマスコンサートだった。「言葉をはっきりと」「口を大きく開けて」、練習中に指摘されたことを意識しながら目の前のお客様に歌を届ける。涙を流してくださるお客様を見て思わずもらい泣きしそうになりながらも、無事アンコールを終えた。
私はコンサート後、お客様からの感想用紙を確認していた。お客様の意見を直接伺うことができる機会は貴重である。特に最後の、「ご意見・ご感想」にはお客様の素直な感想が書かれているため、紙をめくるたび緊張が走る。その多くが「感動した」「素敵だった」と私たちの歌声を褒めてくださるものばかりで安心していたが、その中に、私がいつまでも忘れられない言葉があった。
「耳は聞こえなかったけれど、楽しかった」
思わず涙が溢れた。楽しかったと言ってもらえたことへの安堵、その人に歌声を届けられなかったやるせなさ、たくさんの感情が入り混じっていたと思う。
なにより、この人は耳が聞こえないにもかかわらず、私たちのコンサートを見て感想用紙を書いてくださったことが嬉しくてたまらなかった。「歌声が届かなくても、歌の楽しさは伝えられる」と、この人が教えてくれた。
「奉仕の心」とは、一人ひとりを幸せにしようとする気持ちである。歌声は届かなくても、歌の楽しさを伝えられた。私たちは歌を通して心を通わせることができた。
それ以来私は、歌に手話をつけることを提案して毎年手話歌を歌ったり、表情や目線を意識したりして目も耳でも楽しめるコンサートづくりを心がけている。これからも「奉仕の心」を歌に乗せて、お客様と繋がりたい。
審査員のひとこと
聖歌隊で活動している作者は、コンサート後のアンケートで耳が聞こえない方の感想を読み、その人に歌声を届けられなかったことにやるせなさを抱きます。その思いをエネルギーにして、歌に手話を付けることを提案し、目でも耳でも楽しめるようなコンサートづくりに取り組みました。課題の発見から解決に向けて自ら行動する姿勢に、強い感銘を受けました。
日々の出会いの中で、作者が成長していく様子が感じられます。社会に出た後の活躍ぶりを想像させ、期待で胸がふくらみました。
バレーボールが繋いだもの
金子 杏奈(昭和女子大学附属昭和高等学校 3年)
「負けてしまったけれど、本当にいい試合だった。見ているだけで楽しかったし、成長を見ていて泣きそうになったよ。」
引退試合のあと、卒業した先輩から届いたメッセージを読んだとき、胸が熱くなった。
試合中私たちは相手にリードされていたが、声をかけ合いながら少しずつ点差を縮めていった。そして、私にサーブが回ってきた。逆転のチャンスだった。
その瞬間、体育館全体が一体となって響く歓声が、体全体に伝わってきた。まるでその音が振動として、私の体に伝わるような感覚だった。時間が一瞬止まったように感じ、まるでアニメのワンシーンのように、すべてが静まり返った。心の中がクリアになり、サーブを打つ瞬間だけに集中できた。深く息を吸い、落ちついてボールを打った。
そのボールが決まった瞬間、仲間たちが飛び跳ねて喜んでくれた。あの光景は今でも鮮明に覚えている。バレーボール部に入部したのは中学一年生のときで、それ以来、どんなに厳しい練習や試合があっても続けてこられた。最初は思うようにいかないことも多かったけれど、仲間と一緒に練習を重ねることで少しずつ成長を感じられるようになった。
「仲間を信じて声をかけ合うこと」の大切さを感じたのは試合だけではなく、普段の練習でも実感していた。ミスをして落ち込んだ時、仲間からもらった「大丈夫」「次いこう」という言葉が本当に力になった。練習や試合だけでなく、何気ない日々の中で支え合うことがどれほど大切だったかを感じている。
バレーボールを通して出会った仲間たちとの絆は、今でも私にとって宝物だ。勝敗だけではなく、そこに込められた思い出や共に過ごした時間が、私にとって何より大切なものだと感じる。これからも、どんな場面でも人と協力し、信頼し合うことを大切にしていきたい。バレーボール部での六年間が、それを教えてくれた。
バスケオタクの素敵なおじさん達
若林 憲祐(上海外国語大学附属外国語学校国際部 1年)
何度目かの転校は中学入学と同時だった。新しい学校では部活と友達に恵まれ、すぐにバスケにハマった。僕が部活の友達とバスケの練習へと向かったのはコートのある公園だ。しばらくの間は僕達だけだったが、日が傾き始めると三、四十代のおじさん達が数人やってきた。その気迫に僕らはたじろぎ、追い出されることを覚悟した。
一人がぽっこりお腹を揺らしながら近づいてきて“打不打”と試合に誘ってきた。中国語が話せる友達の通訳で、チーム分けをし、ハーフコートの試合が始まった。彼らは毎日夕方にここで試合をしているらしい。その実力は確かなもので、あらゆる角度からポンポンとボールをリングの中に沈めていく。一方僕はパスを受けたところで、ドリブルも、シュートもミスが恥ずかしくてすぐ味方にパスを戻してしまう。そんな僕にぽっこりお腹のおじさんがゴール下で待つように言った。その通りにしていると僕の手にボールが飛び込んできた。絶好のチャンスだ。着地の後、頭上から心地よいネットの揺れる音が耳に響いて、自然と頬が緩んだ。決して上手いとは言えない僕のシュートにも仲間は、真剣な眼差しで“好球”と僕を褒めてくれた。
それから毎週のように、また彼らと試合がしたくて何度も何度も友達と公園に足を運んだ。一つ分かったことがある。彼らは僕達以外にも同じコートにいたならば誰にでも手を差し伸べる。バスケで繋がった見ず知らずの人達との白熱した試合の後は、敵味方関係なく固い握手を交わしてお互いを称え合った。そんな僕も彼らも純粋にバスケが楽しいから、部活でもなんでもないのに集まるバスケオタクだ。誰のものかも分からない汗の匂いと黒くなった手のひらが愛おしくてたまらなかった。
日本から遠く離れたあのコートでは、深く熱い絆が茶色いボールを経て生まれ続けている。あの汗まみれのおじさん達は最高にかっこいいのだ。
低音が支える音と心
白川 心絆(岐阜県立東濃実業高等学校 1年)
放課後の音楽室。十五キロ近くあるチューバを膝に抱え、ベルの奥まで息を送り込むと、床と肺が同時に震える。練習していたのは、コンクール曲。私たち低音パートは、一定のテンポで土台を刻み続ける。
けれどその日、八分音符の入りをわずかに早くしてしまい、合奏全体のリズムが揺れた。すぐに先輩から、「低音がずれると全部がずれるよ。」と注意され、顔が熱くなる。低音は目立たないと思っていたけれど、崩れると全員に伝わってしまう。
休憩中、同じパートの先輩が「一緒にやってみよう。」と声をかけてくれた。三人で譜面をのぞき込み、息の入れ方やタンギングのタイミングを何度も合わせる。大きな管から響く音がぴたりと重なった瞬間、床の振動が心地よく体に伝わった。友達も「低音って難しいけど、決まるとカッコいいよね。」と笑ってくれ、緊張がふっとほどけ、気づけば自然と笑っていた。
吹奏楽は一人では成り立たない。どんなに技術があっても、心が離れていれば音はまとまらない。低音パートは、旋律を奏でることは少ない。けれど、仲間の音を支える喜びや、全体を包み込むような響きは、低音ならではの魅力だ。あの日の失敗と励ましを通して、私はただ音を出すだけでなく、仲間の心まで支えたいと思うようになった。そしてあの日以来、私は誰かがつまづいたときに、「もう一回やってみよう。」と自然に声をかけるようになった。たった一言でも、人の心を軽くし、音を変える力があることを知ったからだ。
「楽器をもてば、学年は関係ない。」先生の言葉だ。先輩、後輩関係なく、これからも私は、低音で部全体のリズムを守りながら、仲間と励まし合い、音楽も心もひとつにしていきたい。そして笑顔の響く音楽室で音を重ねていきたい。ベルの奥から響く音が、私たちの笑顔を運んでくれると信じて。
結果よりも過程
平井 想(駒沢学園女子高等学校 3年)
「カン!」心地よい弦音と「よし!」という矢声が弓道場の澄んだ空気によく通る。この空間が無性に好きだ。私は高校に入学し、袴に憧れて弓道部に入部した。弓道は単に的に矢を中
弓道の射は「射法八節」という八つの動作から成り立っている。その中でも大切なのが「会
私はできない自分を責め、何度も弓道をやめたいと思った。でもここで逃げたら絶対後悔する。だから練習し続けた。それを繰り返すうちに、私は矢を的に中てることだけが成功だと思い込んでいたことに気づいた。弓を引き、心を整え、体のバランスを感じながら伸び合う。それが「会」であり、私ができていなかったことだ。「会」の動作を丁寧に行うことで、矢は自然と的へ向かう。顧問の先生も言っていた。「弓道は中てることがすべてじゃない」と。最初はピンとこなかったけれど、今はその言葉の意味が分かる気がする。たとえ的を外れても、その射に全力を注いだならそれは失敗じゃない。その過程に意味がある。
一年経過した今でも、「早気」は克服できていない。そして、この先何十年もそれと付き合うことになるだろう。もはや直らないかもしれない。それでも私は弓を引く。そう、大事なのは「結果よりも過程」だから。
みんながいたから
柿木 絢心(津山工業高等専門学校 3年)
足が遅かった。陸上部に入れば速く走れるようになると期待して、入部届を提出した。
しかし、入ってみると想像とは全く違っていた。毎日、ひたすらに走り続ける日々。しかも私は、長距離に配属されてしまった。慣れない長距離の練習は想像以上に厳しく、与えられたメニューをこなすこともできず、毎日辞めたいと思っていた。記録会や大会にも出場したが、目標もなく、自分の記録を伸ばすこともできなかった。
そんなある日、駅伝の大会に補欠として同行することになった。私は「駅伝なんて足の速い人を集めたチームが勝つに決まっている」と、どこか冷めた気持ちでいた。しかし、レースが始まると、チーム全員がいつもより速いペースで走れていた。結果は優勝には届かなかったが、全員限界を超えて走っているように見えた。レース後、先輩たちは口をそろえて「みんながいたから走れた」と言っていた。そう言う先輩たちは輝いて見えた。私もいつか駅伝に出たい、チームの一員として走りたい。そう思うようになった。
駅伝に出るという目標ができたため、つらい練習にも意味を見出せるようになった。また、仲間と競い合いながら一秒ずつタイムを縮めていくことが楽しくなった。
そして迎えた中学生活最後の年、ついに駅伝のメンバーに選ばれた。うれしさの反面、自分の走りでチームの足を引っ張ってしまうのではないかという不安もあった。しかし、いざ襷を受け取ると、その不安は吹き飛んだ。応援してくれる仲間がいる。襷を待つ仲間がいる。一秒でも速くつなげたい。そんな思いでいっぱいだった。レース後、タイムを確認すると、自分でも驚くほど速く走れていた。ほかのメンバーも皆、自己ベストだった。そのとき私は、「みんながいたから走れた」という言葉の意味、仲間の大切さをやっと理解することができた。そして私たちも、自然と口にしていた。「みんながいたから」と。