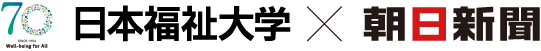入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
わたしが考えるこれからの社会
わたしが考えるこれからの社会 入賞作品
利用者さんの幸せは
介助者の幸せから
仙田 楓(島根県立松江農林高等学校 3年)
毎日のように鳴る母のスマートフォン。その度にイライラする母。
電話の相手は施設で暮らしている祖父だ。私の祖父は祖母が亡くなってしばらくした後自宅で転倒し背中を骨折した。母は一人暮らしは危険だが、一緒に暮らすには狭い家だからと施設入所を決心した。
しかし、その日から祖父は毎日のように母へ電話をかけてくるようになった。はじめは仕方がないと言って温厚に接していた母だったが、何年も経っている今では怒っている母の方が多い。私はいつも怒られている祖父をかわいそうだと思うと同時に、正直他人事のように受け止めていた。
そんなある日、介護の授業で利用者さんの「尊厳」について学び、介助者側の思いが気になった。家に帰りすぐに介護従事者の声をSNSで調べてみると、「辛い」「病む」といった声が多くあった。私は、祖父がいつも母に怒られる原因が私たち家族にあるということに気がついた。
いくら施設に介護職員がいても、家族がやらなければいけないことは多くある。私たち家族はそれを母に任せきっていたのだ。母を孤独にし、そして祖父も孤独にしていた。
それから私は、自分から祖父へ電話をするようになった。
「今日何食べた?来週からテストなんだけど嫌だな。」
こんな日常会話だけど、祖父の笑い声が電話越しに聞こえると安心する。また、「次の休みは家に来てもらおう」と母に提案すると、母は「ありがとう。そうしようか。」と少し笑うようになった。
介護は、利用者と介助者の両者が幸せであるべきだ。そのためには、介助者が心に余裕を持てるように周囲も一緒に介助者になっていく必要があるだろう。利用者さんの幸せは介助者の幸せから始まっていく。
審査員のひとこと
自らの体験を通して、介護の課題の本質が語られています。授業をきっかけに祖父の介護を母1人に背負わせてきたことに思い至り、問題を自分事として考えているところが評価されました。このままでは介護する側・される側ともに不幸という大切なことに気づき、その後の自身の行動の変化に結びつけている点もすばらしかったです。
内容が優れているだけでなく、文章も分かりやすく説得力があり、審査員の心をつかみました。
じぶんいろ
新家 礼響(兵庫県立北摂三田高等学校 3年)
「ナイストゥーミーチュー!」
どきり。私はナイジェリア出身の黒人女性に声をかけられた。小学生の夏休みに参加した、イングリッシュキャンプでの出来事だ。滞在期間中の会話は基本英語。とても不安だった。しかも、当時の私は黒人に対して、何の根拠もないのに怖い、荒っぽい、文化が違って全く分かり合えないなどの偏見を抱いていた。
声をかけられ、私は震えながら自己紹介をした。すると彼女はにっこり笑ってナイジェリアについてたくさんの話をしてくれた。食べ物、自然、服、音楽、生活…。彼女は私に見たこともない世界を見せてくれた。優しさの毛布に包まれているようだった。
キャンプが終わった帰り道、私は「黒人だから○○」という色眼鏡で人を決めつけていたことを本当に後悔した。何の根拠もないのに、そうやって人を見た目だけで判断することは絶対にしてはいけないと思った。そして私のように偏った考え方をする人が少しでも減ればいいなと思った。
数日後、夏休みの宿題の交通安全ポスターを仕上げるため、パレットに絵の具を出していたとき、私は思った。
「絵の具は色とりどりでよいのに、人間の個性は色とりどりじゃだめ?いやいや、そんなこと全くない!」
一人ひとりの色が混じり合ってこそ、この「世界」という絵画は完成するのかもしれない。私は人種、ジェンダー、障害など自分と「違い」がある人を見ると、しばしば関わるのをためらってしまう。でも、そんなときこそ一歩踏み出せるようになりたい。
絵の具は少し水で溶くだけできれいに調和する。人間も、ちょっとしたきっかけで調和できるはずだ。その人にしかない色で自分だけの人生を描き、一人ひとりのよさが溶け合う彩りある社会を構築できるような人間に成長していきたい。
審査員のひとこと
ナイジェリア出身の女性との出会いを題材に、多様性と偏見について取り上げた作品です。肌の色の違いを色とりどりの絵の具の中に感ずる発想が高校生らしく、ユニークで魅力あるエッセイとなっています。色に関連する様々な言葉を盛り込みながら多様性や個性を表現していて、それが効果的に感じました。
「絵の具は水で溶くだけできれいに調和する」という最後の段落に至るまでの展開も良く、作者ならではの表現の豊かさにも魅了されました。
「未知」を「既知」にすれば恐くない。
重村 菜菜子(日本女子大学附属高等学校 3年)
小学6年生のとき、一人の女の子が転校して来た。この時期の転校は珍しいため、クラス中が彼女に注目している中、最初に特別支援学級の先生が教室に入ってきた。
先生が言うには転校して来た彼女は「ダウン症」のようだ。私たちの代には特別支援学級の同級生がいなかったため、私も含め、皆どう反応すれば良いのか、戸惑いがあった。先生は生徒の反応が予想通りだったらしく、以下のように話を切り出した。「人というものは自分が未知の事柄に対し、恐れ、拒絶しようとする傾向がある。だから皆には彼女について積極的に学び関わり、仲良くなって欲しい。」先生は続けてダウン症の基礎知識と共に、彼女の性格なども詳しく説明して下さった。
私たちは最初、緊張はしていたものの「恐れ」や「不安」などは無かった。クラス全員が彼女との交流を図り、仲良くなった。彼女は不思議な力を持っていて、彼女がいるだけで場の雰囲気が明るくなり、ケンカをしていた子たちもすぐに仲直りをした。これには担任の先生も驚き、彼女に感謝を述べた。一緒に学ぶことは叶わなかったが、給食、休み時間、行事などは全て彼女も共に参加した。卒業間際、彼女のお母さんが「泣くことが多かった娘に笑顔が増えたのは皆のおかげだ。ありがとう。」と泣きながら私たちに頭を下げた。
私たちの行動は本人の感情を明るくさせ、彼女の家族をも幸せにしていたのだとそのとき初めて気が付いた。私は安堵と共に嬉しかったことを今でも覚えている。
このクラスは差別が全く無かった。なぜなら、先生の説明により「未知」が「既知」になり、彼女を表面的に見るのではなく彼女自身の内側を見ていたからだと私は考える。世の中には様々な「差別」があり争いを生んでいる。そこにはお互いに未知があり、相手を表面的に見ているのではないだろうか。私は「未知」を「既知」にし、これから出会う人々に対し「一人の人間」として大切に関わっていきたい。
審査員のひとこと
小学6年生のときにダウン症の転校生がやってきたことを描いた作品で、とても良い気づきが示されています。「未知」のものを恐れて排除しがちな人間の心への対応を学び、「知る」ことで壁がなくなった経験を、差別をめぐる議論へ昇華している点が高く評価されました。
深い理解のもとに書かれていることが伝わり、審査員からは「障害者にとって救われる考えで感動した」という声も挙がりました。
チョコレートと41円
小畑 怜子(山口県立徳山商工高等学校 1年)
今日もまた、募金箱に41円がチャリンと音を立てて入っていく。すがすがしい朝を迎えた。
私は高校生になり、よくコンビニを利用するようになったと同時に、お金に触れる機会が多くなった。週に何度かは同じコンビニに通うほどになり、大好きなチョコレートを手に取る。
「ありがとうございました。」と笑顔で商品を渡す店員さんの手には、フェアトレード商品のチョコレートがある。私はふと、中学校で学習した、カカオ豆生産の現状を思い出す。
ガーナをはじめとする西アフリカのカカオ豆生産地域では、学校にも行けずに、朝から晩までカカオ豆の生産や収穫をする子供たちがいる。カカオ豆の収穫には刃物を用いる。大変危険な作業だ。まだ幼い子供が危険を冒してまで仕事をするのに、賃金は低く、自分たちが作ったチョコレートの味すら知らない。
また、発展途上国の作ったものが、先進国との貿易で適正な価値で取引されないことも多い。「1つのチョコレートに、どれだけの人の苦労が詰め込まれているのだろう。私にできることはないのかな。」
フェアトレードのマークを見ながら思う。「募金をしよう。」そう思って始めた私の募金活動は、今日で2か月目を迎える。
このチョコレートが私の手に届くまで、たくさんの人の手によって運ばれている。普段の何気ない日常の中にも、そのようなものが多くある。どんな小さなものでも、たくさんの人に支えられている。そう気づくきっかけをくれた、このチョコレートに感謝を込めて募金をする。
「ありがとうございます。」と笑顔で商品を受け取る私の手には、チョコレートと41円のお釣りがある。“終始良いご縁がありますように”という意味が込められた41円が、今日もチャリンと音を立てて積み重なる。
審査員のひとこと
購入したチョコレートのおつりを募金する行動を通して、途上国の課題に想いを寄せる様子が綴られています。作者はフェアトレードに関心を持ち、原料のカカオ豆の生産現場や児童労働といった世界が抱える問題へ視野を広げていて、小さなチョコレートに大きな意味を見いだしたことに感心しました。
文章は冒頭と末尾をうまく重ね合わせていて、構成もしっかりと練られています。第3分野のテーマに沿った内容で、世界に目を向けている点も評価されました。
一人の人間として、その存在を
大杉 勇介(鈴鹿工業高等専門学校 2年)
言わなければよかった。
「男」も「女」もしっくりこない。「中性」に近いが「どちらでもない」という方がしっくりする。それが私の性だ。
私は女の子といることが多いためか、性について聞かれることが多い。聞かれるようになったのは中学生の頃からだが、進学してからもそれは変わらなかった。
ある日、「男なの?女なの?」とクラスメイトに聞かれた。私は自分の性がコンプレックスではなかったので、いつも通り「どっちでもない。」と答えた。返ってきたのは
「生物学的にまちがっている。」
その返答に対し、私は何も言えなかった。言われた言葉より、その言葉に納得した自分が何よりも嫌だった。それからは自分の性は隠そうと思うようになり、性について聞かれても「男」と答えるようになってしまった。
半年ほど過ぎた時、10代のLGBTについての記事を見つけた。記事を読み、10代のLGBTの1割超が自殺未遂を過去1年で経験、全国調査と比較し、高校生の不登校経験は10倍にもなり、9割超が教職員、保護者に安心して相談できていないということを知った。
中には親に相談したら「死んでほしい」と言われたという人もいた。
勇気を出して相談したら、否定され、笑いものにされる。LGBTという言葉自体は以前よりも広まってきたが、他人事に捉え、心無い言葉で傷つけている人がいる。その事実を改めて見直し、この現状を変えるために、私ができることを考えるうちに他人事に捉えてしまっている人の中には「身近にいないから」と感じている人が多いと知った。より身近に、より課題として感じてほしいという思いから、私は自分の性を隠すことをやめた。
同情してほしい訳でも、特別扱いしてほしい訳でもない。一人の人間として、その存在が認められてほしい。「言わなければよかった」と嘆く人がいるこの世界を私は変えたい。
審査員のひとこと
自身の性と向き合い、性的指向や性自認の多様性を認め合える世界にしたいという作品です。自分の中の気持ちの揺れが綴られ、最後は強い意志とともに締めくくられています。
作者の決意をたたえるとともに、この作品が寄せられるほど、この問題への関心や議論の重要性が高まっていると感じました。
ストーリー展開やデータの提示、自身の主張等の文章構成も適切で、エッセイとしてもまとまっています。
私の選択
伊藤 夕里子(愛知産業大学三河高等学校 2年)
弱い人を強い人が助ける世界。もっと言えば障害者を健常者が助ける世界。これこそが社会のあるべき姿だと私はずっと考えていた。
入学後すぐに、想像とはかなり違う高校生活に私は戸惑いを覚えた。強い人が弱い人を見下し、利用する小さな社会がそこにはあり、それに抗う勇気の無い私は入学して2ヶ月で適応障害と診断された。
そんな時、知的障害者支援施設の職員として働く父から「夏休みに中高生向け放デイのボランティアに来ないか。」と誘いを受けた。ダウン症の兄のおかげで放課後等デイサービスというものを知っていたからこそ、自分の事だけで精一杯な今の私にできるのかどうか悩んだ。しかし、暗い気持ちのままでは良くないと思い、父の誘いを引き受けた。
覚悟はしていたもののスタッフとして、とても神経を使ったし、かなり大変な事も多かった。そんな日々の中で、私の考えが大きく変わる出来事があった。
川に出掛けた日、ある利用者の女の子と手を繋いでいる私の姿を他のスタッフが写真に撮ってくれた。後日、その写真を家に持ち帰ると、母が「夕里子の笑顔が戻ってきた。」と嬉しそうに話しかけてきた。確かに私は高校に入学してから上手く笑えなくなっていたが、そこに映る私は以前のようにキラキラと楽しそうに笑っている。そう、私は彼女を助け支援していただけではなく私も彼女に助けてもらっていたのだ。
助けるはずが助けられていたと気づいた瞬間、弱い人を強い人が助けるべきという私の中の凝り固まった価値観は、まるでオセロのようにパタパタとひっくり返っていった。
人の一面に過ぎない強さ弱さで価値を判断する危うさに気づいた私は、抗う勇気を出して転校することを決心した。これは、違和感がまとわりつく社会に適応するのではなく、社会を作っていく選択に繋がると信じている。
全ての人がお互いに助け合い、支え合う世界、これこそが私が考えるこれからの社会だ。
審査員のひとこと
知的障害者を支援するボランティア体験で得た気づきがうまく描かれています。強い者が弱い者を助ける「する・される」という発想から一歩進んで、相互が主体となる「する・する」という関係性を発見したことに、作者の成長を感じました。
自身が直面する問題についてもきちんと向き合い、自らの決意が表れていることにも好感を持ちました。
知ることで見えるもの
安室 美咲(沖縄県立那覇高等学校 3年)
ある日の学校からの帰り道。歩行者の信号は青なのに渡らず、ずっと立ったままの人がいた。近づくとその人の手には白杖がにぎられていた。
「何かお手伝いしましょうか?」
最初は声をかけようか迷ったが、そこは音響信号機だったのに渡らず、立ったままなのが気になって話しかけてみた。私は、盲目の人は何も見えなくて真っ暗なものだと思っていたが、光が分かる場合もあるらしい。その人も光は分かるそうで、曲がろうとしたが歩行者が渡るのを待っている車の光が見えて、いつ車が来るか分からず渡れないでいたそうだ。私はそのまま案内を頼まれ、一緒に歩いた。その途中、とても短い横断歩道があったが、点字ブロックがなくて私が声をかけながら渡った。案内を終えるとたくさんお礼を言われ、私は今までにないくらいに嬉しい気持ちになったが、それと同時に、少し歩いただけでもこんなに視覚障害者にとって不便な所があるのかと思った。
私は今まで音響信号機があれば視覚障害者も問題なく渡れると思っていたし、自分は問題がなくても、他の人にとっては不便だと感じる場所があると考えたこともなかった。しかし、意識して道を歩いてみると、音の鳴らない信号や点字ブロックのない道、点字ブロックはあってもその上に自転車などの障害物が置かれていたりした。この他にも私が気づかないだけでまだまだたくさん不便に感じているところがあるだろうし、視覚障害者だけでなく他にもたくさんの人がそれぞれ不便に感じているところがあると思う。
私は、たまたま視覚障害者と関わることができて、道を歩いている時に不便に感じている所など、知らなかったことを知ることができた。きっと、あの人と出会ってなかったら知らなかったことだ。もっといろんな人の考え、思っていることを知り、それを暮らしの中に反映していく必要があると思った。そうすれば、みんなにとって暮らしやすい社会に近づくだろう。
出会いの中で
永田 優杏(日本福祉大学付属高等学校 3年)
私がアルバイトをしているコンビニには常連客のおじいちゃんがいる。コロナ禍だからか一言も話さず、ジェスチャーだけでレジを済ます人で、不愛想な人だなと思いながら対応するのだが、いつも帰り際ニコッと笑ってくれるので、よく分からない人だと出会ったころはそう思っていた。コロナの蔓延もおさまってきたころ、常連客のおじいちゃんのレジ対応中にどうしてもジェスチャーが理解できないことがあった。「どういう意味ですか、これですか、あれですか。」と声をかけてみても、おじいちゃんは変わらず首を横に振ったり、よく分からないジェスチャーをするばかりで、困った私は店長に対応をかわってもらった。おじいちゃんはその日もいつものようにニコッと笑って帰っていった。
おじいちゃんの対応を終えた店長に「あの人のジェスチャーって分かりにくいですよね。」と愚痴のように私が言うと「そうだね。あれは手話だからね。」と店長が答えてくれた。その時、私ははじめて障がいと向き合った気がした。そして、誰もがすごしやすい社会について考えるようになった。公共施設にバリアフリーの設置をするだけでなく、障がいがない人がもっと障がいに対して柔軟な考えや対応力をもつことが大切だと、私は思っている。
今、私は、数字などを表す簡単な手話を覚えたり、メモ帳を使って筆談をすることでおじいちゃんとスムーズにコミュニケーションがとれるようになった。おじいちゃんは変わらず帰り際ニコッと笑ってくれる。あの笑顔にはどんな意味が込められているのだろうか。ただ、あの笑顔1つで私はとても幸せな気持ちになる。表情で相手に何かを伝えること、これも素敵なコミュニケーションの1つだ。おじいちゃんに出会って会話だけではない心温まるコミュニケーション方法を学んだ。これからもたくさんの人との関わりの中で、誰もが健やかで幸せな日々を送れるように探求をし続けたい。
幸せの形
川上 柚奈(日本福祉大学付属高等学校 2年)
「幸せ」という言葉は、当たり前にくり返される日常とは無縁のものだと思っていた。
「また明日ね」これは友達との帰り道、かかさず言う言葉だ。自分の近くにいる人は、明日もその次の日も季節が変わっても、当たり前に隣にいる気がしている。誰1人も保証された明日があるわけじゃないのに。私は毎日仮約束の言葉を言っていた。
私は、6人家族の長女だ。去年の春から私は、お母さんと弟3人で、お父さんとは別々で暮らし始めた。でもこの生活は3ヶ月ほどで幕を閉じる。その生活には、割とすぐ慣れていき、高校も楽しかった半面、お父さんが頭の中にずっと居た。連絡がマメだったお父さんだから、待っていればいつか連絡が来るはず、住んでる所は近いからいつかどこかで会うはず、そんなことを思って過ごしていた。連絡はまた今度でいいや。そんな私の考えが裏目に出ることになる。
8月18日、私の誕生日の日、3ヶ月間連絡が途絶えていたが、今日はお父さんからおめでとうと言ってくれると思っていた。でも1日中待ってても連絡が来ないまま、次の日の朝になり、私の誕生日にお父さんが亡くなったことを耳にした。私は心底後悔した。なんでまた今度でいいと思ったのか。待ってればいつか会えると思ったのか。今度なんて、亡くなってからじゃ遅いのに。たくさん泣いたあと、お父さんに会いに行った。私の大好きなお父さんだった。呼んだら起きそうなのに、いくら呼んでも返事は無かった。
その日から私は、毎日が訪れることを当たり前ではなく幸せだと感じられるようになった。人にも以前より優しくなれたと思う。
「幸せ」は決して特別なものではなくて、日常にありふれている。それを自覚すれば誰でも幸せになれると思う。それに気づかせてくれたのは世界に1人だけの私のお父さん。ありがとう。お父さん。
笑顔の力
上田 結愛(京都聖母学院高等学校 2年)
「あなた、だれ?」ばーちゃんは間違いなく私にそう言った。ばーちゃんの中にはもう私は居なかった。
最後に私が会った時、ばーちゃんは「もしばーちゃんが死んじゃったら、この旅行の記録を柩に入れてね。」そう言って私に笑いかけた。もしかしたらもうその時には自分で自分の病気に気づいていたのかもしれない。そんな時、「新型コロナウイルスの今日の感染者数は1万人を越えました。」気づいた時にはもう2年、おばーちゃんとのあるはずだった時間は奪われてしまった。そしてやっと会える!そう思った頃にはもう、ばーちゃんの中に私は居なかった。それを知った時、私は1人で泣いた。今までの思い出が全て消えていることが怖かった。でも、夏休みの間一緒に過ごしていくうちに、ばーちゃんは私を思い出していた。そして名前を呼んでくれた。そんなことはあるのかと、とても驚いたが、それよりもすごく、すごく嬉しかった。明日になったら忘れているかもしれない、そう思うことはとても怖かったが、それよりも今を大切にすることを、ばーちゃんと一緒にいれる時間を大切にしよう。そう考えることにした。
ばーちゃんに「元気でね、またね。」とお別れをした後、残りの時間とどう向き合うかを考えた。いろんな気持ちがごちゃごちゃになって、考えるとつらくなる。でも向き合わなくちゃいけない。そんな気持ちの中から出た私の答えは、「ばーちゃんにいっぱい笑ってもらおう。」ということだった。私は、昔からよく笑うばーちゃんが好きだった。「どんな状況でも笑うことは出来る、だったら笑ってほしい。」そう思った。
今年の夏も、ばーちゃんに会えることになった。もしかしたら、私のことを忘れているかもしれない。けれど、私はどんなばーちゃんでも笑顔にさせると決めている。私は全ての人に、笑顔になるのに記憶は関係無いと伝えたい。だから私は笑顔で言う。「ばーちゃん、ただいま!」
人と家との関わり
森田 美音(桜美林高等学校 2年)
父方の祖母が老人ホームに入ったのは6年前のことである。祖父が亡くなってからの数年間、独りで住むには広すぎる家で祖母は暮らしていたが、老人ホームに移ると同時にその家も売り払うことにした。私が最後に訪れたのは、売る直前に家の中の物を整理するときだった。物がほとんど無くなった家の中を見回すと、思ったより広かったことへの驚きと同時に、この家での思い出が消えてしまう淋しさを感じた。夏休みに水遊びをしたこと、祖父と倉庫で遊んだこと、毎年大晦日に共に年越しをしたことなど、この家には沢山の思い出が詰まっていた。10数年しかこの家と関わりのない私が淋しく感じているので、この家で育った父や50年以上暮らした祖母が私以上に淋しさを感じていたことは表情から伝わった。この家にも近所の公園にも神社にも、もう来ることがないと気づくと、今までの一瞬一瞬が儚く感じた。
老人ホームに入居後、初めて祖母に会ったのは入居してから2年が経った夏だった。私は広大な庭も、思い入れのある家も無くなり、10分の1の大きさになった部屋に住むことになった祖母が家を売ったことを後悔していないか不安だった。しかし、私の予想に反して祖母は元気で幸せそうな姿で現れた。白髪は増え、以前会った時よりも腰は曲がっていたが、表情は私が今までに見たことがない程、生き生きしていた。祖母に理由を聞くと、同年代の人と話すことが増えたり、新しいことに挑戦することが増えて毎日が楽しいと言う。タバコの本数も大幅に減ったと言っていた。
私はこの経験を通して、祖母に必要だったのは広大な家ではなく、人との関わりだったことに気づき、年を重ねても過去に囚われず、新しい挑戦ができる祖母を、とても尊敬するようになった。スマホが普及し、人間関係の問題もインターネット上で何とか解決しようとする私たちに必要なのは、人と直接関わることかもしれない。