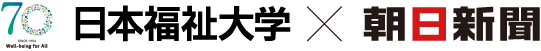入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
ひと・まち・暮らしのなかで
ひと・まち・暮らしのなかで 入賞作品
笑顔のバス
佐伯 理奈(光塩女子学院高等科 2年)
「冷たいお水と、保冷剤と、ハンディファンも持った。よし、行ってくる。」
母に声をかけて私は家を出た。我が家から70m程先にあるバス停の前にある集合住宅に住むたっくんは、人懐っこい性格でバスが大好きな4歳の男の子だ。バス停でバスを見るという日課を持つたっくんに付き添うたっくんのお母さんとは、いつからか挨拶を交わすようになった。そして、やり取りをするなかで、たっくんが闘病中で赤ちゃんの頃から入院と退院を繰り返していることを知った。
ひょんなことから、夏休み中の5日間、私はたっくんの日課に同行することになった。ほんの15分程のこととはいえ、小さなたっくんがうだるような暑さで体調を崩さないか心配した私は、入念な準備をして臨んだ。そんな私の心配をよそに、炎天下でもたっくんは、元気にバスに関しての豆知識を話し続け、お目当てのバスが来ると嬉しそうにはしゃいだ。つないだ手を通して、たっくんの喜びが伝わってきた。可愛さ、この上なしだ。しかし、5日目はたっくんの口数が少なかった。そして、去っていくバスの後ろ姿を見ながら、
「バスのお顔が寂しそうだったね。明日から、たっくん、病院だから。会えないからかな。」
と消え入りそうな声で言った。寂しいお顔なのは、寂しいのは、たっくんの方なんだね。私はつないでいる小さな手をぎゅっと握った。
たっくんを送り届けて自宅に戻った私は、画用紙を出してきて黄緑色のバスの絵を大きく描いた。バスの表情は、もちろん笑顔だ。祈りとエールを込め、丁寧に仕上げた絵をたっくん宅の郵便受けに入れておいた。
数日後、塾から帰宅すると郵便受けに黄緑色のリボンが付いた筒状の紙が入っていた。その場でリボンを外すと思いっきり口を開けて笑っているバスの絵が現れた。たっくんが笑ってる!安堵に包まれ、胸が熱くなった。たっくんが戻ってきたら、また笑顔のバスを見に行こう。涼しげな風鈴の音が聞こえた。
審査員のひとこと
バスが大好きな男の子と作者の交流が生き生きと描かれた、気持ちの良い作品です。バス停の風景や絵を通して会話する様子といった、様々な情景が鮮やかに目に浮かび、審査員一同高く評価しました。
持病のある幼い子を見守る不安な気持ちや、微笑ましいやり取りの中で生じた感動をみずみずしく素直に書いていて、作者のこまやかな心遣いや男の子を想う温かな気持ちも伝わってきました。文章、構成ともにすばらしく、余韻の残る終わり方もとても良かったです。
「生かされた命」を大切に…
土井 杏華(愛媛県立松山盲学校高等部 2年)
7月19日、私の誕生日に母が毎年かけてくれる言葉があります。「生まれてきてくれてありがとう。本当にここまでよく育ったね。」
私の母は、出産のための里帰り前日の平成18年7月18日、自宅近くの個人病院に、念のため健診に行ったところ、「羊水しか見えない」という思いもよらない宣告を受けました。大きな病院に救急搬送され、緊急手術。私は26週792gでこの世に生まれてきました。片手に乗る位の大きさだったそうです。眼の機能が十分に育っておらず、一刻を争うことが分かり、愛媛からドクターヘリで大阪大学医学部附属病院に搬送され、入院しました。数えきれない程の注射や手術で、看病する家族も辛かったそうですが、そこで眼科の名医と出会い、私の眼は救われました。弱視というハンデはありますが、まだ見えています。
私は地元の中学を卒業後、松山盲学校高等部に入学しました。寄宿舎生活は不安でしたが、自分でできることが増えました。また、タブレットで教科書を見る、携帯型の拡大読書器を使うなど、自分の見え方にあった学習方法や、自分の「見えにくさ」と付き合っていく方法を知りました。家庭科のミシン掛けや調理実習では、中学までは他の人より時間がかかっていつも焦っていたけれど、視覚障がい者が使いやすい器具や道具を使えば、「見える人」と変わらない活動ができることを知りました。聴覚を頼りとするSTT(サウンドテーブルテニス)という競技と出会い、部活動も楽しくできています。
どの命も奇跡だと思うけれど、私の命もまた奇跡的…。たくさんの人がつながって、私の命と眼が助けられたことをしあわせだと感じています。「生かされた命」であることに感謝を忘れず、障がいがあっても、それに負けることなく強く生きていきたいです。
もうすぐ17回目の誕生日、今年は私の方から母に言ってみようと思います。「お母さん、私を生んでくれて、ありがとう。」
審査員のひとこと
授かった命を大切に思い、前向きに生きる作者の姿がストレートに伝わってきて、強く胸を打たれました。自身の生い立ちを飾り気なく綴った言葉には、周囲の人々の力添えによって自分がここまで生きてきた、育ってきたことへの実感がこもっています。どの命も奇跡であり、生きる喜び、母への想いが伝わるメッセージ性の強さを評価しました。
結びの「私を生んでくれてありがとう」という母への一言が感動的で、エッセイとして大事なことを伝えてくれています。
当たり前がくれたもの
粟野 愛(桜美林高等学校 2年)
「いってらっしゃい。」
私の通学路には、いつも花が綺麗に咲いている家がある。朝、花の手入れをしているおばあさんは、いつも私にそう挨拶をしてくれる。でも、正直言って名前も知らないし、照れくささもあったのでいつも少し目を合わせて会釈するだけで終わっていた。
そんなある日、そのおばあさんは姿を見せなくなった。花の手入れの時間を変えたのだろうか、どこか体を悪くしてしまったのだろうか。前者であると信じていたかったが、その家の花は段々と元気がなくなっていった。いつもの通学路のはずなのに、どこか寂しいその道を通りながら、当たり前だったあのおばあさんの挨拶は、いつも私を支えてくれていたのだと気づいた。大事なテストの日、友人と仲直りしたかった日、あの挨拶は必ず私の背中を押してくれた。いつかまたおばあさんがこの花の手入れをしに戻ってきたら、その感謝を伝えたいな。
しばらく経ち、見知らぬおじいさんがその家の花の手入れをしていたので、思い切って声をかけてみると、その人はあのおばあさんのご主人で、おばあさんの代わりにこの家の花の手入れをしていたらしい。少しお話をして、おばあさんが亡くなってしまったこと、おばあさんは毎朝花の手入れをしながら私たち子どもの顔を見るのを楽しみにしていたことなどを聞いた。なぜ私はあの挨拶に応えてあげられなかったのだろう、こちらがあんなにも元気をもらっていたのに、私は他の子どもたちのようにおばあさんの楽しみになれていたのだろうか、と後悔が込み上げてきた。
今日もあの家には綺麗に花が咲き乱れ、おじいさんがその手入れをしている。こちらに気づいて声をかけてくれたその姿が、あのおばあさんと重なる。もう遅いかもしれないけれど、私にできる恩返しをしたい。当たり前がくれた元気に微笑みながら、迷わず応える。
「いってきます。」
審査員のひとこと
いつも通学路で声をかけてくれたご近所の方が姿を見せなくなったことで、作者が得た気づきを描いています。こまやかな観察眼のもとに日常の1コマをまとめ上げていて、静かな筆致の中に繊細な心の動きがよく表現されています。
失って初めて当たり前の大切さに気づいた作者の後悔が伝わる一方で、その後、自ら行動を起こしている点に希望を感じました。冒頭の「いってらっしゃい」と末尾の「いってきます」もうまく繋がり、効果的でした。
ありがとう
金城 倫奈(沖縄県立那覇高等学校 3年)
私には、脳性マヒにより肢体不自由で歩くことができず、車椅子で生活を送っている妹がいます。妹はリハビリ施設に通い、自分で出来ることも沢山ありますが、生活の中ではベッドに寝かせる時や、車椅子にテーブルをつける時など、サポートが必要な場面がいくつかあります。
ある日、私が疲れて休もうとしている時に、妹が「姉ちゃん、テーブルつけてちょうだい」と言いました。「めんどくさい」そう思った私は、妹の声を聞こえていないフリをして眠ろうとしました。妹は私の顔色を伺い、気を使ってそれ以上何も言いませんでした。妹の頼みを断ったことに罪悪感を感じた私は、重い体を起こして仕方なく、妹の車椅子にテーブルをつけました。すると妹は屈託のない笑顔を私に向け「ありがとう」と言いました。そう言われた時、胸が締め付けられる思いになりました。10秒もかからない行為なのに、面倒だという自分の気持ちを優先した私と、やりたくてもできない状態で、サポートをお願いした人に嫌な態度を取られて「ありがとう」と言える妹。私は自分が恥ずかしくなり、妹に対する申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。妹はどんな気持ちで私に「ありがとう」と言ったのだろうか。考えれば考えるほど、数分前に自分が妹に対してとってしまった行動を後悔しました。私も妹のように優しくなりたい、妹が気を使わずになんでも頼めるような人に変わりたい、と思いました。
人は皆、頼りながら生きています。「頼る」ということは人によっては難しいことであり、勇気のいることだと思います。私の妹は車椅子に乗って生活している分、他の人よりも人に頼る回数が少しだけ多いのかもしれません。妹は今まで勇気を出して沢山の人に頼りながら、そのたびに応えてくれた人に「ありがとう」を言ってきたのだと思います。「頼ってくれてありがとう。」妹のように心から「ありがとう」が言える人になりたいです。
審査員のひとこと
障害のある妹との間で生じた自分の中の葛藤を正直に書いた作品です。妹の要望にすぐに応えられなかった後ろめたさも含めて、自身の心の動きを丁寧に追っていて説得力があり、姉として表に出しにくい気持ちに向き合っているところに共感を覚えました。日常の小さな体験をきちんと考え、葛藤を乗り越えている点も評価したいと思います。
文章は無駄なく具体的で、よくまとめ上げられています。
ばあちゃんがくれた宝物
森下 礼智(第一学院高等学校 2年)
「ええと。名前なんだっけ?ああ、思い出したよ。デンキ(蛍光灯)のライトだったねえ。」僕と89年も歳の差があるばあちゃん(曾祖母)はいつもにこにこして僕の顔を見るたび、何とか衰えていく自分の記憶をつなぎ留める様に、部屋の照明器具になぞらえて僕を忘れまいとしてくれていた。
曾祖母は98歳の頃、会話が出来なくなってしまった。笑顔が消えて何も話さず1日中横になり痩せていく姿を見ていて、僕は幼いながらも「可哀想。」とショックを受けた。
「いつか人は死んでしまう。それなら一体、何のために人間は生きているのだろう。」僕がそんな自問を続けているうちに、曾祖母が100歳目前で亡くなってから数年が経った。
ついに遺品を片付ける事になり、家族のだれも開けた事がなかった桐タンスを整理する日が来たのだ。引き出しの中には、80年以上前に友人と書きあった遊び心のある暑中見舞いや古い写真の束が出て来た。きりっとした袴姿で女学校に通っていた10代の姿。こども(僕の祖父)が生まれて母となった姿。畑で地域の人達とお茶を飲む姿。そして、孫である僕の母が小さい頃にプレゼントした手紙や沢山の絵、ひ孫である僕が保育園のときあげた粘土細工の飾り。そこには、生前に曾祖母が大切にしていた、人とのつながりの痕跡が残されていた。
「あっ。」と気づいた。「ばあちゃんの人生は、可哀想なんかじゃなかったのだ。」僕が見ていた晩年の姿は長い人生の僅かな時間に過ぎなかった。苦労も沢山あったと思うが、家族に愛され、地域の人達と共に支えあい、精一杯生きた心豊かな人生だったのだ。
「ばあちゃん。僕も精一杯、自分の時間を大切に生きるよ。いつか、天国で再会する時に僕も沢山の思い出を宝箱に詰めて持って行くからさ。お土産話を聞いてね。」
曾祖母が気づかせてくれた事を胸に、限りある人生を大切に生きようと心に誓った。
審査員のひとこと
亡くなった曾祖母の桐タンスを開けたときに生まれた気づきを、若者ならではの感性でみずみずしく書いています。よく練られた構成で「ばあちゃんの人生は、可哀想なんかじゃなかった」と、心が満たされていく様子が伝わり、最後まで引き込まれながら読み進めることができました。
桐タンスに詰まっていた曾祖母の思い出から作者が得たものは、まさに宝物。これからの人生にプラスになるのではないでしょうか。内容にぴったりのタイトルも素敵でした。
言葉の魔法
小栁 香(並木学院福山高等学校 1年)
「もうちょっとスピードアップできる?」
マネージャーの声が厨房中に響き渡る。物を置く音、よく分からない機械音、知らない人たちの話し声。聞こえてくる足音はどれもせかせかとしていて、いかにも忙しそうだ。今から初めてのアルバイトが始まる。私もついていけるかな。ざわざわと絶え間なく続く音に伴って、私の胸の中にも雑音が響き出す。
「やってみようか。」
レジ打ちをしていた先輩が、振り返って話しかけてきた。この制服を着ているということはあなたはもうお店の顔です。マネージャーが言っていた言葉が、頭の中でループする。変なことしないようにしなきゃ。私は緊張感を無視して、思いっきり声を出した。
「いらっしゃいませ…」
だめだ、声が小さい。もっと大きな声を出さなきゃ。聞こえてくる注文にもなかなか追いつかない。お客さんたちが顔を曇らせていく様子に、グサグサと胸を刺される。ドクドクドク…大きく早く変わっていく心拍音が、更に緊張感を掻き立てた。
一人のおばあさんが、にこにこしてカウンターに近づいてきた。気持ちを奮い立たせ、今度は大きな声で私は言った。
「いらっしゃいませ。」
おばあさんは私を見て更に笑いかけた。
「あら、研修生?頑張ってね。」
パッ。モヤモヤとした私の心が瞬時に軽くなった。まるで魔法にかけられたみたい。
「大丈夫よ。」
おばあさんは終始私に笑いかけ、温かい言葉を投げかける。言葉だけで、こんなに気持ちが楽になるなんて。
「ありがとうございます。」
私も笑顔とともに頭を下げていた。私に足りなかったのは言葉の魔法なのだ。
今もざわざわとした音が店中に響いている。これからここで、私も優しい言葉で魔法をかけよう。周りの人へ、そして自分自身へ。
審査員のひとこと
言葉のリズムが良く、文章にスピード感があるため、慣れないアルバイト先での作者の緊張がひしひしと伝わってきます。臨場感たっぷりに描かれた慌ただしい職場と、笑顔で温かな言葉をかけてくれるおばあさんとの対比も効果的でした。
テーマに沿った内容で、構成や会話の流れもうまく考えられ、エッセイとしての高い完成度が評価されました。改行や字下げ、文章の書き方のルールを守って書いているため読みやすく、その点も高評価に繋がりました。
『母娘を繋ぐいただきます』
佐藤 有衣(日本女子大学附属高等学校 1年)
「いただきます」と小さく手を合わせる、至福の時。コロナも5類に引き下がり、みんなと机をくっつけながらお弁当を食べられるようになった。お弁当を食べながら、友達と話す昼休みはほっと一息できる。中学の3年間は黙食が徹底されていて、黒板を見つめながらただお弁当と向き合っていた。しかし、私は黙食が嫌いだった訳ではない。友達と話せない分、母の作るお弁当に幸せを感じていた。
小学生までは2段弁当を使っていたが、中学生の頃から大きめの1段弁当を使い始めた。蓋を開けると、パッと鮮やかなおかずたちが一斉に顔をのぞかせる。「美味しそう。」と心の中で呟き、小さく手を合わせて「いただきます」と言う。新学期、新しい環境に慣れるのに時間がかかる私にとって、母のお弁当は心の拠り所だった。1時間目から4時間目までの栄養補給、そして5、6時間目の活力となり、私のお腹と心を満たしてくれた。中3の時、私の学校生活を彩ってくれたお弁当について文章を書く機会があった。私は、毎日お弁当を作ってくれている母に質問をしながら書いていた。すると、母が思いもよらぬことを言った。「毎日、友達ができないとか言ってたじゃん。だから、少しでも安心できるような時間になればいいなって思ったの」と。私は驚いた。母のその気遣いは、お弁当を通じて私の元へと確実に伝わっていた。どんなに仕事が忙しくても、早く起き、お弁当を作り続けてくれた。私がお弁当箱を洗い忘れ、翌朝迷惑をかけたこともあった。お昼の時間になると、たまに母の言葉を思い出す。母が作るお弁当は、学生のうちにしか味わえない。苦い思い出も、楽しい思い出も丸っと包み込み「美味しかった」に変えてくれる。その包容力が、お弁当にはある。だからこそ、お弁当を作ってくれている母に「ごちそうさま、美味しかったよ」と言葉で伝えたい。
おっと危ない、空になったお弁当箱を洗ってから寝よう。
そふからのめーる
山川 真菜夏
(Gems American Academy Abu Dhabi 2年)
「しやしほしいうい、なかのおよいでるところ」
これは昨年、私の祖父が携帯に送ってきたメールだ。実際は「写真欲しいマナカの泳いでいるところ」と打ちたかったのだろう。祖父は携帯の使い方をよく理解しておらず、頻繁に単語を打ち間違えてしまう。しかし、この解読が不可能に近いメールは、今は親の転勤で海外に住んでいる私(マナカ)と1人で日本の介護施設に住んでいる祖父を結ぶ大切な連絡手段だ。
1年前に祖母が亡くなった後、私は耳が遠い祖父を励ますため、電話の代わりにメールでやり取りを始めた。私と祖父のメールは、主に気温の変化や学校生活などの近況報告を綴るためだけに使われているが、お互いの意思疎通において、最も不可欠な手段にもなっている。私は祖父からのメールを読み続けたことで、どれだけ難解な文章であっても、そこに込められている意図を推測できるようになった。また、どのような文章が祖父にとってわかりやすく、読みやすいかをよく考えてから返事を書くようにもなった。一方、祖父に至ってはメールの内容や構成面での進歩が目覚ましく、最近は「!」や「?」のマークを覚え、時にはハートの絵文字を文末につけて私に送ることもある。
祖父はありふれた日常を共有するだけのメールであっても、常に私のことを考え、何を伝えようか思いを巡らせてくれている。だからこそ、私は祖父の怪文への返事を欠かしたことは1度もない。ただ、メールでは感謝の気持ちを表現する機会が少ないため、私は次の祖父の誕生日には「おじいちゃん、はなれていてもだいすきだよ!」と普段は照れくさくて言葉にできない文章を贈りたい。また、私は人と心を通わせ、遠い距離からも相手を身近に想い続けるためには巧妙な文章よりも、相手のことを考える気持ちが必要だと祖父から学ぶことができたと思っている。
まちの共存
小野里 春花(日本女子大学附属高等学校 3年)
以前、市と大学生が運営している児童のためのボランティアに参加した。それは、市が場所や費用を提供し、有志の大学生数名が集まって計画や実行をしているというもので、普段、私が「ボランティア」と聞いて想像する、地域の大人中心の慈善活動とは違う、その新鮮さと身近さに惹かれ、応募した。
当日の私の役割は、子どもの宿題を一緒に解くこと。緊張と不安があったが、目的地の扉を開くと、子どもの大きな笑い声が行き交っていた。大学生と小学生だけの異様で、どこか温かい空間で、まずその団体の説明を受けた。勉強を教えること以外にも、子ども食堂やミニ運動会など、ほぼ毎日夕方にはボランティア活動を行っていると知り、疑問に思った。
「なぜ、そこまで誰かのために動けるのか。」
返ってきた答えはとてもシンプルだった。「他人に一方的に慈善をしている訳じゃない。僕たちも助けられている。だから何度でもしたいと思うんだ。」
初めはどういう意味なのか、よく分からなかった。誰かのためになりたいという想いだけが、ボランティア活動の主軸だと考えていたのだ。しかし、賑やかさに包まれながら段々とその言葉を理解した。仕事と子育てに挟まれた親が、少しでも自分の時間でリフレッシュできれば、より働きやすく、より子どもに接しやすくなる。また、大学生は子どもとの話が1日の楽しみというほどその時間に大きな意義があったり、自ら運営して社会でのスキルを培えたりと、皆のかけがえのない「居場所」がそこにはある。
私は、まちづくりの本質を見た気がした。「誰かを助けたい」というよりむしろ、そのコミュニティーで、共に活動そのものを作り上げていく中で、それを提供する側も受容する側も、それぞれが個人の在り方を確立していく。そんな共存の関係ひとつひとつが、誰かの居場所として、まちに彩りを与えているのではないか。
自宅で父を看取る
座間 耀永(青山学院高等部 2年)
「早く来て!」
早朝。母の絶叫に叩き起こされ、父の傍に走った。すうっと、父の顔が薄青白になっていく。手を握った。もうだらりとしている。
前日から訪問医に早退するよう言われ、ずっと父の傍にいた。何日も意識が無かった父。それでも3日前には、手を握ると微かな力で握り返してくれた。だが、もうゴムのような感触だった。父を呼んだ。声は最期まで聞こえているはず。そして、私は父を看取った。
10時間以上の大手術をした際、主治医は根治を目指すと言った。「人生100年時代、頑張りましょう。」と鼓舞もした。しかし、次々転移。想定外の出血で3回目の手術後、治療不可と緩和ケアに移行された。緩和ケアの実態は残酷だった。痛みを和らげるため、麻薬を大量に投与して眠らせる。心臓マッサージもしない。ろっ骨を折ることもあるからだ。出血が起きても輸血が回ってこないとも言われた。生きる屍の取扱説明書を聞いているようだった。
父は在宅治療を希望した。下の世話は悲惨だった。疲弊と葛藤。訪問医や地域の福祉サービス支援が支えだった。迅速な対応。寄り添う言葉がけに日々感謝をした。福祉は父だけでなく、母と私に心身共に支援をしてくれた。
だが、いざ「その時」を迎えた後の喪失感。私たちは父を本当に穏やかに逝かせてあげられたのだろうか。葛藤と後悔と悲しみだけが、津波のごとく心に何度も押し寄せた。
一方、柩の中の父の顔は穏やかだった。長い間、褥瘡回避の移動や、痰を引く医療行為に苦痛の表情の日々だった。苦痛から解放された父。私たちの介護が充分だったのか、自信はない。何が正解だったのかもわからない。ただ、地域の福祉のお陰で父の「自宅で最期を迎えたい」を叶えてあげられたことは事実だ。命尽きる迄、父の「尊厳」を家族で守ることができた。それを支えてくれた地域の福祉に、私は心から感謝をするばかりである。
じいちゃんのイス
村上 千紘(屋久島おおぞら高等学校 2年)
私の家は飲食店で、家族で経営している。店の厨房には、じいちゃん専用のイスがある。昔はずっと立って仕事をしていたが、足腰が弱くなって、最近膝の手術をして帰ってきた。入院している間に認知症が少し進んでいた。
若い時、船乗りだったじいちゃんは、真面目で仕事一筋だ。昔は休みの日でも店に来て仕事をしたり、外の草刈りをしたりしていた。だけど、退院後に真面目なじいちゃんが、少し怒りっぽくなったり、仕事でも何か1つにこだわった行動が増えて、不思議に感じていた。この行動が認知症の始まりだとは、この時、家族の誰も思わなかった。そして、じいちゃんは、注文数を間違えたり、お皿を違う場所にしまったりする。狭い通路に自分のイスを移動させて皿をふいている。私はそのじいちゃんのイスを「邪魔やな。皿なら私がふくのに。」と思ったこともある。でも、じいちゃんは店が忙しくなると、注文の魚やあわび、サザエの準備をしたり、私たちが忙しくしていると、料理を運んだりしてくれる。そんな姿を見ると、まだまだこの店で働きたいんだなと思った。
先日テレビで「注文をまちがえる料理店」というのを見た。認知症の人達がホールを担当して、注文を聞き料理を運ぶ。注文を間違えてもお客さんは「まあいいか。」という気持ちで運ばれた料理を食べる。笑顔で働く姿が私には衝撃だった。
以前、母に「歳とったら、老人ホームに入った方がええと思う?」と聞かれた。その答えが今出た気がする。老人ホームに入るのは簡単だけど、まだまだできることがたくさんあるじいちゃんにとっては、この店が輝ける場所だと思う。もしかしたら、私たちとしている仕事を忘れるときが来るかもしれない。だけど、私は覚えておくよ。一緒に仕事をしたことやじいちゃんのイスに座っている姿も。