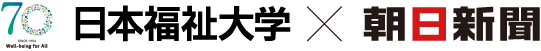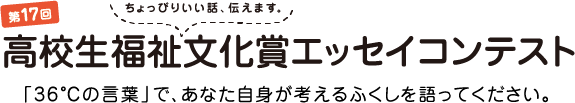
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
グローバルな社会とわたし
グローバルな社会とわたし 入賞作品
その日が来る前に、必ず
馬屋原 瑠美(盈進高等学校 二年)
「She dropped off」は「She was dropped off」に。「It was black」は「It was pitch black」に。被爆証言を中心とした冊子『にんげん坪井直 魂の叫び』の英訳過程で起きた変更のほんのわずかな例である。
私はいま、オバマ前米国大統領の広島訪問の際、最初に握手した被爆者で、広島県原爆被害者団体協議会の理事長を務める坪井直さん(94歳)の半生を描いた冊子を英訳し、世界に発信する準備をつづけている。冊子は、私のクラブの先輩方が2016年3月、2日にわたって聞き取った記録だ。翌年末に完成し、広島平和資料館などに寄贈した。中学3年生だった私は、先輩方と坪井さんを訪ねて直接、冊子を手渡した。坪井さんが満面の笑顔で「ありがとう。長生きすりゃあ(すれば)、ええこと(いいこと)あるのう」と言ってくださった。帰り際の握手。この手で地獄の広島を生き延び、この手が現在にいたる反戦、反核の運動をつくったんだと感じられ、体が熱くなった。
とりかかって約1年。肝に銘じていることは、坪井さんの壮絶かつ尊い生きざまの価値を、私の未熟な訳で下げてはならないということだ。作業の傍らにはいつも、坪井さんと撮った写真を置いた。
いま、京都外国語大学のNET-GTAS(被爆証言の世界化ネットワーク)と力を合わせて作業している。今秋、英語版冊子の発刊と、WEBでの世界発信が実現しそうだ。しかし、冒頭のように、ネイティブの先生の指摘もうけながら、より適切な表現に直すことがとても難しかった。立ち止まってはやり直す日々の連続だった。
だが、私はこの作業が好きだ。誇りも感じる。中学校の校長まで務めた94歳の坪井さん。現在は、介助のある車椅子生活だ。不謹慎かもしれない。そして、考えるだけでも悲しくなるが、「そう遠くはない日」を想像すると、なんとしても私がやるんだと力がわいた。坪井さんの、ケロイドを背負って核廃絶を世界に訴える鬼の形相を見られなくなる前に。そして、他者を愛おしむあのやさしい声が聞かれなくなる前に。
審査員のひとこと
審査員から「文句のつけ所がない」という声が出るほど、構成・文章力ともに優れた作品です。被爆証言の英訳・発信という作者の行動を通して感じたことが具体的で心に迫るものがありました。
タイトルの「その日が来る前に」がややストレートな表現では、という意見もありましたが、逆にリアルで好印象だと評価されました。被爆者が少なくなっていく現実を想起させる結びの言葉も素晴らしいです。
あの日の空は続く
岡村 美也(山口県立萩高等学校 一年)
「チガウッテ、ワルイノ?」
片言で紡がれたその言葉に、私は俯いて何も返せなかった。
私の住むアパートには、ケニアから来た女性が住んでいる。私は彼女と幼い頃から交流があり、私の二つ下にあたる彼女の娘とも昔は遊んだものだ。そして中三の夏。私は進路のことで、隣町の高校へ行くことを反対する母親と毎日口論になっていた。家へ帰るのが憂鬱で、アパートの下に座り込んでいると、
「ハイ!アツイ、ネ」
彼女が話しかけてくれた。
「チョトキイテ、ミヤチャン。」
話を聞くと、中一の娘が学校でいじめられているらしい。黒い、汚い、ゴリラ、なんて。彼女自身も仕事場で、どうせ日本語がわからないんだから、とひどいことを言われているようだった。そこで、冒頭の言葉である。彼女の持っていたペットボトルから水滴が落ちて、アスファルトの色を変える。私は彼女の心の痛みがじんわり黒く広がって、目を閉じて考えあぐねていた。
みんな違ってみんないい、という癖して、私は、私たちは、人と違う所を探してしまう。だが、そんな違いはどんなものであれ、悪いものではない。彼女を「外人だ」と笑う人も、他国から見れば立派にそうなのだ。
今であればそう言えるが、当時の私はじっと黙り込んでしまった。すると突然彼女が「ソトニデナサイ。タクサン、ヒロク、セカイヲミルノ。ソシテ、コタエ、ミツケテ。」と言った。彼女に手渡された言葉がとても重くて、私は思わず顔を上げた。夏の日差しが眩しかった。
彼女の言葉で、私は隣町への進学を心に決めた。本当に小さな一歩だが、あの日の答えを見つけるスタートとなった。誰かじゃなく、まずは私が「違い」を肯定する。顔を上げて目にした隣町の空は雲ひとつなく、どこまでも、どこまでも続いていた。
審査員のひとこと
僅差で優秀賞になりましたが、審査員の多くがこの作品を高く評価しました。グローバル化が進む今日、日本でも外国人とふれ合う機会が増えてきており、隣人としてどう接していけばよいのかを考えさせられる作品に仕上がりました。
タイトルからも隣人と話をした時の気持ちがその日で終わらず、現在も続いていることがよく伝わってきます。
心遣いから
高濵 華奈(立教英国学院高等部 三年)
私は小学四年生から五年間、ベルギーに住んでいました。街中でアジア人と珍しがられ、時には「ニーハオ」と面白がって言われたこともありました。周りと違う人種であり注目されることが嫌でした。それに、西欧人の恵まれた容姿に憧れるあまり、自分に自信が持てませんでした。時には現地の人のように立ち振る舞ったりしましたが、自分ではない誰かになりきっているだけで決して満足することはありませんでした。
そんな日本人であることに自信をもてなかった私が、変わるきっかけがありました。海外に住んで日本を客観的に見るようになり、日本の良さを発見できるようになったのです。特に素晴らしいなと思ったのは心遣いです。これは私が日本でカフェに行ったときの話です。その日は冬の寒い日で、私は飲み物を注文しました。お金を渡した後、店員さんに「このお飲み物は冷たいものしかありませんがいいですか。」と聞かれました。私は自分の勘違いに気づき、改めてあたたかいものをお願いすると店員さんが「さっきお金を受け取ったときに手が冷たかったので確認して良かった」と言いました。この心遣いとお金を払った後にも関わらず臨機応変に対応してくれた店員さんの行動に、心がじんわりと温かくなりました。海外では意思表示しないと対応してもらえないことが多かったので、日本人の細やかさに感動しました。日本への一時帰国のときに今まで見えていなかった礼儀正しさ、和を重んじる文化など他にはない日本の良さを実感し、大切に思うようになりました。
以前までは西欧文化は優れていると考えていましたが、多文化が存在する今、それぞれの文化に優劣をつけることはできないように思います。他と比べることのできない価値が、それぞれの国にあるのではないでしょうか。特有の魅力も持ち伝統を守ろうと努力する日本を誇りに思うと同時に、奥深い日本文化を海外へ発信していきたいです。
審査員のひとこと
海外に住むことで、日本のよさに気づいたことが素直に表現されている作品です。
ただ日本の文化の賞賛で終わることなく、「多文化が存在する今、それぞれの文化に優劣を付けることができない」という発見があった点もよいですね。
まとめの「奥深い日本文化を海外へ発信していきたい」について、具体的にどのように発信していきたいのか説明を加えると、さらに作品の魅力が増すでしょう。
“Love You”から学んだこと
佐野 悠実(静岡県立富士宮北高等学校 三年)
「おやすみなさい」や「いってきます」すら言わなくなってしまった私に、“Love You”という言葉は驚きでしかなかった。
この言葉を聞いたのは、私がホームステイで行ったカナダのある家族内の会話だ。彼らは「おやすみなさい」や「いってきます」などのリビングから離れる時には必ずこれを言っていた。そして共にハグをしていた。私が初めてその光景を目にした時はただ呆然と見つめ、そして同時に日本にいる母を思い出した。
私はだんだん母に挨拶しなくなった。喧嘩をしたわけではない。ただ自然と挨拶をしなくなった。どうしてこんな簡単なことができなくなってしまったのだろう。自分に問い続ける私にはホストファミリーが痛いほど眩しかった。彼らは挨拶を忘れないからだ。そして私へも優しく挨拶をしてくれた。
さらにホストファーザーは私を親戚同士の集まりにも招待してくれた。私にはそれがなによりも嬉しくて、心があたたかくなった。集まりが終わり別れの挨拶はやはり“Love You”とハグだった。
私は英語を学ぶためにホームステイに行ったはずだった。しかし一番学んだのは、家族の大切さだ。ホームステイに行かせてくれた母。準備を手伝ってくれた祖母や従姉。私の周りにはたくさんの支えてくれる家族がいるのにどうして大切さに気づけなかったのだろう。そして私は家族に当たってばかりだ。しかし今後悔していても学びは活かされない。そう思った私は帰国後は欠かさず挨拶をしている。当たり前のことと思うかもしれないが当たり前ではなかった。毎日ご飯を食べて、学校へ行けるのは家族のおかげだ。それに気づけた私でも今すぐに“Love You”なんて言うのは気恥ずかしくて難しいけど、まずはできるところから。私は今朝も「いってきます」と言って家を出てきた。なんて気持ちの良い一日のスタートなのだろう。
審査員のひとこと
ホームステイでの実体験から、作者自身が見て感じたことを等身大の言葉で表現したことで、読み手が共感しやすい作品に仕上がりました。
ホームステイを通して家族の大切さに気づいたが、今すぐに「“Love You”なんて言うのは」と気恥ずかしく思い、まずはできる挨拶をする部分は、作者の心の動きが素直によく表現されています。