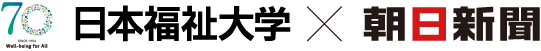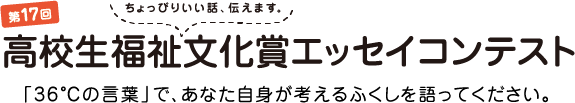
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
スポーツとわたし
スポーツとわたし 入賞作品
音のないスポーツ
中村 美月(宮崎県立都城さくら聴覚支援学校 三年)
いよいよ1500mのスタート、周りの選手は皆、ピストルの音に耳を澄まし、地面に意識を集中している。きこえない私だけ顔をあげ、瞬きもせず、スタートを合図するわずかな手の動きも見逃さないように立つ。合図の手が下りた瞬間、スタートを切る。風を切って走るとき、苦しくてもゴールが見えたとき、私は走ることがこんなにも好きなんだという思いとともにゴールする。それでも、このスタート方法では、音のほうが早く、スタートが遅れてしまう。後ろから迫ってくるライバルの足音の気配もわからない。
私が「音のないスポーツ」に初めて出会ったのは、中学一年のときの聾学校の陸上大会だった。そこで使われていたスタートランプで走ったときの衝撃は忘れられない。これならスタートを気にせず、走ることだけに集中できる。しかし、音のない世界で競うことには、複雑な思いがあった。ハンデなしで戦いたい、きこえないことが恥ずかしかった。
中学三年生のとき、全国障がい者スポーツ岩手大会に参加し、そこでいろいろな障がいをもった人たちと出会った。知的障がいをもっている選手は、私に手話で話してくれ、肢体不自由の選手は、手話を覚えてくれた。そして、いろいろな障がいをもったどの選手も障がいに関係なく生き生きと活躍する姿を見て、心を打たれた。また、今年三月、世界ろう者室内陸上競技選手権エストニア大会に出場した。そこで、きこえないことを言い訳にせず、まぶしく輝き、変わろうとする選手たちの姿を目の当たりにした。音があってもなくても大好きな陸上を続けようと決意した。正直、私はきこえる人として走りたかった。けれど、きこえない私だからこそ、この音のないスポーツに出会い、多くのチャンスをもらった。音のある世界できこえない私が走る、音のない世界できこえる人と一緒に走る、そんなスポーツの懸け橋になりたいと「音のないスポーツ」に出会ったからこそ思う。
審査員のひとこと
書き出しの「いよいよ1500mのスタート」から情景の描写が鮮やかで、ぐっと引きこまれました。
内容も素晴らしく、スポーツというテーマでは障がいを「乗り越えるべきもの」ととらえがちですが、「私はきこえる人として走りたかった」という作者の複雑な思いや葛藤とつなげて、素直に表現している点も高く評価されました。
また、締めくくりの決意も、さわやかな読後感につながりました。
障がいは障害じゃない
白砂 有佳子(日本女子大学附属高等学校 一年)
「障がい者スポーツってどういう気持ちで見たらいいのかわからない。」これが私の障がい者スポーツに対しての思いだった。たまにテレビでパラアスリートの姿を目にすることがあった。確かにその競技に取り組む姿勢は見る人の心を揺さぶる。しかしテレビの画面ごしから見るその様子は私には縁のない遠い世界での出来事のようにも感じた。どこか冷たく、無機質なものに思えた。ただ、あの車いすバスケを体験する前までは…
中学三年の二月の終わり、体育館で実際に車いすバスケの選手の方を招いて、お話を聞いたり、その試合を観戦するという機会があった。たぶん退屈だろうなと思った。しかしその予想は外れた。目の前でくり広げられたゲームは一言でいうと衝撃だった。タイヤの焦げるにおい。火花が散るのではないかと思うほど激しい競り合いに思わず鳥肌がたった。そしてきれいな弧を描くようなシュートが決まった瞬間、自分の中でグッと熱いものが押し寄せてくるのを感じた。もはや障がい者のためのスポーツだという意識はなく、純粋にこの競技を楽しめたことに私は驚いた。
「スポーツにおいて“障がい”は“障害”じゃないんだ。むしろ自分自身を強くしてくれた。」試合後、ある選手の方が仰っていた。障がいを障害とは思わず、前向きに捉えている彼の姿は私にはとてもまぶしく感じられ、心が震えた。そして最後、私はお世話になった選手の方と握手を交わした。彼らの手は皆厳しい練習を積み重ねてきたため、手の平の皮がむけ、硬くなっていた。私はそのゴワゴワとした感触の手に力を込め、「ありがとうございました。これからも頑張ってください。」と心の底からお礼を言った。私は真近で感じたスポーツのパワーとエネルギー、そして、車いすバスケの選手の方々の手を忘れることはないと思う。
審査員のひとこと
「障がい」と「障害」を使い分ける工夫で、身体の機能的な「障がい」と社会的な「障害」の違いについて、作者の気づきや考えをしっかり書いている点が評価されました。「タイヤの焦げるにおい。火花が散るのではないか」などの描写にも迫力があり、臨場感が感じられました。
「スポーツにおいて」と限定するのではなく、もっと普遍的な話に広げてまとめられれば、さらによい作品になったと思います。
彼女がいたから頑張れた私の二年半
川村 碧葵(鈴鹿工業高等専門学校 一年)
「バババン・バババン・バババン・バン・バン」とリズム良く背中を叩いてもらい「頑張れ」と言われ、畳へ上がる。私と彼女は初めて試合に出てから部活を引退するまでの間何度もこれを繰り返し、たくさんの勇気をもらって試合へ挑んできた。
私と彼女が知り合うきっかけとなった中学校の柔道部。私と彼女は柔道未経験者同士で入部して知り合った。同級生は私と彼女以外は経験者の子と男子だけ。実戦形式の練習である乱取りをすれば、女子の経験者の子には技で投げられ、男子には力で投げられ負けてばかりな彼女と私。悔しくて一緒に帰る帰り道に泣く事もあった。だけれど彼女は諦めなかった。そんな彼女に引っ張られる形で私も頑張った。朝練では持久力のある彼女についていけるよう走り、練習ではお互いの技の足りない所をアドバイスしあった。そのうち私と彼女は負けたくないライバルとなり、心から信頼できる親友となった。
三年生の最後の夏の大会。私の二回戦目の相手は前の大会三位の選手。延長戦になり、苦しくて諦めようかと思った時に彼女の声が飛んできた。「まだ行けるって。」今までたくさんの辛い事を一緒に乗り越えてきた彼女の言葉は私に気力をくれた。「負けたくない」その一心で私は必死に戦い勝つ事ができた。準決勝では負けてしまったが、あの時彼女の言葉がなければそこまで行けなかっただろう。
私はきっと彼女と出会えなかったら部活を辞めていた。負けてばかりで大変な練習を乗り越える事を一人ではできなかっただろう。と思うほど私は彼女に助けられた。多くの人はなぜスポーツをするのかと聞かれたら、体力をつけるため、楽しいからと答えるだろう。確かにそうだが「人に出会うため」だとも思う。私がスポーツ、部活で得たもの。それは「最高のライバル」「最高の親友」との出会い。そして彼女と乗り越えた「二年半」の充実した思い出である。
審査員のひとこと
作者の気持ちがストレートに表現されていて、今も昔も変わらない「青春」の素晴らしさが感じられる作品です。
スポーツにおいてライバルは競争相手であり、お互いを高め合う特別な存在であることが作者の経験を通して理解できます。
最後のまとめも、充実した部活に対する作者の思いが素直に表現されています。
強さ
堀中 風歌(兵庫県立北摂三田高等学校 三年)
もう一年以上も前のことなのに、今でも私の心に残っているインタビューがある。
去年の冬、ニュースの話題は平昌オリンピックのことで持ちきりだった。私は特に好きな選手や競技があった訳ではなかったから、テレビをつけたときに偶然中継されていた競技を何気なく見ていた。
その競技は、両足にスキー板をつけて、アップダウンのある長い距離を滑る、というものだった。とてもハードな競技だということは、テレビに映る選手たちの息の上がり方を見て、ルールを知らない私にも分かった。苦しそうに顔をゆがめてラストスパートをかける日本人の選手に、他国の選手が追いつこうとしていた。上位争いは熾烈だった。
私は祈るような気持ちで、知らない間にテレビにくいついていた。
その時だった。カーブでスキー板が他国の選手とぶつかり、日本人の選手が大きく遅れてしまった。
私は「あぁ。」と言ってテレビに近づけていた顔を離した。
その選手はそのまま巻き返すことができなかった。試合直後のインタビューでは、やっぱりあの場面が取り上げられていた。「あのときスキー板がぶつかっていなければ勝てていたように思うのですが。」私もそう思った。しかしその選手は迷いなく「ぶつかっていなくてもこの結果だった。」と答えた。
最高にかっこいいと思った。オリンピックという舞台に向けて何年練習を積んだのだろう。悔しくてたまらないはずなのに、アクシデントを言い訳にせず、自分の力が及ばなかったと言い切れる強さ。勝負に「強い」のも良いけど、それとはまた違う「強さ」。その堂々と断言する強さは、どこかで私の心の琴線に触れた気がした。そんな強さをもつ大人になりたいと思った。
審査員のひとこと
第2分野では自分自身がスポーツを通して得たことや、感じた体験を書く人が多いのですが、テレビを見ながら作者なりの問題意識をもった感性を評価しました。今までなかった視点で表現した新しさから、審査員特別賞に選びました。
己と向き合うことの重要性や、負けた時こそ自己抑制や謙虚な気持ちが大切だといった勝負での強さとは違う「強さ」があることを発見した感動が、素直な文章から伝わってきます。