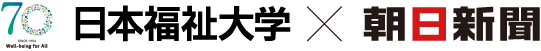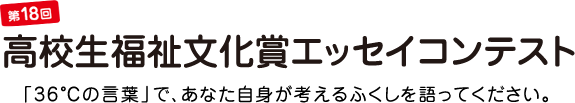
入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
スポーツ・文化活動とわたし
スポーツ・文化活動とわたし
ピアノとオレンジ色の思い出
宮原 毬(女子学院高等学校 三年)
「まりちゃん、ピアノ弾いてくださる?」祖母の家を訪ねる度に、祖母は私にこう尋ねる。私がピアノを弾くと、「また上手になったわね。」と、目を細め、あたたかい手を私の肩に乗せて褒めてくれる。私はその言葉が嬉しくて、一生懸命にピアノを練習した。
小学校四年生の冬、一年ぶりに祖母の家を訪れた私は、楽譜を片手に、いつもの祖母の言葉を待っていた。しかし祖母の言葉は、「あなた、ピアノ弾いたことありますか?」だった。時が一瞬、止まったかのように思えた。私の名前忘れてしまったの?私がピアノを弾いていたことも覚えていないの?その時、私の心の中でオレンジ色の暖かい光を放っていた祖母とのピアノの思い出は、氷のように冷たく固まって、砕け散ってしまった。
祖母は、アルツハイマー病を患っていた。祖母の病気は母から聞いていたが、自分のことを忘れてしまうなんて思ってもいなかった。祖母との思い出が大切にあたためられていた部分にはポッカリと大きな穴が開き、それ以来私はその穴に蓋をして、祖母の前でピアノを弾くことはなくなった。
私が中学三年生の時、祖母は老人ホームに移った。その老人ホームには、一台の電子ピアノが置いてあった。母と一緒に祖母のもとを訪れた時、祖母は私に「あなた、ピアノ弾けますか?」と尋ねたので、私はあの日以来、初めて祖母に向けてピアノを弾いた。演奏が終わって、ふと顔をあげると、目の前には、あたたかな眼差しを私に向け、一生懸命に演奏を聴いてくれる、昔と変わらない祖母の姿があった。その時、昔私の心にあいた大きな穴は、再び暖かいオレンジ色の光に照らされていた。
今でも、私は老人ホームを訪れる度に、祖母のためにピアノを弾く。目の前にいる人が「まりちゃん」だとわからなくても、毎回が初めましてでも、祖母と私の心は、ピアノを通して繋がっているような気がするのだ。
審査員のひとこと
アルツハイマー病を患い変わっていく祖母に最初は戸惑ってしまった作者が、祖母が好きだったピアノを弾くことを通じて、昔と同じ繋がりを感じるようになった様子が、平易な言葉でよく描けています。
タイトルにもあるオレンジ色が、文章の中でも効果的に表現されていて、祖母へのあたたかい思いを感じさせます。
高齢社会をうつして、認知症がテーマの作品が他にもありましたが、その中でもありのままの祖母を受け止めてポジティブにまとめているところが、審査員に評価されました。
“Win-Win”のボランティア
阿部 空也(奈良県立青翔高等学校 二年)
「空念仏さん、お願いします!」
施設の職員に呼ばれるこの瞬間、僕は阿部空也から六斎亭空念仏になる。出囃子と共に高座に上がれば、割れんばかりの拍手。
「えー、一席おつきあいを願います」
高座から見渡す限りのお年寄りの笑顔。掴みはバッチリだ。会場に笑いが満ちてゆく。
「だから食券に書いてますねん。おしょくじけん(お食事券・汚職事件)と」
渾身の力でオチをかまして、爆笑と拍手に包まれ高座を降りる。
「元気もらったわぁ」「面白かったよ!」みんなに喜んでもらえた充実感、しっかりと笑いが取れた達成感は、やみつきになる。
僕は小一の頃から落語を習っていて、福祉施設などで落語を披露する演芸ボランティアを行ってきた。今までに二百回以上、落語を演じている。一見すると、一方的に僕が笑いを提供してあげているように感じられる演芸ボランティア。だが実際は、演者である僕もこの活動から様々なものをもらっている。
「これからも頑張ってな」「プロになれるで!」温かい応援の言葉から、日常生活の活力をもらっている。そして、それ以上にもらえたものが、自分の落語の実力だ。
僕は小三の時に子ども落語大会に参加し、初出場で決勝に進むことができた。ビギナーズラックだ。それなのに当時は「すぐに優勝できるかも」と勘違いしてしまった。その後は色々な大会に出たものの、予選落ち、特別賞、選外…。結果は十連敗で、優勝には手が届かなかった。それでも僕は、年間約三十回のボランティア活動を淡々と続けていた。そして、中一の時に子ども落語全国大会で優勝することができた。ボランティアで高座に上がる事によって、落語の腕も上がったのだ。
いつしか演芸ボランティアは自分のライフワークになっていた。今日も僕は高座に上がり続ける。ボランティアはしてあげるものではなく“Win-Win”だから。
審査員のひとこと
たくさん応募された作品の中で、笑いをテーマにしたものが少ない中で、高校生が落語ボランティアに取り組む様子を描いたユニークさに好感がもてました。
落語を聞いてくれた方から「面白かったよ」と言ってもらい自分自身の成長や上達に繋がったと実感している様子がよく伝わってきます。
ボランティアを「Win-Win」と表現することが適しているのか、という指摘が審査員からありました。伝えたいことに適した言葉を慎重に選ぶことも大切なポイントです。
「上から見るリング」
吉沼 直毅(早稲田大学高等学院 三年)
「お兄さん、一緒にやろう!」
そんな一言が私を変えた。学校から帰り、シャワーを浴びると、私は決まって少し歩いたところの公園へ向かう。そこは市で唯一バスケットコートがある公園だ。ミニバス用のコートと通常のバスケのコートがある。私はいつも通常のコートで練習をするのだが、その日は偶然大学生のグループが使っており、私はコートの隅で練習していた。するとミニバスのコートで遊んでいた子供たちが来て、
「お兄さん、一緒にやろう!」
と言った。自分で良いのだろうかと思いつつ子供たちの試合に入った。私はその子たちと比べれば体も大きく、力も強い。加えてミニバス用のゴールは低く、少し跳べばダンクができる高さだ。子供たちに怪我をさせないように注意しつつ、出来るだけパスを心掛けた。
ある時、私に声を掛けた子がパスを返し、
「お兄ちゃん全然シュート打ってないよ!お兄ちゃんのシュート見てみたい!」
と言った。せっかくならと私は助走をつけ、ダンクシュートを放った。人生初のダンクだった。そして何より初めて上から見るリングは、私を不思議な感覚へと誘った。
「凄い!」「僕もやりたい!」私のシュートを見て、子供たちは一斉に口を開いた。私は順番に子供たちを抱きダンクをさせた。人見知りの私がここまで子供たちと打ち解けたのは初めてだろう。そして子供たちは私にバスケの本当の楽しさを教えてくれた。中学の頃バスケ部だった私は特別シュートが上手いわけではなかった。いつしか私はシュートを避け、磨き続けたパスばかりしていた。試合に勝ってもどこか虚しさがあった。久々の、それもダンクで上から見たリングの景色は、私の心の靄を晴らしてくれた。
やがてパンザマストが帰宅の時間を告げた。
「お兄さん、またやろうね!」
家路をたどる子供たちの背中を、私は手を振りながらいつまでも見守っていた。
審査員のひとこと
バスケットボールを通じて、子どもたちと交流する様子が、夕刻の公園のさりげない情景とともに、微笑ましく伝わってくる作品です。
子どもたちにせがまれて放ったダンクシュートで、リングを俯瞰したことが、これまでとは違った物の見方、視野の広がりにつながったことをうまく表現しています。「バスケの本当の楽しさを教えてくれた」という言葉から、素直な気持ちが伝わってきます。
見えない世界の「ヒカリ」
清水 大智(早稲田大学高等学院 一年)
中学生の頃、ある体育の授業でブラインドマラソンに挑戦する機会があった。その当時は、ほとんどパラリンピックに興味はなく、ましてや競技に関する知識など皆無だった。
挑戦する前は、友達と共に談笑するほど余裕があり、慣れ親しんだ体育館を目隠しした状態で走るだけだと考えていた。しかし、目隠しをした瞬間、自分の考えがいかに甘いかという事を思い知った。五感の一つを遮断しただけで、歩くことさえ難しくなり、友達の手に一生懸命しがみつきながら走ることに精一杯だった。走っている間も自分がどこを走っているのかわからず、周りの雑音がいつにも増して大きく聞こえ、心臓の音もドクドクと聞こえた。走り終わった後は身体中がくたくたで普段走っているタイムに比べ、遥かに遅くなっていた。その後、先生から競技について話を受け、その授業は終わったが、興奮がなかなか冷めず、後日詳しく調べてみることにした。
動画などを見て、一番心動かされたのは選手と伴走者の関係性だ。僕たちが挑戦した時は、ほとんど息が合わず、引っ張りあいながら進んでいたが、プロは引っ張ったり、引きずられたりするわけではなく、絶妙な距離感で、まるで伴走者が選手を見えない糸でリードしているかの様に見えた。僕にとっては、その伴走者の姿が選手の「ヒカリ」だと思えた。確かに競技への慣れはあるとは思うが、選手が実際には見ることの出来ない伴走者という「ヒカリ」を信じ、ひたむきに協力し合いながら息を合わせて走っている姿に、自分の中で何か熱いものが溢れてくるような気がして、とても感動した。
人と人が互いに協力し合いながら、一つのことに向かっていくのはなんて素晴らしいことなのだろうと改めて感じることができた。ぜひ、この感動を実際に見て感じたい。そして、この感動を自分の一生の宝物にしたいと思った。
審査員のひとこと
ブラインドマラソンを体験し、伴走してくれる人との関係性について感じたことがよく描かれている作品です。
「まるで伴走者が選手を見えない糸でリードしている」は、動画で見た選手と伴走者との関係性が印象的に伝わってくる表現です。
タイトルにもなっている、「ヒカリ」を選手にとっての伴走者になぞらえたことは、そこに気づいたことがすばらしいと審査員から評価されました。
最後の一文「この感動を自分の一生の宝物にしたいと思った」は、それまでの内容からすると少し大袈裟な表現なので、もうひと工夫できると、さらによい作品になったと思います。
届け!チアの力!
梅原 まほろ(静岡県立清流館高等学校 二年)
私は小学一年生からチアダンスを始めている。チアダンスをしている時、気持ちが晴れやかになり、至極幸せだ。私たちのチームは、三月に行われる全国大会に出場することが決まっていた。全国大会で入賞できるよう、メンバー全員の動きが揃うまで、床に汗が滴り落ちるくらい、何度も練習を繰り返した。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、メンバーとの練習も、全国大会も中止となってしまった。一年を通して創りあげてきた努力、踊りが全て水の泡になったようだった。その後も三ヶ月間練習ができない状態が続いた。そして、今後の大会予定も見通しが立たず、生きがいの一つを失った気がした。何をするにも全力で取り組むことができなかった。六月になり、ようやく練習が再開されることになったものの、例年参加していた大会は次々と中止になった。これから私は、何を目標にして練習に励めば良いのか途方に暮れていた。そんな時、コーチが言った。
「初心に戻ってみてごらん。」
その言葉で私は気づいた。大会に出場し、入賞することだけがチアダンスではないということ。そう、私たちチアリーダーは自らが輝き、一日一日を大切にすることが、誰かを応援し、励まし、笑顔を届けることだと。そして、自らが身体を鍛え、トレーニングに励み、技術を磨くことで、更に素敵な演技、応援をすることができるのである。
大会が次々と中止になる中で、今私にできることは何か。まず、家族や友人などの身近な人に日々の感謝を伝えることだ。そして、新型コロナウイルスの蔓延が収まり、病院に足を運べるようになったら、病気と闘っている方はもちろん、医療従事者の方に踊りを通して感謝を伝え、笑顔を届けることだと感じた。
これからも笑顔を届けたい、笑顔溢れる日々を過ごしてほしい、この思いを忘れずに、私は今日も笑顔で、全力で踊り続ける。
審査員のひとこと
新型コロナウイルスの影響により、大会に出られなくなって一度は途方に暮れたが、チアダンスを通じて、病気と闘っている方や医療従事者に笑顔を届けることが大切だと前向きな気持ちになったことが、素直な文章で書かれている作品です。
コロナの影響を受けて考えさせられたという作品は他にもありましたが、この作品は、みんなに感動や笑顔を届けようとチアダンスをイキイキと全力で踊ろうとする気持ちがさわやかに伝わってくる点が魅力的でした。
「ありがとう」とできること
伊奈 穂乃佳(日本福祉大学付属高等学校 一年)
『今日はありがとうね。また来てね。』
『お姉ちゃんまた遊ぼうね。』
私がボランティアについて考えるようになったきっかけは母だった。幼い頃、母のボランティア活動によく付いて行っていた。初めは何をやるのかよく分からないまま大人に言われた通りにただ動くだけだった。初めてのボランティアのことは今でもよく覚えている。老人ホームの方々と風船で遊んだり、幼いながらに肩もみをさせてもらったりした。その短い時間でボランティアに対しての思いが変わった。何も考えたことなかったけど、ボランティアはすごいと思った。短い時間で、お互い楽しくなれて、新しい発見ができることに幼いながら感動した。
小学生、中学生になり、夏期休暇のボランティア募集には積極的に参加するようになった。児童センターや老人ホームなどたくさんの場所に行かせてもらった。その中でも老人ホームで一人の方と話した時のことをとても強く覚えている。当然ながら、自分よりも歳を多く重ねている、まさに人生の先輩。普段私生活で聞けないような話をたくさん聞かせてもらった。その方は話し終えると、『聞いてくれてありがとうね。』と言った。思わず嬉しくなった。その方曰く、普段スタッフさんは忙しいから一人だけの相手はできないから話を聞いてもらえて嬉しかっただとか。この言葉を受けて、人の話により耳を傾けたいと思えた。嬉しいことがあったり、相談したいことがあったり、どんな話でもいい。自分が誰かの為にできることがあるならどんなことでもしたい。そう思えたのがその言葉だった。
高校生になった今はなかなかボランティアに行けていないが、自分に何ができるか考えることはできる。ボランティアだけでなく日々の生活で。そして、ボランティアで学んだことをどう活かすかを。
ボランティアで出会った人に伝えたい。
『こちらこそありがとう。また来ます。』と。
審査員のひとこと
老人ホームにボランティアに行って、話を聞かせてもらったお年寄りから「ありがとう」と感謝されたことに、「こちらこそありがとう」という気持ちになったことが、素直な文章で書かれている作品です。
小学生、中学生の頃にボランティアを体験したことをもとに、そのときに感じたことが淡々と書かれていてとても読みやすい文章ですが、少し盛り上がりに欠ける印象もあります。情景が浮かぶような表現をひと工夫することで、さらによい作品になったでしょう。