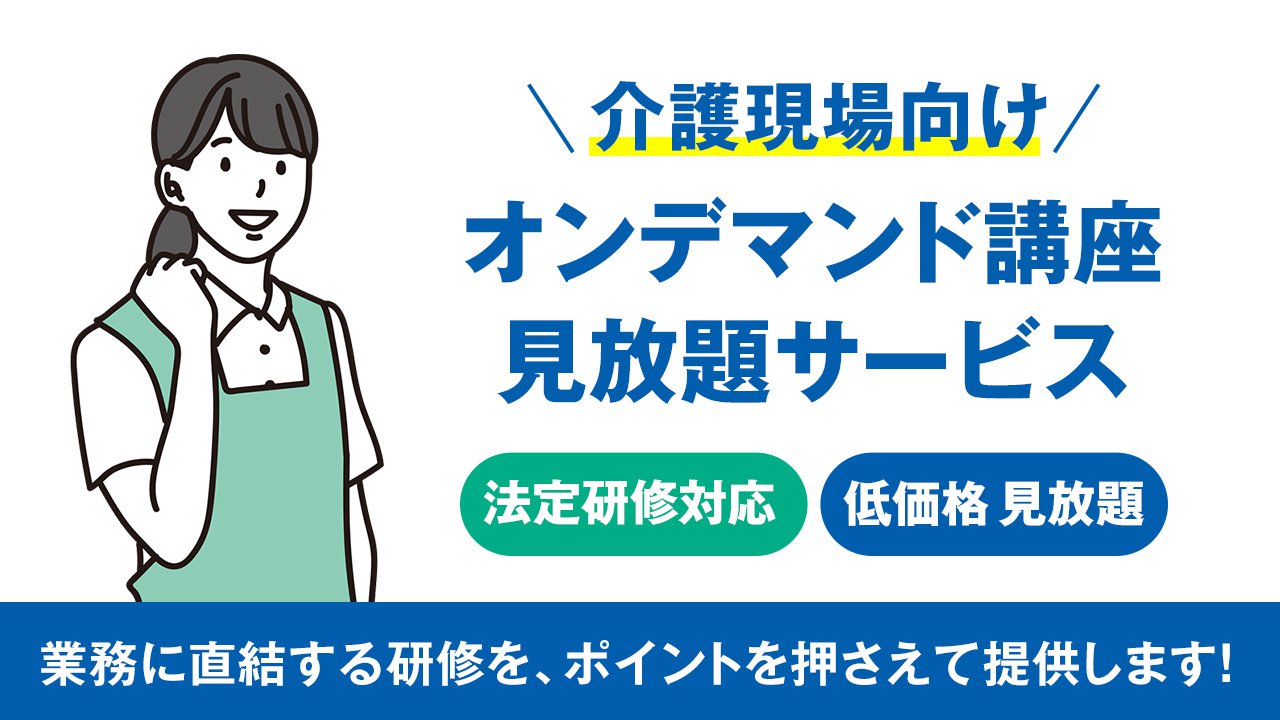FUKU+TOPICS
ホーム FUKU+TOPICS 認知症のBPSD(周辺症状)って何?介護で押さえておきたいポイント
認知症のBPSD(周辺症状)って何?介護で押さえておきたいポイント
2025.07.16
認知症では記憶障害や見当識障害といった中核症状だけでなく、周囲の環境や本人の心理状態などさまざまな要因が重なった結果としてBPSD(行動・心理症状)が現れる場合があります。一般的にBPSDは興奮や妄想、抑うつや睡眠障害といった幅広い症状が含まれ、個人差も大きいため、正しい理解と柔軟な対応が求められます。
介護現場では、BPSDを適切に理解し、利用者さんやご家族が安心して日常生活を送れるようにサポートすることが大切です。本記事ではBPSDがどのような症状として現れ、どのように対応すればよいのかを整理します。中核症状との違いや、介護の視点から行えるケアの工夫などもあわせて紹介します。
また、BPSDの背景には多くの場合、身体的・心理的・社会的・環境的な要素が複雑に関係していることを把握しておくことが大切です。これらの相互作用を理解し、利用者の尊厳を守りつつケアに取り組むことで、症状を軽減したり予防したりすることも期待できます。
介護現場では、BPSDを適切に理解し、利用者さんやご家族が安心して日常生活を送れるようにサポートすることが大切です。本記事ではBPSDがどのような症状として現れ、どのように対応すればよいのかを整理します。中核症状との違いや、介護の視点から行えるケアの工夫などもあわせて紹介します。
また、BPSDの背景には多くの場合、身体的・心理的・社会的・環境的な要素が複雑に関係していることを把握しておくことが大切です。これらの相互作用を理解し、利用者の尊厳を守りつつケアに取り組むことで、症状を軽減したり予防したりすることも期待できます。

- もくじ
BPSDと中核症状の違いを理解する
まずはBPSDと中核症状の違いを押さえ、認知症のケアに欠かせない基本事項を理解しましょう。
中核症状とは、脳の変性に伴う記憶障害や判断力の低下など、認知症の進行に伴ってほぼすべての人に見られる症状を指します。これに対してBPSDは、興奮や不安、暴言・暴力行為など、周囲の環境や個人の心理状態が大きく影響して可変的に現れる症状を意味します。中核症状が認知機能の直接的な変化に起因するのに対し、BPSDは人や環境との相互作用によって引き起こされる点で性質が異なります。
BPSDは、本人が周囲の現状を十分に理解できず混乱していたり、外部からの刺激をうまく処理できなかったりする状況で強く現れることがあります。そのため、BPSDの特性をよく理解し、不必要な刺激を与えないことや良い刺激を提供することが症状緩和に役立ちます。特に人の動きや声、照明、温度などの環境調整は重要です。
中核症状だけで認知症のケアを考えてしまうと、本人にとって負担や不安が大きくなる可能性があります。BPSDという周辺症状を総合的に把握することによって、一人ひとりに適したケアプランを立案することができるでしょう。看護職としては、環境的な要因や利用者の心理面を踏まえながら支援を進めていくことが鍵となります。
中核症状とは、脳の変性に伴う記憶障害や判断力の低下など、認知症の進行に伴ってほぼすべての人に見られる症状を指します。これに対してBPSDは、興奮や不安、暴言・暴力行為など、周囲の環境や個人の心理状態が大きく影響して可変的に現れる症状を意味します。中核症状が認知機能の直接的な変化に起因するのに対し、BPSDは人や環境との相互作用によって引き起こされる点で性質が異なります。
BPSDは、本人が周囲の現状を十分に理解できず混乱していたり、外部からの刺激をうまく処理できなかったりする状況で強く現れることがあります。そのため、BPSDの特性をよく理解し、不必要な刺激を与えないことや良い刺激を提供することが症状緩和に役立ちます。特に人の動きや声、照明、温度などの環境調整は重要です。
中核症状だけで認知症のケアを考えてしまうと、本人にとって負担や不安が大きくなる可能性があります。BPSDという周辺症状を総合的に把握することによって、一人ひとりに適したケアプランを立案することができるでしょう。看護職としては、環境的な要因や利用者の心理面を踏まえながら支援を進めていくことが鍵となります。
BPSDの主な症状と特徴
BPSDとして現れる症状には、多様な行動面や心理面の特徴があります。それぞれの特性を理解し、ケアに生かすことが重要です。
BPSDは周囲の環境変化や身体的な不調、人間関係の不和などをきっかけにして現れることが多くあります。症状は一時的に激しくなることもあれば、比較的穏やかに表面化することもあるため、その人に合った対応を臨機応変に行うことが望まれます。特に重度の混乱や興奮が見られる場合には、早めの対処と観察が必要です。
典型的なBPSDの症状には、徘徊や暴言、介護拒否といった行動面の変化のほか、不安や抑うつといった心理的変化も含まれます。これらの症状は決して「わがまま」や「性格上の問題」と片付けられるものではありません。脳内の変化と周囲の環境要因が複雑に絡み合って生じるため、その背景にある要因を介護職や医療従事者がしっかりと捉え、介入することが必要となります。
BPSDの症状を理解するためには、症状そのものだけでなく、症状が起こる場面や本人の心理状態にも目を向けなければなりません。たとえば、夕方になると徘徊が増えるケースや、特定のケアを拒否する場面が増えるケースなど、時間帯や刺激との関係性も見逃せません。介入・ケアの質を高めるためには、こうした観察に基づく分析とチームでの情報共有が欠かせないのです。
BPSDは周囲の環境変化や身体的な不調、人間関係の不和などをきっかけにして現れることが多くあります。症状は一時的に激しくなることもあれば、比較的穏やかに表面化することもあるため、その人に合った対応を臨機応変に行うことが望まれます。特に重度の混乱や興奮が見られる場合には、早めの対処と観察が必要です。
典型的なBPSDの症状には、徘徊や暴言、介護拒否といった行動面の変化のほか、不安や抑うつといった心理的変化も含まれます。これらの症状は決して「わがまま」や「性格上の問題」と片付けられるものではありません。脳内の変化と周囲の環境要因が複雑に絡み合って生じるため、その背景にある要因を介護職や医療従事者がしっかりと捉え、介入することが必要となります。
BPSDの症状を理解するためには、症状そのものだけでなく、症状が起こる場面や本人の心理状態にも目を向けなければなりません。たとえば、夕方になると徘徊が増えるケースや、特定のケアを拒否する場面が増えるケースなど、時間帯や刺激との関係性も見逃せません。介入・ケアの質を高めるためには、こうした観察に基づく分析とチームでの情報共有が欠かせないのです。
徘徊・多動
徘徊や多動は、頭の中で方向感覚を保てなくなっていることや、不安感から落ち着いていられなくなることで発生します。たとえば「家に帰らなければ」といった思い込みや混乱から、施設や自宅の外へ出ようとしてしまう場合が典型的です。
これらの行為は転倒リスクを高めるため、見守りや安全対策が重要となります。物理的な拘束を安易に行うのではなく、環境を整えたり、声かけなどで本人の心理面をフォローしたりしながら、本人の尊厳を守るケアを実施するよう心がけましょう。
介護職は、「危ないから動かないで」という声かけではなく、「一緒に確認しましょう」といった共感やサポートを感じさせる言葉がけを心掛けると良いでしょう。本人が落ち着ける居場所を確保することで、徘徊の頻度が下がるケースもあります。
これらの行為は転倒リスクを高めるため、見守りや安全対策が重要となります。物理的な拘束を安易に行うのではなく、環境を整えたり、声かけなどで本人の心理面をフォローしたりしながら、本人の尊厳を守るケアを実施するよう心がけましょう。
介護職は、「危ないから動かないで」という声かけではなく、「一緒に確認しましょう」といった共感やサポートを感じさせる言葉がけを心掛けると良いでしょう。本人が落ち着ける居場所を確保することで、徘徊の頻度が下がるケースもあります。
暴言・暴力
暴言・暴力の背景には、本人が強い恐怖や不安を感じている場合があります。脳機能の低下によって自分の置かれた状況をうまく理解できず、それが過剰な反応として現れることがあります。
介護の現場では、その場の言葉や行為にのみ着目せず、なぜそうした行動を取ってしまうのか要因を探る姿勢が重要です。たとえば痛みや疲労があって、本人がそれをうまく言葉にできないことから苛立ちが暴言や暴力という形で表面化している可能性も考えられます。
対応策としては、本人に寄り添って落ち着いた空間を提供し、過度な刺激を避けることが大切です。怒りが強い場面では、対話を続けるよりも一旦距離を置き、お互いがクールダウンできる時間をつくる方が効果的なこともあります。
介護の現場では、その場の言葉や行為にのみ着目せず、なぜそうした行動を取ってしまうのか要因を探る姿勢が重要です。たとえば痛みや疲労があって、本人がそれをうまく言葉にできないことから苛立ちが暴言や暴力という形で表面化している可能性も考えられます。
対応策としては、本人に寄り添って落ち着いた空間を提供し、過度な刺激を避けることが大切です。怒りが強い場面では、対話を続けるよりも一旦距離を置き、お互いがクールダウンできる時間をつくる方が効果的なこともあります。
介護拒否・服薬拒否
介護拒否や服薬拒否は、利用者が不安や不信感を抱えている場合に起こりやすいです。「なぜケアが必要なのか」を本人が理解しきれないために、「やりたくない」という拒否の行動につながってしまうのです。
このような拒否反応は、一方的に押し付けるのではなく、本人の気持ちを尊重しながら対話を重ねることで解消しやすくなります。身体を触れるようなケアを行うときは、必ず声かけと説明を同時に行い、安心と信頼を築いていく工夫が必要です。
納得感を得られるよう配慮することで、拒否行動が緩和することは少なくありません。本人にケアや服薬の意味を少しずつ伝えながら、理解度に合わせたコミュニケーションを心がけましょう。
夜間せん妄・睡眠障害
夜間に混乱や興奮が強まる夜間せん妄は、昼夜のリズムが崩れることでさらに悪化しやすいのが特徴です。環境が変わった直後などに起こりやすく、特に入院や施設入所の直後はリロケーションダメージの影響も懸念されます。
飛び起きて部屋を出ようとしたり、不安を訴えながら歩き回ったりするケースが見られるため、転倒防止には十分な注意が必要です。夜間でもできるだけ安心感のある照明や、一定の生活リズムを保ちやすいような環境整備が役立ちます。
介護職としては、就寝前の落ち着いた雰囲気づくりや、必要に応じて音楽を流すなどの工夫で、利用者の心理的安定を図ることが求められます。こうした配慮を積み重ねることで、せん妄の頻度や深刻度を軽減できる可能性が高まります。
飛び起きて部屋を出ようとしたり、不安を訴えながら歩き回ったりするケースが見られるため、転倒防止には十分な注意が必要です。夜間でもできるだけ安心感のある照明や、一定の生活リズムを保ちやすいような環境整備が役立ちます。
介護職としては、就寝前の落ち着いた雰囲気づくりや、必要に応じて音楽を流すなどの工夫で、利用者の心理的安定を図ることが求められます。こうした配慮を積み重ねることで、せん妄の頻度や深刻度を軽減できる可能性が高まります。
BPSDを引き起こす4つの要因
BPSDには、本人を取り巻く複数の要因が複雑に関係していると考えられます。ここでは代表的な4つの要因を整理します。
BPSDが起きる背景には、身体的・心理的・社会的・環境的な要因が密接に組み合わさっている場合が多いです。たとえば、痛みによるイライラと、環境の変化に対する混乱が同時に発生して、徘徊や暴言といった行動として表れることがあります。
要因をひとつずつ分けて考えるだけでは、複雑な利用者の状態を十分に理解できないことも珍しくありません。介護職はアセスメントの過程で、利用者が置かれている状況を総合的に捉えながら、どの要素が今の行動に影響を与えているかを見極めるスキルが必要です。
こうしたアセスメントを丁寧に行うことで、本来は痛みを訴えたいだけなのに上手に言葉で伝えられず、粗暴な行動になっているなどの真の原因に気付くことがあります。要因の全体像をつかむことは、BPSDの予防や緩和において効果的なケアを行ううえで極めて重要です。
BPSDが起きる背景には、身体的・心理的・社会的・環境的な要因が密接に組み合わさっている場合が多いです。たとえば、痛みによるイライラと、環境の変化に対する混乱が同時に発生して、徘徊や暴言といった行動として表れることがあります。
要因をひとつずつ分けて考えるだけでは、複雑な利用者の状態を十分に理解できないことも珍しくありません。介護職はアセスメントの過程で、利用者が置かれている状況を総合的に捉えながら、どの要素が今の行動に影響を与えているかを見極めるスキルが必要です。
こうしたアセスメントを丁寧に行うことで、本来は痛みを訴えたいだけなのに上手に言葉で伝えられず、粗暴な行動になっているなどの真の原因に気付くことがあります。要因の全体像をつかむことは、BPSDの予防や緩和において効果的なケアを行ううえで極めて重要です。
① 身体的要因:痛み・体調不良・疲労
身体の痛みや体調不良、疲労があると、人は苛立ちやすくなり精神的な余裕を失いがちです。認知症の方の場合、これらの不快感をうまく言語化できず、行動として表出してしまうことがあります。
専門的なケアでは、定期的な健康チェックや検査を実施し、小さな体調変化も見逃さない努力が必要です。医師や介護職だけでなく、多職種がコミュニケーションをとりながらアセスメントを行うことで、手遅れになる前に痛みや不調をケアできます。
体調面の問題を見過ごしてしまうと、結果的に暴言や徘徊といったBPSDが長引く場合もあります。身体面からのアプローチで改善するケースも多いため、常に身体的要因を確認しておく姿勢が求められます。
専門的なケアでは、定期的な健康チェックや検査を実施し、小さな体調変化も見逃さない努力が必要です。医師や介護職だけでなく、多職種がコミュニケーションをとりながらアセスメントを行うことで、手遅れになる前に痛みや不調をケアできます。
体調面の問題を見過ごしてしまうと、結果的に暴言や徘徊といったBPSDが長引く場合もあります。身体面からのアプローチで改善するケースも多いため、常に身体的要因を確認しておく姿勢が求められます。
② 心理的要因:不安・混乱・ストレス
心理的な要因としては、不安感や混乱、日常的なストレスなどが挙げられます。認知症の方は自分を取り巻く環境を正しく把握できないことで、不安が高まりやすい状態にあります。
知らない場所や初めて会う人が多い状況に置かれると、恐怖や緊張が強まり、それがBPSDの引き金となることも少なくありません。安心感を与える声かけや、表情・身振りで伝える配慮が不安をやわらげるうえで効果的です。
心理的要因を緩和するには、見慣れた物や音楽を活用するなど、本人が心を休められる環境をつくることも有効です。好みや過去の趣味を思い出すことで、不安に支配されそうな気持ちを和らげられるケースもあります。
知らない場所や初めて会う人が多い状況に置かれると、恐怖や緊張が強まり、それがBPSDの引き金となることも少なくありません。安心感を与える声かけや、表情・身振りで伝える配慮が不安をやわらげるうえで効果的です。
心理的要因を緩和するには、見慣れた物や音楽を活用するなど、本人が心を休められる環境をつくることも有効です。好みや過去の趣味を思い出すことで、不安に支配されそうな気持ちを和らげられるケースもあります。
③ 社会的要因:家族関係・過去の経験
認知症の方にとって、家族関係や過去のライフヒストリーは大きな意味を持ちます。これまでの経験が現在の行動パターンに影響を及ぼす場合があり、たとえば子育ての経験から特定の時間帯になると落ち着かなくなるケースもあります。
本人が大切にしていた家庭環境や人間関係が崩れたと感じることで、混乱や悲しみがBPSDとして現れる可能性も考えられます。過去を否定するのではなく、それぞれの価値観を尊重しながら受容する態度が重要です。
背景となる家族関係や人生史を知ることで、ケアのアプローチを個別化していくことができます。介護職や介護スタッフは、本人に寄り添う姿勢を持ち、家族とも連携を図りながら最善のケア方法を検討することが大切です。
本人が大切にしていた家庭環境や人間関係が崩れたと感じることで、混乱や悲しみがBPSDとして現れる可能性も考えられます。過去を否定するのではなく、それぞれの価値観を尊重しながら受容する態度が重要です。
背景となる家族関係や人生史を知ることで、ケアのアプローチを個別化していくことができます。介護職や介護スタッフは、本人に寄り添う姿勢を持ち、家族とも連携を図りながら最善のケア方法を検討することが大切です。
④ 環境的要因:住環境・刺激の過多や不足
住み慣れた環境からの急激な変化は、認知症の方にとって大きなストレスになりがちです。実際に居住空間の広さや照明、音の大きさなどの微細な点が、BPSDの発現や重症化に関わっていることがあります。
刺激が多すぎると過敏になり、落ち着きを失う要因となる一方、刺激が少ないと単調さから混乱を招き、別の不安を生じる場合もあります。そのため適度な刺激を与えることが重要であり、個人によって丁度よいレベルは異なるため柔軟な調整が必要です。
施設や在宅の介護ケアでは、なるべく本人が安心できるようなレイアウトの工夫や、照明の明るさ・騒音レベルの調整を行います。こうした環境調整を行うことで、感情面が落ち着いてBPSDの軽減につながる可能性が高まります。
施設や在宅の介護ケアでは、なるべく本人が安心できるようなレイアウトの工夫や、照明の明るさ・騒音レベルの調整を行います。こうした環境調整を行うことで、感情面が落ち着いてBPSDの軽減につながる可能性が高まります。
非薬物療法の活用とコミュニケーション技術
非薬物療法としては、音楽療法や回想法、アロマセラピーなどが活用されることがあります。これらの療法は、本人がリラックスできる環境を作り、不安や混乱から気持ちをそらす効果が期待できます。
コミュニケーションの面では、声のトーンやテンポを落とし、ゆっくりと分かりやすい言葉で話すことが大切です。また、内容だけでなく表情や身振りも含めて“安心してもらう”ための姿勢を意識しましょう。特にBPSDが強く現れているときには、相手の言葉を遮らず最後まで耳を傾けることが求められます。
こうした非薬物療法とコミュニケーション技術を組み合わせることで、症状が大きく緩和するケースも多くあります。薬の使用を最小限に抑えながらケアを行うためにも、介護職が率先してこれらのアプローチを取り入れていくことが重要です。
こうした非薬物療法とコミュニケーション技術を組み合わせることで、症状が大きく緩和するケースも多くあります。薬の使用を最小限に抑えながらケアを行うためにも、介護職が率先してこれらのアプローチを取り入れていくことが重要です。
まとめ・総括:BPSD支援をより充実させるために
BPSDの要因や症状を総合的に捉え、環境を整えながら個々の利用者と向き合うことが、より良いケアに繋がります。
認知症の中核症状では多くの利用者さんに記憶障害や判断力低下がみられますが、BPSDはそれとは別に、環境や心理要因など複数の要因が関与している点が特徴です。介護職は利用者の潜在的なニーズや背景を総合的にアセスメントしながら、チームで協力してケアを提供していく必要があります。
徘徊や暴言といった激しい行動が起きると、周囲は驚き戸惑いますが、本人も大きなストレスや不安を抱えている可能性があります。本人の声に耳を傾け、身体的な不調や環境への違和感を見逃さない努力を続けることで、BPSDの発症を抑えたり緩和したりできるケースも多いのです。
医療や介護の現場が連携し、利用者が安心して生活できる環境づくりを進めることが重要です。今後も認知症介護の需要が高まる中で、BPSDに対してより充実した支援を行うためには、介護職の専門的知識と柔軟な発想が不可欠となるでしょう。
認知症の中核症状では多くの利用者さんに記憶障害や判断力低下がみられますが、BPSDはそれとは別に、環境や心理要因など複数の要因が関与している点が特徴です。介護職は利用者の潜在的なニーズや背景を総合的にアセスメントしながら、チームで協力してケアを提供していく必要があります。
徘徊や暴言といった激しい行動が起きると、周囲は驚き戸惑いますが、本人も大きなストレスや不安を抱えている可能性があります。本人の声に耳を傾け、身体的な不調や環境への違和感を見逃さない努力を続けることで、BPSDの発症を抑えたり緩和したりできるケースも多いのです。
医療や介護の現場が連携し、利用者が安心して生活できる環境づくりを進めることが重要です。今後も認知症介護の需要が高まる中で、BPSDに対してより充実した支援を行うためには、介護職の専門的知識と柔軟な発想が不可欠となるでしょう。
介護現場の研修をアシスト!介護現場向けオンライン・オンデマンド研修動画見放題サービス
介護現場の研修に最適で、法定研修も充実の「オンデマンド研修動画見放題サービス」では、認知症に関連する講座も含め、35講座70時間以上の講座がお申し込みから1年間見放題でサービスを提供中です。2024年4月から義務化された虐待防止などの法定研修にも対応しています。また、管理職やリーダー向けの研修も充実しており、日本福祉大学教員と最前線で活躍する講師が登壇する研修で、業務に直結する内容をポイントを押さえて提供しています!
詳しくは下記ボタンのリンク先のホームページから
介護・福祉分野の人材研修なら日本福祉大学社会福祉総合研修センターへお任せください!