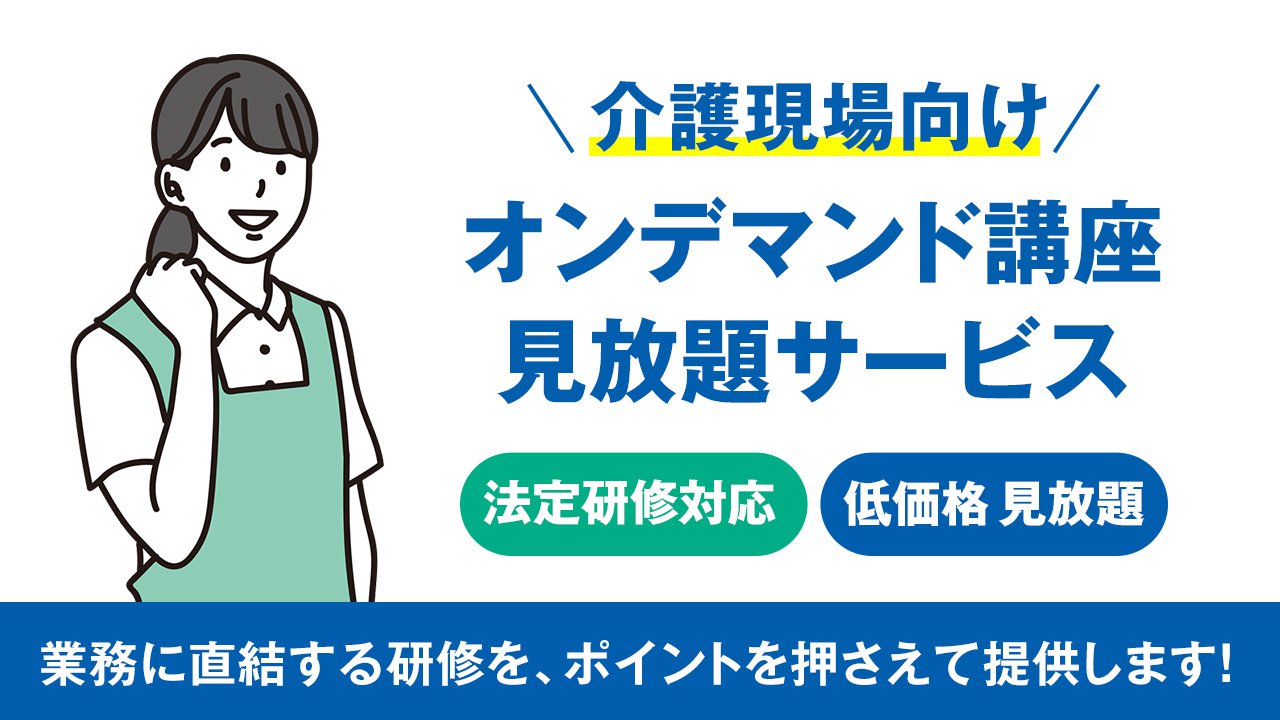FUKU+TOPICS
ホーム FUKU+TOPICS ICF(国際生活機能分類)とは?
ICF(国際生活機能分類)とは?
2025.07.16
ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、WHO(世界保健機関)が策定した健康や生活機能に関する国際的な分類です。身体的・精神的な機能だけでなく、社会や環境との関わりなど多面的な視点を組み込み、個人の生活全体を評価するために用いられます。
近年、高齢化社会の進行や医療・介護領域での多職種連携の必要性が高まるなかで、客観的な評価基準として活用される機会が増えています。ICFによって、分野の違う専門職同士でも共通の理解や情報共有がしやすくなり、利用者一人ひとりに合わせたアプローチが実現可能になります。
ICFの分類コードと評価の仕組みを理解することで、より的確なケアプランやリハビリの目標設定ができるだけでなく、本人のポジティブな側面を尊重した支援思想の形成にもつながる点が大きな特徴となっています。

- もくじ
ICFが注目される背景
ICFが注目を集めるようになった背景には、高齢化社会の進展や多職種連携の重要性が挙げられます。より客観的かつ共通の指標を用いて健康や生活機能を評価する必要性が高まっています。
人口の高齢化に伴って支援やケアを必要とする人が増え、医療・介護・リハビリなど多岐にわたる分野で統一した指標が求められるようになりました。複数の専門家が同じ枠組みをもとに話し合える仕組みとして、WHOが策定したICF(国際生活機能分類)の考え方に注目が集まっています。
以前は病気や障害そのものに焦点を当てがちでしたが、最近では生活全般を評価し、社会参加や個人因子を含めた包括的な見方が必要とされています。ICFでは各領域を有機的につなげ、具体的な支援に落とし込むうえで役立つため、多くの現場で活用が加速しています。
さらに、ICFは健康や障害を単なるマイナス面として捉えるのではなく、機能維持や能力伸長を重視するポジティブな視点を提供します。これにより、本人の強みを引き出しながら生活機能を高めるための計画が作成しやすくなっています。
人口の高齢化に伴って支援やケアを必要とする人が増え、医療・介護・リハビリなど多岐にわたる分野で統一した指標が求められるようになりました。複数の専門家が同じ枠組みをもとに話し合える仕組みとして、WHOが策定したICF(国際生活機能分類)の考え方に注目が集まっています。
以前は病気や障害そのものに焦点を当てがちでしたが、最近では生活全般を評価し、社会参加や個人因子を含めた包括的な見方が必要とされています。ICFでは各領域を有機的につなげ、具体的な支援に落とし込むうえで役立つため、多くの現場で活用が加速しています。
さらに、ICFは健康や障害を単なるマイナス面として捉えるのではなく、機能維持や能力伸長を重視するポジティブな視点を提供します。これにより、本人の強みを引き出しながら生活機能を高めるための計画が作成しやすくなっています。
ICFとは何か? その基本概念
ICFは、従来の障害に焦点を当てた評価から大きく転換し、個人を取り巻く社会的背景を含む生活全体の機能を総合的に捉えるための分類です。
ICFのポイントは、健康状態のみならず、環境因子や個人因子なども含めて多角的に評価することにあります。こうした枠組みによって、単に「何ができないか」を見るのではなく、「どの程度できるか」「どのような支援があれば可能か」といった前向きな視点で生活機能を見極めます。
さらに、ICFは医療・介護・教育など幅広い領域で共通の言語として使われることが想定されており、地域包括ケアやチームアプローチといった多職種連携の場面を支える基盤ともなり得ます。従来の身体機能中心の評価方法に比べ、社会参加や心理的側面も重視されるため、より包括的に個別性に合わせた支援計画を立てやすくなります。
個人の健康や生活上の課題を総合的に理解するうえで、ICFの視点を踏まえれば表面化しにくいニーズにもアプローチしやすくなります。例えば家庭環境や職場環境を含めたサポート体制を考慮することで、支援の精度を高めることができる点が大きな魅力です。
ICFのポイントは、健康状態のみならず、環境因子や個人因子なども含めて多角的に評価することにあります。こうした枠組みによって、単に「何ができないか」を見るのではなく、「どの程度できるか」「どのような支援があれば可能か」といった前向きな視点で生活機能を見極めます。
さらに、ICFは医療・介護・教育など幅広い領域で共通の言語として使われることが想定されており、地域包括ケアやチームアプローチといった多職種連携の場面を支える基盤ともなり得ます。従来の身体機能中心の評価方法に比べ、社会参加や心理的側面も重視されるため、より包括的に個別性に合わせた支援計画を立てやすくなります。
個人の健康や生活上の課題を総合的に理解するうえで、ICFの視点を踏まえれば表面化しにくいニーズにもアプローチしやすくなります。例えば家庭環境や職場環境を含めたサポート体制を考慮することで、支援の精度を高めることができる点が大きな魅力です。
ICIDH(国際障害分類)との違いを理解する
ICFが登場する以前はICIDHという分類があり、主に障害を中心にした捉え方が主流でした。しかしICIDHでは、マイナス面に注目しがちで、社会や環境といったプラスの要素が十分に考慮されていないという指摘がありました。
ICFはこの点を大幅に見直し、個人の「できること」や「潜在能力」にも注目する総合的なアプローチを採っています。障害だけでなく、個人の積極的な機能面を評価し、それらを活用できる環境やサポートをどう整備するかが重要視されるようになりました。
結果として、従来の障害概念から生活機能を包括的に捉える方向に転換したことが、ICFの大きな特徴の一つと言えます。
ICFはこの点を大幅に見直し、個人の「できること」や「潜在能力」にも注目する総合的なアプローチを採っています。障害だけでなく、個人の積極的な機能面を評価し、それらを活用できる環境やサポートをどう整備するかが重要視されるようになりました。
結果として、従来の障害概念から生活機能を包括的に捉える方向に転換したことが、ICFの大きな特徴の一つと言えます。
ICFの目的と特徴
ICFの最大の目的は、異なる専門分野や立場の人が共通言語によって個人の生活機能を評価し、連携しやすい環境をつくることにあります。これにより、医療、介護、教育、福祉などの垣根を超えて協働できる土台が整備されます。
特徴としては、心身機能だけでなく背景要因まで含めてコード化し、視覚的に把握できるように体系化している点が挙げられます。例えば、障害の度合いを数値で示すだけでなく、どのような支援機器や社会制度があるかという環境的な側面まで整理できる点は画期的です。
また、ICFはすべての人を対象とし、障害の有無に関わらず生活機能を把握する枠組みとして設計されています。そのため、予防医療やリハビリだけでなく、健康増進や社会参加の促進といった広い視点でも活用可能です。
特徴としては、心身機能だけでなく背景要因まで含めてコード化し、視覚的に把握できるように体系化している点が挙げられます。例えば、障害の度合いを数値で示すだけでなく、どのような支援機器や社会制度があるかという環境的な側面まで整理できる点は画期的です。
また、ICFはすべての人を対象とし、障害の有無に関わらず生活機能を把握する枠組みとして設計されています。そのため、予防医療やリハビリだけでなく、健康増進や社会参加の促進といった広い視点でも活用可能です。
ICFの生活機能モデルと6つの構成要素
ICFの生活機能モデルは、個人の健康状態や心理的・社会的要因を含めた多角的な視点で評価するために、6つの主要な構成要素を設定しています。
ICFの生活機能モデルでは、身体面だけでなく環境や個人の内面も含めた総合評価が可能になります。これらが相互に影響し合うことで、実際の生活機能や社会参加の程度が決まると考えられているのが大きな特徴です。
例えば健康状態が良くても、環境因子が整っていなければ活動や社会参加が制限されることがあります。一方で、個人因子として高いモチベーションやサポート意欲があれば、ある程度の障害を補って社会参加を続けることも可能です。
こうした複合的な視点から、ICFは生活機能を把握していきます。6つの要素それぞれが独立しているわけではなく、互いに関連し合う存在である点を理解することが、ICFを上手に活用する鍵となります。
ICFの生活機能モデルでは、身体面だけでなく環境や個人の内面も含めた総合評価が可能になります。これらが相互に影響し合うことで、実際の生活機能や社会参加の程度が決まると考えられているのが大きな特徴です。
例えば健康状態が良くても、環境因子が整っていなければ活動や社会参加が制限されることがあります。一方で、個人因子として高いモチベーションやサポート意欲があれば、ある程度の障害を補って社会参加を続けることも可能です。
こうした複合的な視点から、ICFは生活機能を把握していきます。6つの要素それぞれが独立しているわけではなく、互いに関連し合う存在である点を理解することが、ICFを上手に活用する鍵となります。
① 健康状態
健康状態は、病気・外傷・疾患など個人の医学的側面を示す要素です。例えば慢性疾患の有無や症状の進行度合いなどがここに当てはまります。
一般的には、医療的ケアの必要度や服薬状況を評価するため指標として扱われることが多く、他の要素や生活機能と密接に関連します。重篤な疾患がある場合、活動や参加に大きく影響するため、まずはここを正確に把握することが重要です。
ICFの考え方では、健康状態はあくまで全体の一部分として位置づけられ、個人や周囲の環境に応じて多面的に評価される点がポイントです。
一般的には、医療的ケアの必要度や服薬状況を評価するため指標として扱われることが多く、他の要素や生活機能と密接に関連します。重篤な疾患がある場合、活動や参加に大きく影響するため、まずはここを正確に把握することが重要です。
ICFの考え方では、健康状態はあくまで全体の一部分として位置づけられ、個人や周囲の環境に応じて多面的に評価される点がポイントです。
② 心身機能・身体構造
心身機能・身体構造では、解剖学的機能や心理的機能などを総合的に評価します。具体的には、筋力・関節可動域・認知機能・感情面などが含まれます。
例えば「視覚や聴覚にどの程度の支障があるか」「歩行に必要な筋力がどれくらい保たれているか」といった実際の機能面の状況を把握することが重要です。
また、心理的ストレスや認知機能の低下といった要素も含まれ、環境や肥満など生活習慣とも連動しやすい範囲であるため、精度の高いアセスメントが求められます。
例えば「視覚や聴覚にどの程度の支障があるか」「歩行に必要な筋力がどれくらい保たれているか」といった実際の機能面の状況を把握することが重要です。
また、心理的ストレスや認知機能の低下といった要素も含まれ、環境や肥満など生活習慣とも連動しやすい範囲であるため、精度の高いアセスメントが求められます。
③ 活動
活動は、日常生活で行われる具体的な行動や課題の実行状況を指します。例えば食事動作、入浴、家事といった身近な例が挙げられます。
ICFでは、これらの活動がどれくらい自立して行えるか、どんな補助が必要かを評価することで、利用者や患者がどの程度生活機能を獲得しているかを見極めます。
支援プランでは、活動における課題の原因が心身機能にあるのか、環境因子にあるのかなどを併せて検討することで、より効果的なアプローチを導き出すことができます。
ICFでは、これらの活動がどれくらい自立して行えるか、どんな補助が必要かを評価することで、利用者や患者がどの程度生活機能を獲得しているかを見極めます。
支援プランでは、活動における課題の原因が心身機能にあるのか、環境因子にあるのかなどを併せて検討することで、より効果的なアプローチを導き出すことができます。
④ 参加
社会・家庭・地域など、さまざまな場面でその人がどのように関わっているかや役割を担えているかを評価するのが参加の要素です。
活動ができても、社会参加が制限される場合があり、そこで生活機能を阻害する原因を見つけることが必要となります。あるいは活発に参加できることで、逆に心身機能の向上を促す相乗効果も期待できます。
ICFでは、参加が重要であると同時に、その人が社会的にどれだけ望む役割を果たせているかを把握することで、生活の質を高めるケアプランを提案しやすくなります。
活動ができても、社会参加が制限される場合があり、そこで生活機能を阻害する原因を見つけることが必要となります。あるいは活発に参加できることで、逆に心身機能の向上を促す相乗効果も期待できます。
ICFでは、参加が重要であると同時に、その人が社会的にどれだけ望む役割を果たせているかを把握することで、生活の質を高めるケアプランを提案しやすくなります。
⑤ 環境因子
環境因子は、物理的なバリアフリー設備や福祉機器の利用、社会制度の有無といった外部要因を指します。周囲の支援ネットワークや家族構成も重要な要素です。
例えば、段差のある住環境では移動が困難となる場合があり、車椅子や手すりの設置などの支援策が必要になります。また、社会制度が整備されていれば継続的なケアが受けやすくなるなど、生活機能に大きく影響します。
こうした外的要因は、個人の心身機能だけでは解決できない課題を見出す手がかりとなるため、ICFの視点から見ると非常に重要な項目となります。
例えば、段差のある住環境では移動が困難となる場合があり、車椅子や手すりの設置などの支援策が必要になります。また、社会制度が整備されていれば継続的なケアが受けやすくなるなど、生活機能に大きく影響します。
こうした外的要因は、個人の心身機能だけでは解決できない課題を見出す手がかりとなるため、ICFの視点から見ると非常に重要な項目となります。
⑥ 個人因子
個人因子には、年齢、性別、価値観、生活経験、性格など、その人固有の特性が含まれます。どのように励まされればやる気が出るのか、どんなライフスタイルを大切にしているのかなど多方面にわたります。
これらの要素は支援を行う上で見逃せないポイントであり、本人に最適な方法を考えるうえで大いに参考になります。同じ健康状態でも、価値観が異なれば生活機能がまったく異なる形で表れることがあります。
そのため、個人因子はケアプラン策定やリハビリ計画で柔軟性を持たせる指標として重視され、個々の背景や希望に合った支援の基盤となります。
これらの要素は支援を行う上で見逃せないポイントであり、本人に最適な方法を考えるうえで大いに参考になります。同じ健康状態でも、価値観が異なれば生活機能がまったく異なる形で表れることがあります。
そのため、個人因子はケアプラン策定やリハビリ計画で柔軟性を持たせる指標として重視され、個々の背景や希望に合った支援の基盤となります。
ICFの分類コードと評価点の仕組み
ICFでは、各機能や背景因子をコード化し、その状態や影響度を評価点によって示すことで、より客観的な共有が可能となります。
ICFの分類コードはアルファベットで示される領域(bは身体機能、sは身体構造、dは活動と参加、eは環境因子など)と数字の組み合わせによって構成されます。こうした体系があることで、複雑になりがちな項目を整理しやすくなります。
例えば「b280:痛みの感覚」というコード表示を使えば、複数の専門職が該当項目を共有する際にも曖昧さを減らすことが可能です。同時に、どの程度痛みが機能を妨げているかを評価点で示すことで具体的な議論がしやすくなります。
また、評価点は0~4のほか、観察不能などを表す8、該当しない場合を表す9などがあり、状態を段階的に表現できます。こうしたシステムにより、必要に応じた介入や活用方法を検討しやすくなる点がICFの強みです。
ICFの分類コードはアルファベットで示される領域(bは身体機能、sは身体構造、dは活動と参加、eは環境因子など)と数字の組み合わせによって構成されます。こうした体系があることで、複雑になりがちな項目を整理しやすくなります。
例えば「b280:痛みの感覚」というコード表示を使えば、複数の専門職が該当項目を共有する際にも曖昧さを減らすことが可能です。同時に、どの程度痛みが機能を妨げているかを評価点で示すことで具体的な議論がしやすくなります。
また、評価点は0~4のほか、観察不能などを表す8、該当しない場合を表す9などがあり、状態を段階的に表現できます。こうしたシステムにより、必要に応じた介入や活用方法を検討しやすくなる点がICFの強みです。
分類コードの見方
ICFの分類コードには、身体機能を表すb(body functions)、身体構造を表すs(body structures)、活動と参加を表すd(activities and participation)、環境因子を表すe(environmental factors)などが用いられます。
これらのアルファベットのあとに数字が続き、より詳細な項目へと分類されます。例えば手指の機能と聴覚の機能は異なる数字で示され、ケア現場での情報共有を正確に行えるように体系化されています。
こうしたコード表記は国際的に共通化されており、翻訳の壁を越えてICFを活用できる点も大きなメリットです。
これらのアルファベットのあとに数字が続き、より詳細な項目へと分類されます。例えば手指の機能と聴覚の機能は異なる数字で示され、ケア現場での情報共有を正確に行えるように体系化されています。
こうしたコード表記は国際的に共通化されており、翻訳の壁を越えてICFを活用できる点も大きなメリットです。
評価点の区分と活用方法
ICFでは、多くの場合、0~4の5段階評価で状態を把握します。0は問題なし、4は完全に問題があるといった目安となるため、どの程度の支障があるのかを直感的に共有できます。
また、本人の状態がそもそも観察不可能な場合を8、該当しない場合を9などで示すような仕組みも取り入れており、現場での柔軟性を高めています。
ケアプラン作成やリハビリ計画の立案では、この評価点を参考にしながら、支援の優先順位や目標設定を行います。その結果、多職種チームで統一感のある支援方針を立てやすくなるという利点があります。
また、本人の状態がそもそも観察不可能な場合を8、該当しない場合を9などで示すような仕組みも取り入れており、現場での柔軟性を高めています。
ケアプラン作成やリハビリ計画の立案では、この評価点を参考にしながら、支援の優先順位や目標設定を行います。その結果、多職種チームで統一感のある支援方針を立てやすくなるという利点があります。
ICFの考え方を反映したアセスメントと書き方のポイント
ICFの考え方を取り入れたアセスメントでは、利用者の全体像を捉えるための記録と情報整理が重要です。
単に身体的な状況や疾患名を羅列するだけでなく、環境因子や個人因子、社会参加の状況などを含めて整理することで、より精度の高い分析が可能となります。これがICFの考え方を実践するうえでの鍵となります。
具体的には、生活機能モデルの要素別に情報を分類していく作業が大切です。心身機能だけでなく参加や環境因子も評価することで、アプローチすべきポイントが明確になるからです。
このようなアセスメントを通じて、支援目標の方向性を共有しやすくなり、チーム全体で共通理解が深まります。結果として、利用者本人に最適なケアやリハビリプランの作成が実現しやすくなります。
単に身体的な状況や疾患名を羅列するだけでなく、環境因子や個人因子、社会参加の状況などを含めて整理することで、より精度の高い分析が可能となります。これがICFの考え方を実践するうえでの鍵となります。
具体的には、生活機能モデルの要素別に情報を分類していく作業が大切です。心身機能だけでなく参加や環境因子も評価することで、アプローチすべきポイントが明確になるからです。
このようなアセスメントを通じて、支援目標の方向性を共有しやすくなり、チーム全体で共通理解が深まります。結果として、利用者本人に最適なケアやリハビリプランの作成が実現しやすくなります。
ICFシート作成における項目整理
ICFシートを作成する際は、まず健康状態や活動などの大項目を見出しとして用意し、そこに該当する情報を振り分けていきます。疾患の症状、生活の中での困りごと、社会制度の利用状況などを分類コードとともに記載するとスムーズです。
このとき、利用者の強みや得意な部分にも着目することがポイントです。介護や看護の現場では、どうしてもできないことに注目しがちですが、ICFでは「できること」を把握し適切に活かすことが重視されます。
項目整理が進むと、必要な支援の優先順位や具体的な方法が自然と見えてくるため、現場で狙いを定めたサポートが行いやすくなります。
このとき、利用者の強みや得意な部分にも着目することがポイントです。介護や看護の現場では、どうしてもできないことに注目しがちですが、ICFでは「できること」を把握し適切に活かすことが重視されます。
項目整理が進むと、必要な支援の優先順位や具体的な方法が自然と見えてくるため、現場で狙いを定めたサポートが行いやすくなります。
介護・看護・リハビリ現場でのICFの具体的運用例
例えば、リハビリテーションの場ではICFの各要素ごとに目標を設定し、進捗を評価点で記録しながら段階的にアプローチを変えていく実践が行われています。歩行能力の改善が目標の場合、環境因子として家屋のバリアフリー整備も同時に検討するなど、多面的な対応が可能になります。
看護の現場では、ICFの分類コードを元に申し送りやカルテ記載を行うことで、利用者の状態を他職種にわかりやすく伝達できるといったメリットがあります。活動レベルや社会参加の度合いがわかるため、チーム全体で共有しやすいのです。
介護現場では、高齢者のADL(日常生活動作)評価とICFの活動・参加レベルを合わせて考察することで、モチベーションアップや身体機能向上を狙ったケアプランを作成できます。利用者本人にも目標が明確になり、納得感のある支援につながりやすくなります。
看護の現場では、ICFの分類コードを元に申し送りやカルテ記載を行うことで、利用者の状態を他職種にわかりやすく伝達できるといったメリットがあります。活動レベルや社会参加の度合いがわかるため、チーム全体で共有しやすいのです。
介護現場では、高齢者のADL(日常生活動作)評価とICFの活動・参加レベルを合わせて考察することで、モチベーションアップや身体機能向上を狙ったケアプランを作成できます。利用者本人にも目標が明確になり、納得感のある支援につながりやすくなります。
ICFを活用するメリット:生活機能を包括的に把握する
多角的視点からの評価を可能にすることが、ICFを導入する大きなメリットです。
健康状態や心身機能などの医学的要素と、家族構成や居住環境などの生活背景の両面を同時に評価できるため、本人に必要なケアをより正確に見出すことができます。これにより、見落とされがちな社会参加や心理的要素にも着目しやすくなります。
また、ICFの視点を取り入れると、利用者自身が主体的に取り組める部分が明確になり、モチベーションが高まりやすいという点も挙げられます。できることを活かしながら支援することで、生活機能の向上を効果的にサポートできます。
複雑化するケアニーズや多職種連携の必要性が高まる現代において、客観的かつ総合的な評価を共有できるICFは現場の大きな助けとなっています。
健康状態や心身機能などの医学的要素と、家族構成や居住環境などの生活背景の両面を同時に評価できるため、本人に必要なケアをより正確に見出すことができます。これにより、見落とされがちな社会参加や心理的要素にも着目しやすくなります。
また、ICFの視点を取り入れると、利用者自身が主体的に取り組める部分が明確になり、モチベーションが高まりやすいという点も挙げられます。できることを活かしながら支援することで、生活機能の向上を効果的にサポートできます。
複雑化するケアニーズや多職種連携の必要性が高まる現代において、客観的かつ総合的な評価を共有できるICFは現場の大きな助けとなっています。
異職種間での情報共有が容易に
介護職、看護師、リハビリ担当医、ソーシャルワーカーなど、職種によって専門用語や視点は異なります。ICFを基準に情報を整理することで、多職種が同じフレームを使って話し合える点がメリットです。
例えば異なる分野の専門家でも「d540(移動関連の活動)」というコードを用いれば、移動能力の評価をすぐに共有できます。こうした共通言語の存在は、ケアの連続性を高めるうえで欠かせません。
結果として、必要なサポートが漏れにくくなり、利用者の望む生活を形にするためのチームアプローチが円滑に機能するようになります。
例えば異なる分野の専門家でも「d540(移動関連の活動)」というコードを用いれば、移動能力の評価をすぐに共有できます。こうした共通言語の存在は、ケアの連続性を高めるうえで欠かせません。
結果として、必要なサポートが漏れにくくなり、利用者の望む生活を形にするためのチームアプローチが円滑に機能するようになります。
利用者中心のケアプラン作成が可能
ICFの考え方では、利用者の価値観や背景を重視しながら、生活機能モデルをベースにケアプラン全体を設計していきます。そのため、本人の強みや希望を反映しやすく、画一的な支援を回避できます。
また、活動と参加の要素を具体的に捉えることで、どの部分に介入すれば自立度やQOL(生活の質)が向上するかを把握しやすくなります。結果として、細かい目標を設定しやすくなり、達成度をモチベーションにもつなげられます。
利用者が主体的になれるかどうかでケアの効果は大きく左右されますが、ICFの枠組みでは本人や家族が社会参加や生活機能の向上に向けて取り組む意欲を高めやすい環境が整います。
また、活動と参加の要素を具体的に捉えることで、どの部分に介入すれば自立度やQOL(生活の質)が向上するかを把握しやすくなります。結果として、細かい目標を設定しやすくなり、達成度をモチベーションにもつなげられます。
利用者が主体的になれるかどうかでケアの効果は大きく左右されますが、ICFの枠組みでは本人や家族が社会参加や生活機能の向上に向けて取り組む意欲を高めやすい環境が整います。
まとめ・総括:ICFがもたらす可能性と今後の展望
ICFは障害の有無にかかわらず、すべての人を対象として生活機能を捉えることができる有効なツールです。今後もさらなる普及と発展が期待され、多様な状況における包括的なケアや支援を支える指針としての役割を果たしていくでしょう。
ICF(国際生活機能分類)は、個人の健康状態だけでなく背景因子や環境因子も含めた包括的な評価基準を提供し、医療・介護・リハビリテーションの領域だけでなく、教育や福祉分野にも共通言語をもたらします。
分類コードと評価点を活用することで、多職種が連携しやすくなり、本人や家族が主体的に生活機能の向上を目指すためのステップが明確化されます。そうした実効力の高さから、ICFは専門家のみならず多方面の利用者にも関心を集めています。
今後はICTとの連携や、より細分化された評価スケールの導入など、さらにICFを活用しやすくする試みが広がることが期待されます。生活の質や社会参加を重視する時代において、ICFの考え方が果たす役割はますます大きくなっていくと考えられます。
ICF(国際生活機能分類)は、個人の健康状態だけでなく背景因子や環境因子も含めた包括的な評価基準を提供し、医療・介護・リハビリテーションの領域だけでなく、教育や福祉分野にも共通言語をもたらします。
分類コードと評価点を活用することで、多職種が連携しやすくなり、本人や家族が主体的に生活機能の向上を目指すためのステップが明確化されます。そうした実効力の高さから、ICFは専門家のみならず多方面の利用者にも関心を集めています。
今後はICTとの連携や、より細分化された評価スケールの導入など、さらにICFを活用しやすくする試みが広がることが期待されます。生活の質や社会参加を重視する時代において、ICFの考え方が果たす役割はますます大きくなっていくと考えられます。
介護現場の研修をアシスト!介護現場向けオンライン・オンデマンド研修見放題サービス
介護現場の研修に最適で、法定研修も充実の「オンデマンド研修動画見放題サービス」では、ICFに関連する講座も含め、35講座70時間以上の講座がお申し込みから1年間見放題でサービスを提供中です。2024年4月から義務化された虐待防止などの法定研修にも対応しています。また、管理職やリーダー向けの研修も充実しており、日本福祉大学教員と最前線で活躍する講師が登壇する研修で、業務に直結する内容をポイントを押さえて提供しています!
詳しくは下記ボタンのリンク先のホームページから
介護・福祉分野の人材研修なら日本福祉大学社会福祉総合研修センターへお任せください!