FUKU+TOPICS
ホーム FUKU+TOPICS 生活困窮とは?
生活困窮とは?
2025.07.09
生活困窮と聞くと、「お金がない」ことによって経済的に困窮している状態であるというように認識する方が多いかと思います。もちろん上記のような経済的困窮も生活困窮状態の要因ではありますが、伴走型支援の考え方としては「経済的困窮」だけでなく、つながりがない「社会的孤立」、自信・意欲・尊厳が持てない「生への意欲喪失」の大きく3つが複合的に重なり合い、相互に関連しあいながら生活に大きな支障をもたらしている状態のことを指します。
実際に、様々な研究で経済困窮と社会的孤立には関連があることが挙げられており、「2017年 生活と支え合いに関する調査報告書」においても、会話頻度が2週間に1回以下の人の比率が、高所得者層(所得上位10%)の方が0.6%に対して、低所得者層(所得下位10%)の方が7.5%、子供以外の介護や看病で頼れる人がいないと回答した方が、
高所得者層(所得上位10%)の方が21.2%に対して、低所得者層(所得下位10%)の方が40.4%といずれも低所得者層の方が高い割合での回答となっております。
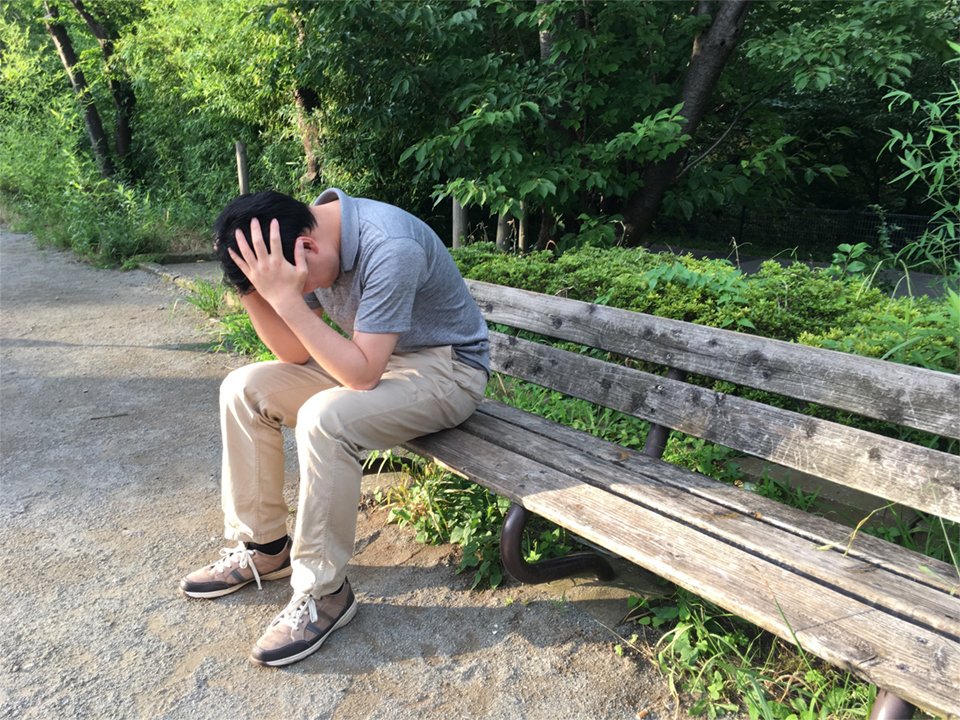
- もくじ
絶対的貧困と相対的貧困
単に貧困といっても、貧困には絶対的貧困と相対的貧困があり、それらは区別されてきました。
以下ではそれらの違いと日本で貧困を考える際の基準について考えていきます。
以下ではそれらの違いと日本で貧困を考える際の基準について考えていきます。
絶対的貧困
人が生存するために必要な食事や衣服や住居を得られない状態のこと。
例えば世界銀行の国際貧困ラインを1日2.15ドル以下(2022年9月改定)とされています。
相対的貧困
その社会のほとんどの人が享受している「ふつうの生活」を送ることが困難な状態のこと。
食事や衣服や住居があることはもちろんのこと、余暇活動や社会的な参加の機会の保障や人としての尊厳が守られることも必要であるとされています。
先進産業国である現在の日本で貧困を考える際は、もちろん基準として絶対的貧困ではなく、相対的貧困を基準において考えるべきであるとされています。
食事や衣服や住居があることはもちろんのこと、余暇活動や社会的な参加の機会の保障や人としての尊厳が守られることも必要であるとされています。
先進産業国である現在の日本で貧困を考える際は、もちろん基準として絶対的貧困ではなく、相対的貧困を基準において考えるべきであるとされています。
生活困窮が広がった背景
日本では1990年代後半から大きく広がったとされています。
ではなぜ1990年代後半から広がり始めたのでしょう?
その理由として、この時期に日本社会の構造が大きく変容したことが挙げられます。 90年後半以前の日本は高度経済成長期からその後のバブル崩壊までに形作られた社会構造によって社会が動いていました。しかしながらバブル崩壊以降は、その社会構造を変容をせざるを得ない状態となり、その結果生じた、「新たな社会的リスク」に既存の社会保障や福祉の制度が対応できていなかったことで大きく広がり始めたと言われています。
上記のようなことから、生活困窮は個人の自己責任ということではなく、社会構造の変容によってもたらされたものとも言えるでしょう。
その理由として、この時期に日本社会の構造が大きく変容したことが挙げられます。 90年後半以前の日本は高度経済成長期からその後のバブル崩壊までに形作られた社会構造によって社会が動いていました。しかしながらバブル崩壊以降は、その社会構造を変容をせざるを得ない状態となり、その結果生じた、「新たな社会的リスク」に既存の社会保障や福祉の制度が対応できていなかったことで大きく広がり始めたと言われています。
上記のようなことから、生活困窮は個人の自己責任ということではなく、社会構造の変容によってもたらされたものとも言えるでしょう。
生活困窮者自立支援制度の概要
現在の日本では、生活困窮者自立支援法に基づき、政府や自治体は相談から就労支援まで多面的なサポートを用意しています。
この制度は2013年に公布され、2015年から本格的に運用が始まりました。生活困窮に陥る手前の段階から早めに相談や支援が受けられるよう、制度設計がなされているのが大きな特徴です。背景には、生活保護を受けてしまう前に支援を行うことで、できるだけ自立を促し安定した暮らしを取り戻す狙いがあります。
実際には、相談支援窓口を開設し、専門の相談員が就労に関するアドバイスや、家計の再建をサポートします。資金面では住居確保給付金などの給付型支援を活用することで、家賃の支払いを一時的に軽減するなど、緊急的なセーフティネットとして機能します。
このように、日常生活の立て直しを多角的にサポートする仕組みがある一方で、制度を知らずに困っている人が数多く存在しています。困窮状態にある方が、自分の状態や年収状況に合わせて適切な支援を受けやすくするためにも、広報や行政窓口の連携強化が求められています。
この制度は2013年に公布され、2015年から本格的に運用が始まりました。生活困窮に陥る手前の段階から早めに相談や支援が受けられるよう、制度設計がなされているのが大きな特徴です。背景には、生活保護を受けてしまう前に支援を行うことで、できるだけ自立を促し安定した暮らしを取り戻す狙いがあります。
実際には、相談支援窓口を開設し、専門の相談員が就労に関するアドバイスや、家計の再建をサポートします。資金面では住居確保給付金などの給付型支援を活用することで、家賃の支払いを一時的に軽減するなど、緊急的なセーフティネットとして機能します。
このように、日常生活の立て直しを多角的にサポートする仕組みがある一方で、制度を知らずに困っている人が数多く存在しています。困窮状態にある方が、自分の状態や年収状況に合わせて適切な支援を受けやすくするためにも、広報や行政窓口の連携強化が求められています。
相談支援・就労支援・住居確保給付金などの主なサポート
相談支援は、まず困窮者が現状を整理し、解決策を模索する場として機能します。ここでは家計の見直しや、能力を活かせる仕事探しのサポートを受けることができます。専門の相談員が寄り添ってくれることで、孤立感や心理的な不安も軽減されるでしょう。
就労支援では、職業訓練や求人情報の提供だけでなく、面接対策や履歴書の書き方など実践的なアドバイスを受けることが可能です。これによって、長年仕事から離れていた方や就労経験が少ない方でも、就職へのハードルを下げることができます。
住居確保給付金は家賃相当額の一部を一定期間サポートし、住まいを失うリスクからの回避を助ける制度です。特に一人暮らしで収入が不安定な方にとっては大きな支えとなりますが、支給要件や申請手続きを知らないがために、本来利用できるはずの人が利用できていない現状も課題です。
住居確保給付金は家賃相当額の一部を一定期間サポートし、住まいを失うリスクからの回避を助ける制度です。特に一人暮らしで収入が不安定な方にとっては大きな支えとなりますが、支給要件や申請手続きを知らないがために、本来利用できるはずの人が利用できていない現状も課題です。
自治体による独自の支援策
国の制度以外にも、各自治体が独自の支援プログラムを運用しているケースもあります。
近年では自治体レベルでの取り組みが活発化し、地域の実情に合わせた細やかな支援施策が盛んに行われています。たとえば、子どもを抱えるひとり親世帯に対して学用品や食糧支援を行う取り組み、また高齢者向けの居場所づくりとして地域サロンを運営する例も徐々に増えてきました。
こうした自治体独自の支援策は、国の制度だけではカバーしきれない部分を補完します。特に、コミュニティのつながりを強めたり、緊急時に助け合う風土づくりに大きな役割を果たすと考えられています。支援を受ける側も、身近な地域でのサポートを実感しやすく、相談のハードルが下がる点がメリットです。
自治体独自の支援を活用することで、生活困窮者の自立につながる学びや経験を得られる機会も増えます。制度の周知がまだ十分でない地域もあるため、地域の広報紙や公式サイトなどをこまめにチェックすることが重要といえます。
近年では自治体レベルでの取り組みが活発化し、地域の実情に合わせた細やかな支援施策が盛んに行われています。たとえば、子どもを抱えるひとり親世帯に対して学用品や食糧支援を行う取り組み、また高齢者向けの居場所づくりとして地域サロンを運営する例も徐々に増えてきました。
こうした自治体独自の支援策は、国の制度だけではカバーしきれない部分を補完します。特に、コミュニティのつながりを強めたり、緊急時に助け合う風土づくりに大きな役割を果たすと考えられています。支援を受ける側も、身近な地域でのサポートを実感しやすく、相談のハードルが下がる点がメリットです。
自治体独自の支援を活用することで、生活困窮者の自立につながる学びや経験を得られる機会も増えます。制度の周知がまだ十分でない地域もあるため、地域の広報紙や公式サイトなどをこまめにチェックすることが重要といえます。
社会福祉協議会など地域の取り組みと活用事例
社会福祉協議会(社協)は、住民同士の支え合いを促進することを目的とした民間組織です。緊急小口資金の貸付けや生活支援ボランティアの派遣など、地域に根ざした柔軟な支援が特徴といえます。
具体的な活用事例としては、マンツーマンで家計管理のアドバイスを行う仕組みや、引きこもりの方の外出支援などがあります。公的機関の制度と連携して、支援を必要とする人へ多層的にアプローチできる点が大きな強みです。
また、地元のNPOやボランティア団体と協力してフードバンクを運営するなど、地域コミュニティで生活困窮を食い止める取り組みも進んでいます。こうした活動に参加することで、支援を受ける側だけでなく、地域住民全体が貧困対策に関心を持つきっかけにもなっています。
具体的な活用事例としては、マンツーマンで家計管理のアドバイスを行う仕組みや、引きこもりの方の外出支援などがあります。公的機関の制度と連携して、支援を必要とする人へ多層的にアプローチできる点が大きな強みです。
また、地元のNPOやボランティア団体と協力してフードバンクを運営するなど、地域コミュニティで生活困窮を食い止める取り組みも進んでいます。こうした活動に参加することで、支援を受ける側だけでなく、地域住民全体が貧困対策に関心を持つきっかけにもなっています。
まとめ・総括
生活困窮者への適切な支援は、自身だけではなく社会全体の課題解決にも大きく寄与します。
生活困窮の背景には、グローバル化による雇用の不安定化や家族形態の変化、高齢化、所得格差など複数の要因が存在しています。一人ひとりが抱える事情は異なるため、より柔軟で包括的なアプローチが求められます。
国はもちろん、自治体や社会福祉協議会、NPO法人など様々な団体が支援策を実施していますが、そのアプローチのひとつとして注目されている支援の考え方が「伴走型支援」です。 個人に対する支援であるとともに、人を孤立させない地域社会の創造を目指す活動でもあります。
生活困窮の背景には、グローバル化による雇用の不安定化や家族形態の変化、高齢化、所得格差など複数の要因が存在しています。一人ひとりが抱える事情は異なるため、より柔軟で包括的なアプローチが求められます。
国はもちろん、自治体や社会福祉協議会、NPO法人など様々な団体が支援策を実施していますが、そのアプローチのひとつとして注目されている支援の考え方が「伴走型支援」です。 個人に対する支援であるとともに、人を孤立させない地域社会の創造を目指す活動でもあります。
伴走型支援基礎講座
伴走型支援は深刻化する「社会的孤立」に対応するために‶つながり続けること”を目的とした支援として生まれた、個人に対する支援であるとともに、人を孤立させない地域社会の創造を目指す活動です。日本の対人援助の現場において培われてきた「伴走型支援」について、その求められてきた背景、この支援で大切にされる理念や哲学、実際の支援や関連する政策動向などについて、多角的に学びます。

