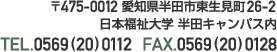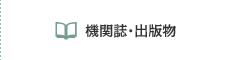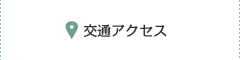地域包括ケア部について
誰もが住み慣れた地域で、その人らしい「ふくし(ふつうのくらしのしあわせ)」を実現していくということを「権利」としてとらえ、その実現に向けて多様な主体の協働によって推進していくということを日本福祉大学は大学の使命として掲げ、「Well-being for All」を探求してきました。
「知多は1つ」という言葉があるように、知多半島に所在する自治体は、横のつながりが深いということがよく言われます。その一方で、地域特性はそれぞれの市町ごとに異なり、地域包括ケアのしくみづくりに向けて取り組む歩みのプロセスや速度、しくみづくりを必要とする地域課題の様相、しくみづくりに必要な人材や資源の配置状況も多様性に満ちています。地域で「ふくし(ふつうのくらしのしあわせ)」を実現するという大きな理念的な目標は共通であったとしても、5市5町の取り組みはそれぞれ固有のものとなり、ともすると「うちはうちのやり方、よそはよそのやり方」ということになりがちです。
地域に根ざした日本福祉大学の1機関としての知多半島総合研究所地域包括ケア部は、1つ1つの市町の地域包括ケアのしくみづくりのプロセスに寄り添うと共に、知多半島を1つの大きな地域として捉え、その地域に蓄積されている「知多の知」を5市5町の社協・NPOをはじめとする実践者の方々、行政の方々と共に、共有できる形に紡いでいくことを目指しています。先進的な事例を取り上げるだけでなく、取り組みの中でなかなかうまくいかないという悩みや不安、一歩ずつ進めるためのコツや実践知を丁寧に抽出し、協働研究のメンバーである知多の実践者の方々と共有し、協議するということを大切にしていきたいと考えています。
地域包括ケア部は、この「知多の知」を紡ぐネットワークのコーディネーター役割として機能することを目指しますが、それは「研究者のための研究」であってはならないと考えています。知多という地域の中で暮らす0から100歳のすべての人々の「ふくし」を実現することが、目指すべきゴールです。そのために「知多の知」を紡ぐこと、その「知」を紡ぐことをめざす協働のパートナーは、5市5町の地域包括ケアを担う実践者であるということが、地域包括ケア部の根幹となります。
また知多で紡いだ「知」は、もちろん知多の地域づくりに還元されていきますが、同時に全国に向けても発信され、「知多の知」がそれぞれの地域で参考にされ、それぞれの地域固有の「知」に発展的に継承されていくということも、また地域包括ケア部の目指すもう一つの方向性です。「知」は開かれ、現場で実装されてこそその価値が高まると考えるからです。
知多半島から全国へ、そして知多半島からそれぞれの5市5町へという往還のハブ機能として、今後も地域包括ケア部の歩みを進めていきたいと思います。

地域包括ケア部長
社会福祉学部 教授
川島 ゆり子
研究分野: 地域福祉,コミュニティソーシャルワーク
主な受託研究(2016年度以降)
東海市
重層的支援体制整備事業に関する職員研修(2023~)
美浜町
地域福祉計画策定(2016)
ニッセイ財団
委託研究「住民主体の包括的支援体制の構築をめざした戦略~0 歳から100 歳のすべての人が安心して暮らせる地域づくりをめざして~」(2017~2019)
(以上の実績は、地域包括ケア部の前身である「地域ケア研究推進センター」のもの)