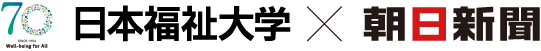入賞作品
- エッセイコンテストTOP
- 入賞作品
-
スポーツ・文化活動を通して
スポーツ・文化活動を通して 入賞作品
私がもらった勇気
遠藤 日和(東日本国際大学附属昌平高等学校 3年)
「一緒に読んでもいいですか?」
思わず私の口から出た一言だった。
所属するJRC部(青少年赤十字連絡協議会)の地区総会でのことだった。
総会は、顧問の先生方の協力を得ながら、私たち高校生が主体となって運営した。参加校に特別支援学校も含まれ、その生徒が開会の言葉を担当した。しかし、壇上の彼の口からは、なかなか声が出てこない。彼に寄り添う先生は「3・2・1」と、指合図で発声を促しているのだが、彼の顔は強張っていくばかり。重い静寂が5分間はあったろうか。会場の参加者たちからの「頑張れ」と応援する眼差しと無言の激励を感じた。
私に何かできないだろうか。なんとかしたい。そんな思いから出たのが、冒頭の私の言葉だった。想定外の事態に、誰からも私の発言に反応はなかったが、無言の承諾と理解して、マイクを前にした彼の横に立った。
彼が手にする原稿には大きな文字で開会の言葉が記されていた。事前にだいぶ練習してきたことがわかった。私は、小声で「せーの」と彼に伝え、「これから」と読み始めた。その瞬間、彼から大きな声が出てきた。
「これから、地区高等学校青少年赤十字連絡協議会開会式を始めます」
会場からは、大きな拍手が湧き起こり、拍手はしばらく止むことはなかった。
壇上から降りた彼と引率の先生から「ありがとう」とお礼を言われた時、何とも言えない穏やかな気持ちになった。勇気をもらったのは私の方なのに…。
この体験を通して、私は、たとえ障害があっても、頑張り方は私たちと同じであること、苦手なこともあるが、助け合うことで一緒に生きていけるのだと実感し、同じ活動を頑張っている高校生がいるのを知った。
後日、特別支援学校から「一緒に読んでくれて、本当にありがとう」との手紙が学校に届いた。自然に笑みが溢れた私だった。
審査員のひとこと
全体に無駄なくまとめ上げられていて、第2分野で抜きん出た作品でした。大勢の人を前にして緊張する特別支援学校の生徒を手助けしたときの様子が、気負いのない文章で書かれていて読みやすく、現場の緊迫感も伝わってきました。
勇気も必要だったと思いますが、思わず体が動いてしまったのでしょう。そこに普段の生活ぶりがにじみ出ているようで好感が持てました。相手も素直に好意を受け取っている様子が分かり、さわやかな読後感に繋がっています。
たとえ才能がなくても。
岩田 夏希(日本女子大学附属高等学校 1年)
今日も私はピアノを弾く。決して才能があるわけではないし得意でもない。でも弾き続けるのは紛れもなくピアノが好きだからだ。
私は幼い頃からずっとピアノを習っている。物心ついた時には相棒のようにピアノを弾いていた。私はピアノを弾くことが何よりも大好きだった。
しかし、その気持ちは小学校低学年の頃に初めて出場したコンクールから変わっていった。大好きなピアノを大きなホールで弾く。それだけで楽しかった。でもそれも束の間、結果発表で私の名前は呼ばれなかった。すごく悔しかった。一緒に出場した友達は入賞していた。そしてとどめを刺すように、「残念だったね。」という声が聞こえた。私のピアノに対する気持ちはここから「上達への義務感」へと変わっていった。認められたい、誉められたい、そんな感情ばかりで楽しいという気持ちはもう消えてしまっていた。気がつくと私はピアノを弾く才能ばかり求めていた。
そんな日々が過ぎる中、コロナウイルスの蔓延によって私の日常は変わり、ピアノに対する気持ちも変化していった。七月にコンクールを控えていた私はいつものように「審査員ウケする演奏」を研究していた。そんな中友達から一件のメールが届いた。「リモート連弾をしない?」と。私はやってみることにした。二人で演奏した音源を合成して学校の友達に公開した。別にコンクールで弾くわけでもないので自分の思う通りにピアノを弾いた。なのに友達はみんな「感動した。」「コロナで落ちこんでいたけど元気が出た。」と言ってくれた。私はまぎれもない自分の演奏が友達に元気を与えていると気づいた。ピアノを弾くことが久しぶりに楽しかった。
それから私はピアノが好き、と言いきれるようになった。審査員が良いと思う演奏ではなくてありのままの自分の演奏ができるようになった。才能がなくても自分が楽しいと思える演奏を私はし続けていきたい。
審査員のひとこと
コンクールの審査員受けする演奏から、もう一度、自分が楽しいと思える演奏へ。ピアノに対する幼い頃の気持ちを取り戻し、大切な気づきに至るまでの葛藤が描かれています。才能があるかないかよりも、まず自分がピアノを好きであることが大事なのだ、という再発見の過程が分かりやすく伝わり、多くの審査員に評価されました。
コンクールで賞を取ることが目的となっているクラブ活動が多い昨今、子どもたちの気持ちや置かれている状況についても考えさせられました。
もうひとりの私
末光 芽衣(愛媛県立宇和島東高等学校 3年)
「本当の私はどれだろう。」高校に入ってそう考えることが多くなった。小中学校は規模の小さな学校に通っていたためひとりひとりが個人として確立していたし、ありのままの私でいることができた。当時は自分でも驚く程に自分に自信があり、他人から何を言われようと私自身のことが好きだった。今思い返せば、親や先生方が私にたくさん愛情を注いでいたから「黒い自分」が現れる暇が無かったんだな。恵まれていたな。と思った。
高校生になって、昔の私は抜けがらになってしまった。笑顔が下手になった。認められたい、好かれたいという気持ちばかりが貼り付いて、本当の私でいることができなくなった。いや、本当の私を捨ててしまったと言う方が正しいかもしれない。小さい頃から好きで描いていた絵も、いつしか自分の価値を上げるためのツールと化していた。
絵に対する認識が変わった。二年生の春だった。誰にも見せることのできない「黒い私」をどう処理しようと悩んだ時に自己表現として絵に起こすことにした。初めて作品にした「黒い私」はデッサンも狂っていたし構図もいつもの何十倍でたらめだったが、「黒い私」が絵に憑依したおかげで少し気持ちが楽になった。
その後、その絵をSNSに投稿すると、思った以上に反応が来た。中には「共感する」や「世界観が好き」などのコメントもあった。行き場のない感情のはけ口くらいのつもりで描いた絵が、まさか「黒い私」も存在してよいことの証明になると思わなかった。
別に私をひとつに絞る必要はないと思った。人に認められたい一心で頑張る私も、おいしいものを食べてほくほくしている私も、この「黒い私」も他の何者でもない本当の私なんだ。受験生になってしまったため絵を描くことは少なくなったが、今も「今日の私」を創作「一方通行」と名付けてSNSに投稿している。
審査員のひとこと
思春期ならではの心の揺れ動き、大人になるまでのプロセスが綴られている作品です。「黒い私」を絵に描いたことをきっかけに、SNSへの絵の投稿という自分なりの表現手段を見つけて成長していく様子が伝わり、審査員の心をつかみました。
作者は人間なら誰もが持っている嫌な部分、恥ずかしい部分を成長の過程で見つめています。それは非常に苦しい作業ですが、しっかりと向き合い、弱い自分や嫌な自分も受け入れている点がすばらしく、その姿勢に共感を覚えました。
先輩の行動で
松田 理穂子(山手学院高等学校 2年)
中学生の頃から、様々なボランティア活動に参加してきた。私はボランティア部に所属しており、学校周辺で行われるボランティアの情報が集まるからだ。砂浜でのゴミ拾いや認知症をもつ人との散歩、子ども食堂の手伝いなど、参加した活動は多岐にわたった。
コロナ禍は、私とボランティアとの関係を一変させた。人との接触が避けられない活動が多く、ボランティアの情報はあまり入ってこなくなった。文化祭での障害者作業所製品の販売も一昨年は中止、昨年は参加してもらう作業所の数を減らして実施した。ボランティアは参加するものと考えていた私は、諦めるしかなかった。
しかし、あるボランティア部の先輩が起こした行動が私を変えた。先輩はオンラインで韓国の高校生と一緒に国際理解を深めるイベントを企画したのだ。同じ高校生なのに、言語の壁まで越えるとは。私は衝撃を受けた。
当日、イベントの手伝いをすることになった。参加者が発表する形式だったので発表の熱量も高く、初めて知ることばかりだった。先輩が行動したことで、参加者の熱い思いが集まった。活動に参加するだけがボランティアではない。人々の思いを結集し、世界をよりよい方向へ動かす手伝いをする。それも、ボランティアだ。そう気づいたとき、今まで参加してきたボランティアの主催者さんの顔が浮かんだ。愛する海を守りたい。最期まで自分らしく生きてほしい。子どもたちを助けたい。そんな思いの連なりの中に、私もいたのだ。私は、ようやくボランティアの意味を理解した。
強い思いを持って行動すること。それが何かを、誰かを変えること。私がどんな思いを持ちどんな行動をすればいいか、まだ分からない。だからこそ、こうして書いて伝えること、これをひとまず私の行動にしようと思う。きっとそれが、誰かを動かす思いに繋がるはずだから。
審査員のひとこと
国際理解を深めるオンラインイベントを企画したボランティア部の先輩の行動を見て、自分が学んだことや気づきが分かりやすく書かれていて、好感が持てました。コロナ禍の経験を通じて、考え学んだことを形にした作品とも言えるでしょう。
先輩の決意と行動力に動かされ、自身の決意も生まれたことが伝わり、今後の行動が変わることへの期待もふくらみました。
イベントの様子の具体的な状況説明があると、さらに良くなったと思います。
「演じること」の魔法
小松 日菜(北杜市立甲陵高等学校 2年)
私が初めて舞台に立ったのは、保育園生の頃です。お遊戯会で村人の役を演じました。その時の、自分ではない自分が話している感覚。なんて新鮮で楽しいのだろうと衝撃を受けたのを覚えています。今思えば、その村人こそ、私の「演じること」の原点です。
私はコミュニケーションを取るのが苦手でした。一人っ子で流行に疎かった私は、周りの話について行けず、いつも一人きりでいました。
そんな私を変える出来事があったのは、中学生の頃です。クラスで、日本と朝鮮を繋いだ英雄、浅川巧の劇を上演することになりました。そこで私は、主役である浅川巧役に立候補したのです。それまでの私からは考えられないことでした。でも、自分を変えたいと思ったのです。忘れていた演劇への情熱が、私を突き動かしました。「静かなあの子が主役に立候補するなんて」とクラスメイトは驚いたでしょう。男性の役を女子が演じるのも異例の事だったと思います。私も初めは不安で仕方ありませんでした。しかし、自分を信じて突き進みました。そして本番。スポットライトの中で精一杯、巧を演じました。ふと、保育園の頃の記憶が蘇ってきました。誰かの人生に自分の人生を重ねることは、こんなに楽しいのだ。割れんばかりの拍手とクラスメイトからの温かい言葉は、私に自信を与えてくれました。
「演じること」は魔法です。時を超え、人種を超え、性別を超え、様々に姿を変えられる魔法です。世界中の誰もが、なりたい姿に変身できるのです。
私は、見ている方に勇気を与える演技をしたいと思い舞台に立っています。私が演技で変わることができたように、私の演劇を見ている人にも素敵な変化が起こって欲しいのです。多くの人を「演じること」の魔法にかけたいのです。
審査員のひとこと
忘れていた「演じること」への情熱を思い出し、中学生のときに自ら主役に立候補して演じた際の高揚感を描いています。演劇に魅せられたきっかけや生き生きとした心の動きが良く表現され、ですます調の文体も効果的でした。
「『演じること』は魔法です」という言葉に、生きていく上での今後の指針を自分なりに見つけたことが感じられ、自分の経験をうまくまとめた作品だと思います。
からくり人形からの言葉
高橋 未來(上海外国語大学附属外国語学校 3年)
私は中国のバレエ団の『くるみ割り人形』に子役として出演した。からくり人形役は私の憧れのバレリーナだった。出演者には様々な国の人が集まっていた。
バレリーナたちが舞い踊る中、私たちもチームに分かれて練習をした。私たちは3人の中国人と日本人の親友と私。早速、3人は中国語で話しかけてきた。日本語以外話せない私たちが、最も恐れていたことだ。私たちは話さず、頷くだけの魔法という名の呪いがかかった。しかしこれは言葉の壁を壊すにはとても厄介なもの。相手に配慮したつもりの行動が、険悪なムードを作り出した。結果、日本人と中国人とで踊りのバラつきが生じた。
人形たちも踊り疲れた休憩中、私の目に憧れのバレリーナが映った。私は声をかけようとしたが、言葉が通じないと簡単に諦めてしまった。だがその時。私の目の前に彼女の笑顔と華奢な手が差し出された。その瞬間私は思わず”I love you”を口にしていた。私は嬉しさと恥ずかしさでほろりと涙を零した。その涙には言葉が通じない恐怖の味も混じっていた。だが、彼女はお構い無しに私の踊りの指導までしてくれた。彼女はバレエに対する愛と熱量、言葉は通じずとも伝えたいという想いが言語の壁を破ったのだった。
レッスンに戻ると私は中国人の3人に表情や仕草、踊りを通して思いを伝えた。私の熱量が伝わったのか最終的に踊りも揃い、私たちの間に絆が生まれた。これは話す言語が同じでも変わらない。相手に「伝える」には多様性を受け入れ、相手に伝えたいという熱量が大切なのだ。実際にお菓子の国の宴でも、異国の人々が踊りという伝え方で会話している。彼女は私たちに素敵なクリスマスプレゼントを残した。くるみ割り人形のように、何も話さず頷くだけの人形から呪いが解け、言葉や熱意で伝える人間らしさを取り戻したのだった。
審査員のひとこと
子役として中国のバレエ団に出演したときの経験を題材にした作品です。中国語が分からず頷くだけの自分たちをからくり人形になぞらえていて、現場の張りつめた状況が良く伝わってきます。構成もしっかりと練られていて、評価されました。
憧れのバレリーナに「I love you」と口にする場面では、緊迫感のある情景が思い浮かび、読み終えてホッとしました。読者にそうした感情を抱かせるのは、それまでの文章がうまく書けているからだと思います。