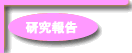 |
実践的活動を通したアシスティブテクノロジー (支援技術)に関する |
- 直接利用者の身体に触れて利用されるもの(座位保持装置など)
- 利用者自身が操作するもの(車いす,操作スイッチ,入力デバイス等)
- 製作・改造対応が必要なもの
これらは,実際利用する生活場面で一定期間利用された後,適用前後の生活の変化などを再評価する必要があり,継続的な支援やモニタリングが不可欠であるからである.
また相談者は,前に述べたように重複した障害を持っていることが多く,認知面,身体感覚等の他者からは見えにくい(理解されていない)障害や,利用者自身も気がついていない生活上の障害を持っていることがある.このことから,顕在化している要望・要求または現在の状態等の限られた情報のみから,短絡的に福祉用具や支援機器の利用につなげていくのではなく,さまざまな視点からケースワークを適宜行なわなければならない.場合によっては,人の部分的介助や社会資源の利用等を合わせて検討することはもちろん,用具を使わない解決手段も考えておく融通性が必要である.
これらのことから,利用者のニーズや生活に適合した支援機器の導入には,次のようなスキルが求められると考えられる.
①コミュニケーションスキル
- 真のニーズをとらえるために,利用者との信頼関係を作り出すこと.
- 利用者の想いを共有するためのコミュニケーション手段の獲得.
- 対話しやすい環境作りや場の提供に関すること.
②ケースワークスキル
- 潜在的な課題を見出し,支援の見通しを立てること
- 解決すべき真のニーズに対して,機器利用の有無にこだわらず具体的かつ柔軟な計画が立てられること.
- 適切な人的資源を結びつけ,活用すること.
③アダプテーションスキル
- 適切な機器を選定するための商品知識.
- 利用者ニーズを満たすための適合技術.
- 適合に必要な周辺の関連知識と各種技能.
4.スイッチ操作制御用インタフェースの開発
特に肢体不自由の障害を持つ人がスイッチを利用して機器等を操作する時には,操作方法,操作部位および利用目的・方法等に適合したスイッチを選定することだけでなく,操作時の入出力信号の制御を含めた検討もしばしば必要とされる.過去にはマイコンを利用したスイッチインタフェースを試作し5),実際の相談での適用事例を示し有効性を報告している7).今回はさらに実利用のために開発したインタフェース基板の仕様について述べるとともに,普及に向けた取り組みについても報告する.
4.1 開発したインタフェースの概要
PIC16F873A(Microchip Technology Inc.社製8))を用いてプログラムによる制御回路を設計した.今回開発した基板の外観を図1に示す.
(1)動作電源
乾電池006P(DC9V)またはACアダプタ(DC6V300mA)
(2)入力部
操作スイッチ入力:接点入力2つ(SW1/SW2).
基板上の3.5ミリモノラルジャックに任意の操作スイッチを接続するか,基板上に設けたランドに入力信号線を接続することができる.
(3)出力部
リレー出力:接点出力2つ(OUT1/OUT2,両方とも1c,接点容量2A 30VDC).
リレー出力用ランドはNO(リレー動作時OFF→ON)とNC(リレー動作時ON→OFF)を設けたため,スイッチ操作時にはリレー出力に接続された操作対象機器を作動または停止のいずれも行なうことができる.
| ←前ページ |