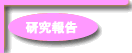 |
実践的活動を通したアシスティブテクノロジー (支援技術)に関する |
| 疾患・障害名 | 人数(人) |
備 考 |
| 脳性マヒ | 16 |
|
| 神経・筋疾患 | 15 |
|
| 脳疾患・脳障害後遺症等 | 5 |
頭部外傷者も含む |
| 脳血管障害 | 3 |
片マヒ, 四肢マヒ者等 |
| 脊髄損傷 | 4 |
全て頸髄損傷者 |
| 欠損・切断 | 3 |
手指欠損,上肢切断,下肢欠損・切断 |
| 疾病による肢体不自由 | 3 |
脊髄腫瘍後遺症等 |
| 骨形成不全 | 2 |
|
| 免疫系疾患 | 1 |
関節リウマチ |
| 不明・その他 | 2 |
3. 2 施設等からの相談対応結果
相談施設数5件に対応し,相談のべ回数は7回であった(表3,表4).個人相談と同じく継続的に相談を受け,相談記録を残したか,継続中の相談事例である.来所・訪問相談とも愛知県内施設の対応である.
| 相談施設数:5 施設 | |
| 相談のべ回数:7 回 | <内訳>来所面接:2 回, 訪問相談:5 回 |
| 平均相談回数 (相談回数/相談施設数) =1.4 回 (最大 3 回) ※継続中も含む |
|
表 4 相談施設の属性
| 施 設 属 性 | 施 設 数 (件) |
| 身体障害・知的授産施設 | 1 |
| 小規模作業所 | 1 |
| 病院 | 1 |
| 社会福祉協議会 | 1 |
| 障害者スポーツセンター | 1 |
3. 3 施設等からの相談対応結果
今年度は学生生活等における支援機器のニーズ把握を行うため,日本福祉大在学生,入学予定の高校生,および付属高校生の相談にも対応した.来所相談の他,美浜キャンパス障害学生支援センターでの相談を月一回の定期相談日を設けて行った.また,必要に応じて訪問相談にも対応した.個別相談のうち,学生からの相談実人数は9名,相談のべ回数は12回であった.
3.4 相談内容の分類
相談内容の分類を表5に示した.一人の相談に対して,関連した複数の福祉用具や支援機器の相談を受けている.表5において,相談内容別のべ件数合計195件に対し,パソコン関連(27%),操作スイッチ(13%),補助用具(13%),移動用具(13%),姿勢保持・座位保持用具(12%),コミュニケーションエイド(9%)の順に多かった.
表5 相談内容の分類(数値はのべ件数)
機器分類 |
件数 |
内訳 |
||
|
個人 |
施設等 |
||
移動用具 |
25 |
車いす |
25 |
|
姿勢保持・座位保持用具 |
24 |
車いす用,作業用いす等 |
24 |
|
ベッド関連用具 |
2 |
ベッド用テーブル |
2 |
|
入浴関連用具 |
2 |
シャワーいす |
2 |
|
コミュニケーションエイド |
17 |
VOCA・電話・その他補助用具等 |
6 |
1 |
重度障害者用意思伝達装置 |
4 |
1 |
||
呼び出し装置 |
2 |
1 |
||
| 人的支援 | 2 |
|||
操作スイッチ |
26 |
|
26 |
|
パソコン関連 |
52 |
入力デバイス |
29 |
|
ソフトウェア |
15 |
|
||
ハードウェア |
8 |
|
||
自助具 |
5 |
趣味・個人的活動 |
2 |
|
食事・調理 |
2 |
|
||
整容・着衣 |
1 |
|
||
補助用具 |
26 |
移動用具(自転車) |
2 |
|
車いす関連 |
5 |
|
||
学習活動 |
2 |
|
||
趣味・個人的活動 |
8 |
|
||
環境制御・電気製品操作 |
3 |
|
||
パソコン操作の環境整備 |
1 |
|
||
投薬管理 |
4 |
|
||
介助者向け |
1 |
|||
スポーツ用具 |
8 |
|
7 |
1 |
住宅・施設改修 |
1 |
|
1 |
|
就労支援用具 |
5 |
|
1 |
4 |
学習支援対応 |
2 |
ボランティアによる継続的支援 |
2 |
|
3.5 考察
相談者一人に対する平均相談回数は,ほぼ2回となった(表1・表3参照).この数値は継続中の相談も含まれているので,この回数内で相談が完了するというわけではないが,逆に言うと1回で相談が終了するのではないことも示している.実際の相談では相談初回も含めて少なくとも1回は詳細な内容の聞き取り,ニーズ把握,用具適合に必要な要因の評価等の時間に当てられ,2回目以降が具体的な用具の適合支援およびその試用評価等に当てられている.特に次のような適合相談に関しては,数ヶ月単位の期間を必要とされる.
| ←前ページ |