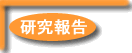 |
筋電図と映像分析からみた介助動作の特徴 |
3) 車いす移乗動作時の姿勢変化
車いす移乗時には, 中腰の姿勢から要介助者を支えながら立位姿勢となり, 約 90 度, 向きを変えながら再び
中腰姿勢で要介助者を支え, 車いすに腰掛けさせる (図 3). そのため, ひねりの要素が関節角度変化に加わり
分析が困難なため, 今回は頸の高さによって姿勢変化を観察した (図 9). 動作開始時と最も姿勢が高くなる
中間時点との差は 22〜26cm, 中間時点と動作終了時の差は 25〜28cm であった. 身長との相関関係はみられなかった.
1 回目の動作では, 動作開始時の頸部の高さが動作終了時と比べて有意に高くなった (p<0.05). 最初は,
被験者が要介助者の背中や腰に手を回すことへの遠慮があり, 組み位置が高くなったと思われるが, 5 回と 10 回
については安定していた. 今回は約 25cm の上下動が観察されたが, 要介助者の座高や身長によって上下動の幅が
変わったり, 中腰姿勢の度合いが変化すると思われる. また, 車いすによる移動先での移乗動作, ベッドに戻る
際の移乗動作, 複数人への介助といった側面を考えると介助者の腰部への負担は非常に大きくなると考えられる.
トレーニング動作では, ウエイトを保持してのハーフスクワットが相当すると思われるが, 腰部への負担を軽減する
ため, 軽い負荷から徐々に身体を慣らしていくことが必要であろう.
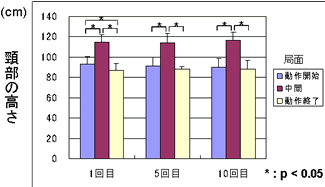 図9 車いす移乗動作の各局面における被験者
図9 車いす移乗動作の各局面における被験者
(介助者)の頸部の高さ
−動作の1回目、 5回目および 10 回目 (最終回) の比較− (各局面の動作は図3参照)
初回は動作開始の姿勢が高い傾向にあることがわかる。
また、 互いにあごを肩に密着した状態で動作を行うので、 介助者の頸部の高さは要介助者とほぼ等しい。
| ←前ページ |
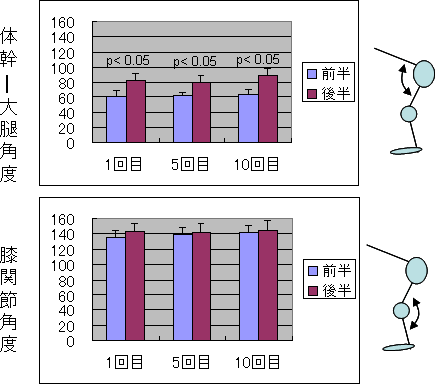
図8 上半身引き上げ局面における体幹ならびに膝の関節角度
−動作の1回目、 5回目および 10 回目 (最終回) の比較−
※前半:介助者の体幹と大腿のなす角度が最も小さくなる時点
後半:介助者の体幹と大腿のなす角度が最も大きくなる時点