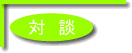
5/6ページ
○飯島
そうですね。その辺は実際にこういう失敗例もあります。例えば、こちらの視点で考えすぎないようにというのがありますよね。要するに「大きなお世話」になっちゃうというのがあります。機器等は実際に言いかえると「使ってもらえる機器」にならないといけないんですね。そういう意味での評価なんだと思うんです。
「使ってもらえる機器」にしなければいけないというのは、幾つかの要素があるんですね。これは当然個人で使うものとして供給するわけですから、例えば研究用につくってモニターでというのと違いますので、まず費用の問題がありますよね。費用については公的な補助制度が使えるのか使えないのか、これが一つキーになってきます。
自己負担でつくる場合も当然あります。これは私たちのサービスが「余暇をどう過ごすか」というスポレクの範囲までやっているために、自己負担で買ってもらうのも当然ここには存在します。そうなってきますと、ある程度手の届く価格でないとこれは話にならない。どんなにその人がこれは欲しい、いいと言っても、「はい、1,000万です」というわけにはいかないわけですよね。ですから、その見合った価格、本人が何とか手に届くそういう価格で供給しなきゃいけないのと、本人が使いたいと思う機器にしていかなきゃいけないというのが、ある意味では我々の腕の見せどころというところがありますね。
その時に、例えば最近は、コンピューターとかIT機器が非常に一般製品も進んできているものですから、我々も助けられている面があります。やり方としては、まず既製品をベースにどうできるか。既製品というのは、我々もいろんな情報を持っているわけです。それは車いすにしろ、電動車いすにしろ、姿勢保持装置にしろ、住宅関連機器にしろ、各企業もいろんな形で頑張ってきてくれていますので、これが10年前、20年前に比べたら、今は非常に整ってきていると思いますね。我々が企業と共同で開発してきたものももちろんあるわけですけれども、そういうものでかなり助けられていますから、まず情報提供で済む場合がありますね。
次に、既製品で使えない場合、要するに甘んじるのではなくて、それにちょっと手を加えるとよりその方に適合度が増すという場合、そういう手法をとります。それによって、「より早く、より使いやすく、より安く」、この3つなんです。ただし、この3つというのは簡単な話ではないと思います。ですから、そのために我々は常に情報にアンテナに張っていますね。
それから、あとは利用者が使ってくれるものにするのに、相当すり合わせをします。評価という形で訪問しますし、ある程度こちらが用意できたら、洋服で言うと仮縫いのような状況を必ずつくります。
どういうことかというと、まずメーカーからデモ機をお借りして現場に持ち込んで、その方の感覚を確認していくということです。「いや、こういうイメージじゃないよね」と言えば、当然そこをまたアレンジしていく。一気に個人用で用意しちゃいますと、とんでもないことになるんですよね。じゃそれどうするのと。それを購入するお金をどうするのということになりますから、試用期間を私たちは今、かなり用いるようにしています。車いすでもそうですけれども、半完成の状態で適合を見て、よければ仕上げていく。そこでまず問題があれば、また修正をかけて仮合わせを行ってやっていくという形ですね。それによって評価をした時のお互いの感覚とか、あるいは各スタッフの意思統一をまず努力して行うんです。それをしないとたいへんなことになることもあります。
今までに失敗はいっぱいありますけど、ひどい場合は全くつくった物を全部つくり直さなきゃいけないというようなこともなきにしもあらずですね。

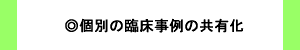
○中村
少し話が変わりますが,コンピューターは標準でユーザー補助の機能がついていますので、そういったものがある程度うまく使いこなせれば、軽度の障害の方とか高齢者の方でさほど機能低下されていない方は、それで十分使えるわけです。マスプロダクトのものが機能を上げることによって、機能が落ちてしまった人が使えるようになるところは、多分進むと思うんです。しかし,今後は,そういったものがほんのちょっと使えない人にどうアプローチするかというところが残されてくるんじゃないかと思うんですね。
そうした時に,足りないところを足していく個々の支援、横浜リハセンさんでやられているような個々の支援というものが、必要になってくると思います.ですから、それは相当限定されたアプリケーションというか適合になってくるかと思うんですね。そういった適合は、お仕事としては非常に重要なことだとは思うんですけれども、エンジニアリングという側面で見ると、そういった個々のアプライの経験がどう積み重なってくるのかなと思います。
当然そういった事例は、類似の事例は過去の事例を引っ張ってきてやって、昔こうやってやったからうまくいくんだよというところで経験を生かしてくると思うんですけれども、そういった事例をダーッと横に並べて、一般の法則みたいなものができてきて、個別の適合,個別最適化を図るというのは多分一番手間がかかって、一番お金がかかるところだと思うんです。そういった事例をたくさん集めてきて、そういったものから共通する法則みたいなものを抽出することによって、さほど手間をかけずに、さほど費用をかけずによりよいものができるようにならないと,これから先、障害者ももっと重篤な人が社会復帰を望むようになったり,もっと高齢化が進んでも働きたいと言うようになるといった時に、個別適合の一般化みたいな、ちょっと話は矛盾しますけれども、そういったものをやらないと、社会が多分支えられないんじゃないかなと思います。
技術的には相当難しいと思うんですけれども、そこをやらないといけないんじゃないかなというふうに思っています。
○飯島
うちのシステムというのは、まさにそういうことを今までずっとやってきているんですね。最初に言った「研究と臨床のキャッチボール」というのは、まさにそのことをやってきたことでして、例えばうちがオープンした当時というのは、やはり個別対応がメーンだったんですね。それは車いす1台にしてもそうですし、コンピューターコミュニケーション機器の話もそうだったんです。
ところが、それを重ねていくうちに臨床側からのテーマが持ち上がってきて、テーマの方というのはある群をとらえてきますから、そうなりますと、より広い範囲にこれを用いられるというベースができ上がってくるんですね。経験から、ある群に対してこういうものが有効に使えるということで、それをどんどん社会に送り出しながら、今まで個別対応でしていた人が、実は今度はこれが世の中に出たことによって対応できるようになってくる。さらに重度化していく。重度化していきますと、当然さらに超スペシャルオーダーというのがどんどん開発されていくわけですね。そうすると、そこをいかに今度は均一化して、それをまたさらに世の中に送り出していくかという形を徐々に徐々に送り出していく。速度は別にしても、そういう流れを今まで行ってきています。
我々の中でもいつもそれは意識して、これは何々さんにやっているんだけれども、どこまでの要素が一般化していけるのか、障害者、高齢者にどういうふうに有効に、このエキスだけをがっちりと製品として使えるようにしていくのか。その間に当然、いろいろな一般企業も、福祉関連の企業も、いろんなものを開発してくれていますので、それも同時にうちのシステムの中に臨床評価というシステムがありますから、それを臨床評価しながらある程度の評価をして、それをまた実際に現場に使えるようにしていく、そういう考え方ですね。
| ←前頁へ |