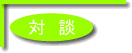
4/6ページ
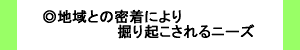
○中村
頸損で体は動かないんだけれども、精神的には非常にアクティブな方は多いわけですし、そういった方がよりよく生きていただくために、損傷を受けた機能を代替するような機器を開発されるという形になってくるのだと思います。
お話では、そういったいろんな要望が出てくるようになったということですが。また、医療の進歩でかなり重い事例でもリハビリテーションを要求されるようになってきたというお話だったんですけれども、30年間で徐々に増えていったのか、急に増えていったのか、そのような時間的な変化というのはありますか。
○飯島
それはその職場の条件なのかなと思うんです。神奈川リハにいた時には、実際には、もちろん我々がいろんな形でボランティアなんかに参加しながら、そして車いすの人たちといろんな旅行もしたりした中で得られた部分というのが当然ないわけではなかったんですけれども、在宅リハという基盤の中で、その人の人となりとか、生活に入り込んだニーズというのはまだ出てきてなかったと思うんですね。
時代の背景ももちろんあったと思うんですが、神奈川リハの中での職域といいますか、プログラムの中ではそこまでまだ入り込んでいなかったと思います。ところが、この横浜リハという基盤があって、それからいろいろな事業が展開されていって、その当時のセンター長も含めてですけれども、やはりこれからは在宅障害者をサポートしていかないといけないという本当の意味でのリハビリテーション、先ほどの余暇をどう過ごすかということも含めてなんですが、本当の意味でのリハビリテーションというのをどうしていくか。障害を負う、あるいは病気で、いろんな形で問題を抱える、そういう中でその人の生活が本当に社会復帰できるというところでのプログラムがここにあったがゆえに、実際にニーズも上がってきましたし、それに対して我々もどうそれに対応するかという苦労をしながら徐々にそれが展開していったんじゃないかなというふうに思いますね。
それと、あともう一つは、先ほど言った福祉機器支援センター等が地域に密着した形で、残念ながら横浜市内が基本になります.けれども、それをどう地域に密着した非常にきめ細かい福祉機器のサービス、あるいはリハビリテーションサービスを実施していくかという体制が整ったがゆえに、そういうニーズもピックアップされてきたと思います.
○中村
ということは、ニーズというかウォンツに近いような状態で潜在的にあったものが、それを個々の生活基盤の中に入っていくことによって掘り起こされてニーズとして明確になってきたと。
○飯島
そういうことですね。ですから、今うちのサービスは、実際に人工呼吸器搭載型の車いす、今まででしたら人工呼吸器をベッドの横に置いてベッドで寝ているような状況ではあったんですが、それが携帯用の人工呼吸器ができてきたこともあって、かなりつくっています。シートの下に人工呼吸器を搭載する。あるいは吸引器を搭載する。いろんなグッズがあるんですけれども、それをシートの中にいろいろ納めて外に出ていくわけですね.
ある筋ジスの方などは、コンピューターも上手に自分でスイッチで操作されますので、実はコンピューターの関係の本を自分で本屋に行って見たいんだというんですね。このままだとベッドに寝たきりなので移動できないから、人工呼吸器搭載の車いすをつくってほしい。それで実際に乗って近くの団地の中に本屋さんがあるので、そこまでご家族に連れていってもらって、自分の欲しい本を買ってくる。そういう生命の維持を考えたものから、先ほど言った余暇をどう過ごすかというところまでの、非常に幅の広い機器の対応、あるいは技術も含めて、実際に対応してきているというのが実情だと思います。

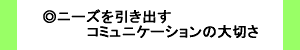
○中村
そういった形で潜在的にあったウォンツが入っていくことによって鮮明になってきたというお話ですけれども、本当のニーズは何なのかと聞き出すことが多分支援機器のフィッティングなり開発の第一歩になるかと思うんですが、そこの入り口が一番難しいんじゃないかと、お話をお伺いしながら思ったわけです。やはり聞き出すのって相当大変になってくるんですか。
○飯島
うちのスタッフは、どちらかというと同じレベルで接するように、指導していますし、そういうふうに努力している面があります。例えば、利用者の前に行った時にどういうふうに接するか。車いすの人だったら、ちょっと膝を落として会話するなら目線が一緒になるんですよね。そうすると、相手の方も話しやすい雰囲気になります.だれでも最初会えばみんな緊張するわけですから、それはどんな状況であっても同じだと思うんです。うちのドクターもそうなんですが、やっぱりできるだけリラックスするような雰囲気づくりを努力していますよね。
最初からポンといきなり「何か困ってますか」って、そういうわけにはいかないですよね。「今日はお天気がいいですね」みたいなところから入って、相手も緊張していますし、こちらも緊張しますから、そういう中では少しリラックスした雰囲気づくりをしながらコミュニケーションをとっていくというのが、一つの大切なことでしょうね。
ある老健施設に,高齢者を何人か集めて話を聞きたいということで,電機メーカーのロボット開発のスタッフを連れて行ったことがありましたが,高齢者が歌なんか歌って楽しんでいる中にそのスタッフが入れないんですね.私がスーッとその中に入って,世間話をしながらそばにいって,「どうですか」なんて話しはじめたんですよ.そうしたら彼らは呆然と立っているわけですね.それで私は,「高齢者とコミュニケーションがとれない人が,コミュニケーションのためのロボットを開発するのは無理ですよ」と言ったんです.
ちゃんとそばに行って,いろいろ話して,そこから彼らがどんなものをほしがっているのか,相手の方に感情移入できたときに,この辺をちょろちょろ動いていて,自然になんとなくさわって,そうしたら「今日天気でいいね」とか何か言ってくれるとか,あるいはさわったものが自然な形で体温がはかれたり,血圧がはかれたりとか,自然な形で高齢者が使えないといけない.面倒くさくて嫌だよという話になっちゃうと,そこの中に入り込めないんですよね.私たちも当然年齢がいけば生活スタイルが変わっていきますよね.今の自分たちが職場で働いているリズムと全然変わってくるわけですから,そういう中にどう機器が入り込めるのか,その範囲まで対応できるのかということは,課題として,より重度化,より難しいニーズにどう対応していくかというのが当然残ってきます.それをどういうふうに具現化して一般化していくかというところですよね.
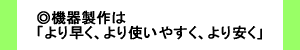
○中村
そういった形で利用者の方のやりたいことを聞き出して、それをフィッティングさせるという話になると思うんですが、こういった福祉支援機器の開発なりフィッティングを考えていく上で難しいのが、機能的な評価も当然出てくるとは思うんですが、その機能がいかに高くても利用者の方が満足していただかなかったら多分評価されないと思うんですよ。だから、機能よりも満足度を上げなきゃいけない。利用者の方が本当に満足して、こんな機能は要らないよとか、いかに欲しているものをできるだけその人に合ったやり方で提供していくのかということが、多分大事なのかなと。

| ←前頁へ |