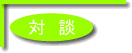
6/6ページ
○中村
そういった意味では、実際の臨床の事例がやっぱりスタートになってくる。それを積み重ねることによってという形になると思うんです。
ただ、今思っているのは、そういった事例の積み重ねというのが、最初は恐らくリハビリテーションエンジニア個人の中に蓄積されていく形になりますよね。それを次に所属されている組織の中でケースを集約していく。その所属を超えた産業としてとらえても、当然これからの日本に必要になってくるところがあると思いますし、臨床の一件一件の事例というのは、非常に貴重な宝になってくると思うんです。そういったものを組織を超えて共有化しよう。それを財産にして、新しい個別最適化というものをより効率的にやっていくというようなエンジニアリングの一分野をつくっていかなきゃいけない。幸いなことにこういったところって公的な機関の方が多いので、うまくできないかなと思っているんですが。
○飯島
その辺は私たちもネットワークを持っていまして、実際にはリハビリテーション工学協会というのがあって、その中でエンジニア同士の連携も当然保っていますし、それからリハビリテーション工学協会の場合には、毎年カンファレンスを開いていて、もうどなたでも参加できる形をとっています。それは中間ユーザーもそうですし、当事者もそうですし、ご家族もそうですし、自由な形で参加をしていただいて、その情報を共有しましょうと。そこの中にまた、スペシャル・インタレスト・グループ(SIG)という個々のテーマごとに研究グループを持っていて、それぞれがいろんな形で毎年1回なり2回なり講習会を開きながら多くの方たちに、しかも場所を変えて順番にやっていきますので、そのエリアの中でまた多くの方たちに参加をしていただいて、常に新しい情報をいろいろな形で工夫をして提供をしていくという中で、限りはあるもののそういう努力をしながら情報提供をしていく。また、それは論文集という形にもなりますし、各SIGがいろいろな形で冊子をつくったりとか、パンフレットをつくったりという形をとりながら、そういう技術あるいは情報を伝達しているというのが実情ですね。
○中村
こういった事例って本当に貴重だと思うんですね。こういった障害者の方のQOLを上げるための取り組みを少し離れたとしても、今までの日本というのは、できるだけ同じものを、できるだけ同じ品質で、たくさんつくって安く売るという産業構造をとっていましたよね。しかし,ある少しのグループの人が、ものすごく欲しいものをちょっと高くてもいいから売ろうという産業に、多分変わらざるを得ないと思うんですよ。そうした時に、障害者、高齢者のものは、その人のニーズに合わせないと意味がないので、やらざるを得ないわけなんです。ですから、そこが先頭を走ってもらって、その人の個別のニーズに最適化したものをいかに少ないコストでつくっていくのかという実績を積み重ねてもらって、それをほかの産業に横に転換してもらうというのが、これから先出てくるんじゃないかと期待しているんです。
○ 飯島
その辺は多分各企業も、今までは個々の製品という考え方だったかもしれないんですけれども、車いすなどもモジュラーという考え方がどんどん日本の企業にも浸透してくると思うんですね。我々もいろいろ個々の方にサービスをしていて、よくスタッフに言うのは、これどこまでか共通パーツとしてキット化できないか。あるパーツとあるパーツを組み合わせて、インターフェースの部分だけ最終的に個別に合わせる。それによってある製品はもうパーツ化してありますから、ある程度コストも下げていけると。このユニット、このユニットを組み合わせていった時にその方のニーズに合わせられる、そういう流れになってくると思うんですね。
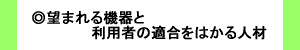
○中村
共通な部分、ベースがあって、「ベース+A+B+スペシャルなもの」という形ですよね。
そういったことを考えると、近い将来、多分そういう世界になってくると思うんですけれども、開発をする、実際にパーツをつくる人間よりも、利用者の方のところに出向いて、それのフィッティングをするとか相談に乗るといったところでエンジニアリングの知識を持っている人間が必要になってくるのかなと。ですから、開発者というよりは、コーディネーターみたいな方のポジションが増えてくるのではないかなというふうにも予想しているんですけれども。
○飯島
そうですね、その辺がちょっと微妙なんですけどね。リハビリテーションエンジニアというのがどの辺のところまで職域を押さえていくのかということとも関係するんですけど、各分野でそういう職域をつくっていかないといけないんだろうなというふうに思うんですね。
その具体例に、車いす姿勢保持協会では「車いすシーティング技能者」という職域をつくっていこうという動きがあって、私たちもそれに協力をして、講習会の講師などもしているんです。それはどういう人たちかというと、車いすや、姿勢保持装置を適合していく時に、ちゃんと機器とそれを使う利用者との適合をきっちり見ていくよと。ただつくったものを「はい」って渡すのではなくて、本当に調整を含めて、フィッティングも含めて、非常に微妙なところのフィッティングも含めて、ちゃんとそれが乗れるの乗れないのだけではなくて、どう質の高いレベルでそれを使えるのか、姿勢保持でいったら股関節の角度、膝関節の角度、体幹の変形に対する対応、緊張が出るの出ないの、それが抑えられるの、リラックスできるのという、そういう人間の生理的なメカニズムに関連するところまでフィッティングを見ていきましょうと。そういうところまでのフィッティング技能者を今つくろうとしていますね。
場合によってはコンピューターコミュニケーションの分野であっても、そういうコンピュータ等はIT機器もどんどん開発が進んできている。非常に機能はどんどん変わっていく。月ごとに変わっていくような世界ですけれども、それをどういうふうに障害の方たち、あるいは高齢者に使えるようにしていくか、そこの部分を見ていくようなスタッフも必要になってくるでしょう.それは企業が持っていくのがいいのか、あるいは公的な機関がそれをサポートしていくのがいいのかというのは、多分これからの社会の動きによって変わってくるのだろうと思います.
当初は多分、こういう公的な機関がある程度サポートしていくというのが一番態勢としてはとりやすいんでしょうけれども、やはりいずれは各企業がきちんとそういう専属のスタッフを抱えながらサポートしていくべきであろうと思います。
○中村
そういった意味では、メーカーに当然そういったフィッティングができる人が入ってくるのも一つあると思いますけれども、もっとお客さんに近いところのディーラーというか販売会社みたいなところにそういったいろんな知識があって、A社のこのパーツとB社のこのパーツを合わせるとあなたにぴったりのものができますよと、そういったような人材が多分必要になってくるかと思います。
福祉車両というのがありますが、ある企業の場合、障害者用の自動車を全部集めて見せているショールームがあるんですけど、説明できる人間がいない。お客さんが勝手に来て、勝手に乗って、「ああ、これが一番いいや」と、それに乗って帰るという非常にお寒い状況なんですね。ですから、先ほどご紹介いただいた車いすシーティング技能者、そういったような形がコンピューターとか福祉車両、いろんなものが全部説明できる、その職域だけだったらその商品が完璧に説明できる。「あなたにはこの製品よりもこの方がいいですね」と、そういったようなご紹介ができるような人が当然必要になってくると思うんですね。それは恐らく企業も、潜在的にそういったマーケットがきっとあるというふうに気がついていると思うんです。将来は公的機関は恐らくはかなり重篤な、難しい事例を扱われるところに軸足を移されて、一般的な事例は企業が見てくるという形になってくる。そうすればそこで必要とされる人材の数も増えていくのではないかなというふうに思うんですけれども。
○飯島
実際は、これは一つの考え方だと思うんです。当然いろんな時代の流れとか社会の構造の変化によって変わってくるのでしょうけれども、とりあえずリハエンジニア等が最初は通訳的な位置づけにあって―現在もそういう役割をしているのも事実なんですけれども―、そういう中で徐々に企業サイドの態勢が整いつつありながら、徐々に徐々にそういう企業サイドに移行していくんだろうなというのは、私もそれは感じますね。
そのリハエンジニアがどういう役割をこれからしていくのかというところも、我々の中でもそれぞれ悩んでいる面でもあるんだと思うんですけれども、やはりスペシャルな対応になっていくのかなと。それから新しい機器の開発にかかわっていくのかなと。それから、あとは一般企業が開発した機器が本当に現場にどう役立つのかというところでの、非常に冷静な目でそれを評価していくという立場になっていくのかなという気はしていますね。
○中村
非常にうまくまとめていただいて、どうもありがとうございました。大変貴重なお話を伺いました。いろいろ課題をいただいたなと今思っておりますので、私どもの大学でできる範囲の形になるかと思いますが、いろいろと取り組ませていただきたいと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
| ←前頁へ |
