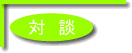
3/6ページ
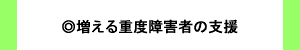
○中村
その当時の主な利用者の方というのは、どういった方が多かったのでしょう。
○飯島
層は、今で言うと脊損の方でしょうか。
○中村
交通事故による障害ですね。
○ 飯島
そうですね。あるいは病気等で脊髄損傷になったとか、あと筋ジスの方も当然いらっしゃいましたし、リウマチの方も一部いらっしゃいました。ただ、今の状況からすると、私たちが在宅にかかわっていく層からしますと、まだ軽度の障害の方たちだったと思います。脳性麻痺の方たちもまだ軽度ですね。車いすも自分で操れるとか。極端な話、頸椎損傷の方たちも、例えば今ですとC−3番とか非常に高位の損傷の方たちのサービスも行いますね。ところがその当時は,医学的な治療のレベルで生命の危険があったと思います.
○中村
高次の脊椎損傷の場合は、恐らく昔ですと病院にとどまって一生寝たきりでもしかたがないというような認識だったんでしょうか。
○飯島
そうだったかもしれません.健康管理ということもあったんでしょうけけれども医学的にまだ,厳しい状況であったと思います.生命の貴重さという点で、医学が進んだことによる成果なんだと思うんですけれども、より重度の障害が残る方たちが増えています。病気も難病と言われる方たちも増えていますよね。ALSの方々もそうですし。そういう意味では障害像が当時に比べますと、今は対象が重度の方たち、最重度の方たちに対するサービスが増えてきたと言えます。
少し話は変わりますが,1999年(平成11年)5月から、横浜は18区あるんですけれども、在宅リハビリテーションサービスが実施されてきた中で、それをより地域に密着した形で在宅リハサービスを行っていこうという目的で,福祉機器支援センターというものができたんです。当初の計画では3区に1カ所つくろうということで、6カ所福祉機器支援センターを横浜市内に点在させて、地域にいる在宅障害者がそこに行くといろんな情報も得られますし、車いすをつくったり、姿勢保持装置をつくったりとか、あるいは在宅の福祉機器も段差解消機とか住宅のサービスも受けられるということをそこで供給していくことになりました.私は泥亀福祉機器支援センターという金沢区の南の端にあるんですけれども、そちらのセンター長という形で、まず異動になりまして、そこでいろいろな在宅障害者の方たちに対するサービスを行ってきたんです。
そこの中では、重度障害のある方たちのサービスが非常に課題になっていました。ここでは地域に入り込んでいますし,規模もここより小さく,350平米ぐらいのところなんですけれども、そこにいろんな機器があって、住宅の評価システムもあるんです。
そこの中で重度の障害者の方たちが在宅で生活していくというのは、まず環境の整備からしなければいけないんですね。お風呂にしろ、トイレにしろ、動線にしろ、玄関までのアプローチにしろ、そこから始めていかなければいけないんですね。また,環境制御装置でコンピューターを使ってテレビをコントロールするとか、環境設定が必要になります.あるいは移動するための車いすも通常のもので座れない、さらに姿勢の保持も加えたり.、耐久性も考えてリクライニングできたり、ティルティングができたりということで、かなり重装備のものを在宅の中に入れ込みながら、その重装備のものを今度はその環境の中で移動できるように、環境整備も整わないと難しいというところで、相当そこでは教えていただきましたね。そこまでやっていかないと、これからは難しいのかなと思います。
一方では、横浜は今グループホームがいろんなところに整えられている市だとは思うんですけれども、各部屋があって、その部屋をうまく使いながらケアできるスタッフがそこに常駐するという形をとりながら、個々の方のプライバシーを守りつつ、そういう重度の障害の方たちのニーズに応えられるようにしています.我々もグループホームに対してリフターの導入であるとか、そこで個々の方が使われる車いすの供給であるとか、トータルにサービスをしているという状況です。
○中村
3区に一つつくられたという福祉機器支援センターの枠組みは、まだ今も残っているのですか。
○ 飯島
今は3カ所できています。
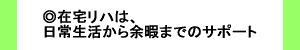
○中村
なるほど。今のお話にもありましたけれども、そこと総合リハビリテーションセンターとの役割分担はどういう形になっていますか。地域のセンターで賄えない事例というのは、やっぱり重篤な…。
○飯島
難しいものですね。
○中村
難しい支援の事例ということですね。
○飯島
障害の重さ云々というのももちろん関係してきますけれども、そうではなくて内容の難しさというのがありますね。それはその方のニーズにもよるんですけれども、実際に中でいろんな環境整備をしたりとか、あるいは最近ですと余暇をどう過ごすか、スポーツ、レクリエーションの分野までというようなことですね。
先ほど伝えなければいけなかったんですけれども、在宅リハサービスを行っていくというのは、その人の生活全般をサポートすることになるんですよね。だから、場合によっては最近は就寝中のことの健康管理なんかももしかしたら関係してくるかもしれませんし、朝起きてから洗面して、トイレへ行って着替えてというようなところから、そのスポットスポットでいろんな問題が生じてきた時にサポートしなければいけないと思うんですよね。あとは余暇をどう過ごすかということで、特に子供なんかはほかの子供たちが自転車に乗っているんだから、自分は障害があるんだけど自分も乗りたいからということで特殊な自転車を工夫したり、サドルにちょっとプラスチックでお尻をサポートできるようなものを取り付けたり,あと自転車が傾けられるように、補助輪もスプリングで動いて、ある程度その子の能力に応じて、できるだけ普通の感覚に近いものを供給したり。
あるいはテレビゲームをやりたい。でも手に障害があるものだからできない。何とかスイッチを考えてほしいということで、ソフトはそのまま使いますけれども、インターフェースの部分をやったりとか。
カメラなんかも多いですね。ある人がおっしゃっていたのは、「自分は家族に写真を撮ってもらうことはあるけど、自分が子供の成長を撮りたいのに撮れない」、もう切実なニーズですよね。頸損の方だったんですけれども、実際にカメラ、最近いろんなオートのいいものが出ていますから、それを呼気スイッチで電動の運台を使ってアングルもある程度コントロールできるようにして、決まったらフッとやるとシャッターがカチャッとおりるとか、ズームはメニューがあって、ズームのところを選べばビューと動いて、いいところへいけばフッとやると止まるとか、そういうものも多いですね。
○中村
QOLみたいなことを考える時に、体に害が及ばないとか、栄養が十分とれるみたいなパッシブのような意味だと、恐らく今の制度である程度確保されていると思うんです。それを超えたところで、先ほどおっしゃられた余暇をどう過ごすとか、もうちょっとアクティブな意味でのQOLを上げるようなことを考えないといけないなと思うんです.
○飯島
より質の高い生活をどういうふうにしていくのか、それは人それぞれ考え方がありますからニーズも変わってくるんですけれども、今までの具体的な例では、例えばお父さんがトライアスロンをやっている。自分の使っているマウンテンバイクに障害児の子供さんを乗せて一緒にトライアスロンに参加したいから、姿勢保持の機能のついたものをわざわざこの自転車につけたいんだって言うんですよね。
我々はもちろん、その道具を使う時というのは、お父さんの責任において子供をそれに乗せて使うという想定で行いますし、あるいは山登りに子供を連れていきたい。上に上がった時に、簡単な移動具として使えて、登っている時には背負子として使いたいんだというわけですよね。そうすると、もうそれはご家族の責任において、もしかしたら途中で転んでけがをするかもしれません。でもそれは自分たちが楽しみたい、あるいは自分の子供にそういう山に登った時のすばらしい景色を見せてあげたいという気持ちがそこにあるから、私たちはそれに対して応えていくということですよね。
| ←前頁へ |