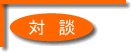
僕はそんなつもりはないので, 短大に手紙を出して, うちの幼稚園の先生と同じような若い子を面接して採用した.
何も知らない人を集めて, 「何も勉強せんでも, 恋だけせい」 と言った. 恋をすれば, 相手の身になって考えるようになるからね. もう 1
つ, 「志があれば道がある. あまり訳け知りに志はない」 と (笑).
でも彼女たちは 「何したらいいんですか」 と言うので, 「痛いと言ったら行けばいい, 暑いと言ったらそばに行ったらいい」 と答えた. 最初は,
「熱が出たけれど, どうしますか」 と, 僕に聞いてくるわけです. 「そんなもの, 氷で冷やせ」 と.
そのころは, すばらしかったですよ, みんながそばに行って, 「どう?」 って, きくんです. でも外へ研修に行くという制度があって行ってくると,
座薬を入れると熱が下がることを覚えた. そうすると, 座薬を入れておいて別の部屋で本を読んだりする. あんなことなら, 座薬を入れずに冷やしておいて,
そばにいた方がいいのにと思っていた.
![]() 原風景を再現するプロセス
原風景を再現するプロセス![]()
○佐々木
あの, 機関誌のインタビューなので, ちょっとだけ情報の話などを, うかがいたいのですが.
今は情報化社会だと言って, たくさんいろいろな情報を集めるために, みんなインターネットだとか何だとか使っていますよね. でも, 自分が本当に欲しい価値ある情報というのは,
そんなに多くないような感じがするんです. ただこれが本当に価値あるものかどうかというのを確かめるために, ほかのものをいろいろいっぱい見て,
やはりこれが自分にとって一番価値があるんだなと納得したいために, たくさん情報を集めたりするんじゃないか. まあそうではなくて, ただ集めることだけが好きな人もいるかもしれないですけれど.
ところが一平さんの動きを見ていると, ぱっと見つけた瞬間, これは自分にとって価値があるとかないとか, その場で判断しているように見えるんです.
そこにとても興味があるんですが, 実はそうでもないのですか. 陰でいろいろ調べたり, あれこれやってみて, 「これはあかんな, やはりこれだ」
というようなプロセスを踏んでいるのですか.
○吉田
あまり踏んでいないね.
○佐々木
でしょ.
○吉田
僕にはたぶん, 自分の育った原風景がある. よく思うのは, ヨーロッパなどでいろいろな町があるけれども, みんなずっとそこに受け継がれたものの中で作っていくからしっかりしている.
ところがみんなの話をいっぱい聞いて, 世界中のものの中から何かを作ると, 本当につまらないものになってしまう.
だから僕は, 自分が 「こういうのがいい」 と思ったら, そういうものがいいというだけなんだね. だから, このグループホームも木を残してぐちゃぐちゃなプランだし,
内装に使っている木もタイルもばらばら. 藤が丘でつくっているのも, 建物の柱にはカンナをかけるな, しかも柱の四隅に皮を残せと言ったわけ.
カンナはかけない, 板もざらざらがいい, そういうのがいいと言った.
![]()
![]()
![]()
なぜかと言うと, ふつうの建物というのは結局, プロが造っちゃったもので, 壊れたときにも, プロに直してもらわないと場違いになってしまう.
そうではなくて, わしらが直しても近所の人が直してもいい. そういうものにしてほしいと言った.
職人さんは 「そんなの家じゃない.」 と言うんだね. この建物もそう言われた. でも, 結果はこんないいのに仕上がったわけ. 結局, それは僕が子どものときの原風景なのです.
みんなが参加して, みんなでカンカン直して, みんなで造っていく. そこにお互いが参加して, みんなで造っていく風景があった. それが分業化して専門化したのは本当に昭和
39 年ころからで, 豊かになるために手分けしてきたものをもう一度統合して小さい単位にしていくという方向に今また変わりはじめたと, 僕は思っている.
たぶん, うまくできなくて遠回りすると, 参加者は多くなる. 今の普通のやり方では, 早くきれいになっちゃうから, だれも参加できないのです.
そうではなくて, みんながわあわあやっている, 私の子どものころの風景のようにしたいわけです. このグループホームの庭でも外構でも, 絶対きちっと造らない.
おっさんたちがみんなキュッキュキュッキュ造っている. 西洋風なのか和風なのかよくわからないけれど, みんなで造っています, カンカン掘って,
わあわあ, ぐちゃぐちゃしている, ごちゃごちゃのその風景は, たぶん, 僕の江戸時代の風景なんだな. そういうのがあって, 何かふっとしたときに勘が働くのだと思う.
○佐々木
そこには, ものすごく難しい問題があると思う. というのは, 今は素人のみんなが参加して, 寄ってたかって何かをやるようなことをワークショップと言って,
結構やっているんです. 公園を造って, 近所の子どもたちを呼んできて, 子どもの絵を描いたタイルを貼ったりしている. それが必ずしも, 出来上がったときに美しくない.
魅力的でないどころか, ただ汚いと思われるものって, ものすごくたくさんあるのですよ.
○吉田
あるある.
○佐々木
だから, そういう汚さと, 一平さんが言っている, みんなが入ってくちゃくちゃやっているものの汚さ, いやきれいじゃないけれど魅力的という,
この 2 つをどうやって峻別するかが難しい.
それは根っこのところの違いかもしれない. 例えばこの建物だってくちゃくちゃ曲がっているのは, もとは木が生えていたとか, 地形がこうなっていたとか,
何かそういうしっかりしたシステムがあって, その上にどんどん, より微細なくちゃくちゃを載せているから汚らしくならない.
ところが子どもたちの描いたタイル貼りの公園がものすごく汚く見えるのは, ベースのところがものすごく人工的で均一なのに, 「はい, ここは描いていいよ」
という唐突な場所にただのくちゃくちゃを入れるから, すごく汚ならしいのかもしれない.
○吉田
そうだね.
○佐々木
その違いを考えずに何か勘違いをしている例が結構増えているから, 気をつけないといけないなと思います.
