 |
|
|
のぞみヶ丘では,高根の森より少ない15種類の発生が確認された.そのうち落葉分解菌や木材腐朽菌のキノコが5種ずつ確認でき,のぞみヶ丘で発生したキノコ種の3分の2が「腐生型」キノコであった(表−3).菌根菌のキノコの発生は,降雨の多い時期に限られ,種類も2種しか確認できなかった.落葉分解菌のキノコは降雨の多い時期に限らず,7,8月の降雨の少ない時期にも発生が確認された.木材腐朽菌のキノコはカワラタケ(写真−3)などの倒木上からの発生が多く認められ,生立木からの発生も確認された.このように,のぞみヶ丘では,落葉や倒木などの有機物が多く,多湿な環境のためそのような環境を好む腐生菌にとっては生育しやすく,またキノコを発生しやすい環境であると考えられた. |
高根の森のように太陽光が林床によく当たる環境では,温度が上昇し,土壌中の水分を蒸発させ,有機物の分解速度も促進されるため,倒木や落葉などの有機物が減少する.こうした環境は,落葉分解菌や木材腐朽菌にとっては生育しにくく,菌根菌にとっては,生育しやすい環境であるといえる.また樹木は,効率的な水分吸収をするために積極的に菌根を形成するのではないかと考えられた.しかし,のぞみヶ丘のように,太陽光が林床にまで到達しにくい環境では,有機物は分解されにくく,また人為的な管理がないことも重なって,有機物が厚く堆積し,土壌は多くの水分を含んでいる.こうした環境では,落葉分解菌や木材腐朽菌にとって生育しやすい環境であるが,菌根菌にとっては,生育しにくい環境であると考えられた. |
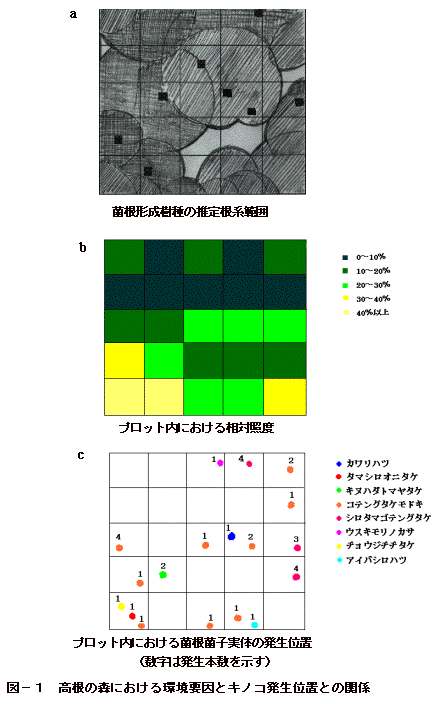 |
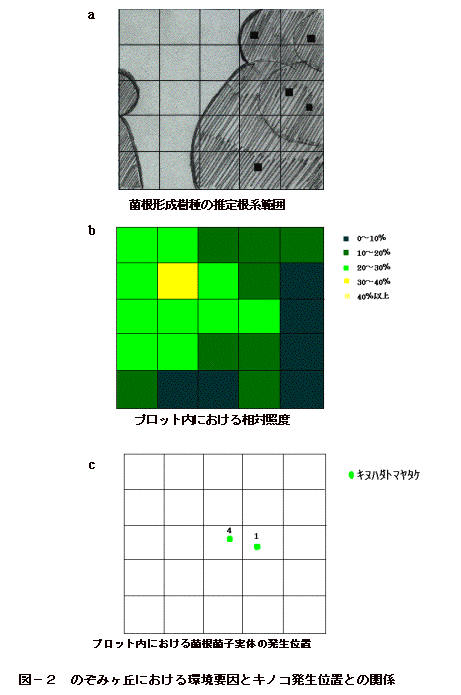 |