 | |

| JAM SESSION |
| STAGE 2 |
| 情報社会とモノ | |||||

<佐々木> 伊藤さんは元はトヨタで車のデザインをされていたわけですが, その後はじつに多様なものに関わられていますよね. (今回のインタビューでも籐の自転車, 草木染め, 日乾しレンガ, 絞り, カヌー, 瓦などのお話がありました) でもやはり, 「もの」 のデザイン, リアルに存在するものを扱っておられる. そうしたデザイナーとして, 情報という一見目に見えないものが価値を持つ社会のデザインをどう考えられますか. 私自身はしばらく前から, 携帯電話がただで手に入るということが気になっています. もちろん契約料などに含まれていることになるのでしょうが, 表向きはゼロ円. 携帯電話機そのものは, ものすごくたくさんデザインがありますし, いかに小さく軽く, 使いやすくするかを考えて, デザイナーや技術者は相当頑張っているはずです. そうした成果品である電話機がタダ, というのはどうも違和感がある. その一方でサッカーの中田の携帯電話はフェラーリのいくらのものだ, なんてことが話題になる. <伊藤> 僕の事務所のメンバーも皆言ってますが, 要するに工業化社会が情報化社会に替わる境目の最たる商品ですね. でも情報化社会って本当に何なのかが, みんなよく分かっていないような気が実はするんです. 今までもので動いてきたのが, これからは情報なんですといった時に, やはり何に価値があるのか, 人が働いたり活動したりする対象もものから情報とか, 目に見えないものに変わっていく, そのことをもう少しみんな明確に分かってないといけない. 今の経済は確実にそうですよね. それからもう一つ, 情報ってお知らせ (報) だけって思われがちだけれど, なさけ (情) の部分が相手に伝わるかどうかも重要ですよね. 情報という目には見えないものに価値のある社会になった時, 情報の本当の価値は 「報せ」 と同時に 「情け」 という人間性にもとづく価値に目を向けられるべきです. 海外旅行に行くとき, どこにどんなものがあってこんな興味深いものがある. |
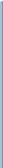 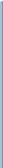 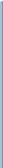 |
<伊藤> その体験コストは, という 「報せ」 よりも 「報せ」 の受け手, 本人は 「誰」 といきたいのか, 「何」 をしにいきたいのか, という 「情け」 にプライオリティーをもつべきではないでしょうか. <佐々木> なるほど. 情けないお知らせをたくさんやり取りしてもむなしいですね. 情報の質の話はひとまずおいて, 伊藤さんは確実にこの世の中は情報社会になっていくと思われていますか? <伊藤> 情報化は進んでいくと思いますね. ものすごく便利だもの. だけどモノはなくならない. その中でさっきの携帯電話のような話が出てくる. 僕はそれはビジネスだからいいと思っている. ただ 「捨てるなよ」 って言いたい. たとえ 10 円でも, タダでも手にしたものなら捨てないで, と言いたい. どうせ機能というのは目に見えないもので, 見えているのは構造体だけ. だからこの構造でずっともっていて欲しい. でも作る方も使う方もそうは思わずにモノが出来上がっている. そこがすごく悲しい. <佐々木> コンピュータでも携帯電話でも, 今かなりのスピードで使い捨てられていると思うんです. それは, 新しく出た目にみえない優れた機能を獲得しようとすると, 入れ物も変えないとだめだという形になっているから. それで古いコンピュータは捨てることになる. こうしたことはどこかで歯止めがかかるべきなのか, あるいが仕方がないからそういう状況に対応した構造体のデザインを考えて行くべきなのか. 伊藤さんは資源のリサイクルというよりも長寿命化をとおっしゃっていますが, どうでしょう? <伊藤> 新しくいいものを出すと昨日までのものは捨てられますよね. 今手にしているのはここで使っている一番古い携帯電話だけれど, 例えばうちのお袋が使うとすればこれで十分だと思うんですよ. 例えばソニーのテープレコーダーが凄い競争の中でミリ単位で小さくなっていった. 本当は 10 ミリ単位で縮まった時まで待った方がよかったかも知れない. 1ミリずつ小さくしたものを全部捨ててきたとすれば. つまり作ることの意味と, 世に出すことの意味とは違うわけですよ. だから世に出すには何らかのコントロールとか社会規範みたいなものを, 誰かがきちんと言っていかないといけないだろうなとは思うんですね. ただまあ, ある人がいらなくなった物を別の人が使いまわすという使い方は自然発生的に出てくるといいなと思います.
| |||
