 | |

| |
| 中国における軍隊の徴兵は志願兵制度で行われている. 18 才以上の国民は自己申請に基づいて入隊して奉仕する. 軍隊の奉仕期間が種類によって2−4年に定められている. 奉仕期間を終えると出身地に帰ることが原則であるから, 軍隊で優秀な人材と認められ, 幹部に昇級し軍隊に残るわずか少数の人以外, 多くの農村出身の若者は農村に戻らなければならない. しかし, 亦工亦農制度や軍隊への入隊によって, 農村の若者たちは工場と軍隊の場を通じて都市の生活を経験し, 都市の人と社会的ネットワークの接点を結ぶ機会を提供されたのである. その接点は彼等の企業の設立とビジネスの展開にとって大きな役割を果たしたことが調査から分かった. たとえば, 温州のC.Z氏は亦工亦農労働者として市の食品工場の買い上げ部門で約 10 年働いたのち, 1979 年農村に戻って養鶏業をはじめた. 当初は卵と鳥肉を以前働いた市の食品工場に出荷して販売を行った. 養鶏で資本の蓄積を達成した. 彼は今は養鶏を止めたものの, その代わりに食品工場を経営し, 原料の仕入れと製品販売先には亦工亦農時代の経験と友人が大きな頼りになっているようである. また江西のS.H氏も似たことを語った. 彼は3年間の兵役期間を終えて 1981 年農村に戻った. 最初どうしても農民のままで一生を送ることに気が済まずに, たった 100 元の資金から個体戸1) として担いで羽毛回収の仕事をはじめた. 3年の間で 6,000 元を貯めてから他人と合資で羽毛加工の工場を設立した. 工場を設立するにあたって, 軍隊の戦友たちから大きな協力を得た. 彼の戦友には現在市と県政府の各部門の責任者となっている人が多くいて, 情報の流れや企業に関わる諸手続きなどいろいろな側面で協力してくれたのである. | 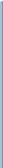 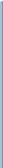 |
彼は 「毎年正月の4日が戦友たちの新年の集まり日となっている. 県内はもちろん, 遠方からも多くの人が来るよ」 と語った. 最後に下放二世について見よう. 下放二世とは 70 年代までに都市から農村に移住・下放された人の子女を指している. ここでは移住と下放との異なりについて説明を加える. 移住とは中国語で 「遣返回郷」 と言われ, 政治運動の対象となった人に対する処罰の一種類である. ところが, 下放とは移住と異なって, 政府の呼びかけを応して都市の戸籍を放棄し農村に行くことを指している. 下放する人は一般的には行き先を選択でき, 本人だけで行く場合もあれば, 家族連れで行く場合もある. 下放運動には 1962 年の 「都市住民上山下郷」, 1966-1976 年の 「知識青年上山下郷」, 1970-1975 年の 「幹部上山下郷」 などが含まれ, 何千万の人に及んだが, 1973 年から 1980 年にかけて何らかの形で都市に戻ることが許可されたため, 現在まで農村に残っている人は多くはない. 調査対象となった 6 人の下放二世の場合, その父親のうち4人が上海, 西安, 南昌などの大都市から農村に移住し, 一人は下放した人である. 移住・下放した人は長年にわたって都市での生活経験をもっていたため, 都市に親戚や友人を持っている人が多い. これを通じて彼等の二世は都市との接点を結ぶことができる. 80 年代までは制度的には農村戸籍をもっている人はすべて人民公社の組織にきちんと組み込まれ, 都市と農村との隔離制度によって彼等の都市での雇用と生活が許されなかった. しかし, 社会的ネットワークを通じて人と人とのつながりは制度の限界をつらぬいて異質な人と接点を結ぶことが可能となった. その接点を通じて閉鎖された農村以外の社会と情報にアクセスすることができ, 経営者としての資質を育むことが可能となった. |
| BACK | NEXT |