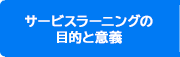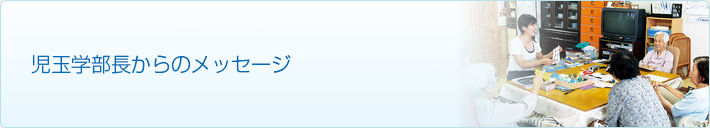- HOME

- サービスラーニングの目的と意義

- 児玉学部長からのメッセージ

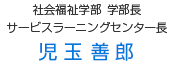
サービスラーニングという教育方法は、アメリカで開発された学習形態です。本学社会福祉学部では、平成20年度に文部科学省教育GPにおいて「協働型サービスラーニングと学びの拠点形成」が採択されたことを契機に、社会福祉系大学としては全国で初めて、サービスラーニングに本格的に取り組み初めました。
このサービスラーニングは、市民社会を担う一員として地域で役割を担う力、いわば“市民力”を育むことをねらいとしています。日本福祉大学の歴史をふりかえると、地域社会のなかで、市民として、職業人として、どういう役割を担うのかという問いかけに対して、学生は自分たちなりの答えを見いだそうと、自主的、自発的な活動を行ってきた系譜があります。例えば、古くは1959年9月に東海地方を襲った伊勢湾台風の救援活動に多くの学生たちが自発的に参加し、被災者の生活再建の支援を通して、被災者の役に立つ活動をすることが自分たちの学びにつながることを知るきっかけとなりました。以来、地域を対象とした日常的なボランティア活動、サークル活動、阪神・淡路大震災や東日本大震災における被災地支援の活動など、その伝統は脈々と受け継がれています。
こうした本学の学生たちが地域社会と関わってきた歴史と伝統を、大学の位置する愛知県の知多半島を舞台にしたサービスラーニングという教育プログラムにより、さらに展開していきたいと考えています。知多半島は、全国的にも注目されるほどにNPO活動が活発に取り組まれている地域です。50を超える福祉系NPOがあり、そこでは市民による主体的な活動が展開されています。
本学のサービスラーニングは、これらの知多半島で活躍するNPO法人の皆さんの協力により実施することが可能となっています。とくに、知多半島のNPO法人をネットワークしている「地域福祉サポートちた」の全面的な協力のもと、大学とNPO法人の皆さんとの協働により、サービスラーニングのプログラムを創り上げてきました。
学生たちが、地域の歴史、NPO活動の経緯、そして地域の生活者の皆さんにふれ、課題の発見と地域への貢献活動に取り組むことを通して、多くのことを学ばせていただくとともに、地域の皆さんと学生・大学との新しい協働関係につなげていければと思っています。
今後とも、地域の皆さん、NPOの皆さんのご協力とご支援のもと、サービスラーニングが学生にとっても、地域にとっても、意義のあるプログラムとなるように努めていきたいと考えています。