 |
|
 |
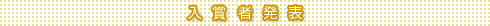 |
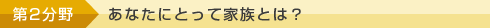 |

 |
 |
 |
「遠距離検温」 |
| 立命館宇治高等学校 三年 徳田 奈緒子 |

私は高校生になると共に、生徒寮に入った。とにかく、うるさい親から離れることが出来てせいせいしていた。自分からはろくに連絡も取らず、家からの電話にも、いつも適当に受け答えをしていたのだった。
三年生になって少しした頃、私は勉強について悩んでいた。そんな時に携帯の着信音が鳴った。週一間隔でかかってくる、母からの電話だ。通話ボタンを押し耳を近づけると、聞き慣れた母の陽気な声が、私の耳に届いてきた。「なおちゃん元気か?」「うん、まあまあ。」胸がきゅっとして心が落ちついた。悩みについては触れず、ただ、いつものように他愛のない会話をして、電話を切った。
翌日、母からメールが届いた。「昨日のなおちゃんは元気のない声してたで。何か心配事でもあるん?」と。それを見た瞬間、「あ、ちゃんとつながっているんだ」と感じて、少し泣きそうになった。
今、人々のメールへの依存が非難されている。やはり実際にその人に触れ、瞳を見て、息づかいを感じながら会話をする方が良いだろう。しかし私たち親子は今、めったにそうすることが出来ない。私は、離れて暮らすと家族といえどもお互いを思う気持ちは薄れてしまうのかな、と考えていた。だから親との電話やメールも意味がなく感じていた。しかし、母からのあの電話やメールからは、確かに母の体温が伝わってきていた。たまに、酔っぱらいながら説教してくる父からもだ。そして、私も無意識に自分の体温を発信していたのである。離れていても、私たちはちゃんと気持ちを交わしていたのに、私は三年目までそれに気付けなかった。直接感じる事はできないが、互いの温もりは何十キロもの距離をいつも飛び交っていた。メールや電話で、私たち家族は検温しあっているのだ。
高校卒業までは、携帯電話ひとつが私たち親子をつなぐ。明日は、たまには私から携帯を手にとって、今の私の体温、伝えよう。 |

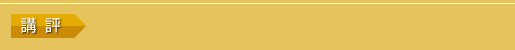 |
10代の少女が生徒寮に入って一人暮らしを始め、最初は「うるさい親から離れることが出来てせいせいしていた」という気持ちが、次第に家族のことを意識するようになっていく移り変わりがよく表現されています。言葉では言わなくても、声のトーンで心配事があったのではないかと察する母親の温かい思いに気付き、その母親の愛情に応えようという作者の気持ちが伝わってきます。
ただ、「体温」という言葉が多すぎること、そして、「遠距離検温」というタイトルは少しこじつけ過ぎの印象を与える点がマイナスになりました。 |
|
|
 |
|
 |