 |
「青年海外協力隊としての国際貢献の夢」 |
| 兵庫県立播磨農業高等学校 三年 宮永 幸則 |
世界中には、数えきれない程多くの職業があり、それぞれの職業が社会に与える影響はとても大きなものがあります。しかし、自分に合った職業はその中のほんの一握りであり、自分の将来像は自分自身の手で模索していかなければなりません。
私は今、兵庫県立播磨農業高校で無農薬・有機栽培についての勉強をしています。農業高校では、授業時間の半分以上が畑や田んぼなどで行う実習で占められています。夏は炎天下の中での除草作業、冬は凍える寒さの中でキャベツや大根などを収穫します。入学当時はこの実習が何度もいやになり、くじけそうになった事も一度や二度ではありません。しかし、こうして三年生になって思うことは、「やっていてよかった」ということです。こうした辛い作業を耐え抜くことが出来たのも、将来への一途な夢があったからです。
その夢のきっかけになったのが、中学二年生の頃にテレビで見たパプアニューギニアでの青年海外協力隊の映像でした。日本の青年海外協力隊の隊員が、「世界の飢餓を自分の手で救いたい」という強い夢を持ち、青年海外協力隊の厳しい試験や言語訓練をクリアーして、派遣先のパプアニューギニアでさつまいもの普及活動を成功させるまでのドキュメンタリー番組で、慣れない言葉、慣れない文化の中で、自分の夢を貫き通すその姿勢に強くひかれ、私はそれ以来、「自分も将来は世界の苦しんでいる人たちを、農業技術援助という形で救っていきたい」と強く感じるようになりました。
私は高校卒業後、さらなる技術取得のために大学の農学部に進学し、将来はパプアニューギニアで稲作の普及活動を行いたいと思います。世界の主食の半分以上を占めるコメの栽培技術の向上は、世界の食糧問題を解決するきっかけになると確信しています。国際社会の現在、青年海外協力隊という職業を通じて、国際貢献に参加していきたいと思います。 |
 |
 |
 |
 |
 |
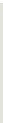 |
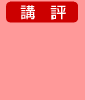 |
農業高校で無農薬・有機栽培についての勉強をしている作者の「農業を自分の職業としてやっていきたい。そして、世界の食糧問題を解決して国際貢献に参加したい」という一途さが伝わってきます。エッセイというより、決意表明に近い作品ですが、自分の夢を素直に表現している点を評価しました。起承転結を頭に入れてのことかもしれませんが、最初の段落は無くてもいいかもしれません。 |
 |
 |
|



