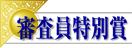 |
「最期の時」 |
| 立教池袋高等学校 三年 高嶋 浩嗣 |
しーんと静まり返った廊下に、僕の足音が響く。病室のドアの前で、深呼吸をした後、音を立てないよう気をつけて扉を開ける。
午後の日差しに包まれながら、ベッドの上の祖父が僕の方に視線を向ける。傍らに付き添っている祖母の笑顔にほっとする。
「具合はどう。」
と、僕は学校の鞄を入口の横に置き、声を掛けると、祖父は右手をちょっと挙げ、微笑んで答えてくれた。 祖父が癌を発病して一年三ヶ月。入退院を繰り返し、手術も四回を越えた。しかしいよいよ打つ手が無くなった時、祖父はホスピスに入る事を選んだ。今までの闘病で家族の誰もが疲れ切っていた。病院への送り迎え、自宅での看病、気持ちはあっても、もう限界であった。そんな家族の様子に、祖父自身が下した決断であった。
だが、亡くなる数日前、車椅子で廊下を散歩している時、大きな窓から外を見て、ポツリと独り言のように、
「家に戻りたいなぁ。」
と、つぶやいた。きっと祖父は、慣れ親しんだ想い出のいっぱい詰まっている家で、本当は逝きたいのだろうなぁ、と思うと胸が詰まってしまった。そしてそのまま家に連れ帰ってやれたらと心から思ったが、体力の弱った祖父にその機会はとうとう訪れなかった。
今、多くの人が、自宅での終焉を望みつつも、願いが叶わず、病院の手厚い看護のもとで亡くなっている。しかし、それは本当に幸せな最期なのだろうか。
最高の医療とは一体何なのであろうか。
僕は祖父の死を通して、考えてしまった。現代は医療が前に出過ぎて、患者の気持ちがなおざりになっているような気がしてならないのだ。誰もが納得して迎えられる最期の時を、今後は様々な側面から考えてみたいと思っている。 |
 |
 |
 |
 |
 |
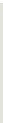 |
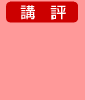 |
淡々とした書き方の中、祖父の死という大きな体験が素直に表現されています。特に、「最後の時」が、具体的に書かれており「家に戻りたいなぁ」のつぶやきでは、おじいさんの気持ちがよく伝わってきます。この作品もまた、最後の「誰もが納得して…」以降のまとめが平凡です。作者自身の気持ちを自分の言葉で表現すれば、もっと印象が深まるでしょう。 |
 |
 |
|



