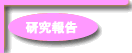 |
高齢者の色彩認識特性の実験心理学的分析 研究代表者:中村 信次 |
3. 結果と考察
3.1 因子分析
14個のSD尺度に対し共通因子の抽出を試みた.因子分析(主因子法・バリマックス回転)の結果、1)良し悪しなど一般的な評価にかかわる因子(評価性因子;快−不快、派手―地味、など)、2)和風・洋風など料理の類別にかかわる因子(類別性因子;和風―洋風、西洋的―東洋的)、3)画像の深み感にかかわる因子(深み感因子;浅い―深い、薄い―濃い、など)、4)画像の力動性にかかわる因子(力動感因子;止まっている―動いている、静か―にぎやか、など)の4因子が得られた(累積寄与率54.6%).3.2 視覚印象評価と味覚評価との関連
上述の4種の視覚印象評価因子と、味覚に関する評価項目との間の相関を分析した.評価性因子得点と「おいしさ」評価得点との間に高い正の相関が認められる(r=.74, p<.01)以外は、明瞭な相関関係は認められなかった.この結果は、特定の味覚成分(甘さ・しょっぱさなど)の予期が、特定の視覚印象(力動感・深み感など)により生起することはないことを示している.
3.3 照明効果
図2に6種の味覚に関する評価得点を、図3に4種の視覚印象評価因子得点を、色光照明条件ごとに示す.食品に対する総体的な評価をしめす「おいしさ」評価得点においては、通常の食卓環境に最も近い白色照明条件において最も評価が高く、青色照明条件において最も評価が低くなった(F(2,834)=143.90, p<.01).被験者の内観報告によると、青色照明のもたらす”冷たさ”が評価を悪化させる要因となっているように思われる.また、赤色照明は「辛さ」の、青色照明は「苦さ」の評価得点を上昇させる効果を持つことが示された(それぞれ、F(2,834)=19.37, p<.01、F(2,834)=14.11, p<.01).この傾向に関しては、それぞれの色彩を有する食材の持つ味からの連想により説明することが可能であろう(たとえば、赤→唐辛子→辛い、青→青野菜→苦い). 一方、評価性因子得点は、「おいしさ」評価得点と同様、白>赤>青の順で因子得点が高くなっており、通常の観察環境との類似性により解釈されうる(F(2,834)=381.00, p<.01).「深み感」因子得点は、白色照明条件において他の2条 件よりも因子得点が高く(F(2,384)=8.89, p<.01)、本実験において用いた極端な色光照明(赤色・青色)が、題材として用いた料理写真の持つ空間性を損ね、それを平板なものとしてしまった可能性が考えられる.また、青色照明条件において、力動感因子得点が高くなっていたが(F(2,834)=22.38, p<.01)、これは非現実的な照明条件下(青色)で、観察・評価の対象としての料理写真の安定感が失われたことを反映しているものと思われる.| ←前ページ |
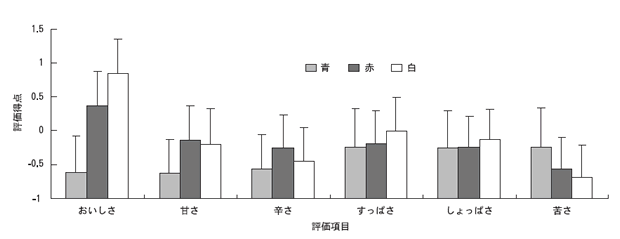
図2 色光照明条件ごとの味覚評価得点