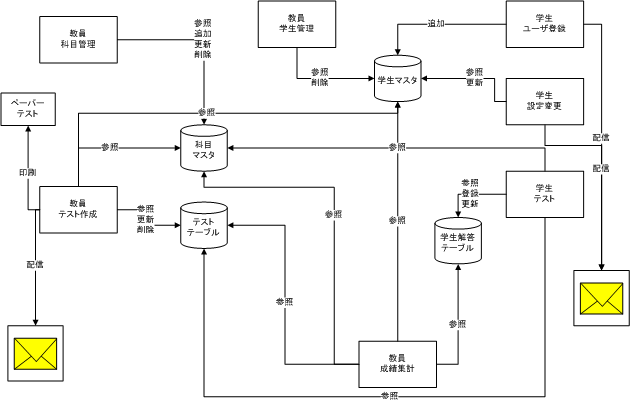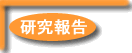 |
携帯電話対応型 e-learning の開発とコンテンツ流通システムの構築 |
本研究にて開発された e-learning システムを利用することにより, 学習者は PC, 携帯電話, 紙媒体等, 場所や時間を選ばず学習することが可能となる. 授業の合間の時間などを利用して繰り返し 学習するという, 新たな学習スタイルの実現を支援する. また, Web 上で利用可能なサービスを提供することに より, 学校教員の他, 従来まで e-learning システムを使用するのが困難であった家庭教師, 塾の講師など, 幅広いユーザが利用可能となる.
今日, 携帯電話の普及率は高く, 内閣府調査では 2004 年で 85.1%となっている. メールや Web 閲覧などは, パソコンを使わず携帯電話で充分と考えている学生も多い. 現在の e-learning はパソコンでの学習だが, 今後,携帯電話でも学習できるようになれば, 学生はより機動性のある携帯電話での学習を望むようになるだろう.また,Web 上で利用可能なサービスを提供することにより, 学校単位での導入だけではなく, 学校教員の他, 従来まで e-learningシステムを使用するのが困難であった家庭教師, 塾の講師など, 個人単位での利用が可能となり,幅広いユーザ層が期待される.
使いやすさ, 操作の単純さを追求した, どこでも学習可能な e-learning システムの開発
e-learning システムは, 学習者にとって自分のペースで学習できることが最大のメリットであるが, パソコンで学習を行うのは時間, 場所ともに限定される. そこで, 現在広く普及している携帯電話にも対応し, 学習者は何時でも どのような場所でも学習可能となる. 後藤が講義にて使用するにあたり, 必要と思われる機能情報を提供し, また大学の講義にて 実証実験を行うことにより, 実際に使う立場の人間の目から見た使いやすさや本当に必要な機能を追求する.
構築した e-learning システムの機能は以下の図のようなものである.
| ←前ページ |