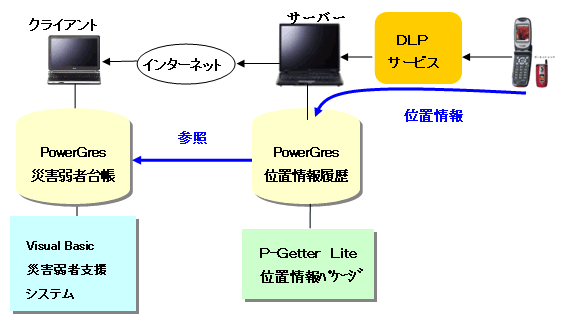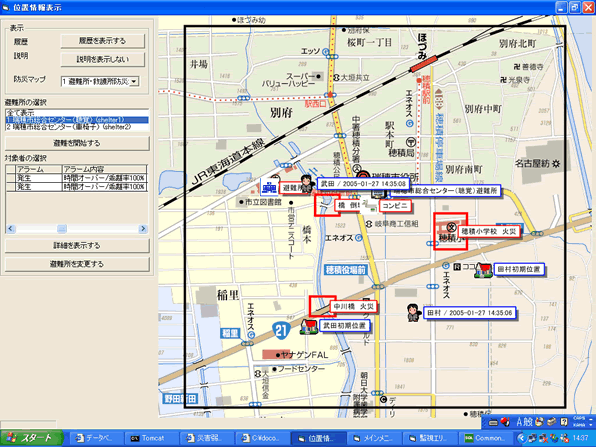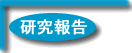
5.瑞穂市における実証実験
瑞穂市総合センターを避難所と想定し,聴覚障害者の避難及び車椅子利用者の避難それぞれに,災害弱者及び見守りネットワークの役割を持つ被験者(日本福祉大学学生)を割り当て,実験シナリオに基づき実証実験を実施した.
瑞穂市総合センターを避難所と想定し,聴覚障害者の避難及び車椅子利用者の避難それぞれに,災害弱者及び見守りネットワークの役割を持つ被験者(日本福祉大学学生)を割り当て,実験シナリオに基づき実証実験を実施した.
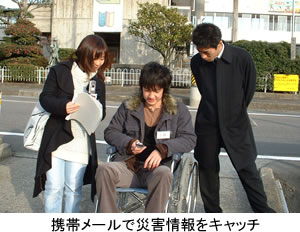
5.1 実施方法
実施日:平成17年1月27日(木)13:00-16:00
実施場所:瑞穂市総合センター周辺地域
シナリオ概要:災害対策本部(瑞穂市総合センター)
より以下のメールを発出
① 地震発生を被験者へ一斉メール発出
② 災害弱者へ安否確認メール発出→ Web入力により回答
③ 見守りネットワークへ支援要請メール
発出 → Web入力により回答
④ 災害弱者へ見守りネットワーク到着確認 メール発出 → Web入力により回答
⑤ 被験者へ地震による災害発生及び避難 開始連絡メール発出
⑥ 災害弱者へ位置モニタ開始連絡メール 発出
⑦ 災害弱者の避難経路が想定されている経路から 外れていることを発見.災害弱者及び見守り
ネットワークへ経路間違いの連絡メール発出→ Web入力により回答
⑧ 避難経路変更理由の確認メール発出
⑨ 避難所到着連絡
5.2 システムの有効性評価
実証実験を通じて,以下の有効性が確認できた.
① 文字情報で伝わるため,情報の誤解が少ない.
② Web連携機能によりメッセージの返信が可能であり,到着確認が確実に行える.
③ 返信には,メッセージの候補が登録でき,災害弱者にも操作が容易である.
④ 余裕のある弱者からは,災害情報も返信され,システムの危険エリアの追加等に利用できる.
⑤ 送信側についても,事前に避難指示メッセージが登録でき,変更にも容易に対応できる.
5.3 課題
実証実験を通じて,以下の課題が確認できた.
① 災害時にはメール遅延等の影響が懸念される.
② メール送信時にGPSの位置検索のメッセージが表示されると,誤って位置検索をキャンセルするケースがあった.結果,その回の位置登録が行えないことが発生した.
③ GPSについては,普段とは違う携帯機種を使ったため,メール確認等に手間取るケースがあった.
④ 今回実験した聴覚障害,車椅子利用の災害弱者については,携帯電話によるメールを普段使い慣れているという点で,メールによる情報提供は有効な方式であることを確認した.ただし,災害弱者の障害タイプにより違いが発生するため,音声や手話テレビ電話等の併用を検討する必要がある.
| ←前ページ |