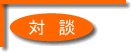
○佐々木
寛容という言葉が, 21 世紀のキーワードだという話がありますよね, どこまで寛容になれるか.
○吉田
寛容というのは, 引家のようなもので, 全部をジャッキで少しずつ上げていくのですよね. ちょっとずつバランスを取っていかないとだめだろうね.
○佐々木
一気に寛容にはなれない.
○吉田
そう. 寛容を続けさせるためには, いろいろなことをやっていかないといけない. 女性を口説くみたいなもので, まめでなければいけない.
○佐々木
あまり口説かれたことないから, わからないですが.
○吉田
「おいしい物食べない?」 って言って, 中華にするか, 鮨にするか, 目を見てある程度わかる. しゃべっているうちに, 目がちらっと輝いたときに
「じゃ, 鮨にしようか」 ってなもので行くわけでしょう. 今度 1 週間後に会って, また鮨というわけにいかないわけだ.
○佐々木
そうですね.
○吉田
寛容なんて, まさしく形容詞の世界なもので, 数字のあることじゃない. それは本当にまめにちょっとずつ行くしかないわけだ.
いつも僕は, 私の仕事は 「皿回しだ」 と言っています. ある人が 「これはモグラたたきだ」 と言ったけれどそれは失礼で, 皿回しです.
こうやってぴっと回して, 「おちこまないで」 って, つぎのはこうやって 「やめないで」 と回す. またこっちに行って, 「おい, 頑張れよ」
「わかった, わかった」 って. そうすると, また向こうが止まりそうになってそっちへ行く. この仕事は, 皿回しなんです. まめにやるしかない.
形容詞の世界の仕事をマネジメントするというのは, 皿回ししかない!.
○佐々木
ものすごくよくわかるたとえですね. それで, いくつも回っている皿をケアしているうちに, 今度はこんな皿を回してやろうかな, というようなアイディアが出てくるわけですよね.
それは突然出てくるのですか?
○吉田
顔を見ていると, 出てくる. 問題は必ず, 目を合わせるとわかる, そうすると, そこへ行って話をするのです. そのときに問題を抱えていても,
会えば解決していくのです. 楽になるんだ.
![]()
![]()
![]()
今は, 携帯電話や e メールでいつでもどこでも連絡が取れるようになっていて, ものすごく密なコミュニケーションが取れているような気になるけれど, それは錯覚で, とても危ないですよね. e メールは仕事には便利. それからコミュニケーションを直接取りたくない人との連絡にもいい.
○吉田
そうそう, 別れ話もいいんだわ (笑). コミュニケーションというのは, 時間の長さではなくて, 目と目を合わせるだけでも, コミュニケーションは取れるのですよね.
たぶん, 今の人たちはそうではなくて, 長い時間いてコミュニケーションが取れると思っているんだね. 長さではないと思う, そういう何かがあるんだと思う.
![]() 長久手という街
長久手という街![]()
○佐々木
さて, ずいぶん酔っ払ってきて, わけがわからなくなって来ましたが, 今日初めて聞くお話もいろいろあって,
とても楽しかったし, 納得できたところもありました. その中で一平さんにとっては, この長久手というところがものすごく大事なのだなあ, ということがよくわかりました.
○吉田
そう. いまグループホームをやっている藤が丘でも, 長久手の町からは絶対外れていない. 長久手の町から外へは出ない. 僕は長久手の町の中の暮らしという部分でいくわけだから,
結局それは子どものこと, 年寄りのこと, 地域のつきあいのこと, 町づくりのこと, 建物のこと, 道のことというように, 長久手の中のことだけだものね.
世界や, 日本, 名古屋市では通用しないことかもしれない.
○佐々木
その中で, これが長久手 「らしい」 というもの, 長久手にあってほかにはないというようなものはあるのですか?
○吉田
ないね.
○佐々木
たまたま長久手というところに生まれ育って, その縁を大事にしようということですか.
○吉田
自分でもそう思っているよ, 長久手の何がいいのか. 考えてみると, ふるさとの遊んだ風景は全部, 区画整理でなくなってしまった.
そうすると, 建物も変わって, 人も増えちゃった. 自分の同級生たちは仲がいいかと言うと, 仲の悪いやつもいる. 不思議なんだよね.
でも, 長久手というものが, 今の長久手とかじゃなくて, 先程しゃべった, タケノコを掘ったり田んぼで遊んだり, なくなっちゃったけれど,
その長久手というのはここにしかない. そういう長久手が, 昔, 友達と仲がよかった, みんな遊んだ. いろいろな意味のこの長久手. そんなものかもわからんね.
○佐々木
今日はどうもありがとうございました. それにごちそうさまでした.

対談を終えて一言:対談後しばらくして, 一平さんから電話がありました. 「例の区画整理のまちづくりの話,
また動き出すからいっしょにやらない?」 もちろん私は 「やる, やる」. 戸建てのグループホームのような新しいまちを森の中につくる. つきることのない夢の実現にむけて常に動いている一平さん.
そのエネルギーの源の風景が少し見えたような気がしました. (佐々木)